東浩紀編集「ゲンロン8 ゲームの時代特集」を読了。
前号の「ロシア」の特集より、理解しやすかったです。ゲームは以前はときどきやっていて、今はスマホのゲームぐらいで、本格的なのはやっていないのですが、またやってみたいなあと思いました。
「批評的な言語がゲームを苦手とするのは、映画における監督のような、なにを撮り、なにを撮らないかを決める主体が存在しないからです。」という発言がすごく腑に落ちました。
また「ノットゲーム」というジャンルの存在が面白いと思いました。
Kero Blaster、Life is strangeというゲームをやってみたいなあとメモしました。
読んでいて難しいのは、「中国における技術への問い」、「ゲーム的行為四つのモメント」」などでした。
随筆「新しい目の旅立ち」、「独立国家論」、「ディスクロニアの鳩時計」といった連載ものはいつも楽しく読みます。
今回もEbookで読みました。
こういう雑誌は、普段なら手を出さないことについて深く考える機会を与えてくれて、とても貴重です。刊行の頻度も私にはちょうどよいです。
次号を楽しみにしています。
前号の「ロシア」の特集より、理解しやすかったです。ゲームは以前はときどきやっていて、今はスマホのゲームぐらいで、本格的なのはやっていないのですが、またやってみたいなあと思いました。
「批評的な言語がゲームを苦手とするのは、映画における監督のような、なにを撮り、なにを撮らないかを決める主体が存在しないからです。」という発言がすごく腑に落ちました。
また「ノットゲーム」というジャンルの存在が面白いと思いました。
Kero Blaster、Life is strangeというゲームをやってみたいなあとメモしました。
読んでいて難しいのは、「中国における技術への問い」、「ゲーム的行為四つのモメント」」などでした。
随筆「新しい目の旅立ち」、「独立国家論」、「ディスクロニアの鳩時計」といった連載ものはいつも楽しく読みます。
今回もEbookで読みました。
こういう雑誌は、普段なら手を出さないことについて深く考える機会を与えてくれて、とても貴重です。刊行の頻度も私にはちょうどよいです。
次号を楽しみにしています。
















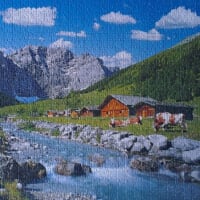




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます