
暑中お見舞い申し上げます
各地ともそろそろ、梅雨明けでしょうか
また暑い夏が始まりそうです
ご自愛下さい
さて
暑い時期、食べ物にもいろいろ注意が必要であります
今回のお題は「七袋のポテトチップス」であります
※宣伝
求人しております 60over歓迎!
不動産に関わる人材募集しておりますのでお問合せ下さい
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
参考図書)
湯沢規子著「7袋のポテトチップス」
~食べるを語る、胃袋の戦後史~
◆著者の息子さんの小学校時代
自宅に7人の少年が集まり、それぞれ1袋のポテトチップスを持ってきた
7袋のポテトチップスが集まったことにまず驚いた
友達の家に遊びに行くときは一人一つのお菓子を持っていく
という暗黙のルールがある、とのこと
さらに驚いたことに、彼らは誰かと分けることなく
自分の袋からそれぞれのポテトチップスを食べ続けた
著者は、まだ小さなその背中を見つめながら、考えこんだ
そして次の機会、著者は彼らの前でクッキーを焼いてみせた
大成功、子供たちは争ってクッキーを食べ始めた
しかし、一人の少年がクッキーを食べない
「どうしたの」と尋ねると
「人の家でつくってもらった食べものを食べてはいけない」
と言われている、と
彼の表情は、確固たる決意をもって答えているが
少し寂しそうでもあった
「秘密にして食べてみれば」と声をかけたが、
彼は「それはできない」と首をふった
◆「他人がつくったものは危険だから」という考え方
手づくりのクッキーはみんなが喜ぶはず
と思った著者にとって思いもしない発想であった
◆最近は人の手で握ったおにぎりが食べられない
学生たちへのアンケート
人の手で握ったおにぎりと
コンビニで買うおにぎりとどちらが好きか?
「人の手で握ったおにぎりが好き」53%(29/55人)
「コンビニで買うおにぎりが好き」42%(23/55人)
「温かいものであれば手で握ったおにぎり、
冷たいものであればコンビニ」 という回答もあった
コンビニのおにぎりを好む学生たちは
「人の手で作ったおにぎりを食べる機会がそもそもない」
「自分と自分の親がにぎった以外のおにぎりに抵抗がある」
「清潔な感じがする」
と答えている
◆高度消費社会の胃袋
~食べものをどこで食べるか
「胃袋」で食べる
「舌」で食べる
「目」で食べる
「頭」で食べる
このうち、「目」で食べるまでは身体感覚を伴う食事
「頭」で食べるようになってからは
身体感覚を手放して、言葉と記号を食べる行為へと偏重していった
感覚が言葉や知識や情報に絡めとられ
食べるという身体感覚と共在感覚を忘却していく時代が到来
食べることの「多元的意味」は失われ
食べることの意味は一元化、 単純化していく
食べものは、 ひとつの物質として
カロリー、ビタミン、蛋白質、炭水化物、コラーゲン、アミノ酸
などという言葉や知識で理解され、認識される
あるいは
他人に「いいね」と言われるためのアイコン
記号と意味づけられることも多い
誰もが写真やコメントを自由に発信できる情報化社会がそれを後押し
「胃袋」で食べる前に
「心」で食べる(神様と食べる)所作があったことなど
想像すらできない世の中になったのか
戦前戦後の食物語と比べると、隔世の感
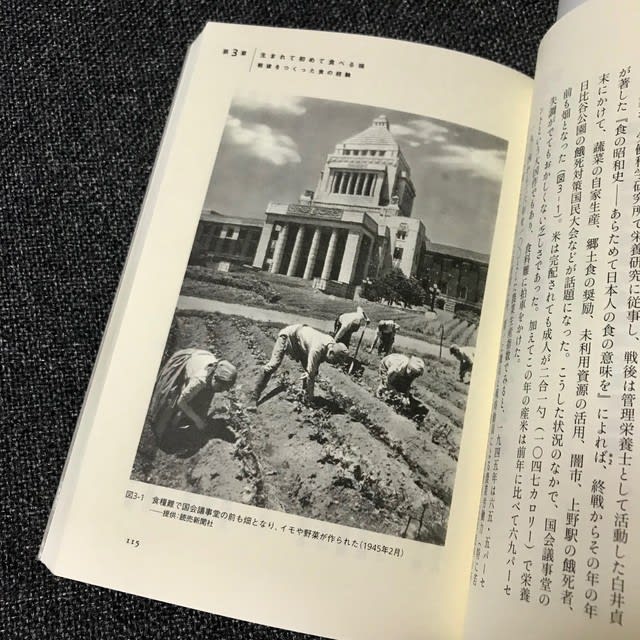
◆昭和が終わり、平成が幕を開ける頃
暉峻淑子著「豊かさとは何か」から
------------------------------------
効率を競う社会の制度は、個人の行動と、
連鎖的に反応しあっているから、
やがては生活も教育も福祉も、
経済価値を求める効率社会の歯車に巻き込まれるようになる。
競争は人を利己的にし、一方が利己的になれば、
他の者も自分を守るために利己的にならざるを得ないから、
万人は万人の敵となり、自分を守る力はカネだけになる。
そんな社会では、人の能力は、 経済価値をふやすか否か、
で判断され、同じように社会のために働いている人であっても、
経済価値に貢献しない人は認められることが少ない。
暉峻淑子著「豊かさとは何か」1989年
------------------------------------
人には何が残っていくのだろうか?
言葉が溢れ、人工知能が登場する時代
生きている実感と本当の豊かさは
どうしたら手に入れることができるのか?
◆ごはん食べた?
中国から来た留学生に
「日本ではあいさつに、ごはん食べた?とは言わないんですね」
と聞かれる
中国では「吃飯了吗(ごはん食べた?)」が
「こんにちは」のあいさつになる
「さようなら」は
「改天来我家吃飯ー(今度、うちにごはんを食べに来てね)」
中国だけでなく、アジアでは
「ごはん食べた?」、「なに食べた?」
があいさつになる国が少なくない
◆その後
彼らは中学生になり、 何かを食べ、時には一緒に料理をした
なかでもクッキーを食べなかった少年は
「おいしい」「すごい」「うまい」「さすが」という素直な言葉で
食べる喜びを著者に伝えるようになった
ある時「今までここで食べたなかで、何が一番おいしかった?」と聞いた
彼は「やっぱりワッフル。焼き立てっていうの、初めて食べたんだ」と答えた
少し大人になりかけの表情を消して見せた満面の笑顔が忘れられない
7袋のポテトチップスは、個に閉じた胃袋の象徴
著者は「他人」に対しては完全に閉じている彼らの胃袋が
いつか開くことを願って、クッキーを焼いた

◆ ◆ ◆ ◆ ◆
ということでした
食べるコト
共に在る世界で、共に在ることを実感することでありたい
と愚考する次第です
ではまた









