まだまだ鍋の美味しい季節です 日本橋人形町に勤務し 近くの日本橋蛎殻町という標識を目にしたあと本屋さんに立ち寄ると
ついつい「牡蠣礼賛」という本を買ってしまいました
 |
牡蠣礼讃 (文春新書) 価格:¥ 840(税込) 発売日:2006-11 |
■料理レシピなんかが載っているんだろうと思っていたら
これが牡蠣職人 畠山重篤氏が 精魂込めた牡蠣の大河ドラマ 面白い本です 何より気になったのはこの畠山氏の行動力 著書の取材でアポなしでも海外まで
アメリカ留学中の娘さんを通訳兼運転手としてシアトルまで呼びよせると 「そんな雲をつかむような無計画な旅程でアメリカくんだりまで来るなんて、非常識よ・・・」
「お父さんは不思議な能力を持った人で、とにかくそこへ行けば、必ず会いたい人が待っていてくれるから運転して頂戴」と奥さんが助け舟をだすくだりがありますが
「奇跡はやはり起こった。」となり本当に各地で目的を果たしていかれます
本気でやりきる すると本気の人と出会える ということでしょうか
■本気でやりきる
話題は飛びますがMCEI大阪支部2010年2月度定例会でりそな総合研究所の藤原 明さんから りそな銀行が様々な企業や地域大学などとのコラボレーション(協働)企画を推進している「REENALプロジェクト」のお話をお聞きしました
私のメモから
銀行=パワーセールスに頼っている=無理が生じる
「実需」を生まなければならないハズ
社会問題の克服=企業のビジネスチャンス
問題が一杯ある 課題がある つまりビジネスチャンスが一杯ある
企業感性による実需創造 = 「形にすること」が大事
予算「0円」で企画している組織間コラボレーション
無いモノは他から補い結びつける
自ら行動する
高い志を持った信頼をベースにした有機的なネットワークが加速度的に形成される
やりきる 本気でやりきる = 本気の人(企業)が集まる
■「牡蠣礼賛」目次を紹介しますと
第1章 Rのつかない月の牡蠣を食べよう!?
牡蠣の旬はいつか?
水山養殖場の四季―宮城県・舞根湾
第2章 おいしい牡蠣ができるまで
宮城種の故郷
牡蠣に憑かれた男―宮城新昌と水上助三郎
第3章 世界の牡蠣を食べる
日本一の生産地から学ぶ―広島県・広島湾
日本の牡蠣がフランスを救った―フランス・ラングドック
魅惑の味・オリンピアオイスター―アメリカ・シアトル
顰めっ面をした牡蠣―熊本県・有明海
干し牡蠣は万能薬―中国・沙井
タスマニアデビルオイスター―オーストラリア・タスマニア
第4章 知られざる「カキ殻」パワー
カキ殻が地球を救う
日本の白を彩る胡粉
おわりに 牡蠣がつなぐ世界
二十年ぶりの南仏ラングドック
非常に多岐にわたり牡蠣ストーリーが展開されます
■「漁師さんはドロボー?」
牡蠣養殖場に見学に訪れた小学生の発した言葉です 飼育や養殖にはエサが不可欠 でも牡蠣のエサは植物性プランクトンで これは 山 川 海のバランスが創造する命
海の幸は上流の豊かな森が育てる 畠山氏らも水源地帯に大規模な植林造林運動を進めているという(森は海の恋人キャンペーン)
■真剣に ケメジャン&戯言写真“展”
京都七条のサカタニでのLIVE&写真展について さくらさんが「さくらダイアリー」にて触れておられます
2010/2/20
朝から着物を着て、一度我が家でお稽古をしたあと挑んだケメコジャンボリーでの「たえカン」初お披露目ということで、気合いが十分過ぎて(!)本番では考えも寄らないところで迷子になってしまったけれどそこから立て直したのはよい経験になったと思う。ほんと、ライブの怖さを思い知った2人だったんじゃないか。(^^;)
※橋長注
カンチさんと結風亭多恵近さんによる「ブルース落語」
同じく、サカタニホールでは大坂城(だいはんじょう)ジャグバンドのkanbaiさんの写真展も行われていた。この日参加出来なかった、ケメコジャンボリー常連の満月堂さんはこの時間、NHKのどじまんの予選に挑戦していた。
誰に強要されたわけでもない。みんな自分の意志でそれぞれの舞台に立っている。いいことばかりじゃない。時に失敗もする。いや…むしろ、自分の普段の力を出し切って思い通りに出来るほうが少ないともいえる。
舞台の上には、少なからず「今の自分」が映し出される。おとなしくしていたら、見えない自分の欠点も舞台に立つがゆえに、みんな暴露されてしまう。それなのに舞台に立つ。
なぜ?
やっぱりみんな人を求めている。人に聴いてもらいたい、人と一緒に楽しみたい。だから、もしかしたらということも承知で舞台に立つ。
何が良かったんだろう、何が悪かったんだろう。その日の自分を反芻しながら、また次を思う。ライブだからやり直しは利かない。
あの時「私」はどうすればよかったのか。どういう位置取りにいればよかったのか。どう関わり、どう関わらなかったらよかったのか。思うことは山ほどある。
真剣に遊ぶということは、つまりは人間を鍛錬することに繋がっているようだ。
■宮城新昌
1884年沖縄県に生まれ
沖縄の農業に懸念をもち1905年ハワイへ移民として渡り サトウキビ耕作や肥料工場で働く
農場経営を夢見て貨物船に炊事係として潜り込み シアトルへ
ワシントン州都オリンピアに滞在中 T.ルーズベルトの「日本を見習い、浅海開発を」という“Sea Farm”構想に共鳴し牡蠣と出会う
オリンピアオイスターカンパニーに入社 牡蠣の養殖を一生の仕事と決意 鉄道王ハリマンの奨学金を得てオランダへ留学
ライン河口の汚染で牡蠣輸出国の没落を予感 外国人の企業化を認めないワシントン州を去り カナダのバンクーバーに移住して帰化
ロイヤルフィッシュカンパニーを買収して重役に就任 日本種の輸入を画策
大正2年(29歳)日本政府の牡蠣種輸出に協力するため帰国 農商大臣・海軍大臣の支援を得てロイヤル商会設立 輸出用牡蠣の開発のため金沢湾(現横浜市)ほかに研究施設を建てた
第1次大戦が勃発して輸出計画は頓挫 しかし水上助三郎が資金を提供この難局を救う
大震災がきっかけで より過酷な条件で育てた稚貝が長期輸送に耐えうることを実証 このマガキ(宮城種)が養殖最適品種として今や世界に普及 「世界の牡蠣王」と呼ばれる
「おいしゅうございます」の料理研究家 岸朝子さんの父が宮城新昌 ぜひドラマ化してほしい人生です
■水上助三郎
1864年岩手県生まれ
三陸沖に出没する米英加露のオットセイ猟船団に対抗して74トンの船で日本のオットセイ王として財をなす
吉浜湾のアワビ乱獲防止にも尽力 漁業と林業のバランスを提唱
国有林の払い下げを受け 部下の漁師に強制的に山林を持たせ植林させることにより 漁師を経済的に支援 結果的に山と川を そして海を守る
ウナギの養殖に失敗後 宮城新昌の牡蠣養殖に資金援助
「つくり育てる漁業」の先駆者 晩年 牡蠣がアメリカに輸出され好評となるが 本人は牡蠣養殖の成功を確認出来ず58歳で他界
こちらも映画化どうでしょう
■牡蠣
海のミルクとも完全栄養食品とも言われる牡蠣 フランスでは1970年代 養殖牡蠣が絶滅の危機に そこで日本の宮城種を輸出 フランスの牡蠣を救ったということも
モノづくり日本の面目躍如であります
■ ■ ■ ■ ■
ということでした
Oyster should not be eaten in any month whose name lacks an R.
“Rのつかない月の牡蠣は食べるな”は欧米の諺のようです February March April まだまだ牡蠣の旬のよです
牡蠣 アイラ島のシングルモルトウイスキーとの相性もバッチリです もちろん同じ山河が育ててくれたキリリとした日本酒にも “本気”を肴に語りたいものです
LS EHAGAKI #213















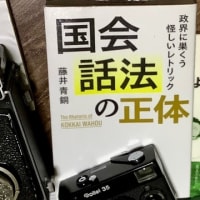





この度水山養殖場WebStoreがOPENいたしました。夏に向けて旬の牡蠣、帆立等の他、
限定の牡蠣等も掲載しております。お気軽にご利用くださいませ。
http://mizuyama-oyster-farm.com
今後とも宜しくお願いいたします。
*HP、ブログ等で弊社に関するコメントいただいている方にのみご案内しております。