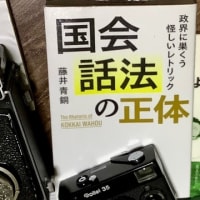梅雨の時期、釈然としない、憤りを感じるニュースに溢れています
それと同時にニュースを聞く我々の側も、乱暴になっている気がします
「ツッコミ」という動きが溢れる昨今であります
今回のお題は、芸人、マキタスポーツ氏による「現代ポップス論考」であります
参考図書)
それと同時にニュースを聞く我々の側も、乱暴になっている気がします
「ツッコミ」という動きが溢れる昨今であります
今回のお題は、芸人、マキタスポーツ氏による「現代ポップス論考」であります
参考図書)
 |
すべてのJ-POPはパクリである (~現代ポップス論考) |
| マキタスポーツ | |
| 扶桑社 |
但し、今回この本を読んでおりません
ラジオ、文化放送「武田鉄矢・今朝の三枚下ろし」で取り上げていたモノ、耳で聞いたメモであります
■ ■ ■ ■ ■
■現代に対するモノの見方
今の世の中はツッコミに溢れている
多罰的に人を責める
■ツッコミ
元々はお笑いの技であった
上から目線のツッコミが多い 人を傷つける
反撃してこない芸能人に対して容赦なくツッコム~文春ヒーロー
■メタ視線
上からツッコミ時代に入ったのは、1985年 ソニーが8mmビデオを発売
ビートたけしが激しく突っ込んだ、あるあるネタ
ドラマ、ワイドショー、演歌など、ありがちなパターンにツッコミを入れて笑いをとる、という手法を確立
■メタ視線はまた、秋元 康によって新しいパターンを作った
アイドルがアイドルにツッコミを入れた
小泉今日子
アイドルはやめられない 「なんてったてアイドル」
チェッカーズ
なぜ、売れたんですか?という問いに対し藤井フミヤ曰く
「俺たちは、軽薄短小ですよ」
軽いから売れた
ガツガツ、お涙ちょうだい、必死に熱演という、ありがちなコトに対し、クールにすかし、ツッコミを入れる
■感動
コンパクト、お手軽な感動が求められる
=長編に耐えられなくなってきた
ドラマが厳しくなっていく
日本の消費は「情報をしっかり咀嚼できる僅かな層」と「ふわふわした不動層」に大別できるが
感動なるものに、はまりつつ、ちょと馬鹿にして大多数に身を寄せる受動層が大半である
この上から目線のツッコミに対して、如何にヒットを放つか
それこそが「パクリの法則」である
感動なるものにはまりつつ、ちょと馬鹿にする人に受ける

■法則1:コード進行
カノン進行を繰り返す
●カノンコード基本形-ハ長調| C | G | Am | Em | F | C | F | G |
ヨハン・パッヘルベルのカノンで出てくるコード進行で、黄金コードと言われ、ソナタ形式と並ぶクラシックの二大看板
クリスマスイブ(山下達郎),終わりなき旅(Mr.Chirdren),Endless Rain / Tears(X JAPAN),HOWEVER / ずっと2人で(GLAY),愛を込めて花束を(Superfly),守ってあげたい(松任谷由実),上からマリコ / 恋するフォーチュンクッキー(AKB48),さくら(森山直太朗),明日への扉(I WiSH),負けないで(ZARD),突然 / DANDAN心魅かれてく(FIELD OF VIEW),真夏の果実(サザンオールスターズ),空も飛べるはず / チェリー(スピッツ),シングルベッド/シャ乱Q,桜坂/福山雅治,Love is…(河村隆一),さくらんぼ(大塚愛),出逢ったころのように(Every Little Thing),Buttefly(木村カエラ),壊れかけのRadio(徳永英明),言えないよ(郷ひろみ),ALONE(B’z),ハナミズキ(一青窈),DIVE TO BLUE(L’Arc~en~Ciel)・・・ ※WEB情報から
カノン進行を繰り返す
●カノンコード基本形-ハ長調| C | G | Am | Em | F | C | F | G |
ヨハン・パッヘルベルのカノンで出てくるコード進行で、黄金コードと言われ、ソナタ形式と並ぶクラシックの二大看板
クリスマスイブ(山下達郎),終わりなき旅(Mr.Chirdren),Endless Rain / Tears(X JAPAN),HOWEVER / ずっと2人で(GLAY),愛を込めて花束を(Superfly),守ってあげたい(松任谷由実),上からマリコ / 恋するフォーチュンクッキー(AKB48),さくら(森山直太朗),明日への扉(I WiSH),負けないで(ZARD),突然 / DANDAN心魅かれてく(FIELD OF VIEW),真夏の果実(サザンオールスターズ),空も飛べるはず / チェリー(スピッツ),シングルベッド/シャ乱Q,桜坂/福山雅治,Love is…(河村隆一),さくらんぼ(大塚愛),出逢ったころのように(Every Little Thing),Buttefly(木村カエラ),壊れかけのRadio(徳永英明),言えないよ(郷ひろみ),ALONE(B’z),ハナミズキ(一青窈),DIVE TO BLUE(L’Arc~en~Ciel)・・・ ※WEB情報から
■法則2:歌詞
J-POPのヒット曲の歌詞の材料は決まっている
180の言葉の使い回し
翼、扉、桜、奇跡、永遠、エール、大丈夫、受け止める、ありがとう、歩き出そう
これをはめこんでいけばヒットする
「J-POPは音楽ではありません、工業製品です」
■「さくら」は売れる
河口恭吾「さくら」 は別の歌だった?
その出だしは
ぼくがそばにいる、君を笑わせるから
アニメのエンディングにでも、というイメージでつくった、 そう「どらえもん」
「さくら」にヒットの匂いを感じたので、ねじ込むことにしたら大ヒット
サビ)
ぼくがそばにいる、君を笑わせるから
桜舞う季節かぞえ、君と歩いていこう
※桜が出てくるのはココだけ
■法則3:楽曲構成
「J-POPは工業製品である、故に部品があればプラモデルと同様、あなたにも出来ます」
「J-POPは工業製品である、故に部品があればプラモデルと同様、あなたにも出来ます」
■歌謡曲における大変革は1972年に起こっていた
阿久悠、筒美京平、尾崎紀世彦
「またあう日まで」
Aメロ Bメロ にCメロが入った
Cメロでドラマチックに
これがJ-POPの原型
さらに営業の技術が大切である↓
■法則4:オリジナリティー
トイレの神様
トイレの神様が居る、というおばあちゃんの言葉(=個人的な事情)を発表する
私の恋、私の暮し、それがヒットのダメ押しになる
オリジナリティは才能ではなく“私の事情” それを入れる
そういうことが盛り上げる
先人の知恵や情報を編集し直す力、それが現代の才能である
■ミリオンセラー(100万枚)は1968年から2013年までで258曲 、うち173曲(66.8%)が1990年代である
■1982年 CDプレーヤーは16~18万円 CDは3,500円~3,800円した
レコード鑑賞が大人の趣味の頂点の一つであった そしてCD登場とともに一気にCDへ
■勝手にシンドバット ~ いとしのエリー 登場
サザンの登場とともに、演歌が斜陽に
■J-POPは、マニア化、インディーズ化していく、つまり小粒化した
ポピュラー化よりも先鋭化の方向に向かった
■高いCD → 安いCD
あれほどあこがれたCD、そのあまりにも丈夫さ故にレコードほど大事にされなくなった
CDそのものが廉価になっていく
大事に扱ったレコードとは違い、安物になっていく
J-POPそのものが変質していく
■すこし脱線:演歌は日本の伝統?
※WEB情報から
「演歌は日本の伝統」
ごく当たり前のように感じますが、演歌とは?
実は1960年代に誕生!
1948年より刊行されている『現代用語の基礎知識』(自由国民社)に「演歌」の項目が立てられたのも70年版からでそれまでは登場していない
演歌とは?
明治時代、自由民権運動の流れのなかで、政府が公開演説会を取り締まりの対象としたために、規制を免れるべく演説を「歌」のかたちで展開したのが「演歌」であったが、昭和初期には衰退した
60年代後半、ポピュラーミュージックの世界は、グループサウンズ、フォーク、そして、後のニューミュージックへとつながっていく「若者音楽」大変革期であった
古いスタイルのレコード歌謡と、新しい音楽との間に乖離が生まれ、古いレコード歌謡を「リバイバルもの」としてプロモーションしたいレコード会社の思惑により、旧来のレコード歌謡をまとめて「演歌」と呼ぶようにした
今、ロックもフォークもアイドルも、昭和期にお茶の間を賑わせた音楽を「昭和歌謡」として、アルバムが盛んに制作されているのと同じ様な状況であった
「演歌」といっても、そこに厳格な音楽的基準はなく、民謡や浪花節のような日本的な音楽も含まれれば、ムード歌謡のようにジャズの影響を色濃くもち、かつての音楽界ではむしろモダンなものとして受容されたものまで混ざっている つまり、ロックやジャズよりも若いジャンルである
『創られた「日本の心」神話 「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史』 輪島裕介:著(光文社)
http://lite-ra.com/2016/03/post-2075.html
「演歌は日本の伝統」を掲げる議員連盟に「?」演歌は1960年代に生まれたもの、みだりに「伝統」を使うな!(新田 樹)
阿久悠、筒美京平、尾崎紀世彦
「またあう日まで」
Aメロ Bメロ にCメロが入った
Cメロでドラマチックに
これがJ-POPの原型
さらに営業の技術が大切である↓
■法則4:オリジナリティー
トイレの神様
トイレの神様が居る、というおばあちゃんの言葉(=個人的な事情)を発表する
私の恋、私の暮し、それがヒットのダメ押しになる
オリジナリティは才能ではなく“私の事情” それを入れる
そういうことが盛り上げる
先人の知恵や情報を編集し直す力、それが現代の才能である
■ミリオンセラー(100万枚)は1968年から2013年までで258曲 、うち173曲(66.8%)が1990年代である
■1982年 CDプレーヤーは16~18万円 CDは3,500円~3,800円した
レコード鑑賞が大人の趣味の頂点の一つであった そしてCD登場とともに一気にCDへ
■勝手にシンドバット ~ いとしのエリー 登場
サザンの登場とともに、演歌が斜陽に
■J-POPは、マニア化、インディーズ化していく、つまり小粒化した
ポピュラー化よりも先鋭化の方向に向かった
■高いCD → 安いCD
あれほどあこがれたCD、そのあまりにも丈夫さ故にレコードほど大事にされなくなった
CDそのものが廉価になっていく
大事に扱ったレコードとは違い、安物になっていく
J-POPそのものが変質していく
■すこし脱線:演歌は日本の伝統?
※WEB情報から
「演歌は日本の伝統」
ごく当たり前のように感じますが、演歌とは?
実は1960年代に誕生!
1948年より刊行されている『現代用語の基礎知識』(自由国民社)に「演歌」の項目が立てられたのも70年版からでそれまでは登場していない
演歌とは?
明治時代、自由民権運動の流れのなかで、政府が公開演説会を取り締まりの対象としたために、規制を免れるべく演説を「歌」のかたちで展開したのが「演歌」であったが、昭和初期には衰退した
60年代後半、ポピュラーミュージックの世界は、グループサウンズ、フォーク、そして、後のニューミュージックへとつながっていく「若者音楽」大変革期であった
古いスタイルのレコード歌謡と、新しい音楽との間に乖離が生まれ、古いレコード歌謡を「リバイバルもの」としてプロモーションしたいレコード会社の思惑により、旧来のレコード歌謡をまとめて「演歌」と呼ぶようにした
今、ロックもフォークもアイドルも、昭和期にお茶の間を賑わせた音楽を「昭和歌謡」として、アルバムが盛んに制作されているのと同じ様な状況であった
「演歌」といっても、そこに厳格な音楽的基準はなく、民謡や浪花節のような日本的な音楽も含まれれば、ムード歌謡のようにジャズの影響を色濃くもち、かつての音楽界ではむしろモダンなものとして受容されたものまで混ざっている つまり、ロックやジャズよりも若いジャンルである
『創られた「日本の心」神話 「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史』 輪島裕介:著(光文社)
http://lite-ra.com/2016/03/post-2075.html
「演歌は日本の伝統」を掲げる議員連盟に「?」演歌は1960年代に生まれたもの、みだりに「伝統」を使うな!(新田 樹)
■音楽の番組がTVから消える~小粒化していく
好きな人が聞いてくれれば良い、というスタンスになってきた
CDを売る方法が、アイドル、ジャニーズ、アニメ、ビジュアル系という4つの道になってきた
AKB、ジャニーズが主流に
■AKB
CD=イベント参加のチケット(=有料チラシ)となった
AKB=卒業がかかせない=終わることを前提、目指すことでアイドルを演じている
ずっと居ると人気が落ちる?
■ジャニーズ
一つの事務所に所属することが特徴
=ディズニーランドと同じ=ブランドイメージを守る為 → テーマパークのアトラクション
疑似愛のカタログ化
パンフレットを広げると、お好みのタレントさんたちが並んでいて、自分の好きなアトラクションの主人公「これが私のミッキーよミニ―よ」という子を選べる それがジャニーズによる「 ジャニーズ・ランド 」
■アニメ
アニメの基本は懐メロ感の味付け
「エヴァンゲリオン」のテーマ 「残酷な天使のテーゼ」
「蒼い風がいま胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなた・・」
この大仰な始まりは「月光仮面」に似てるような
■ヴィジアル系
キーワードは3つ「キメ・カオ・ヒモ」
「キメ」
歌いながら「くれないのぉ~」って言いながら、最高音を歌いながら、キメる
見得を切る
見得を切る
「 ヒモ 」
ヒモ感覚を刺激 女性にめんどうをみてもらうヒモ 女性の裁量に従う
「ルナシー」はファンのことを「スレイブ(奴隷)」と呼ぶ
非日常感を出す
この「 S M 的世界 」
どのくらいファンと特別に結びついているか、というのが彼らの世界
みんなにウケようなんて誰も思わない
そのためには、ハッキリした傾向を持たなければならない
その傾向が「 手癖・メロ癖・のど癖・歌詞癖 」
■手癖
ヒモ感覚を刺激 女性にめんどうをみてもらうヒモ 女性の裁量に従う
「ルナシー」はファンのことを「スレイブ(奴隷)」と呼ぶ
非日常感を出す
この「 S M 的世界 」
どのくらいファンと特別に結びついているか、というのが彼らの世界
みんなにウケようなんて誰も思わない
そのためには、ハッキリした傾向を持たなければならない
その傾向が「 手癖・メロ癖・のど癖・歌詞癖 」
■手癖
「 Am F G C 」
これがサザンがよく使う手癖
これで生まれたヒット曲
「勝手にシンドバッド」 今何時 そうねだいたいね 今何時 ちょっと待っててオー・・
「チャコの海岸物語」 海岸で若い二人が恋をする物語 目を閉じて胸を開いて・・
そして
「希望の轍」 「エロティカ・セブン 」
せつない泣きと過激な脅し、これがサザンの手癖で、桑田サウンドの最大の特徴は、和風スパゲッティ
これがサザンがよく使う手癖
これで生まれたヒット曲
「勝手にシンドバッド」 今何時 そうねだいたいね 今何時 ちょっと待っててオー・・
「チャコの海岸物語」 海岸で若い二人が恋をする物語 目を閉じて胸を開いて・・
そして
「希望の轍」 「エロティカ・セブン 」
せつない泣きと過激な脅し、これがサザンの手癖で、桑田サウンドの最大の特徴は、和風スパゲッティ
スパゲッティなんだけど和風、基本的に醤油味でまとめる
■歌詞癖
語尾に出てくる個性の持ち主、長渕剛
語尾に「 ちまった 」
枯れちまった、なじられちまった、やっちまった、の言葉使い
これは真に受動的で主体的ではなく「巻き込まれてしまっちゃった」
これは真に受動的で主体的ではなく「巻き込まれてしまっちゃった」
「オレじゃねえんだよ。オレはやりたくなかったんだけど、ヤツがああいう態度に出たからヤっちまったんだ」
基本的には、田舎者の被害者意識
■「ヒットする曲には全て同じタレがかかっている」
様々なヒット曲があるがそれは、まるでうなぎ屋の秘伝のタレのように「継ぎた足し継ぎ足し」なのだ
■「すべてのJ-POPはパクリである」 マキタスポーツ氏
■「すべてのJ-POPはパクリである」 マキタスポーツ氏
※WEB情報から
著者は「パクリ論争」について、こう述べています。
パクリか、パクリじゃないか」などという論争は途端にバカバカしいものに思えてきます。何しろ、ポップスやロックは「規格」そのものが輸入されてきたものなのですから。
そして、ついつい「規格」にばかり目が行きがちですが「人格」が乗っかっていることを忘れてはいけません。逆にいえば、これさえあればどんな作品も「パクリ」になりようがないはずだ、とさえいえます。
意図的に盗作をするのではない限り、重要になってくるのが、「一流のアーティストであれば元ネタを引用し、解釈して新しいものを作っていく手法にこそオリジナリティが発揮される」という話なのです。
■ ■ ■ ■ ■
ということでした
私などは学生の頃よりブルーグラスという超マイナーな音楽(=小粒化した音楽)が好きだったので、日本のメジャーな音楽シーンには、あまり興味無かったのですが、納得の内容でありました
すでにCDから配信の時代になり、ますます小粒化(先鋭化)していくことでしょう 「個人の好み」のモノを広い選択肢から選べる これはこれで良い傾向である、と愚考うる次第です
著者は「パクリ論争」について、こう述べています。
パクリか、パクリじゃないか」などという論争は途端にバカバカしいものに思えてきます。何しろ、ポップスやロックは「規格」そのものが輸入されてきたものなのですから。
そして、ついつい「規格」にばかり目が行きがちですが「人格」が乗っかっていることを忘れてはいけません。逆にいえば、これさえあればどんな作品も「パクリ」になりようがないはずだ、とさえいえます。
意図的に盗作をするのではない限り、重要になってくるのが、「一流のアーティストであれば元ネタを引用し、解釈して新しいものを作っていく手法にこそオリジナリティが発揮される」という話なのです。
■ ■ ■ ■ ■
ということでした
私などは学生の頃よりブルーグラスという超マイナーな音楽(=小粒化した音楽)が好きだったので、日本のメジャーな音楽シーンには、あまり興味無かったのですが、納得の内容でありました
すでにCDから配信の時代になり、ますます小粒化(先鋭化)していくことでしょう 「個人の好み」のモノを広い選択肢から選べる これはこれで良い傾向である、と愚考うる次第です
ではまた