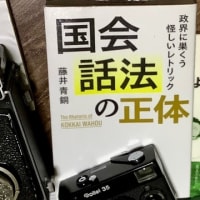「お天道様が見ている」
だから嘘をついてはいけない
と幼いころ呪文の様に聞かされました
Honesty pays in the long run
中学の英語で習う格言で
「長い眼で見れば、正直の方が割に合う」という意味
逆に言えば
「短期的に見れば、嘘は割に合う」ということ
利己的で近視眼的なものの見方をする人々が増殖する社会を
「サル化」と定義した思想家・内田樹氏の
新著「サル化する世界」※1での考察であります
「サル化」は昨年9月、この通信で
EHAGAKI#379≪サル化する社会≫※2を発信しました
それは生物学的アプローチ
ゴリラ的であった人間社会がサル的になってきた
というお話でした
ところがこの内田樹氏は別の視点
人間側からのアプローチ
今回のお題は「Honesty pays in the long run」であります
※1
「サル化する世界」内田樹著


EHAGAKI#379≪サル化する社会≫
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

インタビューに答えて
現代社会を「サル化」というキーワードで斬ったのは?
◆「サル化」とは
「今さえよければそれでいい」
という発想の人をサルと呼んだ
目の前の出来事について
どういう歴史的文脈で形成されたか
どう変化していくかを広いスパンの中で観察/分析しない人たち
目の前に断片的な情報が散乱
↓
何が起きたのかををいくつかのパターンで考え
↓
すべての断片をつなぐことのできるストーリーを選ぶ
それが論理的思考
しかし
今の日本では政治家も官僚もビジネスマンもメディアも
論理的にものを考える力そのものが急速に衰えている
歴史的スパンの中で
「今」を見るという習慣、時間意識が無くなった
それが「サル化した社会」

◆朝三暮四
「サル化」という言葉は
【朝三暮四/ちょうさん‐ぼし】の故事から採った
宋の狙公(そこう)が、飼っている猿にトチの実を与えるのに
朝に三つ、暮れに四つやる、と言うと猿が少ないと怒った
朝に四つ、暮れに三つやると言うと
たいそう喜んだという
朝の自分と夕方の自分が同一である
ということが仮想できなかった
ある程度長い時間を通じて
自己同一性を保持できない人を笑った故事
どうして「こんな話」が何千年も語り伝えられるのか
【守株待兎/しゅしゅ-たいと】
切り株に偶然ウサギがぶつかったら、次の日から野良仕事を止めてしまい
偶然の幸運をあてにする、愚かさのたとえ
【矛盾/む‐じゅん】
矛(ほこ)と盾(たて)とを売っていた者が
「この矛はどんなかたい盾をも突き通す」
「この盾はどんな矛でも突き通すことができない」
と誇ったが
「それではお前の矛でお前の盾を突けばどうなるか」
と尋ねられて答えに窮した
武器商人は
「矛を売っているときの自分」と
「盾を売っているときの自分」が同一である
ということをうまく想像できなかった
これらの逸話が春秋戦国時代に集中している
この時期に「時間意識が成熟した人間」と
「時間意識が未成熟な人間」が混在していた
だから
「時間意識が未成熟な人間」を文明化すること
適切な時間意識を持たないと、人に笑われるぞ
という「脅し」によって、人々を教化しようとした
◆時間意識
時間意識とは
「もう消え去った過去」と
「まだ到来していない未来」を自分の中に引き受けること
過去の自分のふるまいの結果として今の自分がある
未来の自分は今の自分の行動の結果を引き受けなければいけない
骨格のはっきりした、ある程度の時間を持ちこたえられるような
自己同一性がその時代から要求されるようになった

◆現代人が「退化のフェーズ」に入った
「今だけ、自分だけよければ」
という現代人に特徴的な時間意識の縮減は
春秋戦国時代から二千年以上経って
人類が「退化のフェーズ」に入ったのではないか
◆産業構造の変化
株の売買はマイクロセコンド単位で、アルゴリズムが行う
今の経済活動の基本時間はもう人間的時間ではない
人間の身体感覚や知性が通用する時間の流れ方ではない
1950年代は
生産者のうち農業従事者人口が50%を占めた
◆植物的時間
経済活動の時間単位が「植物的」だった
だから
学校教育でも、子どもたちの成長は農業のメタファーで語られていた
種子を撒いて、水と肥料をやって、日に当てて
風水害や病虫害から守ると、収穫期には果実が実る
という言い方で家庭教育も学校教育も語られた
子どもたちは「種子」育ち方はお天道さま頼り
先行きどのようなものに結実するか予測できない
キュウリができるのかトマトができるのかは分からない
きちんと手入れをすれば
この子が持ってる潜在可能性は開花するだろう
という諦観と楽観が混じって子どもは育てられた
いくら手入れをしてもさっぱり芽を出さない子については
「大器晩成」そのうち何か大きなものに結実するんじゃないか
と気楽なことが言われた
◆工学的時間
産業構造が変わって、第二次産業が基幹産業になる
と同時に
工場での工業製品の生産プロセスに準拠したメタファーが用いられる
そういう転換は無意識に変わり、誰も気づかなかった
人間は生身の生き物缶詰や乾電池じゃない
今は学期ごとに学習到達目標が数値的に示される
そこで示された
「納期」と「仕様」に合わせて「生産」がなされなければいけない
精密な工程管理と品質保証がうるさく言われる
教育について語る言葉遣いも工学の用語になってきた
「シラバス通りの授業をしろ」とか
「学士号の質保証」とか「PDCAサイクルを回す」とか

◆植物的時間から工学的時間
それと同時に
四季のサイクルを基準にした植物的時間が棄てられ
代わりに納期と仕様に合わせて工業製品を生産する
工学的時間が採用される
人間では制御できない巨大な自然力が子どもの成長に介入する
という考え方そのものが廃棄され
すべては人工的に管理できるということが前提になった
◆でもね
人間は長らく植物的な時間のなかで子どもを育ててきた
何千年かやってきて、うまくいった
産業構造が変わったからと言って
教育まで、支配的な産業構造に合わせて変える必要なんかない
子どもは植物的時間の中で成長すればいいじゃないか
人間は生身の生き物
缶詰や乾電池じゃない
◆Honesty pays in the long run
「長期的に見れば、正直は割に合う」
逆に言えば
「短期的に見れば、嘘は割に合う」ということ
「短期的に見る」ことしかしない人間にとっては
「嘘をつくことの方が割に合う」
◆嘘は割に合う
ドナルド・トランプは長期的なスパンでは
米国史上もっとも愚鈍で邪悪な大統領として歴史に名を残す
国益を大きく損なった人として世界史に記録される
しかし短期的に見れば大成功している
ファクトチェックによると
就任からすでに1万以上の嘘を重ね
フェイクニュースを垂れ流したことによって成功した
「嘘は割に合う」の最も説得力のある事例
◆アメリカで「サル化」が進行している
約束を守る
隣国との信頼関係を構築する
短期的にはコストがかかるかも知れないが
長期的には安全保障コスト、外交コストを引き下げる
しかし今のアメリカには出来ない
他国を恫喝し、外交的な危機を煽ると
有権者は喜ぶし、兵器産業は儲かる
トランプが今もアメリカ国民の相当数から支持されてる
ということはアメリカでも「サル化」が進行しているということ
◆日本でも同じ
長期的に見た場合、こんな嘘を言って帳尻は合うのか
という考え方をしない人間にとっては
「正直」にインセンティブはない
世界中が「サル化」している
そうした時間意識が社会の分断化をより強めてきた
どうしたらいい?

◆公人たるもの
「敵と共に共生する、反対者とともに統治する」
というのが民主主義(哲学者のオルテガ・イ・ガセット)
だから
公人たる者は反対者たちの意向も代弁し
集団の利益を代表するのが仕事
自分の支持者の利益を代表するわけではない
それがいまや民主主義というのは
多数決のことだというシンプルな理解が支配的になった
選挙結果が51対49だったら
敗けた49についてはまったく配慮する必要がない
と公言するような人物が首長になったり議員になったりしてる
彼らは自分が公人であるという自覚がない
自分の支持者を代表しているだけだから
「権力を持った私人」でしかない
◆気まずい共生
公人たる者は
自分の個人的な思いは痩せ我慢してでも抑制し
異論と対話し、反対者と共生する作法を学ばなければいけない
それが「気まずい共生」ということ
「気まずい」から、さっぱり楽しくない
合意形成にもやたら時間がかかる
しかしそれが民主主義のコスト
民主主義のコストを引き受ける気がないなら
独裁制か無秩序か、どちらかを選ぶしかない
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
ということでした
正直に生きる
それに時間と手間をかける
つまりコストをかける
そのことにあまりにも無頓着になった社会
それに加担してしまっている自分
気まずくても言うべきことを言う
10年後の自分の為に
子供たちの為に
と愚考する今日この頃です
ではまた