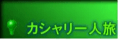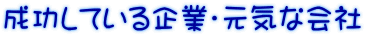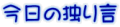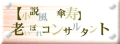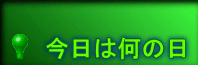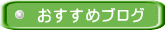【カシャリ! ひとり旅】 福岡県宗像市 宗像大社 末社7000を持つ格式高い神社
若い頃からひとり旅が好きで、経営コンサルタントとして独立してからは、仕事の合間か、旅行の合間に仕事をしたのかわかりませんが<笑い>、カメラをぶら下げて【カシャリ! ひとり旅】をしてきました。
下手の横好きで続けていますが、その一環で訪れた名所旧跡・庭園等を順次紹介してまいりたいと思います。
宗像大社は沖ノ島の沖津宮(おきつぐう)、宗像市内沖にある筑前大島の中津宮(なかつぐう)、宗像市内にある辺津宮(へつぐう)の三社をさします。
伊勢の伊勢神宮に対して「裏伊勢」とも呼ばれています。
福岡県の北東部に位置し、上述の三社を線で結ぶと朝鮮半島に繋がります。このように中国大陸や朝鮮半島に近い位置にあり、海外との貿易が盛んで、その交流から海外の文化が入りやすかったのです。交通の要衝にあることから、海上・交通安全の神として信仰され、福岡では宗像大社のステッカーを貼ってある車をよく見ます。
日本最古の歴史書といわれる「日本書紀」には、「歴代天皇のまつりごとを助け、丁重な祭祀を受けられよ」との 神勅(天照大神のお言葉)があり、三女神がこの宗像の地に降りられたと記されています。
三女神の一神の田心姫神(たごりひめのかみ)は、沖ノ島の沖津宮に祀られています。湍津姫神(たぎつひめのかみ)は、筑前大島の中津宮に、市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)は辺津宮 にそれぞれお祀りされています。
沖ノ島は、海上交通の要所に位置するために、戦時中には砲台が作られたりしました。今は緊急避難港に指定されていますが、島全体が御神体ですので、女人禁制となっています。例え男性であっても、上陸前には禊を行なわなければなりません。
昭和29年から沖の島の発掘調査が行われました。4~5世紀から9世紀までの石舞台や古代装飾品などの大量の祭祀遺物が発見されました。沖の島は「海の正倉院」とも呼ばれています。古代から信仰の島だったのですね。
海の正倉院と呼ばれるゆえんとして、仁徳陵などでしか発掘されないような宝物が多数出土しています。このことからも、この地の支配者が強大な権力を持っていたと考えられます。
| 宗像大社 | |
| 大鳥居と祈願殿 | |
| 中門 | |
| 太鼓橋 | |
| 心字池 | |
| 手水舎と祓殿 | |
| 神門と本殿 | |
| 御神木 | |
| 末社・儀式殿 | |
| 相生の樫 | |
| 三笠宮殿下歌碑と神宝館 | |
| 第二宮・第三宮 | |
| 高宮斎場への道 | |
| 高宮斎場 | |
| 宗像大社パンフレット | |
| 鎮国寺 | |
| 名所旧跡インデックス |