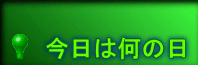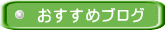【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記 8月12日 徒然草 第65段 この比の冠は 権力欲はいつの世にもはびこる
平素は、私どものブログをご愛読くださりありがとうございます。
この度、下記のように新カテゴリー「【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記」を連載しています。
日記ですので、原則的には毎日更新、毎日複数本発信すべきなのでしょうが、表題のように「老いぼれ」ですので、気が向いたときに書くことをご容赦ください。

紀貫之の『土佐日記』の冒頭を模して、「をとこもすなる日記といふものを をきなもしてみんとてするなり」と、日々、日暮パソコンにむかひて、つれづれにおもふところを記るさん。
【 注 】
日記の発信は、1日遅れ、すなわち内容は前日のことです。
■【小説風 傘寿の日記】
私自身の前日の出来事を小説日記風に記述しています。
【カシャリ!ひとり旅】の写真は、整理が追いつかず、増える一方です。 何かと忙しく動いていますので、気分転換をするようにしています。 音楽を聴くことが多いですが、過去の写真や動画を見ることも楽しみです。
*
◆ 第65段 この比の冠は 権力欲はいつの世にもはびこる
徒然草の中でも、短い段のひとつですが、兼好の時代を観る眼が、現代でも通じるような気がしています。
*
【原文】
この比(ごろ)の冠(こうぶり)は、昔よりはるかに高くなりたるなり。
古代の冠桶(こうむりおけ)を持ちたる人は、はたを継ぎて、今用ゐるなり。
*
【用語】
冠(こうぶり): 衣冠・束帯の折にかぶるもの
冠桶(かむりおけ、こうむりおけ): 冠をおさめておく円柱状の木箱
はた: 桶の縁
*
【要旨】
最近の冠は、時代が経ると共に、次第に高くなってきています。
冠を収めておく古代の冠桶を持っている人は、冠の高さが高くなるにつれ、その上辺に木を継ぎ足して、今でも使えるようにしています。
*
【 コメント 】
冠桶というのは、正式な装束であります衣冠束帯の時に、頭に付ける冠を入れておく円柱状をした木でできた箱のことです。冠は、時代を経るに付けて華美に、豪華になってゆき、それを見せびらかせることが、自分を大きく見せることに繋がります。
おそらく冠もひとつではなく、数も増えてゆくでしょう。
表では、そのようにして見栄を張り、裏では、経済的に苦しく、それを悟られないように昔から使っている木の箱を、背が高くなった冠が入るように継ぎ足して、冠が収まるようにして使い続けています。
このようなことは、昨今でも類似現象として起きていまると思います。
その背景には、人間の権力欲や承認欲を求める性癖を利用して、権力を高めてゆく政治家の策略でもあります。
昨今でも、権力欲・出世欲丸出しで、周囲の人を蹴落としてでも上に上がろうとする人や、勲章や名誉職をむやみに欲しがり、目立ちたがる人が見られます。
兼好は、このような欲望を否定し、また、保守的な面を持ち、新しいものをあまり好まない傾向があるように見受けられます。

■【今日は何の日】
当ブログは、既述の通り首題月日の日記で、1日遅れで発信されています。
この欄には、発信日の【今日は何の日】と【きょうの人】などをご紹介します。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/7c95cf6be2a48538c0855431edba1930

■【経営コンサルタントの独り言】
その日の出来事や自分がしたことをもとに、随筆風に記述してゆきます。経営コンサルティング経験からの見解は、上から目線的に見えるかも知れませんが、反面教師として読んでくださると幸いです。
*
◆ 君が代の作詞・作曲者をご存知ですか? 812
君が代は、日本国の国歌であることは、日本国民としては、考え方が異なる人もいるようですが、当然知っているはずです。
この歌の主旨は、「天皇の治世を奉祝する」歌です。
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
その意味は、よくわからないと思っている人も多いと思います。
日本語がわからないときには、英語を通じて理解すると良いです。
【Wikipedia】に、バジル・ホール・チェンバレンの英訳が出ていましたので、紹介します。
A thousand years of happy life be thine!
Live on, my Lord, till what are pebbles now,
By age united, to great rocks shall grow,
Whose venerable sides the moss doth line.
汝(なんじ)の治世が幸せな数千年であるように
われらが主よ、治めつづけたまえ、今は小石であるものが
時代を経て、あつまりて大いなる岩となり
神さびたその側面に苔が生(は)える日まで
英訳を和訳した日本語から、生の賛歌であり、平穏な世の中が永く続くことを願っている歌であると解しています。
*
因みに「さざれ石」は、日本全国処々に見られます。
小石が集まって、岩となったものです。
自宅からは、日枝神社が最も近いところにあります。
*
歌詞は10世紀初めに編纂された『古今和歌集』の短歌の一つで、詠み人知らずです。
しかし、実際には作曲者が誰であるのか、研究者の間では特定できているようです。
詠み人知らずとした方が、なんとなく日本人受けするような気もします。
作曲は、林廣守、奥好義で、1880年(明治13年)に曲が付けられました。

■【老いぼれコンサルタントのブログ】
ブログで、このようなことをつぶやきました。タイトルだけのご案内です。詳細はリンク先にありますので、ご笑覧くださると嬉しいです。
本日は、明細リストからではなく、下記の総合URLよりご覧下さるようお願いします。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17

■【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記 バックナンバー
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/a8e7a72e1eada198f474d86d7aaf43db