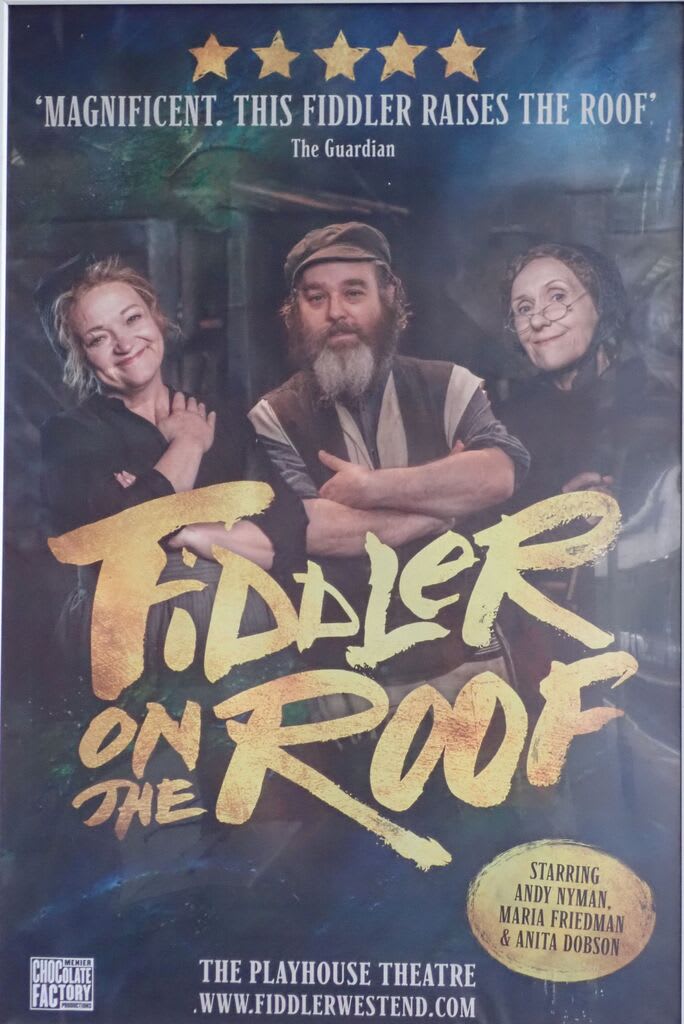ノッティングヒルズの古書店にて。この中に置かれている書籍「JIMMY CHOO」。日本の百貨店でも見かける有名ファッションブランドだが、このブランド名ともなったジミーは、1948年にイギリス領マラヤの直轄植民地ペナン生まれ(現マレーシア)。
長じてイギリスに渡り、両親も彼の店の立ち上げ時にイギリスに移民として移住した。彼が作る靴はダイアナ妃はじめ、各国セレブが愛用し、評判となる。1996年『ヴォーグ』イギリス版の編集者とともにブランドを立ち上げたものの、あくまでオートクチュールにこだわる彼はブランドを離脱。かわって、中心となったのが彼の姪のサンドラ・チョイ。ずっとジミーの元で靴を学び、ブランド設立時から一貫してクリエイティブディレクターとして活躍している。彼女はイギリス・ワイト島に生まれ、生後すぐに香港の祖父母の元で育った人物。現在も同ブランドの中心だ。
このような大英帝国時代からの自由な移動を可能にしているのが、イギリス政府が発行し、更新しているパスポートだといえよう。
【歴史のはざまに浮かぶBNOパスポート】
ここで香港の歴史のおさらいを。
1840年にイギリスが清国(中国)にしかけたアヘン戦争に勝ち、1842年に今の香港の一部がイギリス領になりました。その後も戦争や事件を起こしては、香港の領土を広げていきます。
そしてアヘン戦争から58年が過ぎた1898年には九龍半島北部の新界と呼ぶ深圳河までの地域を99年後に返還するという期限つきの租借地としました。現在の香港領の完成です。
以後は中国が共産党と国民党の覇権争いが続き、間に日本の占領などを経て、戦後は再びイギリス政府機関が元に戻りました。
それから84年の時を経た1982年。植民地支配の時代が終わり、イギリスのサッチャー首相が訪中。そこから急に「香港返還」の約束を果たす話が進みだします。そして本当に約束の年の1997年に返還されたのでした。
その時の約束は「一国二制度」。
当時、香港市民の多くが自由の空気を謳歌しており(香港映画も隆盛や香港スターが日本でコンサートをひらいていました。私の友達もイソイソと駆けつけては黄色い声援を送り、映画を見るために広東語を学んでいた人もいました)、もともと歴史的にも不安定な中国から脱出してきた人々及びその子孫中国が支配することに嫌悪感を抱いていましたので、中国に飲み込まれるなんて、ありえなかったのです。
そのため人生に保険をかけるために、多くの市民がイギリス政府が発給したパスポートを持ち、更新し続け、なおかつ、海外への移住権も確保して、いつでも香港を飛び立つ算段をつけたというわけ。
案の定、10年タームで一国二制度の約束はグダグダになり、ついにBNOパスポートは香港市民だけでなく、イギリス政府にとっても政治の手札となっていったのでした。 (つづく)