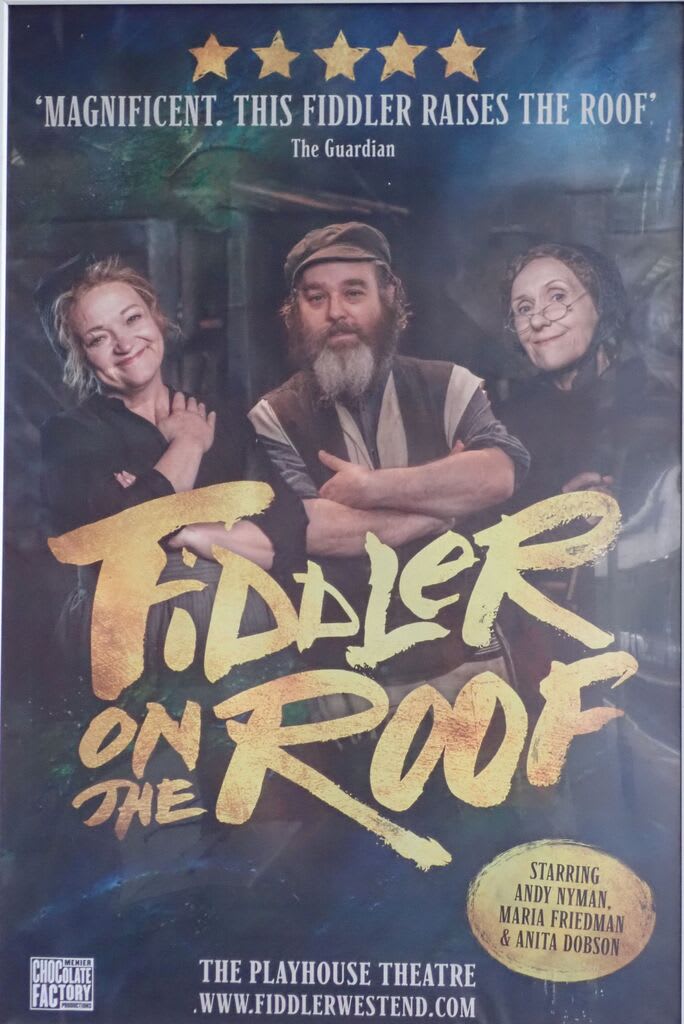ロンドンの自然史博物館の柱下部の彫刻。このように動植物をあしらったさりげない彫刻物があちらこちらにある。「リバティ」百貨店の手すりの彫刻たちと雰囲気と同じだ。同じ時代の建造物なので、この手の装飾がはやっていたのだろう。
( 2度目のロンドン12 憧れのリバティへ 下 - 雲南、見たり聞いたり感じたりhttps://blog.goo.ne.jp/madoka1994/e/0fc15fd5abb1c009bca29509d8418d4f)
【無料のスタンスとボランティア精神】
ハロッズから徒歩20分ほど(約1.5キロ)の自然史博物館にも足を伸ばしました。ハイドパークの南側では何度か言及している1851年にロンドン万国博覧会が行われました。その跡地の一角を1862年に大英博物館の自然史部門を移転するために購入し、現在では独立した博物館となっています。このあたりの建物の多くは万国博覧会に通じてしまうのです。
入場料は大英博物館と同様に無料で、寄付を投入できるボックスが置かれています。
日曜日のせいか、日本のラッシュアワーのように込んでいました。日本のラッシュアワーで数十年鍛えられた身としては、なされるままに、ゆっくりと進んでいきました。入口付近を過ぎれば、巨大な博物館に吸い込まれるように、やがて人もばらけて、じっくり見ることができました。だから慌てる必要なまったくありません。たとえ人がまったくいなくてもゆっくりと進みたくなるほど見どころがいっぱい。
建物は1880年に完成したロマネスク様式の黄色みがかった石造りで、大聖堂の内部のようなクラシカルな雰囲気。ところどころに動植物をあしらった彫刻も気になるところです。

正面入り口から入ると、頭上には巨大なシルナガスクジラの骨格標本が悠然と泳ぎ、2階付近をめぐる美しい回廊を眺め渡しているかのよう。回廊は各研究室をつなぎ、現代とヴィクトリア時代をうまく交差させています。あれ? なぜ私は「研究室」とわかったのかしら?
ほぼ毎夏、日本でも放映されるBBCが子供向けに作る恐竜と冒険家風の科学者と子供が織りなすアドベンチャー番組。つい子供と一緒に見ていたのですが、そこでは定番の光景だったのです。またBBCのドキュメンタリーでもしょっちゅう登場します。
あの二階のドアから小さな恐竜が現れて、かくれんぼしていたなあ、あそこあたりで、気づかないで人が歩いていて…、なんて映像が脳内再生されるほどで、懐かしさすら覚えるのです。ロンドンは、歩けば、何かしらのロケ地に知らないうちに行ってしまうほど、映像作品の宝庫。ここもEテレ好きなら、意識せずにロケ地めぐりになることでしょう。
(つづく)