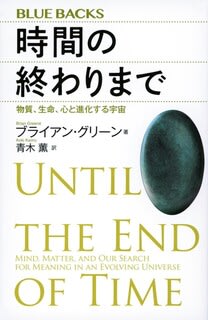ブライアン・グリーン/著 青木薫/訳 「時間の終わりまで 物質、生命、心と進化する宇宙 」読了
著者は、理論物理学者で超弦理論の研究者だそうだ。学生時代から自分が数学と物理学に心惹かれてきた理由を、『自然法則が心に訴えかけるのは、それが時間を超越した特性を持つからかも。では、時間を超越したものの研究、永遠に保たれるかもしれない特質の探索へと、われわれを駆り立てているものはいったい何なのだろう?もしかすると、人は時間を超越していないということ、人生には限りがあることをわれわれは知っているということが、すべての始まりなのだろうか?この考えは、少し前に気づいたばかりの数学と物理学と永遠の魅惑に関するひとつの見方と響き合って、ずばり的を射ているように思われた。それは、誰もが知っている死というものへの当然の反応に基礎づけられた、人間の動機を理解するためのひとつのアプローチだった。』
と考えた。自分の命が有限であるがゆえに無限に続くのかもしれない時間の流れ、すなわち宇宙の過去から未来への姿の解明に魅了されたということだろうか。
オットー・ランクという心理学者は、『芸術家とは創造への衝動を持つ者であり、「その衝動は、儚い人生を永遠の命に代変えようとする試み」だった。』と言う。サルトルは、『人間が「自分は永遠に存在し続けるという幻想を失う時」、人生そのものから意味が失われる』と言った。それはあたかもものを創造する能力を使って、心を苛む不安(=死への不安)に対抗する、強力な防衛手段を作り上げてきたかのようである。
この世界はどこから来てどこへ行くのか、その世界の中で僕が生きていることについてはどんな意味があるのか(多分何の意味もないと思うが・・)、そして人が生きて死ぬということとはどういうことなのか。それは科学で説明できるのか・・。序盤の部分を読んでいるとこの本は僕が知りたいと思ってきたことの集大成のような気がした。まあ、個人が生きている限り、その人に見合った能力に応じてでしかないがその意味を知りたいと思うのに違いない。
芸術の探求から科学の発見まで、人類の文化のかなりの部分は、限りある生命の本性について思索する生命によって駆動される。これを著者は人間文明の統一理論と呼ぶ。
目次を見てみると、時間の始まりから生命の誕生、意識の獲得、言語、信仰・・そして時間の終わりすなわち宇宙の終焉、そういったものを物理学の理論を使って説明しようというのである。
宇宙の始まりや時間の流れというのは物理学となじみが深いと思うが、意識や信仰というとどうもそうとは思わないけれどもやはり物理法則に支配されているというのである。
まあ、結果から先に書くと、それは現在のところ見つけられてはいない。もし見つけることができていたのならこの本よりも早くニュースになり、テレビの科学番組が取り上げているだろう。
しかし、著者の考えというのは非常に興味がある。これまで3000年以上の間、幾多の哲学者や科学者がこの問題に取り組んできたのだが、そういった歴史を交えながらひょっとしたらこうなのではないかということを最新の物理学理論を使って考察している。
それをなんとか凡人にもわかるようにと一所懸命600ページ近くにわたって解説してくれているのだが如何せん凡人以下の脳みそではなかなかそうもいかない。
いつもの通り、ぼくが勝手にこうなのかなと考えたことを書いてゆく。
この統一理論のキーのひとつとなるのが「エントロピー」だという。エントロピーとは、熱力学の第二法則に基づく考え方である。物質の状態は必ずエントロピーが少ない状態から増大する方向に変化するというものだ。もっと簡単に言うと、世界は必ずカオスの状態に向かうというものである。そしてこのエントロピーが、時間は一方向にしか流れないということを決定づけているという。
それはどういうことか。
物理法則というのは未来と過去を区別しないのであるが、秩序正しい状態が出現する確率とまったくランダムな状態が出現する確率とを比べるとランダムな状態が出現する確率のほうがはるかに高いのでエントロピーが増大した状態(カオス状態)はエントロピーが少ない状態(秩序正しい状態)には確率的に戻ることはまずないので時間を巻き戻すことはできないというわけだ。
うまく表現できていないのだが、物質の状態を分子レベルで見てみると、それぞれの分子がどの位置にあるのかというのは確率的であるというのである。例えば、風呂場に漂う湯気(水の分子)は時間によってあちこちに存在する。ひょっとしてある時には風呂場の一角に一斉に集まっているときがあるかもしれないが確率的にはそんなことはまず起こりえない。それよりも風呂場全体に湯気が漂っている場合のほうがはるかにあり得る。それは水分子が風呂場のあちこちに存在する場合の数のほうが風呂場の一角に集まっている場合の数よりも天文学的といっていいほど多いからだ。すなわち、秩序正しい状態が一度崩れてしまうと、元の秩序正しいというほんのわずかな場合の数に戻ることができない。すなわち時間は一方向にしか進めないというのである。
この性質を使って、人間の存在というものの意味を解いていこうというのだが、一体、どんな解が飛び出してくるのだろうか。
物語の最初の部分は時間の始まり、すなわち宇宙の始まりから書かれているのだが、それはよくわかる。ビッグバンの直前が宇宙の中で最もエントロピーが少ない状態で、空間が広がるにつれてエントロピーが増大する。そんな中でも、重力が存在するおかげで所々にエントロピーが少ない状態ができる。それが恒星の誕生の要因になる。
しかし、それが生物にも当てはまるというのである。それはどうしてか、生物もどんどん細かく見てゆくと原子の集合体である。それならば量子物理学が解明した振る舞いに支配されているはずである。それは岩石も生物も同じなのである。
生物は分子が極度に秩序化されて形作られているので代謝や自己複製という複雑で不思議な作用をおこなうことができるというのである。いうなればエントロピーが極度に減少した状態を維持しているということになるのである。「動的平衡」という言葉も言いかえれば、極度にエントロピーが減少した状態を維持する働きであるといえるのかもしれない。
その延長線上に意識の発生がある。その意識でさえも、様々な科学者がいろいろな説を唱えているのであるが、原子が持っている物理法則に則って動いている結果であるというのである。しかし、そのメカニズムについては残念ながら解明されているわけではない。意識を作り出している脳のシナプスの数というのは、一説では10の15乗個もあるそうである。
そこで働く原子の数というと、天文学的な数字ということになるのだが、それらすべてが個々に働くことで意識というものが作られているというのだから解らなくて当然なのである。
そして、その「意識」が言葉や宗教が生み出すのである。
っそして、この本の中心をなす一番興味深い部分というのは、宇宙の中で地球人というものが生まれ意識を宿し、宗教や芸術を生み出したのはなぜかという部分だが、その前に、現在からその先に待っているときの流れ、すなわち宇宙の姿はどうなっていくのかということを書いていきたいと思う。
ビッグバンから138億年経過した宇宙は、限りなく膨張してゆくという考えといつかは収縮に転じるという考えがあるらしい。どちらに転ぶかというのは、宇宙空間に満ちているダークエネルギーの分量にかかっているそうだが、この本ではとりあえずは限りなく膨張してゆくという仮定で進められていく。
膨張し続ける宇宙空間のなかで物質=粒子はどうなってゆくか。空間が広がるにつれて物質間の距離は広がり、それは低エントロピーの物質、星や生物を構成する物質にまで及ぶ。それはそれらの物質の崩壊を意味する。もし、われわれが生き残っていたとしても、身体も同じようにバラバラに引き裂かれ原子よりも小さな単位に分解されてしまうということだ。10の14乗年後にはすべての恒星は燃料を使い果たして燃え尽きる。10の19乗年後には銀河の構成もなくなりほとんどの恒星は灰になったまま宇宙をあてどなくさまようようになる。10の24乗年後、一部の恒星だけが銀河中心にある巨大ブラックホールの周りを回転しながら次第に飲み込まれてゆく。10の30乗年後にはほとんどの銀河らか恒星はいなくなってしまう。
さらに時間が進むと、強力な重力で物質を飲み込んできたブラックホールも蒸発を始める。それは原子の崩壊を意味し、太陽サイズの質量のブラックホールは10の68乗年後には消滅してしまう。10の102乗年後には太陽質量の1000億倍という超巨大ブラックホール(そんなにでかいやつが存在するのかどうかは知らないが・・)も消えてしまう。こうなってしまうと、宇宙空間には霧のように漂う粒子が存在するだけである。
物理学者たちはこの時代を「時間の終わり」と表現し、宇宙は忘却の彼方に去り宇宙を知るものも誰もいなくなってしまう。
しかし、著者が語る宇宙の物語はここで終了するわけではない。
ヒッグス粒子というものがある。この粒子は1964年にピーター・ウェア・ヒッグスによってその存在が予言され、2012年に初めてその実在が確認された粒子だが、物質に質量を与える粒子である。この粒子はビッグバン以来安定した状態を保っているのでこの世界は安定していると言える。しかし、この粒子も永遠に安定しているわけではないらしい。その意味はまったくわからないが量子トンネル効果によって、現在の値(246.22ギガ電子ボルト)から変化する可能性がある。今から10の102乗年から10の359乗年後のどこかの時点だそうだ。そして、この変化は何を意味するかというと、宇宙空間がまったく新しい物理法則に支配されるということらしい。そんな事態がおこると、まったく新しい意識が生まれる可能性もある。
現在の物理法則がまったく新しいものに変わってしまうなどというと、もそれよりも先のことなど考えるのはまったく無駄だと思えるのだが、著者はさらに先の未来を見る。
そんな未来ではボルツマン脳という概念が語られる。
著者の考えが独特なのは、すべての根源は原子の粒子配置なのであるというところであるが、どこまでも増えてゆく指数の年月の中で、粒子の配置がある確率の偶然から人間が持つ脳組織と同じ配置になり、宇宙はいかにして出現したのだろうかと考えることができる粒子の集合体が生まれるというのである。それがボルツマン脳である。これもエントロピーの法則から導き出せる現象である。
それはもう、人類とはまったく関係がない知性ではあるが、そういった、「思考するもの」がいなくなれば宇宙そのものの存在が認識されないのだから、「思考するもの」がある限り宇宙の時間も存在し続けると言える。しかし、そのスケールは10の10乗のさらに68乗年という時間だそうだ。どれくらいの数字になるかというと、かつて印刷されたことのあるすべての本のページを0で埋めてもまだ足らないくらいだ。
もう、それは永遠と言ってもいいくらいの長さなのである。
こういう考えは現在の数学と物理学が描き出す未来なので本当にそれが的を射ているかどうかは誰にもわからない。そんな未来まで人間の意識や思考が受け継がれるとも思えないのであるが・・。
しかし、現代の物理学と数学はこういうストーリーを描くのだ。
再び現在に戻り、著者が最も不思議だと考えている、「意識」が生み出した宗教や芸術は宇宙の時間の流れの中でどういった意味付けがあるのだろうか・・。著者の考えはシンプルで説得力がある。
『宗教の多くは古いということだ。その古さが需要なのである。そのことから、主教的実践は、何千年とは言わないまでも何百年のあいだ、人々の意識をしっかり捉えてきたことがわかる。また、さまざまな取り合わせで儀式に構造を与え、この世界にはあなたの居場所があるということを人々に伝え、道徳的感性を導き、芸術的霊感を与えて作品を作らせ、あなたを英雄的な物語に参加しようと誘いかけ、死がすべての終わりではないという約束を与えてきた。もちろん、厳しい罰で脅すこともあれば、人をけしかけて戦わせることもあったし、教えに反した人々を奴隷にしたり殺したりすることを正当化することもあった。宗教は善いこともやってきたし、おぞましと言うしかないこともやった。しかし、そのすべてをやったうえで、宗教的な伝統は続いてきた。物質的実在に関する証明可能な基礎についてはまったく洞察を与えなかったが(それをするのが科学だ)、宗教は、それを信奉する人たちの一部に対し、すべては調和しているという感覚を与えてきた。その感覚が、人生に文脈を与え、よく知るものも見知らぬものも、喜びも苦しみも、より大きな物語の中に位置づけを与える。そうしてすべてを位置づけることによって、長い歴史のある宗教は、その始まりのときから今日までの信者をつなぐ系譜を提供してきたのである。』
その根源は物理法則ではなく、生物が生き残るため、すなわち進化論的な側面が強いようである。自分の血縁以外の遺伝子を残して、種としての永続を実現するためにはDNA以外の何かが必要であったに違いないというのである。
芸術もしかりである。独創性を磨き、創造性を鍛え、それはもの見方を拡張し、人々の団結を強めるというのである。
宗教的世界観と、最新の物理学が描き出す世界はあまりにもよく似ていると感じることがある。それは僕だけが思うのではなく、いろいろな人がそんな意見を書いている。釈迦や空海は実は宇宙のどこかからやってきた人ではないのかと思ったりもするのだが、著者の見解はかなりクールだ。
理解の『ハードルを下げることを第一に考えて、数学はあまり使わないようにするのが普通だ。しかし、数学は、決定的に需要な科学の拠り所なのである。どれだけ注意深く選ばれ、練り上げられた表現でも言葉は方程式を翻訳したものでしかない。そんな翻訳を、他の分野との接点を確立するための基礎にしたところで、そんなつながりが詩的な類似性のレベルを超えることはまずないのだ。』
ということがそのからくりである。凡人ほどそんな幻想をいだくということか・・。
知識のある人は、『冷え切った不毛な宇宙に向かって突き進んでいけば、「大いなるデザイン[神の計画]」などと言うものはないのだとみとめざるをえなくなる。粒子に目的が与えられているのではない。最終的な答えが深宇宙にぽっかりと浮かんで、発見されるのを待っているのでもない。』というのである。
しかし、一方で、ある粒子配置(=思考する存在)が、考え、感じ、内省する力を持つことで自分自身の存在の意味を構築することができるようになったというのである。科学は、外なる実在を理解するための強力にして精巧なツールであるが、それを認めたうえで、受け継いでいく必要のあるものは何かを把握しながら、物語や芸術、そして宗教を創り出してきたのが人類という種なのであると著者は結んでいる。
まあ、5回ぐらい読まないと、この本の意味はわからないな・・。きっと・・。
著者は、理論物理学者で超弦理論の研究者だそうだ。学生時代から自分が数学と物理学に心惹かれてきた理由を、『自然法則が心に訴えかけるのは、それが時間を超越した特性を持つからかも。では、時間を超越したものの研究、永遠に保たれるかもしれない特質の探索へと、われわれを駆り立てているものはいったい何なのだろう?もしかすると、人は時間を超越していないということ、人生には限りがあることをわれわれは知っているということが、すべての始まりなのだろうか?この考えは、少し前に気づいたばかりの数学と物理学と永遠の魅惑に関するひとつの見方と響き合って、ずばり的を射ているように思われた。それは、誰もが知っている死というものへの当然の反応に基礎づけられた、人間の動機を理解するためのひとつのアプローチだった。』
と考えた。自分の命が有限であるがゆえに無限に続くのかもしれない時間の流れ、すなわち宇宙の過去から未来への姿の解明に魅了されたということだろうか。
オットー・ランクという心理学者は、『芸術家とは創造への衝動を持つ者であり、「その衝動は、儚い人生を永遠の命に代変えようとする試み」だった。』と言う。サルトルは、『人間が「自分は永遠に存在し続けるという幻想を失う時」、人生そのものから意味が失われる』と言った。それはあたかもものを創造する能力を使って、心を苛む不安(=死への不安)に対抗する、強力な防衛手段を作り上げてきたかのようである。
この世界はどこから来てどこへ行くのか、その世界の中で僕が生きていることについてはどんな意味があるのか(多分何の意味もないと思うが・・)、そして人が生きて死ぬということとはどういうことなのか。それは科学で説明できるのか・・。序盤の部分を読んでいるとこの本は僕が知りたいと思ってきたことの集大成のような気がした。まあ、個人が生きている限り、その人に見合った能力に応じてでしかないがその意味を知りたいと思うのに違いない。
芸術の探求から科学の発見まで、人類の文化のかなりの部分は、限りある生命の本性について思索する生命によって駆動される。これを著者は人間文明の統一理論と呼ぶ。
目次を見てみると、時間の始まりから生命の誕生、意識の獲得、言語、信仰・・そして時間の終わりすなわち宇宙の終焉、そういったものを物理学の理論を使って説明しようというのである。
宇宙の始まりや時間の流れというのは物理学となじみが深いと思うが、意識や信仰というとどうもそうとは思わないけれどもやはり物理法則に支配されているというのである。
まあ、結果から先に書くと、それは現在のところ見つけられてはいない。もし見つけることができていたのならこの本よりも早くニュースになり、テレビの科学番組が取り上げているだろう。
しかし、著者の考えというのは非常に興味がある。これまで3000年以上の間、幾多の哲学者や科学者がこの問題に取り組んできたのだが、そういった歴史を交えながらひょっとしたらこうなのではないかということを最新の物理学理論を使って考察している。
それをなんとか凡人にもわかるようにと一所懸命600ページ近くにわたって解説してくれているのだが如何せん凡人以下の脳みそではなかなかそうもいかない。
いつもの通り、ぼくが勝手にこうなのかなと考えたことを書いてゆく。
この統一理論のキーのひとつとなるのが「エントロピー」だという。エントロピーとは、熱力学の第二法則に基づく考え方である。物質の状態は必ずエントロピーが少ない状態から増大する方向に変化するというものだ。もっと簡単に言うと、世界は必ずカオスの状態に向かうというものである。そしてこのエントロピーが、時間は一方向にしか流れないということを決定づけているという。
それはどういうことか。
物理法則というのは未来と過去を区別しないのであるが、秩序正しい状態が出現する確率とまったくランダムな状態が出現する確率とを比べるとランダムな状態が出現する確率のほうがはるかに高いのでエントロピーが増大した状態(カオス状態)はエントロピーが少ない状態(秩序正しい状態)には確率的に戻ることはまずないので時間を巻き戻すことはできないというわけだ。
うまく表現できていないのだが、物質の状態を分子レベルで見てみると、それぞれの分子がどの位置にあるのかというのは確率的であるというのである。例えば、風呂場に漂う湯気(水の分子)は時間によってあちこちに存在する。ひょっとしてある時には風呂場の一角に一斉に集まっているときがあるかもしれないが確率的にはそんなことはまず起こりえない。それよりも風呂場全体に湯気が漂っている場合のほうがはるかにあり得る。それは水分子が風呂場のあちこちに存在する場合の数のほうが風呂場の一角に集まっている場合の数よりも天文学的といっていいほど多いからだ。すなわち、秩序正しい状態が一度崩れてしまうと、元の秩序正しいというほんのわずかな場合の数に戻ることができない。すなわち時間は一方向にしか進めないというのである。
この性質を使って、人間の存在というものの意味を解いていこうというのだが、一体、どんな解が飛び出してくるのだろうか。
物語の最初の部分は時間の始まり、すなわち宇宙の始まりから書かれているのだが、それはよくわかる。ビッグバンの直前が宇宙の中で最もエントロピーが少ない状態で、空間が広がるにつれてエントロピーが増大する。そんな中でも、重力が存在するおかげで所々にエントロピーが少ない状態ができる。それが恒星の誕生の要因になる。
しかし、それが生物にも当てはまるというのである。それはどうしてか、生物もどんどん細かく見てゆくと原子の集合体である。それならば量子物理学が解明した振る舞いに支配されているはずである。それは岩石も生物も同じなのである。
生物は分子が極度に秩序化されて形作られているので代謝や自己複製という複雑で不思議な作用をおこなうことができるというのである。いうなればエントロピーが極度に減少した状態を維持しているということになるのである。「動的平衡」という言葉も言いかえれば、極度にエントロピーが減少した状態を維持する働きであるといえるのかもしれない。
その延長線上に意識の発生がある。その意識でさえも、様々な科学者がいろいろな説を唱えているのであるが、原子が持っている物理法則に則って動いている結果であるというのである。しかし、そのメカニズムについては残念ながら解明されているわけではない。意識を作り出している脳のシナプスの数というのは、一説では10の15乗個もあるそうである。
そこで働く原子の数というと、天文学的な数字ということになるのだが、それらすべてが個々に働くことで意識というものが作られているというのだから解らなくて当然なのである。
そして、その「意識」が言葉や宗教が生み出すのである。
っそして、この本の中心をなす一番興味深い部分というのは、宇宙の中で地球人というものが生まれ意識を宿し、宗教や芸術を生み出したのはなぜかという部分だが、その前に、現在からその先に待っているときの流れ、すなわち宇宙の姿はどうなっていくのかということを書いていきたいと思う。
ビッグバンから138億年経過した宇宙は、限りなく膨張してゆくという考えといつかは収縮に転じるという考えがあるらしい。どちらに転ぶかというのは、宇宙空間に満ちているダークエネルギーの分量にかかっているそうだが、この本ではとりあえずは限りなく膨張してゆくという仮定で進められていく。
膨張し続ける宇宙空間のなかで物質=粒子はどうなってゆくか。空間が広がるにつれて物質間の距離は広がり、それは低エントロピーの物質、星や生物を構成する物質にまで及ぶ。それはそれらの物質の崩壊を意味する。もし、われわれが生き残っていたとしても、身体も同じようにバラバラに引き裂かれ原子よりも小さな単位に分解されてしまうということだ。10の14乗年後にはすべての恒星は燃料を使い果たして燃え尽きる。10の19乗年後には銀河の構成もなくなりほとんどの恒星は灰になったまま宇宙をあてどなくさまようようになる。10の24乗年後、一部の恒星だけが銀河中心にある巨大ブラックホールの周りを回転しながら次第に飲み込まれてゆく。10の30乗年後にはほとんどの銀河らか恒星はいなくなってしまう。
さらに時間が進むと、強力な重力で物質を飲み込んできたブラックホールも蒸発を始める。それは原子の崩壊を意味し、太陽サイズの質量のブラックホールは10の68乗年後には消滅してしまう。10の102乗年後には太陽質量の1000億倍という超巨大ブラックホール(そんなにでかいやつが存在するのかどうかは知らないが・・)も消えてしまう。こうなってしまうと、宇宙空間には霧のように漂う粒子が存在するだけである。
物理学者たちはこの時代を「時間の終わり」と表現し、宇宙は忘却の彼方に去り宇宙を知るものも誰もいなくなってしまう。
しかし、著者が語る宇宙の物語はここで終了するわけではない。
ヒッグス粒子というものがある。この粒子は1964年にピーター・ウェア・ヒッグスによってその存在が予言され、2012年に初めてその実在が確認された粒子だが、物質に質量を与える粒子である。この粒子はビッグバン以来安定した状態を保っているのでこの世界は安定していると言える。しかし、この粒子も永遠に安定しているわけではないらしい。その意味はまったくわからないが量子トンネル効果によって、現在の値(246.22ギガ電子ボルト)から変化する可能性がある。今から10の102乗年から10の359乗年後のどこかの時点だそうだ。そして、この変化は何を意味するかというと、宇宙空間がまったく新しい物理法則に支配されるということらしい。そんな事態がおこると、まったく新しい意識が生まれる可能性もある。
現在の物理法則がまったく新しいものに変わってしまうなどというと、もそれよりも先のことなど考えるのはまったく無駄だと思えるのだが、著者はさらに先の未来を見る。
そんな未来ではボルツマン脳という概念が語られる。
著者の考えが独特なのは、すべての根源は原子の粒子配置なのであるというところであるが、どこまでも増えてゆく指数の年月の中で、粒子の配置がある確率の偶然から人間が持つ脳組織と同じ配置になり、宇宙はいかにして出現したのだろうかと考えることができる粒子の集合体が生まれるというのである。それがボルツマン脳である。これもエントロピーの法則から導き出せる現象である。
それはもう、人類とはまったく関係がない知性ではあるが、そういった、「思考するもの」がいなくなれば宇宙そのものの存在が認識されないのだから、「思考するもの」がある限り宇宙の時間も存在し続けると言える。しかし、そのスケールは10の10乗のさらに68乗年という時間だそうだ。どれくらいの数字になるかというと、かつて印刷されたことのあるすべての本のページを0で埋めてもまだ足らないくらいだ。
もう、それは永遠と言ってもいいくらいの長さなのである。
こういう考えは現在の数学と物理学が描き出す未来なので本当にそれが的を射ているかどうかは誰にもわからない。そんな未来まで人間の意識や思考が受け継がれるとも思えないのであるが・・。
しかし、現代の物理学と数学はこういうストーリーを描くのだ。
再び現在に戻り、著者が最も不思議だと考えている、「意識」が生み出した宗教や芸術は宇宙の時間の流れの中でどういった意味付けがあるのだろうか・・。著者の考えはシンプルで説得力がある。
『宗教の多くは古いということだ。その古さが需要なのである。そのことから、主教的実践は、何千年とは言わないまでも何百年のあいだ、人々の意識をしっかり捉えてきたことがわかる。また、さまざまな取り合わせで儀式に構造を与え、この世界にはあなたの居場所があるということを人々に伝え、道徳的感性を導き、芸術的霊感を与えて作品を作らせ、あなたを英雄的な物語に参加しようと誘いかけ、死がすべての終わりではないという約束を与えてきた。もちろん、厳しい罰で脅すこともあれば、人をけしかけて戦わせることもあったし、教えに反した人々を奴隷にしたり殺したりすることを正当化することもあった。宗教は善いこともやってきたし、おぞましと言うしかないこともやった。しかし、そのすべてをやったうえで、宗教的な伝統は続いてきた。物質的実在に関する証明可能な基礎についてはまったく洞察を与えなかったが(それをするのが科学だ)、宗教は、それを信奉する人たちの一部に対し、すべては調和しているという感覚を与えてきた。その感覚が、人生に文脈を与え、よく知るものも見知らぬものも、喜びも苦しみも、より大きな物語の中に位置づけを与える。そうしてすべてを位置づけることによって、長い歴史のある宗教は、その始まりのときから今日までの信者をつなぐ系譜を提供してきたのである。』
その根源は物理法則ではなく、生物が生き残るため、すなわち進化論的な側面が強いようである。自分の血縁以外の遺伝子を残して、種としての永続を実現するためにはDNA以外の何かが必要であったに違いないというのである。
芸術もしかりである。独創性を磨き、創造性を鍛え、それはもの見方を拡張し、人々の団結を強めるというのである。
宗教的世界観と、最新の物理学が描き出す世界はあまりにもよく似ていると感じることがある。それは僕だけが思うのではなく、いろいろな人がそんな意見を書いている。釈迦や空海は実は宇宙のどこかからやってきた人ではないのかと思ったりもするのだが、著者の見解はかなりクールだ。
理解の『ハードルを下げることを第一に考えて、数学はあまり使わないようにするのが普通だ。しかし、数学は、決定的に需要な科学の拠り所なのである。どれだけ注意深く選ばれ、練り上げられた表現でも言葉は方程式を翻訳したものでしかない。そんな翻訳を、他の分野との接点を確立するための基礎にしたところで、そんなつながりが詩的な類似性のレベルを超えることはまずないのだ。』
ということがそのからくりである。凡人ほどそんな幻想をいだくということか・・。
知識のある人は、『冷え切った不毛な宇宙に向かって突き進んでいけば、「大いなるデザイン[神の計画]」などと言うものはないのだとみとめざるをえなくなる。粒子に目的が与えられているのではない。最終的な答えが深宇宙にぽっかりと浮かんで、発見されるのを待っているのでもない。』というのである。
しかし、一方で、ある粒子配置(=思考する存在)が、考え、感じ、内省する力を持つことで自分自身の存在の意味を構築することができるようになったというのである。科学は、外なる実在を理解するための強力にして精巧なツールであるが、それを認めたうえで、受け継いでいく必要のあるものは何かを把握しながら、物語や芸術、そして宗教を創り出してきたのが人類という種なのであると著者は結んでいる。
まあ、5回ぐらい読まないと、この本の意味はわからないな・・。きっと・・。