なぜ長谷川等伯「松林図屏風」を現代的に感じるのか?
疑問は疑問のまま帰ってきて、「別冊太陽」を読んでいたら、
鈴木廣之さんが「神品・『松林図』を描く」と題されて
松林図の成立の謎について述べられていて、参考になりました。
どうやら松林図はもともと屏風画ではなく、
もっと大きな障壁画の草稿として書かれたものらしいのです。
それは印が通常のものではないこと、
紙が薄手のものであり張り合わせ方が異例であること、
構図が屏風画としては不自然であることからの推測らしいのです。
鈴木さんはさらにその襖や壁貼り付けといった障壁画が
どのような場所に貼られる予定であったかを推測、
西と北の2面を直角に使い、
左隻右上の遠景雪山を中心とする構図であったであろうとされています。
松の木の配置も、屏風に貼りなおされたものは
松林が左右に広がる感じですが、
もともとは上下にずれているのでもっと変化に富んでいて、
雪山を中心とした奥行きが出ます。
そうなのか!(´・ω・`)
と思ったのは、草稿であったという点です。
緩みのない渾身の作でありながら、
草稿の未完成感が私をひきつけるのかもしれません。

松林図の描法については没骨描(もっこつびょう・・輪郭線を用いない)で
撥墨(はつぼく・・墨を撥ね散らかすように用いる)と
渇筆(かっぴつ・・生乾きの筆を擦り付けるように用いる)の技法が
目につくそうです。
画面に近づくと荒々しい筆致が見え、
ものの形は遠ざかることによって見えてきます。
ここからは鈴木さんの文章があまりに素晴らしいので
引用させていただきます。(p102)
「画面に近づいたり離れたり、何度も繰り返すと、墨と筆の痕跡がぎりぎりのところで、ものの形を維持しているのがわかってくる。松の松露はこの位置にないと、のたくる蛇のようにしか見えないのだろう。撥ねとんだ墨の飛沫や穂先の乱れが松の葉叢に見えるかどうかは疑問だ。
ここではすべての形象が偶然性に依存している。描き直しの許されない水墨で、これほど大きな画面を破綻なく仕上げるには、筆のタッチの偶然性にかける大胆さと、暴走しがちな筆の動きを巧みにコントロールする繊細さを併せもつ、高度の技術と熟練が求められる。
・・草稿といえども、本番さながらの気迫をもって描き切らなけば、完成することのできない描法なのだ。」
日本画は何故こんなにも明るくて破綻なく完成されているのだろう
という疑問は以前からもっていて、
それは岩絵具の特性からくることなのだと教えられましたが、
その物足りなさを補って完全に満足させるものが
この画には感じられました。
荒々しい筆致を用いながら、
色彩豊かにきっちりと描き込んできた画面の密度が、
水墨を用いても表現されているのでしょう。
まず御舟のデッサンに惹かれたように、
目の動きがそのまま見えるような生き生きとした線が、
私は好きなのかもしれません。
疑問は疑問のまま帰ってきて、「別冊太陽」を読んでいたら、
鈴木廣之さんが「神品・『松林図』を描く」と題されて
松林図の成立の謎について述べられていて、参考になりました。
どうやら松林図はもともと屏風画ではなく、
もっと大きな障壁画の草稿として書かれたものらしいのです。
それは印が通常のものではないこと、
紙が薄手のものであり張り合わせ方が異例であること、
構図が屏風画としては不自然であることからの推測らしいのです。
鈴木さんはさらにその襖や壁貼り付けといった障壁画が
どのような場所に貼られる予定であったかを推測、
西と北の2面を直角に使い、
左隻右上の遠景雪山を中心とする構図であったであろうとされています。
松の木の配置も、屏風に貼りなおされたものは
松林が左右に広がる感じですが、
もともとは上下にずれているのでもっと変化に富んでいて、
雪山を中心とした奥行きが出ます。
そうなのか!(´・ω・`)
と思ったのは、草稿であったという点です。
緩みのない渾身の作でありながら、
草稿の未完成感が私をひきつけるのかもしれません。

松林図の描法については没骨描(もっこつびょう・・輪郭線を用いない)で
撥墨(はつぼく・・墨を撥ね散らかすように用いる)と
渇筆(かっぴつ・・生乾きの筆を擦り付けるように用いる)の技法が
目につくそうです。
画面に近づくと荒々しい筆致が見え、
ものの形は遠ざかることによって見えてきます。
ここからは鈴木さんの文章があまりに素晴らしいので
引用させていただきます。(p102)
「画面に近づいたり離れたり、何度も繰り返すと、墨と筆の痕跡がぎりぎりのところで、ものの形を維持しているのがわかってくる。松の松露はこの位置にないと、のたくる蛇のようにしか見えないのだろう。撥ねとんだ墨の飛沫や穂先の乱れが松の葉叢に見えるかどうかは疑問だ。
ここではすべての形象が偶然性に依存している。描き直しの許されない水墨で、これほど大きな画面を破綻なく仕上げるには、筆のタッチの偶然性にかける大胆さと、暴走しがちな筆の動きを巧みにコントロールする繊細さを併せもつ、高度の技術と熟練が求められる。
・・草稿といえども、本番さながらの気迫をもって描き切らなけば、完成することのできない描法なのだ。」
日本画は何故こんなにも明るくて破綻なく完成されているのだろう
という疑問は以前からもっていて、
それは岩絵具の特性からくることなのだと教えられましたが、
その物足りなさを補って完全に満足させるものが
この画には感じられました。
荒々しい筆致を用いながら、
色彩豊かにきっちりと描き込んできた画面の密度が、
水墨を用いても表現されているのでしょう。
まず御舟のデッサンに惹かれたように、
目の動きがそのまま見えるような生き生きとした線が、
私は好きなのかもしれません。



















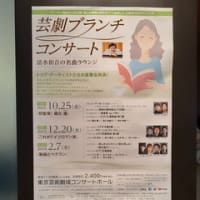
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます