今年、平成24年分の確定申告書を提出しようと思って税務署を訪れた方は、ちょっと嫌な思いをしたかもしれない。
実は昨年くらいから、一部の税務署では確定申告書の提出なら受け付けるが、申告書の作成となると署では受け付けず、他の場所に設けた確定申告の相談及び作成所に行くようになっている。
ただし、全国一律ではないので、例年通り税務署内に設けられた相談所で確定申告書を記入して提出した人もけっこういるはずだ。だが23区内など都心の税務署では、毎年と同じつもりで行ったところ、相談及び作成は他会場でやっているので、そちらに行くようにと指示されてしまう。
私の職場である銀座では、既に昨年から京橋税務署では作成会場は設けられず、大手町の国税局の一部に設けられた確定申告書作成コーナーに納税者は集められている。そのため、せっかく新富町にある京橋税務署まで来たのに、大手町へ行くようにと言われて不愉快な思いをした納税者がけっこういたらしい。
無理もない。一応、ポスターなどの情報告示もしたし、なにより税務署から送られてくる申告書を同封した封筒に、その旨を書いてあるとはいっても、長年の習慣から税務署に行ってしまう人は少なくないからだ。
大人しい都会の人たちでも苛立つ人は少なくないのだから、これを地方の税務署でやったら大変だと思う。いったい、なんだってこんなことになったのか。
以下の文は、ひねくれ者ヌマンタの独断と偏見に基づく落書きですので、そのつもりでお読み下さい。
数年前から税務署では困った事態に頭を抱えていた。2月、3月の所得税の確定申告になると、税務署の一角を片付けて申告書の作成相談場所を設けてきた。所得税の担当部署である個人課税部門の人だけでは足りず、法人税や源泉所得税、資産税部門からも応援を頼むのが通例だ。
また税理士会の支部に頼んで応援の税理士を派遣してもらい、無料相談にも応じてもらってきた。そうでもしないと、大量に訪れる相談者に応じ切ることは出来ない。日頃、税務調査の場では対立し合う税理士と税務署職員が、肩を並べて仲良く仕事をする不思議な光景でもある。
ところで、私が税法を勉強した昭和の頃に比べると、現在の税法は一段と複雑化している。法規集自体、ページ数は飛躍的に増大し、重くかさばるようになって久しい。高度成長時代は製造業や小売、卸などが経済の中心であった。
しかし、現在は3次産業とりわけサービス業の割合が増大している。そのうえ、株式、保険などの分野では従来にはなかった金融商品が毎年のように現れて、税務上の判断を迷わせる。さらに国際化の問題もある。経済活動の内容が変わりつつあるのに、税法がその変化に十分追いついていないのが実情だ。
もちろん国税当局もこの問題には早期から対処している。その結果、税務署の職員の研修時間は増え、各職員はその担当している分野にはかなり精通するようになってきている。しかし、あまりに専門分野に偏って研修をしているため、法人税課の職員は法人税に特化し、他の税目には疎くなっている。
それにもかかわらず、この確定申告の時期になると、応援のため駆り出される。多忙な最中、間違った指導をしてしまったらしい。
これは納税者の立場からすると、たまったものではない。わざわざ税務署に赴き、そこで職員から指導された通りに申告書を記入して提出したうえ納税まで済ませた。ところが6月ぐらいになって税務署から呼び出され、申告書の内容に間違いがあるので、追加の税金を払って欲しいなどと言われたら、怒らずにいられようか。
いや、怒るどころか裁判に訴え出たケースもあったようだ。まァ、裁判はその訴えた動機よりも、申告の内容の是非を問うものになるので、法令解釈を優先するので、結果、納税者敗訴のケースが多い。
ただ、税務署の指導で間違えたのだから、所得税そのものは仕方ないが、罰金的性格のある過少申告加算税は免除された判決が出ている。これを国税当局は大いに気にしていたらしい。
数年前から、申告書は納税者本人が記入するようにとの通知があり、それまで無料相談会で私ら税理士や税務署職員が記入していたのに、納税者に記入させる方式に変更されたのが皮切りだった。
ついには税務署内での申告書作成まで止めてしまい、わざわざ他の施設を借りて申告書作成会場を設ける始末。当たり前だが、相談に来た納税者に対応するのは、税務署の個人課税部門を中心とした職員と応援の税理士である。一応は精鋭を揃えたことになっている。でも、わざわざ税務署のではなく、他会場を借りる必要あったのか?
意地悪な私は、それで責任回避したつもりなのかと、ついつい文句を言いたくなる。
でも言わない。だって間違えて指導してしまった税務署職員の気持ちは良く分かるから。これだけ多様化し、複雑化した経済のなかで、見たこともない、聞いたこともない新しい金融取引は珍しくもない。
現に私自身、この所得は課税対象なのは分かるが、どの所得区分(十種類あり、計算方法がそれぞれ異なる)なのか迷うことは珍しくない。法令を精読しても、複数の解釈が可能だし、通達集や質疑応答集にも該当する事例はない。ただ近似の事例から推察するしかない。
迷った末に自分なりに納得した申告書を作成し提出してから、やっぱりあれは訂正すべきだったのかも?と迷うことさえある。同じ悩みを抱える税理士の先生方は少なくないし、税務署の職員も同様だ。
せっかく申告会場で相談して申告書を作成し、提出して納税までした。それなのに数か月後に呼び出されて、申告書の内容に間違いがあると言われたら、誰だって納得いくわけない。追徴税額を納めねばならぬだけでなく、過少申告加算税や延滞税まで納めねばならぬ。これじゃあ頭に来るのも良く分かる。
いささか暴言なのは承知しているが、納税者に税務当局が明確な判断を示せないような新しい経済行為による所得について,その是正のための修正申告に過少申告加算税を課すことは止めたほうがいいと思う。利息である延滞税は致し方ないが、罰金的性格の強い加算税はこの場合相応しくないと思う。
煮え切らない怪物、それが故・ジャンボ鶴田であった。
日本人離れした長身だけでなく、バランスのとれた頑健な体格、怪物じみたスタミナと優れた運動神経。その才能は、おそらくは日本人プロレスラー随一であったと思われる。
ただし、その実力をプロレスのリングの上で100%発揮したことはなかった。その事は引退後、鶴田自身がインタビューで明言しているが、そんなことはプロレスファンなら皆が知っていた。
手抜きとは言わない。根は真面目な鶴田は、それなりにプロレスのファイトを演じていた。だが、本当に実力があったがゆえに、本気を出すことを控えていた。真面目なだけに、その演技は完璧とは程遠くて、それゆえに手加減していることが観客にばれてしまっていた。
もちろん、そのことを痛感していたのは対戦したプロレスラーたちだろう。ジャンボのぬるい試合ぶりに苛立ち、その本気を引き出そうとした選手もいた。新日を離脱して全日に乗り込んだ長州力もその一人だ。
韓国籍の長州は、オリンピックの韓国レスリング代表としての実績を持つ実力派だ。それだけに、同じオリンピック代表(日本)であった鶴田には猛烈なライバル意識を燃やしていたのだろう。
闘志を燃やしていきり立つ長州とは裏腹に、淡々とリングの中央に構える鶴田は、なんでそんなにむきになるの?と言わんばかりの醒めた態度。実力派として定評あった長州ではあるが、率直に言って鶴田の牙城を崩すことは出来なかった。
その光景を見て、密かに闘志を燃やしていたのが、鶴田の下で永遠のナンバー3(もちろんトップはジャイアント馬場)のポジションに甘んじていた天龍源一郎であった。
同門対決であり、当初渋っていた馬場も鶴田との対戦を望む天龍の熱い闘志を抑えることが出来なかった。そして、天龍こそがジャンボ鶴田の本気の一端を引き出した唯一の日本人レスラーとなった。
角界出身の天龍は、その打たれ強い頑健な身体で鶴田を追い詰めた。追い詰められて初めて鶴田は、本気の技を出した。それがアマレス仕込みの本格的なバックドロップであった。
試合を観ていた観客が、思わず悲鳴を挙げたくなるほどの高角度、高スピードのバックドロップで、天龍をマットに叩きつけた。朦朧としながらも天龍が立ち上がった時には、それだけで観客席から拍手が沸いたほどだ。
結果的には、天龍は鶴田に勝てなかった。それどころか、首に大きな怪我を負ってしまったほどだ。だが、プロレスファンは、鶴田の本気を引き出した天龍の心意気を忘れはしなかった。鶴田自身は、天龍に怪我を負わせたことを負い目に思っていたようだが、この試合以降あからさまな手抜き試合をしなくなったのも事実だ。
なお、この試合の後、何度か二人は戦っているが、最後に天龍が勝って三冠王者となったのは、プロレス的展開であったと思っている。私個人は天龍が鶴田に勝った試合よりも、鶴田の本気を引き出して負けた試合の方を高く評価している。
煮え切らない怪物、ジャンボ鶴田は、その後観客を沸かせる試合をすることを強く意識するようになったと思う。ただし、相手選手を怪我させるような技を駆使することは、今まで以上に控えるようになった。その代わりに、観客の雰囲気を読んで、相手の技を今までより受け、そのうえで見栄えのする技で勝つように心がけるようになった。
全日の若大将と言われたジャンボ鶴田は、今や人気では天龍に差を付けられていたことを自覚せざるを得なかったのだろう。結果、鶴田の試合ぶりは、以前よりも盛り上がるようになったのだから、天龍の功績は大きいと思う。
決して全力を出さないジャンボ鶴田の本気を引き出した天龍は、あの試合に負けても勝負に勝ったと私は信じています。
東京(本当は千葉だが)のディズニーランドには何度となく足を運んでいる。
ほぼ、毎回というか定番になっているアトラクションの一つにモンスターズ・インクがある。だいたい1時間から2時間ちかく並んで乗り物に乗って、ライトで照らして得点を挙げる他愛無い遊びだ。
何度も乗っているので、なんとなく分かった気になっていたが、今回3D版の映画を観て気が付いた。私、この映画観るの初めてだ。
おそらく子供向けを強く意識しているためだと思うが、3Dの感覚は薄い。あの眼鏡をかけていなければ、3Dだと気付かないぐらいだ。だから、敢えて3Dにする意義はなかったようにさえ思った。
おそらく強すぎる三次元映像(3D)は、子供によっては気分が悪くなることへの対処だと思う。私の周囲でも、子供とりわけ幼い子供が3D映画を観て気持ち悪いと言っていた話は聞いている。特に3D映画の嚆矢といっていい「アバター」が顕著であったらしい。
三次元感覚を強調すると、どうしても不自然な映像にならざるを得ないのではないかと私は思っている。私自身、弱視に近いほどの近視であり、乱視もあるので、ときおり3D映画に、目が疲れると感じることがある。
もっとも、この疲労感は最近の3D映画では感じていないので、映画業界も相当に力を入れて改善しているのだろうとも思っている。でも、今までの2D映画が3Dに劣るとは思えない。無理に3D化する必要はないはずだ。
にもかかわらず、かつての名作が3D映画としてリメイクされているのは、おそらくは経営上の理由だと思う。3D撮影技術には、相当な資金が投入されているはずだ。その投下資金を回収するためには、まったくの新作を作るよりも、かつての名作をリメイクした方がリスクは少ないと投資家たちは考えているはずだ。
現在の映画、とりわけハリウッド映画は、その映画製作費用を投資家から募るケースが非常に多い。映画は投資として結構リスクが高い。専門家の評価は高くても人気の出ない作品もあるし、その逆のケースも珍しくない。
確実に投下資金を回収したいと考えれば、はやりかつてのヒット作のリメイクは魅力的なのだろう。3Dに代表される高い撮影技術の行使には、高額な撮影機具が必要不可欠だし、映像をコンピューターで編集するのにも多額の経費がかかる。その資金のためにも、名作のリメイクは必要不可欠な経営戦略なのだろう。
あれこれ金勘定の面から理屈をこねたが、その一方で映画自体は十二分に楽しめたのも事実だ。しかも、サリーとマイクの学生時代を描いた次回作が現在制作中であるらしい。その前座としても悪くない。
単なる時間潰しのつもりでしたが、十分楽しめた作品でしたよ。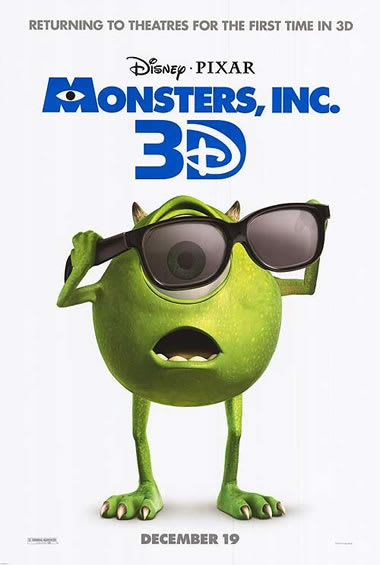
お金は怖い。
怖いものだからこそ、細心の注意と覚悟が必要なものだとも思っている。お金の基本的性質は流通手段であったはずだ。物々交換の域を超えて、物資の流通を円滑に行う手段として、通貨は非常に効率のよいものであった。
だが、お金は財産としての性格も有する。安定した生活を保証するだけでなく、人よりも豊かな生活さえ実現してくれる。使い方次第では、権力にさえ成りうる。
しかも、お金には色はつかない。コツコツと貯めようと、他人から強奪しようと、お金そのものには変わりはない。それゆえに、古来よりお金は犯罪につきものであった。
今、曖昧にお金と書いたが、金地金はともかく、通常お金の価値は通貨として測られる。もっといえば、お金は国家が通貨として保証して初めてお金になる。
通貨は国家なくしてありえない。もちろん過去においてはディナール金貨のように、複数の国家間どころか、広大な地域にあっても通貨として通用したものもあった。
しかし、それは金や銀といった稀少金属の含有あってのもの。今日のように経済規模が飛躍的に拡大した世界では、金や銀といった稀少金属は通貨の主役とはなりえない。あまりに量が少なすぎるのだ。
今日のこの超巨大な経済市場を支える通貨の大半が、金銀との兌換を前提としない国家保証の通貨なのも当然のことだ。
ところが巨額のお金を有するようになったもの(個人、法人問わず)は、自分の有するお金について国家の干渉を嫌うようになる。つまり税金というコストを国家に払いたくない。
そこから生まれたのが所謂タックスヘイブンだ。租税回避地とされ、ケイマン諸島や香港などが有名だ。先進国の政府は、このタックスヘイブンを利用した脱税を抑制しようと、様々な会議を開き情報を集めて努力している。
しかし、未だ根絶には程遠く、むしろ租税回避の手段は巧妙化しているのが現状だろう。無理もないと思う。私に言わせればロンドンのシティだって広い意味ではタックスヘイブンに思えるし、アメリカとりわけデラウェア州なんざ政府ぐるみでタックスヘイブン政策を推進しているようにみえてならない。
ところがアルカイーダによる9、11以降、少し風向きが変わった。タックスヘイブンがテロ組織のマネーロンダリング(資金洗浄)に使われている現実が明らかになったからだ。
対テロ・ヒステリーに陥ったアメリカのせいで、匿名口座などは極めて作るのが難しくなっているようだ。もっとも、自分の稼ぎを税金にもっていかれたくないと考える人は、あいも変わらず跡を絶たず、新たな租税回避の手段が考案されては、それを各国政府が追いかけることにも変わりはない。
表題の作品は、そんなタックスヘイブンの実情を舞台に描かれている。比較的分かりやすいと思うので、興味がありましたら是非どうぞ。個人的には、税理士として色々考えさせられた問題作です。
馬鹿だから貧乏。
かなり乱暴な言い様だとは思うが、否定しがたいのは真実の一面をついているからだ。実際問題、貧乏人の子は貧乏人に育つことが少なくない。もちろん例外も数多あることは知っている。
だが貧乏から抜け出した人の大半は、家庭での躾がしっかりしてた人たちだ。倹約に励み、地味な仕事を厭わず、華美に走らず、酒や賭け事に手を出さない。学校では教わらない人生の基本だと思うが、これを実践してきたからこそ貧乏から抜け出せた。
それとは逆に親が馬鹿だから貧乏である場合、それを見て育った子供も馬鹿に育ち、結果的に貧乏となることが多い。
かつて社会主義がまだ輝きを失ってなかった頃、真面目な共産党の政治家が「資本主義こそが貧乏の原因です。貪欲な資本家から労働者の正当な権利を取り戻さなければイケません」と叫んでいるのを聴きながら、私は違和感を禁じ得なかった。
資本主義だろうが、社会主義だろうが、馬鹿は馬鹿のままじゃないか?
私は知っていた。いくら金を稼いでも、馬鹿はその金を馬鹿らしいことに使ってしまう。稼ぐ以上に使ってしまい、残ったのは借金ばかり。馬鹿が貧乏なのは当たり前じゃないか。
進学する気がないゆえに勉強に興味はなかったが、馬鹿で貧乏なのは嫌だったので、本だけは読んでいたのは知識欲だけが理由ではなかった。世の中の仕組みが分かっていれば、学歴がなくても稼げることを知っていたからでもある。
もっとも馬鹿でもなく、学歴もあって、それでも貧乏な人がいることも知っていた。
あるいは馬鹿ではあっても、その馬鹿が愛される人がいることも知っていた。馬鹿にもいろいろあるのだと、子供心に不思議に思っていた。
実際のところ、馬鹿は強い。馬鹿は逞しい。そして馬鹿はふてぶてしい。知識はなくても腕力で乗り切ってしまう。知恵はなくてもずる賢さなら確かにある。そして常識が通じないがゆえに、世間の常識に押し潰されることがない。
若い頃はけっこう馬鹿を馬鹿にしていたが、最近はそうでもないのは、この馬鹿ゆえの強さを知ったからだと思う。
表題の作品の著者は、西原理恵子の初期の漫画で「金角」として登場していたから、西原ファンの間では有名であった。西原が用心棒として連れ歩いていたようだが、いろいろな出版社に「面白い文章を書く人」と紹介してまくっていたらしい。
暴走族あがりであり、まともな職に就いても長続きしたことなく、問題があればそのぶっとい腕で強引に解決しちゃう乱暴な大男でしかなかった。にもかかわらず、西原は見捨てることなく、彼を売り込むことを止めなかった。のちにゲッツ板谷のペンネームでライターとして活躍することになるとは、予想だに出来なかった。
いったい西原は、何時から、いかにして彼の才能を知っていたのだろうか。大ヒット作こそないが、現在は20冊近い著作を世に出しているプロのライター(原稿書き)である。
西原は、漫画やエッセーのなかで、時折板谷氏のことを「本当は優しいイイ子」だと語っている。暴走族あがりで、やくざになりかけた板谷氏を文筆業の世界に引き込み、まともに育て上げたのは、西原のお節介あってのものなのだろう。
嫌な言い方で申し訳ないが、もし西原がいなかったら板谷氏はあまりまともな人生を送ることはなかった気がする。だが、それを契機にフリーのライターとして活躍できたのは、上記の作品中にはほとんど出てこない真面目な母親の存在あってこそではないかと思っている。
この作品で散々書かれている板谷氏の祖母、父親、そして弟の馬鹿ぶりは笑うしかない見事なものだが、その家庭を裏で支える優しい母親あってこそ「本当は優しいイイ子」のゲッツ板谷氏が育ったように思う。そして、それゆえに作中にはほとんど登場しないのだろう。
無理に読むような本ではないが、暇な時に十分笑いを提供してくれる、妙におかしい本なので興味がありましたら、どうぞ。
おまけに西原&金角

















