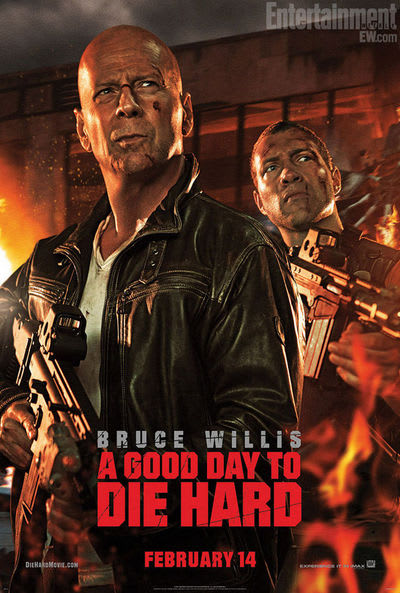大騒ぎする村人が可笑しくて、何度も大声で嘘をついた少年は、本当に狼が襲ってきたときに警告を告げても信用されませんでした。
幼い頃に読み聞かされたイソップ童話だが、おそらく北の金正恩は知らないのではないかと思う人は少なくないだろう。核実験の強行に反発する米中などの意向を受けて、国連での制裁決議に反発するのは予測の範囲内だ。
しかし、アメリカへの先制攻撃を叫ぶなど、呆れるほどに好戦的な発言が相次ぐ。もっとも、その一方で資源に乏しい北朝鮮が外国の支援なしに戦争をすることは不可能に近いことも分かっている。
だからこそ、イソップ童話を思い出して、「狼が来たぞゥ~」と叫ぶことの愚かさと危険性を危惧してしまう。しかしだ、恐らく知っていて、分かっていても叫ばざるを得ないのだろうと思う。
三代目として独裁者の座に就いた金正恩だが、実力不足というか、権力基盤はまだまだ弱い。当初、経済改革などを志向していたようだが、これが軍の反発を生んだ。
もとより頼りになるのは妹の配偶者と、母の存在であったが、軍に対する支配力は弱い。だからこそ、軍部の意向に沿わざるを得ない。ここに虚構と知りつつ「狼が来たぞゥ~」と叫ばねばならぬ理由がある。
軍の存在価値は、敵があってこそである。軍隊にとって最大の脅威とは、敵ではなく平和による存在価値の喪失である。
軍隊というものは、巨大な官僚機構でもある。官僚機構であるがゆえに、組織は硬直化しがちであり、旧来の思考に縛られる。間違っても軍隊自らが新しい時代に適応して、自ら改革を求めることはしない。
これは旧・ソ連軍でも、シナの人民解放軍でも変わりない。むしろ社会主義を掲げるような国々は、そうじて軍隊は官僚機構として肥大化する傾向が強い。もちろん、その傾向は資本主義国でも変わりはしない。
ただ、西側先進国の多くは三権(行政、司法、立法)、もしくは二権力(司法、行政)による抑制機能がある。いくら軍が既得権力保持を固守しようと、予算権限を持たぬが故に、その力は著しく弱められる。
これは現在、世界最大の規模を誇るアメリカ軍とても同様であり、軍がいくら高性能(高価格)な武器を欲しがろうと、予算を握る立法府の賛意なくしては動けない。
そのため、アメリカ軍は世界規模での軍のリストラを敢行中である。これを軍縮だと勘違いしている向きもあるようだが、まるで見当違いである。むしろ施設の集中と、高機能化を求めた動きであり、限られた予算で如何に軍事力を維持するかを目的としている。
具体的に云えば、GPSやレーダーを使って飛躍的に命中率を高めたミサイルは、目標に当たらぬ無駄を減らすための方策であり、無人の偵察機、攻撃機の開発と運用は人的被害の抑制に大きな主眼を置いている。
だからこそ、冷戦後に置いてイラク戦争をはじめテロとの戦いでも、優位を保てているのだ。そのことは、当然北朝鮮の軍首脳部だって知っている。本当にアメリカと戦火を交えることとなれば、勝つ見込みはなく、イラクのフセインのように優位な社会的地位や権勢を失うことも分かっている。
だからこそ、核兵器の開発こそが生命線なのだ。核爆弾を搭載できる弾道ミサイルあってこそ、自国の立場を保てる。いや、もっといえば、核ミサイルなくして軍隊の存在意義はない。なぜなら、北朝鮮軍は、もはや近代的戦争を遂行する能力に欠けているからだ。
北朝鮮政府にとって核兵器とミサイルが国家の生命線であると同時に、唯一世界に誇示できる武器でもある。
それは使ってはならぬ兵器であり、使ってしまえばお終いの自殺兵器でもある。だが、使わずに威嚇に使う限りにおいては、きわめて有用な手段であることは、イランやイスラエルをみれば分かること。だから半島の戦火を恐れる必要はないと思う。
むしろ注意すべきは、北の政府の権力構造の変化だろう。初代の金日成、二代目の金正日は、ほぼ完全に軍及び行政府を掌握していた。しかし、三代目は厳しいというよりも、かなり微妙な立場にあるようだ。
だからこそ、軍に媚びて「狼が来たぞゥ~」と殊更大声で叫ばねばならないのだろうと思う。
私はそう遠くない将来において、北京政府が謀略により傀儡政権を打ち立てるのではないかと想像している。これは他人事ではない。
なんとなれば、尖閣諸島どころか、沖縄に於いて親シナ寄りの政治集団を立ち上げて、日本からの独立を画策することだってやりかねない。オスプレイに反対しているような状況ではないと思いますね。
まァ、平和馬鹿の耳には届かないのは分かっているのですが・・・