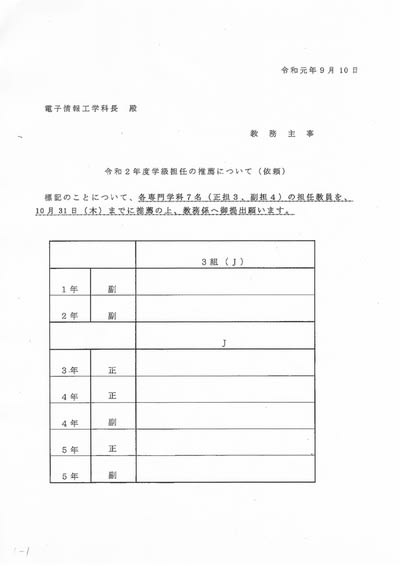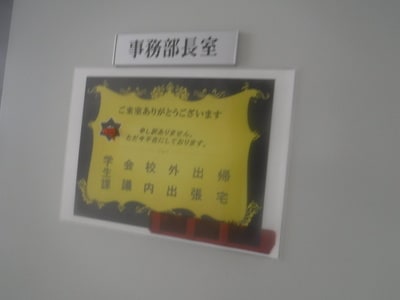■高専組織の情報隠蔽体質の是正のため、当会では2019年10月に第一次・第二次の二回にわたり高専機構を東京地裁に提訴し、「高専過剰不開示体質是正訴訟」プロジェクトとして法廷の闘いを行ってまいりました。新型コロナ禍による裁判所の機能停止や、被告高専機構とその訴訟代理人である銀座の弁護士による幾度もの卑怯な法廷戦術といった苦境に見舞われつつも、提訴から1年をかけてようやく両訴訟は結審し、同日同時刻に示し合わせて「ダブル判決」が設定されました。ところが判決言渡日となる2020年11月24日に待ち受けていたのは、被告高専機構の杜撰な言い分と姑息な法廷戦術を片端から丸々素通し状態の「ダブル不当判決」でした。
○2020年11月25日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟98%敗訴・第二次訴訟全面敗訴のダブル不当判決に仰天!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3244.html
当会では、この2件の不当判決についてそれぞれ精査と検討を重ねた結果、その両方について控訴することに決定しました。判決後、平素より心強い支援を賜っている高専関係者の方々から、「このような不当判決を絶対に許してはいけない」といった意見や投書が次々寄せられたことも、その判断を固くしました。
したがって、判決言渡から2週間目の控訴期限当日となる12月8日、東京高裁への控訴状2通を提出することにしました。

■12月8日は誰もが知る太平洋戦争開戦日です。記録によると、真珠湾攻撃が行われた1941年(昭和16年)12月8日の午前8時、中央気象台の藤原咲平台長は、陸軍大臣と海軍大臣から口頭で気象報道管制実施を命令されました。そして終戦までの3年8ヵ月間、天気予報はいっさい報じられませんでした。そうした情報管制下にあった戦時中はともかく、79年後の現代に至っても、当然開示されなければならない情報を国が非開示とする風潮が未だに続いています。
この日の午前中までに2件の控訴状を仕上げて、一審で東京地裁から返却された郵便切手の不足分を最寄りの郵便局で買い求め、6000円分の予納切手セット(当事者(原告・被告)がそれぞれ1名の場合。1セットの内訳は500円×8枚、100円×10枚、84円×5枚、50円×4枚、20円×10枚、10円×10枚、5円×10枚、2円×10枚、1円×10枚)を2セット揃えました。高崎駅14時14分発の北陸新幹線あさま618号に乗車し、15時12分に東京駅に到着しました。午前中、群馬県では日差しが出ていましたが、東京に着くと曇りになっていました。そして地下鉄丸ノ内線に乗り換え、15時24分に霞ヶ関駅に到着し、地上に出ると、裁判所の前の街路樹もすっかり色づき、樹木の上部の枯葉はずいぶん落葉しています。



■ゲートから構内に入ると、何やら玄関に向かって右手から人声がします。見ると、大勢の傍聴希望者が待機エリアで抽選を待っている様子でした。好奇心旺盛な筆者は、いったい何の裁判だろうかと傍聴事件表示板のところに近づくと「傍聴ご希望ですか」と裁判所の管理職員に声をかけていただきました。表示板には平成医療学園による処分取消訴訟とありました。国を相手取った訴訟のようです。「時間がないもので」と丁重に遠慮申し上げ、そのまま裁判所の玄関に向かいました。
※参考情報 URL ⇒ https://www.tokyo-np.co.jp/article/73146?rct=national
裁判所合同ビルの入口で、コロナ禍勃発以後常識となった手指のアルコール消毒を済ませてから、手荷物検査を通過し、中に入りました。初めに地下1階の郵便局に行き、19500円の収入印紙2枚を購入しました。これで、控訴状提出に向け準備は全て用意万端整えられました。
そして14階に上り、控訴状の提出窓口となる民事事件係(受付)を訪れました。廊下から部屋に入ると、正面に順番待ちの番号札を交付するためのディスプレーがあり、「控訴・上告」の欄を指でタッチすると「309」の番号札が印刷されて出てきました。4つの欄がありましたが、いずれも順番待ち人数はゼロとなっていました。窓口の前にある長椅子(中央部にはコロナ対策で使用禁止のテープが貼付)の端に腰かけて待機していると、すぐに中から男性職員が現れ、「309の番号札をお持ちの方どうぞ」と告げました。
■さっそく、用意してきた控訴状正本・副本各2通と予納切手2セットを提示すると、職員は「初めに切手を確認させてください」と言って、予納切手が指定の金額と枚数になっているか、一枚一枚チェックしました。今回は一審の予納切手を使いまわしているため、過不足の無いように買い足しましたが、間違っていないかと、ちょっぴり緊張しました。
予納切手が2セット共に所定の金額と枚数から構成されていることを確認した職員は、次に2件の控訴状に目を通し始めましたが、その途端、「一審の判決正本のコピーをお持ちですか?」と筆者に訊いてきました。長い活動上でもそうした質問をされたことがないため、驚いた筆者が「いいえ、コピーは持参していませんが」と返答すると、職員は「いえ、持参していなければそれで構わないのですが、こちらとしては判決正本のコピーを付けてもらえると事務手続きがスムーズにいくので、今後はそうしてもらえると助かります」とのこと。そう説明しつつ、筆者の提出したクリアファイル入りの2通の控訴状に目を落とした職員は、「ああ、こちらのクリアファイルには担当民事部の番号が書いてありますね。それならこれですぐにわかります」と言いました。職員の予期せぬ質問は、判決正本そのものが必要というよりは、担当民事部の情報が必要という趣旨だったようです。
■職員はそのまま「後ほどお呼びするまで、そこの椅子にかけてお待ちください」と言って、書類と予納切手セットを携えて自席に戻りました。数分後、男性職員が控訴状2通を持って来て、「内容を拝見しました。受け付けますので、今、印紙はお持ちですか」と訊くので、「はい、ここにあります」と持参した19500円の収入印紙セット(内訳:1万円×1、5千円×1、4千円×1、5百円×1)2組を示しました。
すると男性職員は、「では、こちらの控訴状の上部に、一番上の余白は2センチほど開けていただくようにして、また、“控訴状”と書いてある文字にかからないように、そして収入印紙同士は重ならないように、できればそれぞれ少し(数ミリずつ)離して貼ってください」と細かく指示されたので、カウンターに用意されていた水に濡れたスポンジに印紙を浸けて順番に2通の控訴状に貼っていきました。
収入印紙を貼った控訴状2通を職員に提出すると、職員は「はい、これで手続きが済みました。ここに受付票をお渡ししますので、今後何かあるときには、この事件番号を言っていただければ、すぐ対応できます」というと、奥に引っ込んでいきました。
■こうして、午後4時半前に控訴手続きが済みました。帰る前に、ひとつ確認しておかねばらないことに気がつき、14階から一旦10階の民事第2部の受付に立ち寄りました。ここでも、テレワーク推進中なのか職員が少ないようすでした。
そこに居合わせた男性書記官に声をかけて「第2部で担当いただいた令和2年(行ウ)第515号事件(当会呼称:第一次訴訟)ですが、一応原告完全敗訴ではなく一部勝訴している判決になっています。この原告勝訴部分について、被告側から控訴しているのかどうか、どこに行けば確かめられますか」と尋ねました。
すると男性書記官は、「こちらで確認できます」というので、再度事件番号を伝えると、パソコンで検索しに自席へ戻りました。そして窓口に戻ってきて「調べてみましたが、この事件では現時点でまだ控訴されていないようです」と言いました。控訴期限日の定時ギリギリの確認なので、さすがの高専機構も50分の1の敗訴部分についてわざわざ控訴することはしなかったと考えてよさそうです。
余談となりますが、控訴手続をすべて終えて裁判所出口から外に出ると、右手に傍聴抽選用の看板が撤去されないまま置かれていました。見ると、今をときめく河井夫妻の夫の方の公選法違反事件について、その日の10時に公判が開かれていたらしいことがわかりました。ところで妻の方についても、佐野太の公判と日程を被せて公判が開かれていることは以前報告のとおりです。夫婦ともども、既に数多くの公判が重ねられているようです。
※※参考情報 URL ⇒ https://www.news24.jp/feature/421/feature421_01.html
■さて、12月8日に東京地裁民事窓口に提出した第一次訴訟および第二次訴訟にかかる本件控訴状2通の内容は以下のとおりです。
*****第一次訴訟控訴状*****ZIP ⇒ 20201208iti.zip
控 訴 状
令和2年12月8日
東京高等裁判所民事部 御中
〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10(送達先)
控訴人(第1審原告) 市民オンブズマン群馬
同代表 小川 賢
電 話 090-5302-8312
(控訴人代表直通)
又は 027-224-8567
(控訴人事務局)
FAX 027-224-6624
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2番地
被控訴人(第1審被告) 独立行政法人国立高等専門学校機構
同代表理事長 谷口 功
法人文書不開示処分取消請求控訴事件
訴訟物価額 金160万円(算定不能)
貼用印紙額 金1万9500円
上記当事者間の東京地方裁判所令和元年(行ウ)第515号法人文書不開示処分取消請求事件について,令和2年11月24日に言い渡された下記判決のうち控訴人敗訴部分につき不服であるから控訴する。
第1 原判決の主文
1 被告が平成31年4月16日付けで原告に対してした法人文書開示決定のうち,別紙1記載1の部分について,項目名及び整理Noに係る情報を不開示とした部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 被控訴人が控訴人に対し,平成31年4月16日付高機総第19号法人文書開示決定において不開示とした箇所のうち,別紙に示す部分について不開示を取消せ。
2 訴訟費用は第1審,第2審ともに被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
おって,控訴理由書を提出する。
附 属 書 類
控訴状副本 1通
以上
*****控訴状別紙*****
(控訴状別紙)
控訴の趣旨1項に係る不開示処分取消請求箇所
1 平成23年4月1日付けから平成31年4月付けまでの「国立高等専門学校長候補者一覧」について,「各一覧表が扱う推薦機関の種別の表示」,「選考通過者のうち実際に校長に就任した者にかかる記載情報すべて」,「各候補者の推薦機関又はその種別に係る情報」。
2 西尾典眞の平成29年3月15日付け辞職願の不開示部分のうち辞職理由が記載された部分。
3 群馬工業高等専門学校「校報」第129号から第131号までの表紙及び人事関係の不開示部分のうち,不開示とされている同校職員すべてについて,「人事前後の同校における所属・職名にかかる情報」,とくに教育研究支援センター所属の技術補佐員については,「氏名および人事前後の同校における所属・職名にかかる情報」。
4 平成28年度から平成30年度支払決議書の不開示部分のうち,「合計金額」,「支払金額」。
5 「事件・事故等発生状況報告書【第一報】」(報告日時の時刻が1時40分のものと15時0分のもの),「事件・事故等発生状況報告書【第二報】」(6枚のものと2枚のもの),「事件・事故等発生状況報告書【最終報】」(7枚のものと4枚のもの)および「故■■■■君に関する報告書」に対する不開示箇所のうち,年月日や時刻に関する記載。
以上
**********
*****第二次訴訟控訴状*****ZIP ⇒ 20201208iti.zip
控 訴 状
令和2年12月8日
東京高等裁判所民事部 御中
〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10(送達先)
控訴人(第1審原告) 市民オンブズマン群馬
同代表 小川 賢
電 話 090-5302-8312
(控訴人代表直通)
又は 027-224-8567
(控訴人事務局)
FAX 027-224-6624
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2番地
被控訴人(第1審被告) 独立行政法人国立高等専門学校機構
同代表理事長 谷口 功
法人文書不開示処分取消請求控訴事件
訴訟物価額 金160万円(算定不能)
貼用印紙額 金1万9500円
上記当事者間の東京地方裁判所令和元年(行ウ)第549号法人文書不開示処分取消請求事件について,令和2年11月24日に言い渡された下記判決は全部不服であるので控訴する。
第1 原判決の主文
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 原判決を破棄する。本件を東京地方裁判所に差し戻す。
2 訴訟費用は第1審,第2審ともに被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
おって,控訴理由書を提出する。
附 属 書 類
控訴状副本 1通
以上
**********
■こうして、太平洋戦争の端緒となった真珠湾攻撃の日から79年目にあたる日の活動を済ませました。当会の控訴状が不備なしとして受理されれば、追って控訴人となった当会から控訴理由書を提出し、そこから被控訴人となった高専機構の控訴答弁書が返されて、控訴審の第一回口頭弁論が開かれるはこびになります。当会の実質的な不服内容となる控訴理由書は、控訴した日の翌日から起算して50日以内、すなわち2021年1月27日までに東京高裁の担当部に提出することになります。
すでに、高専組織の数々の不祥事をめぐる真相解明・責任所在の明確化・再発防止のために当会が取り組みを始めてから相当な時間が経過しています。これからも国の機関である高専組織の底の見えない闇に光を当て、腐敗・隠蔽体質を是正させるべく、果てしない活動を継続してまいります。本件推移についても、追ってご報告してまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
○2020年11月25日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟98%敗訴・第二次訴訟全面敗訴のダブル不当判決に仰天!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3244.html
当会では、この2件の不当判決についてそれぞれ精査と検討を重ねた結果、その両方について控訴することに決定しました。判決後、平素より心強い支援を賜っている高専関係者の方々から、「このような不当判決を絶対に許してはいけない」といった意見や投書が次々寄せられたことも、その判断を固くしました。
したがって、判決言渡から2週間目の控訴期限当日となる12月8日、東京高裁への控訴状2通を提出することにしました。

■12月8日は誰もが知る太平洋戦争開戦日です。記録によると、真珠湾攻撃が行われた1941年(昭和16年)12月8日の午前8時、中央気象台の藤原咲平台長は、陸軍大臣と海軍大臣から口頭で気象報道管制実施を命令されました。そして終戦までの3年8ヵ月間、天気予報はいっさい報じられませんでした。そうした情報管制下にあった戦時中はともかく、79年後の現代に至っても、当然開示されなければならない情報を国が非開示とする風潮が未だに続いています。
この日の午前中までに2件の控訴状を仕上げて、一審で東京地裁から返却された郵便切手の不足分を最寄りの郵便局で買い求め、6000円分の予納切手セット(当事者(原告・被告)がそれぞれ1名の場合。1セットの内訳は500円×8枚、100円×10枚、84円×5枚、50円×4枚、20円×10枚、10円×10枚、5円×10枚、2円×10枚、1円×10枚)を2セット揃えました。高崎駅14時14分発の北陸新幹線あさま618号に乗車し、15時12分に東京駅に到着しました。午前中、群馬県では日差しが出ていましたが、東京に着くと曇りになっていました。そして地下鉄丸ノ内線に乗り換え、15時24分に霞ヶ関駅に到着し、地上に出ると、裁判所の前の街路樹もすっかり色づき、樹木の上部の枯葉はずいぶん落葉しています。



■ゲートから構内に入ると、何やら玄関に向かって右手から人声がします。見ると、大勢の傍聴希望者が待機エリアで抽選を待っている様子でした。好奇心旺盛な筆者は、いったい何の裁判だろうかと傍聴事件表示板のところに近づくと「傍聴ご希望ですか」と裁判所の管理職員に声をかけていただきました。表示板には平成医療学園による処分取消訴訟とありました。国を相手取った訴訟のようです。「時間がないもので」と丁重に遠慮申し上げ、そのまま裁判所の玄関に向かいました。
※参考情報 URL ⇒ https://www.tokyo-np.co.jp/article/73146?rct=national
裁判所合同ビルの入口で、コロナ禍勃発以後常識となった手指のアルコール消毒を済ませてから、手荷物検査を通過し、中に入りました。初めに地下1階の郵便局に行き、19500円の収入印紙2枚を購入しました。これで、控訴状提出に向け準備は全て用意万端整えられました。
そして14階に上り、控訴状の提出窓口となる民事事件係(受付)を訪れました。廊下から部屋に入ると、正面に順番待ちの番号札を交付するためのディスプレーがあり、「控訴・上告」の欄を指でタッチすると「309」の番号札が印刷されて出てきました。4つの欄がありましたが、いずれも順番待ち人数はゼロとなっていました。窓口の前にある長椅子(中央部にはコロナ対策で使用禁止のテープが貼付)の端に腰かけて待機していると、すぐに中から男性職員が現れ、「309の番号札をお持ちの方どうぞ」と告げました。
■さっそく、用意してきた控訴状正本・副本各2通と予納切手2セットを提示すると、職員は「初めに切手を確認させてください」と言って、予納切手が指定の金額と枚数になっているか、一枚一枚チェックしました。今回は一審の予納切手を使いまわしているため、過不足の無いように買い足しましたが、間違っていないかと、ちょっぴり緊張しました。
予納切手が2セット共に所定の金額と枚数から構成されていることを確認した職員は、次に2件の控訴状に目を通し始めましたが、その途端、「一審の判決正本のコピーをお持ちですか?」と筆者に訊いてきました。長い活動上でもそうした質問をされたことがないため、驚いた筆者が「いいえ、コピーは持参していませんが」と返答すると、職員は「いえ、持参していなければそれで構わないのですが、こちらとしては判決正本のコピーを付けてもらえると事務手続きがスムーズにいくので、今後はそうしてもらえると助かります」とのこと。そう説明しつつ、筆者の提出したクリアファイル入りの2通の控訴状に目を落とした職員は、「ああ、こちらのクリアファイルには担当民事部の番号が書いてありますね。それならこれですぐにわかります」と言いました。職員の予期せぬ質問は、判決正本そのものが必要というよりは、担当民事部の情報が必要という趣旨だったようです。
■職員はそのまま「後ほどお呼びするまで、そこの椅子にかけてお待ちください」と言って、書類と予納切手セットを携えて自席に戻りました。数分後、男性職員が控訴状2通を持って来て、「内容を拝見しました。受け付けますので、今、印紙はお持ちですか」と訊くので、「はい、ここにあります」と持参した19500円の収入印紙セット(内訳:1万円×1、5千円×1、4千円×1、5百円×1)2組を示しました。
すると男性職員は、「では、こちらの控訴状の上部に、一番上の余白は2センチほど開けていただくようにして、また、“控訴状”と書いてある文字にかからないように、そして収入印紙同士は重ならないように、できればそれぞれ少し(数ミリずつ)離して貼ってください」と細かく指示されたので、カウンターに用意されていた水に濡れたスポンジに印紙を浸けて順番に2通の控訴状に貼っていきました。
収入印紙を貼った控訴状2通を職員に提出すると、職員は「はい、これで手続きが済みました。ここに受付票をお渡ししますので、今後何かあるときには、この事件番号を言っていただければ、すぐ対応できます」というと、奥に引っ込んでいきました。
■こうして、午後4時半前に控訴手続きが済みました。帰る前に、ひとつ確認しておかねばらないことに気がつき、14階から一旦10階の民事第2部の受付に立ち寄りました。ここでも、テレワーク推進中なのか職員が少ないようすでした。
そこに居合わせた男性書記官に声をかけて「第2部で担当いただいた令和2年(行ウ)第515号事件(当会呼称:第一次訴訟)ですが、一応原告完全敗訴ではなく一部勝訴している判決になっています。この原告勝訴部分について、被告側から控訴しているのかどうか、どこに行けば確かめられますか」と尋ねました。
すると男性書記官は、「こちらで確認できます」というので、再度事件番号を伝えると、パソコンで検索しに自席へ戻りました。そして窓口に戻ってきて「調べてみましたが、この事件では現時点でまだ控訴されていないようです」と言いました。控訴期限日の定時ギリギリの確認なので、さすがの高専機構も50分の1の敗訴部分についてわざわざ控訴することはしなかったと考えてよさそうです。
余談となりますが、控訴手続をすべて終えて裁判所出口から外に出ると、右手に傍聴抽選用の看板が撤去されないまま置かれていました。見ると、今をときめく河井夫妻の夫の方の公選法違反事件について、その日の10時に公判が開かれていたらしいことがわかりました。ところで妻の方についても、佐野太の公判と日程を被せて公判が開かれていることは以前報告のとおりです。夫婦ともども、既に数多くの公判が重ねられているようです。
※※参考情報 URL ⇒ https://www.news24.jp/feature/421/feature421_01.html
■さて、12月8日に東京地裁民事窓口に提出した第一次訴訟および第二次訴訟にかかる本件控訴状2通の内容は以下のとおりです。
*****第一次訴訟控訴状*****ZIP ⇒ 20201208iti.zip
控 訴 状
令和2年12月8日
東京高等裁判所民事部 御中
〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10(送達先)
控訴人(第1審原告) 市民オンブズマン群馬
同代表 小川 賢
電 話 090-5302-8312
(控訴人代表直通)
又は 027-224-8567
(控訴人事務局)
FAX 027-224-6624
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2番地
被控訴人(第1審被告) 独立行政法人国立高等専門学校機構
同代表理事長 谷口 功
法人文書不開示処分取消請求控訴事件
訴訟物価額 金160万円(算定不能)
貼用印紙額 金1万9500円
上記当事者間の東京地方裁判所令和元年(行ウ)第515号法人文書不開示処分取消請求事件について,令和2年11月24日に言い渡された下記判決のうち控訴人敗訴部分につき不服であるから控訴する。
第1 原判決の主文
1 被告が平成31年4月16日付けで原告に対してした法人文書開示決定のうち,別紙1記載1の部分について,項目名及び整理Noに係る情報を不開示とした部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 被控訴人が控訴人に対し,平成31年4月16日付高機総第19号法人文書開示決定において不開示とした箇所のうち,別紙に示す部分について不開示を取消せ。
2 訴訟費用は第1審,第2審ともに被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
おって,控訴理由書を提出する。
附 属 書 類
控訴状副本 1通
以上
*****控訴状別紙*****
(控訴状別紙)
控訴の趣旨1項に係る不開示処分取消請求箇所
1 平成23年4月1日付けから平成31年4月付けまでの「国立高等専門学校長候補者一覧」について,「各一覧表が扱う推薦機関の種別の表示」,「選考通過者のうち実際に校長に就任した者にかかる記載情報すべて」,「各候補者の推薦機関又はその種別に係る情報」。
2 西尾典眞の平成29年3月15日付け辞職願の不開示部分のうち辞職理由が記載された部分。
3 群馬工業高等専門学校「校報」第129号から第131号までの表紙及び人事関係の不開示部分のうち,不開示とされている同校職員すべてについて,「人事前後の同校における所属・職名にかかる情報」,とくに教育研究支援センター所属の技術補佐員については,「氏名および人事前後の同校における所属・職名にかかる情報」。
4 平成28年度から平成30年度支払決議書の不開示部分のうち,「合計金額」,「支払金額」。
5 「事件・事故等発生状況報告書【第一報】」(報告日時の時刻が1時40分のものと15時0分のもの),「事件・事故等発生状況報告書【第二報】」(6枚のものと2枚のもの),「事件・事故等発生状況報告書【最終報】」(7枚のものと4枚のもの)および「故■■■■君に関する報告書」に対する不開示箇所のうち,年月日や時刻に関する記載。
以上
**********
*****第二次訴訟控訴状*****ZIP ⇒ 20201208iti.zip
控 訴 状
令和2年12月8日
東京高等裁判所民事部 御中
〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10(送達先)
控訴人(第1審原告) 市民オンブズマン群馬
同代表 小川 賢
電 話 090-5302-8312
(控訴人代表直通)
又は 027-224-8567
(控訴人事務局)
FAX 027-224-6624
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2番地
被控訴人(第1審被告) 独立行政法人国立高等専門学校機構
同代表理事長 谷口 功
法人文書不開示処分取消請求控訴事件
訴訟物価額 金160万円(算定不能)
貼用印紙額 金1万9500円
上記当事者間の東京地方裁判所令和元年(行ウ)第549号法人文書不開示処分取消請求事件について,令和2年11月24日に言い渡された下記判決は全部不服であるので控訴する。
第1 原判決の主文
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 原判決を破棄する。本件を東京地方裁判所に差し戻す。
2 訴訟費用は第1審,第2審ともに被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
おって,控訴理由書を提出する。
附 属 書 類
控訴状副本 1通
以上
**********
■こうして、太平洋戦争の端緒となった真珠湾攻撃の日から79年目にあたる日の活動を済ませました。当会の控訴状が不備なしとして受理されれば、追って控訴人となった当会から控訴理由書を提出し、そこから被控訴人となった高専機構の控訴答弁書が返されて、控訴審の第一回口頭弁論が開かれるはこびになります。当会の実質的な不服内容となる控訴理由書は、控訴した日の翌日から起算して50日以内、すなわち2021年1月27日までに東京高裁の担当部に提出することになります。
すでに、高専組織の数々の不祥事をめぐる真相解明・責任所在の明確化・再発防止のために当会が取り組みを始めてから相当な時間が経過しています。これからも国の機関である高専組織の底の見えない闇に光を当て、腐敗・隠蔽体質を是正させるべく、果てしない活動を継続してまいります。本件推移についても、追ってご報告してまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】