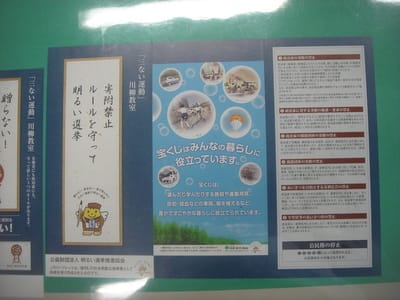■公務員の仕事の「ズサンぶり」や「楽さ加減」は、民間にはつとに知られるところですが、管理の不行き届きのために、内部の実態が外部に漏れてしまうことがたまに起きます。東日本大震災の4周年目となる平成27年3月10日に群馬県が公表した勤務中の半年間にわたるエロ画像編集作業による補佐級職員の停職15日間の懲戒処分について、2年半前にも同じような問題で企業局の次長級職員が停職2か月の懲戒処分をうけていたことから、群馬県による再発防止策が不徹底であることが判明したため、市民オンブズマン群馬では、一罰百戒の意味を込めて平成27年3月23日に住民監査請求を群馬県監査委員に提出しました。その監査結果が、同5月28日付で同29日に簡易書留で送られてきました。

**********送り状**********

20150528_adultgazouhenshu_juminkansakekka.pdf
群監第202-12号
平成27年5月28日
小 川 賢 様
群馬県監査委員 横 田 秀 治
同 丸 山 幸 男
同 久保田 順一郎
同 狩 野 浩 志
住民監査請求に係る監査結果について
平成27年3月23日付けで収受した標記請求に係る監査結果は、別紙のとおりです。
群馬県監査委員事務局
特定監査係
T E L : 027-226-2767
**********住民監査結果**********
群馬県職員措置請求監査結果
第1 請求人
安中市野殿980番地
小川 賢
前橋市文京町一丁目15番10号
鈴木庸
第2 請求書の提出
平成27年3月23日
なお、請求人に対し、同年4月3日に補正を求め、同月8日に補正が行われた。さらに、同月10日に再補正を求め、同月15日に再補正が行われた。
第3 請求の内容
1 請求書の内容(原文をそのまま掲載)
マスコミ報道によると、平成27年3月10日付で群馬県は、県庁内の行政事務用パソコンでアダルト動画などのファイルの編集作業をしたとして、会計局の50代の課長補佐(係長)の男性職員を停職15日の懲戒処分とした、県は同職員を近く移動させる方針。
群馬県人事課によると、同職員は昨年4月末~12月10日ごろ、自宅のパソコンからダウンロードした動画をUSBメモリーなどの記録媒体に保存し、それを職場に持ち込み、事務用の卓上パソコンに接続し、ファイル名の編集作業などを行った。「アダルト動画の編集作業だったため、アダルト画像の閲覧はしていない」というが、それが本人の供述なのか、人事課の独自の調査結果なのか、あるいは独自判断なのかは不明である。
また、群馬県人事課によれば、同職員は、勤務日の勤務時間中に、ほぼ毎日、平均して約30分間、アダルト動画ファイルのタイトル名の編集や、再生時間、映像の解析度等の情報書き込み編集をしていたという。また、事件発覚の経緯について人事課によれば、昨年12月10日、会計局(会計課若しくは審査課か)にある
職場のパソコンが、アダルト動画とは別の理由でウイルスに感染した疑いが生じた際に、過去のフアイル操作の履歴からアダルト動画などの編集作業が発覚したという。
報道によれば、群馬県人事課の情報として、同職員は「自宅のパソコンは家族共有のため、作業を職場でやった。猛省している」と話しているという。また、群馬県は、パソコンの業務外使用、私物の記録媒体との接続などを禁じているとしているが、この事件発覚により、平成27年3月10日に、パソコンの適正使用を徹底するよう各部署に通知して、「今後このようなことが生じないよう指導を徹底する」と話しているという。
人事課によると、「(この同職員のアダルト動画などの編集作業にかかる」一連の操作で、コンピューターウイルスに感染したことなどはなく、県庁のネットワークヘの影響は出ていない」という。その一方で、群馬県は3月10日、各部署に対して「パソコンの適正使用を徹底すること」を通知し、「今後このようなことが生じないように指導を徹底する」とマスコミに向けて話したという。
このように、群馬県は同職員を地方公務員法第30条及び34条に該当すると思しき、職務専念義務に違反したとして、わざわざ、東日本大震災から4周年目にあたる3.11の前日にあたる平成27年3月10日というタイミングを狙って、マスコミ発表に踏み切った。
群馬県では、2012年夏に勤務時間中にもかかわらず大勢の職員がソフトボール大会に興じていたことが市民オンブズマン群馬の指摘で発覚したり、同年5月から6月19日までの出勤日の勤務時聞中、企業局の男性次長(当時)が、ほぼ毎日約2時間半にわたり職場でアダルト画像などを閲覧したりして給与30万円を自主的に返納し降格を申し出て停職2か月の懲戒処分を行ったりしたことがあり、今回2年半で再び類似の不祥事が発生したことになる。
この不祥事の詳細について、請求人らは群馬県に対して直ちに公文書開示請求を行い、事実関係を正確に把握するための方策を取る所存であるが、群馬県は情報開示に消極的な姿勢をとることが懸念されるため、取り急ぎ住民監査請求を行うものである。
同職員の職務専念義務違反行為により、群馬県が被った損害としては、職務とは無関係のアダルト動画などの編集作業に費やした時間と、公務以外の目的で使用した行政事務用のパソコン使用に伴う発生費用(減耗償却ないし損耗減価償却、消費電気代など)が想定される。
請求人らは、損害額の算定に必要な情報についても上記公文書開示請求により、群馬県から入手することを考えているが、無用な時間の経過を強いられる可能性が高いため、敢えてここに住民監査請求を行うものである。
よって、監査委員は、知事に対し次のように勧告するよう求める。
「同職員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」
なお、今回の不祥事では、同職員の懲戒処分を「停職15日」としているが、停職15日間の処遇について不明である。一般論でいえば、停職中の給与は不支給となるのであろうが、この間、同職員を自宅で無為に自由時間を過ごさせるのではなく、公務員としての自覚を、身をもって認識させるために、社会福祉施設での介護補助作業、あるいは公園などの公共施設での清掃作業など、社会貢献に役立つボランティア作業に従事させること、そしてそうした義務を職員就業規則等の内規に明記することが、再発防止の観点から有効であると思料する。
2 請求内容の解釈
請求人から提出された上記措置請求書及び添付の資料並びに補正書の記述から、本件措置請求の内容を次のとおりと解した。
群馬県知事は、職務専念義務に違反して、勤務時間中に行政事務用パソコンを不適正に使用し、アダルト動画のファイル名の編集等を行っていた職員(以下「本件職員」という。)に対して、当該行為を行っていた時間分に相当する金額を減額することなく、不当に給料を支払い、群馬県に損害を与えた。
よって、群馬県知事に対し、本件職員に支払われた給料のうち、本件職員が当該パソコンの不適正使用を行っていた時間分に相当する金額を本件職員から群馬県に返還させるよう、監査委員が勧告することを求める。
3 請求人が主張する違法性・不当性
本件職員は、勤務時間中に行政事務用パソコンを不適正に使用し、アダルト動画のファイル名の編集等を行っていた(以下「本件不適正使用」という。)。これは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)に規定する職務専念義務に違反する行為であり、勤務した時間とは認められないものであるから、本件職員に対して支払われた給料のうち、本件不適正使用を行っていた時間分に相当する金額は、減額されなければならないものである。
群馬県知事がこれを減額することなく、本件職員に対して、適正な勤務があった場合に支払われるべき給料額を支払ったことは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地自法」という。)第242条第1項に規定する不当な公金の支出に当たる。
4 事実証明書等について
請求人から提出された事実証明書等は、次のとおりである。
(1)事実証明書
平成27年3月11日付け東京新聞記事
(2)群馬県職員措置請求書の補正書(平成27年4月8日提出)
(3)群馬県職貝措置請求書の再補正書(平成27年4月15日提出)
ア 添付資料1 平成27年3月31日付け市民オンブズマン群馬代表宛て公文書部分開示決定通知書
イ 添付資料2 ■■課職員行政事務用パソコン不適正使用事案概要
ウ 添付資料3 群馬県総務部人事課起案文書「職員の懲戒処分について」一式
工 添付資料4 平成27年3月10日付け各所属長(各情報セキュリティ責任者)宛て企画部長(情報統括管理者)通知「パソコン及びインターネットの適正使用について(通知)」
オ 添付資料5 平成27年4月15日付け市民オンプズマン群馬代表及び事務局長宛て群馬県総務部人事課長通知「事実確認依頼への回答について」
(4)意見書(平成27年4月22口請求人陳述時に追加提出)
5 補正書及び再補正書の内容(当委員が補正を求めた事項に対する請求人の回答を要約したもの。)
(1)群馬県職員措置請求書の補正書(平成27年4月8日提出)
ア 本件措置請求は、「知事に対して」、「懲戒処分のあった職員に群馬県が被った損害を返還するよう義務づけを求める」ものと解釈してよい。
イ 本件措置請求の対象とする財務会計上の行為は、懲戒処分を受けた職員に対して支払われた給料のうち、当該職員が勤務時間中にアダルト動画編集作業を行っていた時間分に相当する金額の支出である。
ウ イで挙げた財務会計上の行為は、地公法に規定する職務専念義務違反に当たるものであり、群馬県知事が本件職員にその時間分に相当する給料を支払ったことは、余計な人件費を無駄に費消したことになるから、群馬県に損害が発生している。
エ 本件措置請求の対象とした財務会計上の行為があったことを示す事実証明書の提出はなかった。
(2)群馬県職員措置請求書の再補正書(平成27年4月15日提出)
ア 本件措置請求の対象とした財務会計上の行為があったことを示す事実証明書として、添付資料1から5までが追加提出された。
第4 請求の受理
本件措置請求は、地自法第242条第1項に規定する要件を具備しているものと認め、平成27年4月17日に受理を決定した。
第5 監査の実施
1 監査対象事項
本件請求に係る措置請求書及び事実証明書から判断し、監査対象事項は次のとおりとした。
職務専念義務に違反する行為を行った職員に対する給料等の支出
2 監査対象機関
総務部人事課(以下「人事課」という。)
会計局会計課(以下「会計課」という。)
3 請求人の証拠の提出及び陳述
(1)証拠の提出及び陳述の機会の付与
平成27年4月22日、地自法第242条第6項の規定に基づき、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人は意見書を追加提出し、陳述を行った。
(2)請求人陳述の要旨
ア 請求対象事案の態様
本件職員は、平成26年4月29日頃から同年12月10日までの間、行政事務用パソコンを不適正に使用し、アダルト動画のファイル名の編集等を行った。1日平均の不適正使用回数は70回程度、不適正使用時間は30分程度とされている。
イ 不正行為に対する公金の支出
本件不適正使用は、法令、条例等に示された公務員の職務専念義務の免除に含まれないことは明白であり、地公法第35条に規定する職務専念義務に違反している。
ウ 損害金額
本件職員は、50代で補佐級の職員であるから、その年収は700万円を超えるものとみられるが、仮に700万円として、損害金額を算出してみる。
年収700万円を月収に計算すると、58万円を超えることになり、1日当たりの勤務時間を7.75時間と仮定して、週5日で38.75時間、月20日で155時間勤務するとした場合、1日当たり2万9,166円66銭、1時間当たり3,763円44銭となる。
本件職員の自己申告が正しいと仮定した場合、本件不適正使用を始めた平成26年4月29日から同年12月10日まで、毎日約30分程度、アダルト動画の編集作業をしていたとすれば、7か月と10日で150日間となり、職務専念義務に違反していた勤務時間数は、75時間と試算できる。
これに先ほど算出した1時間当たりの金額3,763円44銭を掛けると、28万2,258円となる。
以上は、あくまでも本件職員の自己申告によるものであり、実際にはもっと多くの時間を本件不適正使用に費やしていたと考えられる。県が行った1日平均70回程度・30分程度との集計は、到底、信用できない。1日2時間程度はアダルト動画の編集に費やしていたと考えられ、この場合、損害金額は100万円近くとなる。
群馬県監査委員においては、不当な公金の支出を是正し、損害を回復するよう、切に願うものである。
4 監査委員による対面監査の実施
平成27年5月7日、人事課及び会計課に対し、監査委員による対面監査を行った。
5 関係人調査の実施
平成27年5月1日、地自法第199条第8項の規定に基づき、本件措置請求に係る事実関係の確認のため、企画部情報政策課長(以下「情報政策課長」という。)に対し、文書による調査を行い、同月8日に回答を得た。
6 監査委員の交代
本件措置請求書が提出された時点における地自法第196条第1項の規定により議員のうちから選任された監査委員は、星野寛及び福重隆浩であったところ、平成27年5月11日付けで、久保田順一郎及び狩野浩志が新たに選任された。
本件事案については、旧委員から新委員に引継ぎを行ったほか、事務局から新委員に対して、本件措置請求の概要、経過等について、説明が行われた。
第6 監査の結果
関係書類の調査、監査対象機関への聴取等により確認した事実は、次のとおりである。
1 関連する法令等(各法令等の記載は、該当部分の抜粋である。)
(1)地公法
(服務の根本基準)
第30条すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の執行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(職務に専念する義務)
第35条職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(2)群馬県職員の給与に関する条例(昭和26年群馬県条例第55号。以下「給与条例」という。)
(給料)
第3条 給料は、群馬県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第13条の3の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び農林漁業普及指導手当を除いたものとする。
2(略)
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、・・(略)・・その勤務しない時間1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額を減額して給与を支給する。
2 人事課及び会計課の見解
(1)本件不適正使用等について
ア 本件不適正使用の概要について
本件職員は、自宅パソコンでダウンロードしたアダルト動画をUSBメモリに保存して職場に持ち込み、長期間にわたって、勤務時間中に行政事務用パソコンを使用して、その動画のファイル名を編集するなどの行為を行っていた。
編集内容は、インターネット検索で得た動画情報(女優名、作品名、配信日、商品番号等)やSMプレーヤー(動画再生ソフト)で得た動画ファイルの構成情報(再生時間、解像度等)を動画のフアイル名に書き込んでいたものである。
当該編集作業は、1件の動画フアイルにつき1回で終わるものではなく、本件職員は作業途中でファイルを保存するなどして、業務の合間で繰り返し行っていた。
イ 本件不適正使用の発覚の端緒及び経緯について
平成26年12月9日、県庁ネットワーク運用委託事業者から、企画部情報政策課(以下「情報政策課」という。)に、本件職員の行政事務用パソコンにおいて、「コンピュータ・ウイルスによる通信が行われたことを検知した記録がある」との連絡があったため、情報政策課が本件職員の行政事務用パソコンの操作履歴を確認したところ、この通信記録は誤報だったことが判明したが、別途、アダルト動画と思われるフアイルの操作履歴や女優名等のインターネット検索が行われた履歴が多数あることが分かった。
その情報は、翌10日に情報政策課から会計課に伝えられ、同日、会計課長及び会計課次長が本件職員に事実を確認したところ、本人が本件不適正使用を認めたものである。
ウ 本件不適正使用をしていた期間について
会計課では、本件職員が「平成26年4月29日頃から本件不適正使用を開始した」と主張したことから、情報政策課に対して、同月以後における本件職員の行政事務用パソコンに係るログ履歴(以下「本件ログ履歴」という。)の提供を依頼し、同年10月1日から同年12月10日までの分の提供を受けた。
エ 本件不適正使用をしていた時間等の特定について
会計課では、本件不適正使用の内容を詳細に把握するため、情報政策課から提供された平成26年10月1日から同年12月10日までの本件ログ履歴について、1件ずつ本件職員に操作内容の確認を求め、これを集計した。
その結果、1日平均の不適正使用回数は69件、使用時間は32分であった。
オ 本件ログ履歴から特定した本件不適正使用の時間等について
上記エで算定した集計結果は、本件ログ履歴において、本件不適正使用が疑われる個々の操作の開始時刻に着目して、当該操作の次の操作の開始時刻から当該操作の開始時刻を差し引いて、その時間を算定し、そこに本件ログ履歴に記録された操作内容や本件職員の申立てに基づく操作内容を当てはめ、これを集計したものであって、不適正な目的でインターネット検索を行いつつ、これと並行して本来の業務を行っていた時間等も含まれていることなどから、本件職員が実際に本件不適正使用を行っていた時間を正確に特定したものではない。
カ アダルト動画の閲覧について
本件職員は、本件不適正使用については認めているが、動画自体は閲覧していないと主張している。また、本件ログ履歴からも、動画を閲覧した事実は認められなかった。
キ 本件職員の勤務態度等について
本件職員は、本件不適正使用をしていた期間及びその前後において、勤務態度に変化はなく、特異なものは見受けられなかった。
本件職員は、業務によく精通し、係員の信頼も厚かった。平成26年度は、有給休暇もわずかな日数しか取得しておらず、遅刻、欠勤、長時間の無断離席、電話に対応しないなどの事実もなかった。
ク 本件不適正使用を現認できなかったことについて
会計課では、管理職員を含め、本件不適正使用に気が付いた者はいなかった。本件職員は、アダルト動画そのものを閲覧していたのではないことに加え、本件職員が行っていたフアイル名の編集作業を行う画面は、本件職員が業務として行っているであろうと判断される文字や数宇やアルファベットが表示された画面と、外見上、大きく異なるものではないため、極めて分かりづらい状態だった。
また、職員が勤務時間中に不適正な行為をしているはずがないという認識もあり、監視するような行為はしていなかった。
(2)職務専念義務違反について
ア 職務専念義務違反について
職務専念義務違反は、地公法第35条において、「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と規定されている。
この「勤務時間」とは、条例等に基づき割り振られた正規の勤務時間に加え、時間外勤務、週休日の勤務等を命じられて、これに服する時間も当然含まれる。
また、「職務上の注意力のすべて」とは、常識的にみてその者の有する能力を最大限に発揮せよということであって、勤務時間及び注意力の全てを物理的に職場や職務に拘束する意味ではない。
イ 本件職員の職務専念義務違反について
本件事案は、本件職員が行政事務用パソコンを業務外の目的で不適正に使用していたものであり、常識的にみて本件職員の有する能力が最大限に発揮されていないことから、職務専念義務に違反すると判断した。
(3)給与の減額等について
ア 給与条例上の給与の減額に関する規定について
職員の給与の減額に関する規定は、給与条例第10条において、「職員が勤務しないときは、・・(略)・・その勤務しない時間1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額を減額して給与を支給する」と規定されている。
イ「勤務しないとき」について
給与条例第10条に規定する「勤務しないとき」とは、人事課の取扱いとして、事前の承認手続を欠く遅刻、欠勤、勤務時間中の無断離席の繰り返し、長時間離席の場合等で、所属長がこれを現認する等により明確に特定して「勤務しないとき」と判断した場合をいうこととしている。
ウ 本件不適正使用をしていた時間の「勤務時間」の認定について
本件不適正使用は、地公法第35条に規定する職務専念義務に違反する行為であると認められるものの、自らの席において行政事務用パソコンを不適正に使用していたものであり、上司の指揮命令下から離れるなどの事実があったものではないことから、勤務時間に該当すると判断した。
なお、労働時間(勤務時間)に関して、最高裁は、「労働基準法第32条の労働時間・・(略)・・とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの・・(略)・・と解するのが相当である」(最小判平成12年3月9日)としている。
(4)その他請求人の主張に対する見解について
ア 本件措置請求書の記載事項について
(ア)本件不適正使用の事実認定について
請求人は、本件措置請求書等において、本件職員が「アダルト動画などの編集作業」をしていたと主張しているが、本件職員は、動画そのものの編集ではなく、動画のフアイル名の編集を行っていたものである。
(イ)本件懲戒処分の公表時期について
請求人は、本件措置請求書等において、本件職員の懲戒処分について、「わざわざ、東日本大震災から4周年目にあたる3.11の前日にあたる平成27年3月10日というタイミングを狙って、マスコミ発表に踏み切った」としているが、本件懲戒処分については、同年1月15日に会計課から事件報告書が提出された後、人事課において正確な事実認定を行うための追加調査を同年3月5日まで実施し、これらの結果を踏まえて、同月9日に意思決定を行い、翌10日付けで懲戒処分を行ったものである。
イ 本件職員の申告内容等の信憑性について
請求人は、陳述時において、「本件職員が本件不適正使用を開始したと申告している平成26年4月29日は祝日であり、その申告の信憑性は疑われる」としているが、人事課では、本件職員の「4月半ば頃に自宅パソコンを購入した」という申告内容と「4月29日頃から行政事務用パソコンの不適正使用を始めた」という申告内容には整合性があり、そのように事実認定するに足りると判断した。
また、請求人は、陳述時において、「職場でアダルト画像サイトにアクセスしており、“いずれにおいても鑑賞は行っていない”などということは到底信じられない」としているが、会計課の周囲の職員は、本件職員が動画を鑑賞していた様子は把握しておらず、所属の座席配置状況等を総合的に勘案しても、「鑑賞していない」という申告内容により事実認定することが適当であると判断した。
3 事実関係の確認
(1)関係人調査の結果について
情報政策課長に対して関係人調査を行った結果、本件ログ履歴のうち、データが保存されているのは、平成26年10月1日から同年12月10日までのもののみであり、同年9月30日以前のデータについては既に廃棄されており、存在しないことが確認された。
(2)本件不適正使用の事実認定等について
平成26年10月1日から同年12月10日までの本件ログ履歴の内容を調査したところ、本件職員による本件不適正使用については、その事実があったことが確認され、その件数、時間等についても、会計課が特定し、集計したとおりの件数、時間等が確認された。
また、本件不適正使用の作業を再現したところ、本件職員が行っていた編集作業は、インターネット検索で得た動画に関する情報や動画再生ソフトで得た動画ファイルの構成情報を動画のファイル名に書き込む作業であり、1回当たりの所要時間は数秒から数十秒であることが確認された。
(3)本件職員への給料の支払いについて
人事課は、本件不適正使用について、地公法第35条に規定する職務専念義務に違反する行為であると認められるものの、自らの席において行政事務用パソコンを不適正に使用していたものであり、上司の指揮命令下から離れるなどの事実があったものではないとして、本件職員が本件不適正使用をしていた期間におけるその時間分に相当する給料額を減額しておらず、又は返還を請求していなかった。
(4)本件職員による自主返納
本件職員は、平成27年5月8日付けで、群馬県知事に対して、本件職員が職務専念義務に違反して本件不適正使用をしていた期間におけるその時間分の給与相当額として、現金50万円を自主的に返還する旨の上申書を提出し、同日、同額が群馬県に納付されていた。
この金額は、本件措置請求において、請求人が本件不適正使用に関し県が被った損害であると主張する金額28万2、258円を上回るものであった。
第7 監査委員の判断
1 判断 ’
上記事実認定のとおり、本件不適正使用に係る本件職員の給料相当額については、既に本件職員から群馬県に自主的に返還されており、その納付された金額は、本件措置請求において、請求人が本件不適正使用に関し県が被った損害であると主張する金額を上回るものであることから、本件措置請求における請求人が主張する損害については、既に補填されていると認められる。
2 結論
したがって、本件措置請求は、監査を実施する理由がなくなっているものと判断し、これを却下する。
以上
********************
■このような身内の不祥事が発覚した場合、外部になるべく詳細を知らせないまま内部処理をするのが役所の傾向です。今回の不祥事でも群馬県は、当該職員への半月間の停職処分と他部署への配置換えで、済ますつもりだったのでしょう。そこに市民オンブズマン群馬から「ちょっと待った」を掛けたわけです。
しかし群馬県は、地方自治法第2条第14項「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という義務を軽視し、当会のような納税者による市民団体からの忠告に対して、常に上から目線で対応してきます。
今回の住民監査請求に対しても、監査委員の判断は「棄却」という結果に終わりました。それも、当該職員から自主的に50万円が返納されたのだから、オンブズマンの監査請求を監査する理由が消滅したのだから、監査請求そのものが不要だ、というものです。
これでは、再発防止が図れないわけです。納税者からの監査請求に対して、真摯に対応すべきなのに、結局、役所の目線で対応するのが群馬県監査委員の実態です。
しかも今回の監査では、4月12日の県議選を受けて、当会が県庁23階の監査委員事務局で陳述した際に、県議会選出の監査委員だった星野寛と福重隆浩はともに当選を果たしたのに、5月11日付で、久保田順一郎と狩野浩志に交替されてしまいました。
このうち狩野浩志は、大沢正明・群馬県知事の愛人連込みによる知事公舎妾宅化問題でも、当会の監査請求を棄却したことがあります。本人もその後認知したものの、当時、愛人との間にトラブルを抱えており、当会では、狩野浩志の監査委員としての忌避を監査委員事務局に申し立てましたが、認められませんでした。
■さて5月29日に届いた監査結果の内容を検証してみましょう。
最初に全体の感想としては、群馬県のいい加減な職員管理の実態です。
今回の群馬県監査委員の監査結果は、「エロ動画編集をしていた当該職員が自主的に50万円を返納したから、オンブズマンの言う損害額をはるかに上回っており、文句はあるまい」というものですが、オンブズマンが住民監査請求を提起しなければ、職員が自席で上司の管理下でパソコンに向かっていたのだから、時間的に拘束されていたわけなので、給与の減額は行う必要がなかったと判断していたのです。
このような考え方なので、今後とも、類似の事件が発生した場合、オンブズマンとしてその都度住民監査請求をしないと、公金の無駄遣いの是正措置が取られないことになります。
やはり、公務員同士で仲間意識に染まっているため、きちんとルールが徹底せず、曖昧な状態で判断されてしまうのです。県庁内に市民オンブズマンの監視の目を行き届かせるために、監査委員だけではなく、当会のような外部の第三者による監視を恒常的に行う体制への改善が不可避です。
■続いて、監査委員の判断の中で、首をかしげざるを得ない項目を挙げてみます。
<2度も補正を求めるなど嫌がらせ>
今回、3月23日に住民監査請求を提出後、監査委員事務局は、4月3日と4月10日に2度も当会に補正を求めてきました。こんな単純な事件なのに、明らかに時間稼ぎです。当会は、このような嫌がらせにもめげずに、迅速に補正指示に対応し、出来る限り早期に決定通知が出されるよう、終始、最善の努力を傾注しました。その結果、監査委員事務局では4月17日に受理をしましたが、結局監査請求から決定通知まで60日以上を掛けさせられてしまったのでした。
<正確な給与の減額査定根拠が示されていない>
今回の問題で、当会は当該職員(50代、補佐級)の年収を仮に700万円として、当該職員が没頭していたエロ動画編集時間を本人の申告通りの時間数と仮定して損害金額を算出した結果、28万2258円という数字を得ました。ところが、当該職員から返納された金額は2倍近い金額でした。ということは群馬県では、50代で補佐級の職員ともなると、年収が1240万円となるわけです。こんなに高給取りが、勤務中パソコンでエロ動画編集三昧できるほど暇だというのですから、公務員という職業は正に濡れ手で粟の人生が送れることを示しています。
それにつけても遺憾なのは、公務員のこうしたバブリィな給与支給の実態を、納税者である県民にきちんと公表しようとしない体質です。
<本当にエロ動画を閲覧せずに編集ができるのか>
監査結果によれば「本件職員は、自宅パソコンでダウンロードしたアダルト動画をUSBメモリに保存して職場に持ち込み、長期間にわたって、勤務時間中に行政事務用パソコンを使用して、その動画のファイル名を編集するなどの行為を行っていた。編集内容は、インターネット検索で得た動画情報(女優名、作品名、配信日、商品番号等)やSMプレーヤー(動画再生ソフト)で得た動画ファイルの構成情報(再生時間、解像度等)を動画のフアイル名に書き込んでいたものである。当該編集作業は、1件の動画フアイルにつき1回で終わるものではなく、本件職員は作業途中でファイルを保存するなどして、業務の合間で繰り返し行っていた」と記してあります。
また、「平成26年12月9日、県庁ネットワーク運用委託事業者から、企画部情報政策課(以下「情報政策課」という。)に、本件職員の行政事務用パソコンにおいて、「コンピュータ・ウイルスによる通信が行われたことを検知した記録がある」との連絡があったため、情報政策課が本件職員の行政事務用パソコンの操作履歴を確認したところ、この通信記録は誤報だったことが判明したが、別途、アダルト動画と思われるフアイルの操作履歴や女優名等のインターネット検索が行われた履歴が多数あることが分かった」とも記しています。
すなわち、当該職員は恒常的にエロ動画関連情報の収集のため、インターネットで検索をしており、ウイルス感染の疑いのあるサイトにアクセスをしていたのも一度や二度ではなかったと見られます。
にもかかわらず、「この通信記録は誤報だった」などとして、大きな原因ではないかのように取り繕っています。
この他にも、さまざまな疑義があります。
こうした中途半端な監査結果のため、さらに内容を精査したうえで、今後の対応策について、当会の例会で討議をしたうえで、方針を決定したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

**********送り状**********

20150528_adultgazouhenshu_juminkansakekka.pdf
群監第202-12号
平成27年5月28日
小 川 賢 様
群馬県監査委員 横 田 秀 治
同 丸 山 幸 男
同 久保田 順一郎
同 狩 野 浩 志
住民監査請求に係る監査結果について
平成27年3月23日付けで収受した標記請求に係る監査結果は、別紙のとおりです。
群馬県監査委員事務局
特定監査係
T E L : 027-226-2767
**********住民監査結果**********
群馬県職員措置請求監査結果
第1 請求人
安中市野殿980番地
小川 賢
前橋市文京町一丁目15番10号
鈴木庸
第2 請求書の提出
平成27年3月23日
なお、請求人に対し、同年4月3日に補正を求め、同月8日に補正が行われた。さらに、同月10日に再補正を求め、同月15日に再補正が行われた。
第3 請求の内容
1 請求書の内容(原文をそのまま掲載)
マスコミ報道によると、平成27年3月10日付で群馬県は、県庁内の行政事務用パソコンでアダルト動画などのファイルの編集作業をしたとして、会計局の50代の課長補佐(係長)の男性職員を停職15日の懲戒処分とした、県は同職員を近く移動させる方針。
群馬県人事課によると、同職員は昨年4月末~12月10日ごろ、自宅のパソコンからダウンロードした動画をUSBメモリーなどの記録媒体に保存し、それを職場に持ち込み、事務用の卓上パソコンに接続し、ファイル名の編集作業などを行った。「アダルト動画の編集作業だったため、アダルト画像の閲覧はしていない」というが、それが本人の供述なのか、人事課の独自の調査結果なのか、あるいは独自判断なのかは不明である。
また、群馬県人事課によれば、同職員は、勤務日の勤務時間中に、ほぼ毎日、平均して約30分間、アダルト動画ファイルのタイトル名の編集や、再生時間、映像の解析度等の情報書き込み編集をしていたという。また、事件発覚の経緯について人事課によれば、昨年12月10日、会計局(会計課若しくは審査課か)にある
職場のパソコンが、アダルト動画とは別の理由でウイルスに感染した疑いが生じた際に、過去のフアイル操作の履歴からアダルト動画などの編集作業が発覚したという。
報道によれば、群馬県人事課の情報として、同職員は「自宅のパソコンは家族共有のため、作業を職場でやった。猛省している」と話しているという。また、群馬県は、パソコンの業務外使用、私物の記録媒体との接続などを禁じているとしているが、この事件発覚により、平成27年3月10日に、パソコンの適正使用を徹底するよう各部署に通知して、「今後このようなことが生じないよう指導を徹底する」と話しているという。
人事課によると、「(この同職員のアダルト動画などの編集作業にかかる」一連の操作で、コンピューターウイルスに感染したことなどはなく、県庁のネットワークヘの影響は出ていない」という。その一方で、群馬県は3月10日、各部署に対して「パソコンの適正使用を徹底すること」を通知し、「今後このようなことが生じないように指導を徹底する」とマスコミに向けて話したという。
このように、群馬県は同職員を地方公務員法第30条及び34条に該当すると思しき、職務専念義務に違反したとして、わざわざ、東日本大震災から4周年目にあたる3.11の前日にあたる平成27年3月10日というタイミングを狙って、マスコミ発表に踏み切った。
群馬県では、2012年夏に勤務時間中にもかかわらず大勢の職員がソフトボール大会に興じていたことが市民オンブズマン群馬の指摘で発覚したり、同年5月から6月19日までの出勤日の勤務時聞中、企業局の男性次長(当時)が、ほぼ毎日約2時間半にわたり職場でアダルト画像などを閲覧したりして給与30万円を自主的に返納し降格を申し出て停職2か月の懲戒処分を行ったりしたことがあり、今回2年半で再び類似の不祥事が発生したことになる。
この不祥事の詳細について、請求人らは群馬県に対して直ちに公文書開示請求を行い、事実関係を正確に把握するための方策を取る所存であるが、群馬県は情報開示に消極的な姿勢をとることが懸念されるため、取り急ぎ住民監査請求を行うものである。
同職員の職務専念義務違反行為により、群馬県が被った損害としては、職務とは無関係のアダルト動画などの編集作業に費やした時間と、公務以外の目的で使用した行政事務用のパソコン使用に伴う発生費用(減耗償却ないし損耗減価償却、消費電気代など)が想定される。
請求人らは、損害額の算定に必要な情報についても上記公文書開示請求により、群馬県から入手することを考えているが、無用な時間の経過を強いられる可能性が高いため、敢えてここに住民監査請求を行うものである。
よって、監査委員は、知事に対し次のように勧告するよう求める。
「同職員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」
なお、今回の不祥事では、同職員の懲戒処分を「停職15日」としているが、停職15日間の処遇について不明である。一般論でいえば、停職中の給与は不支給となるのであろうが、この間、同職員を自宅で無為に自由時間を過ごさせるのではなく、公務員としての自覚を、身をもって認識させるために、社会福祉施設での介護補助作業、あるいは公園などの公共施設での清掃作業など、社会貢献に役立つボランティア作業に従事させること、そしてそうした義務を職員就業規則等の内規に明記することが、再発防止の観点から有効であると思料する。
2 請求内容の解釈
請求人から提出された上記措置請求書及び添付の資料並びに補正書の記述から、本件措置請求の内容を次のとおりと解した。
群馬県知事は、職務専念義務に違反して、勤務時間中に行政事務用パソコンを不適正に使用し、アダルト動画のファイル名の編集等を行っていた職員(以下「本件職員」という。)に対して、当該行為を行っていた時間分に相当する金額を減額することなく、不当に給料を支払い、群馬県に損害を与えた。
よって、群馬県知事に対し、本件職員に支払われた給料のうち、本件職員が当該パソコンの不適正使用を行っていた時間分に相当する金額を本件職員から群馬県に返還させるよう、監査委員が勧告することを求める。
3 請求人が主張する違法性・不当性
本件職員は、勤務時間中に行政事務用パソコンを不適正に使用し、アダルト動画のファイル名の編集等を行っていた(以下「本件不適正使用」という。)。これは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)に規定する職務専念義務に違反する行為であり、勤務した時間とは認められないものであるから、本件職員に対して支払われた給料のうち、本件不適正使用を行っていた時間分に相当する金額は、減額されなければならないものである。
群馬県知事がこれを減額することなく、本件職員に対して、適正な勤務があった場合に支払われるべき給料額を支払ったことは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地自法」という。)第242条第1項に規定する不当な公金の支出に当たる。
4 事実証明書等について
請求人から提出された事実証明書等は、次のとおりである。
(1)事実証明書
平成27年3月11日付け東京新聞記事
(2)群馬県職員措置請求書の補正書(平成27年4月8日提出)
(3)群馬県職貝措置請求書の再補正書(平成27年4月15日提出)
ア 添付資料1 平成27年3月31日付け市民オンブズマン群馬代表宛て公文書部分開示決定通知書
イ 添付資料2 ■■課職員行政事務用パソコン不適正使用事案概要
ウ 添付資料3 群馬県総務部人事課起案文書「職員の懲戒処分について」一式
工 添付資料4 平成27年3月10日付け各所属長(各情報セキュリティ責任者)宛て企画部長(情報統括管理者)通知「パソコン及びインターネットの適正使用について(通知)」
オ 添付資料5 平成27年4月15日付け市民オンプズマン群馬代表及び事務局長宛て群馬県総務部人事課長通知「事実確認依頼への回答について」
(4)意見書(平成27年4月22口請求人陳述時に追加提出)
5 補正書及び再補正書の内容(当委員が補正を求めた事項に対する請求人の回答を要約したもの。)
(1)群馬県職員措置請求書の補正書(平成27年4月8日提出)
ア 本件措置請求は、「知事に対して」、「懲戒処分のあった職員に群馬県が被った損害を返還するよう義務づけを求める」ものと解釈してよい。
イ 本件措置請求の対象とする財務会計上の行為は、懲戒処分を受けた職員に対して支払われた給料のうち、当該職員が勤務時間中にアダルト動画編集作業を行っていた時間分に相当する金額の支出である。
ウ イで挙げた財務会計上の行為は、地公法に規定する職務専念義務違反に当たるものであり、群馬県知事が本件職員にその時間分に相当する給料を支払ったことは、余計な人件費を無駄に費消したことになるから、群馬県に損害が発生している。
エ 本件措置請求の対象とした財務会計上の行為があったことを示す事実証明書の提出はなかった。
(2)群馬県職員措置請求書の再補正書(平成27年4月15日提出)
ア 本件措置請求の対象とした財務会計上の行為があったことを示す事実証明書として、添付資料1から5までが追加提出された。
第4 請求の受理
本件措置請求は、地自法第242条第1項に規定する要件を具備しているものと認め、平成27年4月17日に受理を決定した。
第5 監査の実施
1 監査対象事項
本件請求に係る措置請求書及び事実証明書から判断し、監査対象事項は次のとおりとした。
職務専念義務に違反する行為を行った職員に対する給料等の支出
2 監査対象機関
総務部人事課(以下「人事課」という。)
会計局会計課(以下「会計課」という。)
3 請求人の証拠の提出及び陳述
(1)証拠の提出及び陳述の機会の付与
平成27年4月22日、地自法第242条第6項の規定に基づき、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人は意見書を追加提出し、陳述を行った。
(2)請求人陳述の要旨
ア 請求対象事案の態様
本件職員は、平成26年4月29日頃から同年12月10日までの間、行政事務用パソコンを不適正に使用し、アダルト動画のファイル名の編集等を行った。1日平均の不適正使用回数は70回程度、不適正使用時間は30分程度とされている。
イ 不正行為に対する公金の支出
本件不適正使用は、法令、条例等に示された公務員の職務専念義務の免除に含まれないことは明白であり、地公法第35条に規定する職務専念義務に違反している。
ウ 損害金額
本件職員は、50代で補佐級の職員であるから、その年収は700万円を超えるものとみられるが、仮に700万円として、損害金額を算出してみる。
年収700万円を月収に計算すると、58万円を超えることになり、1日当たりの勤務時間を7.75時間と仮定して、週5日で38.75時間、月20日で155時間勤務するとした場合、1日当たり2万9,166円66銭、1時間当たり3,763円44銭となる。
本件職員の自己申告が正しいと仮定した場合、本件不適正使用を始めた平成26年4月29日から同年12月10日まで、毎日約30分程度、アダルト動画の編集作業をしていたとすれば、7か月と10日で150日間となり、職務専念義務に違反していた勤務時間数は、75時間と試算できる。
これに先ほど算出した1時間当たりの金額3,763円44銭を掛けると、28万2,258円となる。
以上は、あくまでも本件職員の自己申告によるものであり、実際にはもっと多くの時間を本件不適正使用に費やしていたと考えられる。県が行った1日平均70回程度・30分程度との集計は、到底、信用できない。1日2時間程度はアダルト動画の編集に費やしていたと考えられ、この場合、損害金額は100万円近くとなる。
群馬県監査委員においては、不当な公金の支出を是正し、損害を回復するよう、切に願うものである。
4 監査委員による対面監査の実施
平成27年5月7日、人事課及び会計課に対し、監査委員による対面監査を行った。
5 関係人調査の実施
平成27年5月1日、地自法第199条第8項の規定に基づき、本件措置請求に係る事実関係の確認のため、企画部情報政策課長(以下「情報政策課長」という。)に対し、文書による調査を行い、同月8日に回答を得た。
6 監査委員の交代
本件措置請求書が提出された時点における地自法第196条第1項の規定により議員のうちから選任された監査委員は、星野寛及び福重隆浩であったところ、平成27年5月11日付けで、久保田順一郎及び狩野浩志が新たに選任された。
本件事案については、旧委員から新委員に引継ぎを行ったほか、事務局から新委員に対して、本件措置請求の概要、経過等について、説明が行われた。
第6 監査の結果
関係書類の調査、監査対象機関への聴取等により確認した事実は、次のとおりである。
1 関連する法令等(各法令等の記載は、該当部分の抜粋である。)
(1)地公法
(服務の根本基準)
第30条すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の執行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(職務に専念する義務)
第35条職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(2)群馬県職員の給与に関する条例(昭和26年群馬県条例第55号。以下「給与条例」という。)
(給料)
第3条 給料は、群馬県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第13条の3の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び農林漁業普及指導手当を除いたものとする。
2(略)
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、・・(略)・・その勤務しない時間1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額を減額して給与を支給する。
2 人事課及び会計課の見解
(1)本件不適正使用等について
ア 本件不適正使用の概要について
本件職員は、自宅パソコンでダウンロードしたアダルト動画をUSBメモリに保存して職場に持ち込み、長期間にわたって、勤務時間中に行政事務用パソコンを使用して、その動画のファイル名を編集するなどの行為を行っていた。
編集内容は、インターネット検索で得た動画情報(女優名、作品名、配信日、商品番号等)やSMプレーヤー(動画再生ソフト)で得た動画ファイルの構成情報(再生時間、解像度等)を動画のフアイル名に書き込んでいたものである。
当該編集作業は、1件の動画フアイルにつき1回で終わるものではなく、本件職員は作業途中でファイルを保存するなどして、業務の合間で繰り返し行っていた。
イ 本件不適正使用の発覚の端緒及び経緯について
平成26年12月9日、県庁ネットワーク運用委託事業者から、企画部情報政策課(以下「情報政策課」という。)に、本件職員の行政事務用パソコンにおいて、「コンピュータ・ウイルスによる通信が行われたことを検知した記録がある」との連絡があったため、情報政策課が本件職員の行政事務用パソコンの操作履歴を確認したところ、この通信記録は誤報だったことが判明したが、別途、アダルト動画と思われるフアイルの操作履歴や女優名等のインターネット検索が行われた履歴が多数あることが分かった。
その情報は、翌10日に情報政策課から会計課に伝えられ、同日、会計課長及び会計課次長が本件職員に事実を確認したところ、本人が本件不適正使用を認めたものである。
ウ 本件不適正使用をしていた期間について
会計課では、本件職員が「平成26年4月29日頃から本件不適正使用を開始した」と主張したことから、情報政策課に対して、同月以後における本件職員の行政事務用パソコンに係るログ履歴(以下「本件ログ履歴」という。)の提供を依頼し、同年10月1日から同年12月10日までの分の提供を受けた。
エ 本件不適正使用をしていた時間等の特定について
会計課では、本件不適正使用の内容を詳細に把握するため、情報政策課から提供された平成26年10月1日から同年12月10日までの本件ログ履歴について、1件ずつ本件職員に操作内容の確認を求め、これを集計した。
その結果、1日平均の不適正使用回数は69件、使用時間は32分であった。
オ 本件ログ履歴から特定した本件不適正使用の時間等について
上記エで算定した集計結果は、本件ログ履歴において、本件不適正使用が疑われる個々の操作の開始時刻に着目して、当該操作の次の操作の開始時刻から当該操作の開始時刻を差し引いて、その時間を算定し、そこに本件ログ履歴に記録された操作内容や本件職員の申立てに基づく操作内容を当てはめ、これを集計したものであって、不適正な目的でインターネット検索を行いつつ、これと並行して本来の業務を行っていた時間等も含まれていることなどから、本件職員が実際に本件不適正使用を行っていた時間を正確に特定したものではない。
カ アダルト動画の閲覧について
本件職員は、本件不適正使用については認めているが、動画自体は閲覧していないと主張している。また、本件ログ履歴からも、動画を閲覧した事実は認められなかった。
キ 本件職員の勤務態度等について
本件職員は、本件不適正使用をしていた期間及びその前後において、勤務態度に変化はなく、特異なものは見受けられなかった。
本件職員は、業務によく精通し、係員の信頼も厚かった。平成26年度は、有給休暇もわずかな日数しか取得しておらず、遅刻、欠勤、長時間の無断離席、電話に対応しないなどの事実もなかった。
ク 本件不適正使用を現認できなかったことについて
会計課では、管理職員を含め、本件不適正使用に気が付いた者はいなかった。本件職員は、アダルト動画そのものを閲覧していたのではないことに加え、本件職員が行っていたフアイル名の編集作業を行う画面は、本件職員が業務として行っているであろうと判断される文字や数宇やアルファベットが表示された画面と、外見上、大きく異なるものではないため、極めて分かりづらい状態だった。
また、職員が勤務時間中に不適正な行為をしているはずがないという認識もあり、監視するような行為はしていなかった。
(2)職務専念義務違反について
ア 職務専念義務違反について
職務専念義務違反は、地公法第35条において、「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と規定されている。
この「勤務時間」とは、条例等に基づき割り振られた正規の勤務時間に加え、時間外勤務、週休日の勤務等を命じられて、これに服する時間も当然含まれる。
また、「職務上の注意力のすべて」とは、常識的にみてその者の有する能力を最大限に発揮せよということであって、勤務時間及び注意力の全てを物理的に職場や職務に拘束する意味ではない。
イ 本件職員の職務専念義務違反について
本件事案は、本件職員が行政事務用パソコンを業務外の目的で不適正に使用していたものであり、常識的にみて本件職員の有する能力が最大限に発揮されていないことから、職務専念義務に違反すると判断した。
(3)給与の減額等について
ア 給与条例上の給与の減額に関する規定について
職員の給与の減額に関する規定は、給与条例第10条において、「職員が勤務しないときは、・・(略)・・その勤務しない時間1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額を減額して給与を支給する」と規定されている。
イ「勤務しないとき」について
給与条例第10条に規定する「勤務しないとき」とは、人事課の取扱いとして、事前の承認手続を欠く遅刻、欠勤、勤務時間中の無断離席の繰り返し、長時間離席の場合等で、所属長がこれを現認する等により明確に特定して「勤務しないとき」と判断した場合をいうこととしている。
ウ 本件不適正使用をしていた時間の「勤務時間」の認定について
本件不適正使用は、地公法第35条に規定する職務専念義務に違反する行為であると認められるものの、自らの席において行政事務用パソコンを不適正に使用していたものであり、上司の指揮命令下から離れるなどの事実があったものではないことから、勤務時間に該当すると判断した。
なお、労働時間(勤務時間)に関して、最高裁は、「労働基準法第32条の労働時間・・(略)・・とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの・・(略)・・と解するのが相当である」(最小判平成12年3月9日)としている。
(4)その他請求人の主張に対する見解について
ア 本件措置請求書の記載事項について
(ア)本件不適正使用の事実認定について
請求人は、本件措置請求書等において、本件職員が「アダルト動画などの編集作業」をしていたと主張しているが、本件職員は、動画そのものの編集ではなく、動画のフアイル名の編集を行っていたものである。
(イ)本件懲戒処分の公表時期について
請求人は、本件措置請求書等において、本件職員の懲戒処分について、「わざわざ、東日本大震災から4周年目にあたる3.11の前日にあたる平成27年3月10日というタイミングを狙って、マスコミ発表に踏み切った」としているが、本件懲戒処分については、同年1月15日に会計課から事件報告書が提出された後、人事課において正確な事実認定を行うための追加調査を同年3月5日まで実施し、これらの結果を踏まえて、同月9日に意思決定を行い、翌10日付けで懲戒処分を行ったものである。
イ 本件職員の申告内容等の信憑性について
請求人は、陳述時において、「本件職員が本件不適正使用を開始したと申告している平成26年4月29日は祝日であり、その申告の信憑性は疑われる」としているが、人事課では、本件職員の「4月半ば頃に自宅パソコンを購入した」という申告内容と「4月29日頃から行政事務用パソコンの不適正使用を始めた」という申告内容には整合性があり、そのように事実認定するに足りると判断した。
また、請求人は、陳述時において、「職場でアダルト画像サイトにアクセスしており、“いずれにおいても鑑賞は行っていない”などということは到底信じられない」としているが、会計課の周囲の職員は、本件職員が動画を鑑賞していた様子は把握しておらず、所属の座席配置状況等を総合的に勘案しても、「鑑賞していない」という申告内容により事実認定することが適当であると判断した。
3 事実関係の確認
(1)関係人調査の結果について
情報政策課長に対して関係人調査を行った結果、本件ログ履歴のうち、データが保存されているのは、平成26年10月1日から同年12月10日までのもののみであり、同年9月30日以前のデータについては既に廃棄されており、存在しないことが確認された。
(2)本件不適正使用の事実認定等について
平成26年10月1日から同年12月10日までの本件ログ履歴の内容を調査したところ、本件職員による本件不適正使用については、その事実があったことが確認され、その件数、時間等についても、会計課が特定し、集計したとおりの件数、時間等が確認された。
また、本件不適正使用の作業を再現したところ、本件職員が行っていた編集作業は、インターネット検索で得た動画に関する情報や動画再生ソフトで得た動画ファイルの構成情報を動画のファイル名に書き込む作業であり、1回当たりの所要時間は数秒から数十秒であることが確認された。
(3)本件職員への給料の支払いについて
人事課は、本件不適正使用について、地公法第35条に規定する職務専念義務に違反する行為であると認められるものの、自らの席において行政事務用パソコンを不適正に使用していたものであり、上司の指揮命令下から離れるなどの事実があったものではないとして、本件職員が本件不適正使用をしていた期間におけるその時間分に相当する給料額を減額しておらず、又は返還を請求していなかった。
(4)本件職員による自主返納
本件職員は、平成27年5月8日付けで、群馬県知事に対して、本件職員が職務専念義務に違反して本件不適正使用をしていた期間におけるその時間分の給与相当額として、現金50万円を自主的に返還する旨の上申書を提出し、同日、同額が群馬県に納付されていた。
この金額は、本件措置請求において、請求人が本件不適正使用に関し県が被った損害であると主張する金額28万2、258円を上回るものであった。
第7 監査委員の判断
1 判断 ’
上記事実認定のとおり、本件不適正使用に係る本件職員の給料相当額については、既に本件職員から群馬県に自主的に返還されており、その納付された金額は、本件措置請求において、請求人が本件不適正使用に関し県が被った損害であると主張する金額を上回るものであることから、本件措置請求における請求人が主張する損害については、既に補填されていると認められる。
2 結論
したがって、本件措置請求は、監査を実施する理由がなくなっているものと判断し、これを却下する。
以上
********************
■このような身内の不祥事が発覚した場合、外部になるべく詳細を知らせないまま内部処理をするのが役所の傾向です。今回の不祥事でも群馬県は、当該職員への半月間の停職処分と他部署への配置換えで、済ますつもりだったのでしょう。そこに市民オンブズマン群馬から「ちょっと待った」を掛けたわけです。
しかし群馬県は、地方自治法第2条第14項「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という義務を軽視し、当会のような納税者による市民団体からの忠告に対して、常に上から目線で対応してきます。
今回の住民監査請求に対しても、監査委員の判断は「棄却」という結果に終わりました。それも、当該職員から自主的に50万円が返納されたのだから、オンブズマンの監査請求を監査する理由が消滅したのだから、監査請求そのものが不要だ、というものです。
これでは、再発防止が図れないわけです。納税者からの監査請求に対して、真摯に対応すべきなのに、結局、役所の目線で対応するのが群馬県監査委員の実態です。
しかも今回の監査では、4月12日の県議選を受けて、当会が県庁23階の監査委員事務局で陳述した際に、県議会選出の監査委員だった星野寛と福重隆浩はともに当選を果たしたのに、5月11日付で、久保田順一郎と狩野浩志に交替されてしまいました。
このうち狩野浩志は、大沢正明・群馬県知事の愛人連込みによる知事公舎妾宅化問題でも、当会の監査請求を棄却したことがあります。本人もその後認知したものの、当時、愛人との間にトラブルを抱えており、当会では、狩野浩志の監査委員としての忌避を監査委員事務局に申し立てましたが、認められませんでした。
■さて5月29日に届いた監査結果の内容を検証してみましょう。
最初に全体の感想としては、群馬県のいい加減な職員管理の実態です。
今回の群馬県監査委員の監査結果は、「エロ動画編集をしていた当該職員が自主的に50万円を返納したから、オンブズマンの言う損害額をはるかに上回っており、文句はあるまい」というものですが、オンブズマンが住民監査請求を提起しなければ、職員が自席で上司の管理下でパソコンに向かっていたのだから、時間的に拘束されていたわけなので、給与の減額は行う必要がなかったと判断していたのです。
このような考え方なので、今後とも、類似の事件が発生した場合、オンブズマンとしてその都度住民監査請求をしないと、公金の無駄遣いの是正措置が取られないことになります。
やはり、公務員同士で仲間意識に染まっているため、きちんとルールが徹底せず、曖昧な状態で判断されてしまうのです。県庁内に市民オンブズマンの監視の目を行き届かせるために、監査委員だけではなく、当会のような外部の第三者による監視を恒常的に行う体制への改善が不可避です。
■続いて、監査委員の判断の中で、首をかしげざるを得ない項目を挙げてみます。
<2度も補正を求めるなど嫌がらせ>
今回、3月23日に住民監査請求を提出後、監査委員事務局は、4月3日と4月10日に2度も当会に補正を求めてきました。こんな単純な事件なのに、明らかに時間稼ぎです。当会は、このような嫌がらせにもめげずに、迅速に補正指示に対応し、出来る限り早期に決定通知が出されるよう、終始、最善の努力を傾注しました。その結果、監査委員事務局では4月17日に受理をしましたが、結局監査請求から決定通知まで60日以上を掛けさせられてしまったのでした。
<正確な給与の減額査定根拠が示されていない>
今回の問題で、当会は当該職員(50代、補佐級)の年収を仮に700万円として、当該職員が没頭していたエロ動画編集時間を本人の申告通りの時間数と仮定して損害金額を算出した結果、28万2258円という数字を得ました。ところが、当該職員から返納された金額は2倍近い金額でした。ということは群馬県では、50代で補佐級の職員ともなると、年収が1240万円となるわけです。こんなに高給取りが、勤務中パソコンでエロ動画編集三昧できるほど暇だというのですから、公務員という職業は正に濡れ手で粟の人生が送れることを示しています。
それにつけても遺憾なのは、公務員のこうしたバブリィな給与支給の実態を、納税者である県民にきちんと公表しようとしない体質です。
<本当にエロ動画を閲覧せずに編集ができるのか>
監査結果によれば「本件職員は、自宅パソコンでダウンロードしたアダルト動画をUSBメモリに保存して職場に持ち込み、長期間にわたって、勤務時間中に行政事務用パソコンを使用して、その動画のファイル名を編集するなどの行為を行っていた。編集内容は、インターネット検索で得た動画情報(女優名、作品名、配信日、商品番号等)やSMプレーヤー(動画再生ソフト)で得た動画ファイルの構成情報(再生時間、解像度等)を動画のフアイル名に書き込んでいたものである。当該編集作業は、1件の動画フアイルにつき1回で終わるものではなく、本件職員は作業途中でファイルを保存するなどして、業務の合間で繰り返し行っていた」と記してあります。
また、「平成26年12月9日、県庁ネットワーク運用委託事業者から、企画部情報政策課(以下「情報政策課」という。)に、本件職員の行政事務用パソコンにおいて、「コンピュータ・ウイルスによる通信が行われたことを検知した記録がある」との連絡があったため、情報政策課が本件職員の行政事務用パソコンの操作履歴を確認したところ、この通信記録は誤報だったことが判明したが、別途、アダルト動画と思われるフアイルの操作履歴や女優名等のインターネット検索が行われた履歴が多数あることが分かった」とも記しています。
すなわち、当該職員は恒常的にエロ動画関連情報の収集のため、インターネットで検索をしており、ウイルス感染の疑いのあるサイトにアクセスをしていたのも一度や二度ではなかったと見られます。
にもかかわらず、「この通信記録は誤報だった」などとして、大きな原因ではないかのように取り繕っています。
この他にも、さまざまな疑義があります。
こうした中途半端な監査結果のため、さらに内容を精査したうえで、今後の対応策について、当会の例会で討議をしたうえで、方針を決定したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】