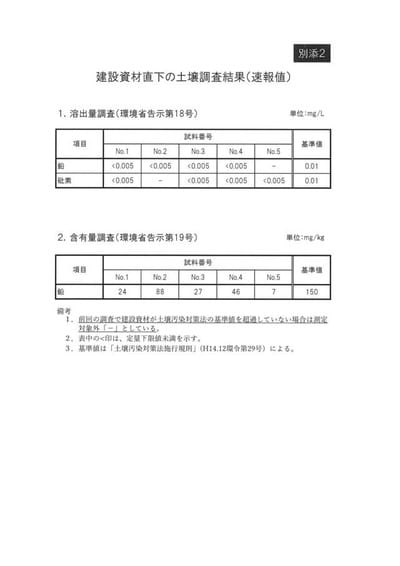■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、昨年末迄に事実上竣工し、本年2月から本格運転が開始され、4月24日には行政関係者を招いて完成披露式=開所式まで開かれてしまいました。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。それから早くも2年が経過し、先日8月1日付で被告群馬県から第7準備書面が送られてきました。そして、この度、8月28日付で原告住民は、反論の為に原告準備書面(9)を郵送で提出しました。

↑
原告準備書面(9)はレターパックで正本を裁判所、副本を被告訴訟代理人弁護士事務所あてに本日郵送。↑
前回、6月20日の第9回口頭弁論に先立ち、当会が提出した原告準備書面(8)の内容は次のブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html
また、8月1日付で被告群馬県が提出した被告第7準備書面の内容は次のブログ記事を御覧下さい。
○2018年8月4日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html
■今回、原告住民らが提出した裁判資料は次のとおりです。
*****
送付書兼受領書*****
PDF ⇒ 20180828tei9j.pdf
送付書・受領書
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人
弁護士 関 夕 三 郎 殿
FAX:027-230-9622
平成30年8月28日
〒371-0244
前橋市鼻毛石町1991-42
原 告 羽 鳥 昌 行
TEL 027-283-4150 / FAX 027-224-6624(鈴木庸)
送 付 書
事件の表示 : 前橋地裁 平成28年(行ウ)第27号
当 事 者 : 原 告 小 川 賢 外1名
被 告 群 馬 県 大澤正明
次回期日 : 平成30年9月5日(水)16時00分(弁論準備)
下記書類を送付致します。
1 原告準備書面(9) 1通
以 上
--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------
受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
平成30年 月 日
被 告 群 馬 県
被告訴訟代理人
弁護士
前橋地方裁判所民事1部合議係(森山書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901
羽鳥昌行あて(市民オンブズマン群馬事務局鈴木)あて:FAX 027-224-6624
*****
原告準備書面(9)*****
PDF ⇒ 20180828r1ixjoowj.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第27号 補助金返還履行請求事件
原告 小 川 賢 外1名
被告 群馬県知事 大澤正明
平成30年8月28日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中
原告準備書面(9)
原告 小 川 賢 ㊞
原告 羽 鳥 昌 行 ㊞
平成30年8月1日付の被告第7準備書面および乙14から乙15号証に関して、原告らは次のとおり反論する。
第1 争点と証拠について
1 前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電が別法人であるとの被告の主張への反論
(1)被告は、所在地や取締役が異なることや出資者及び出資比率が異なることから両法人は別法人であると主張しているが、失当である。本件は、発電を共通の目的とする一体的事業であり、その事業責任も両法人が連帯して一体的にとる必要がある。
(2)被告は、乙15号証において、「必ずしも前橋バイオマス燃料が前橋バイオマス発電に全ての燃料を供給しなければならないものではないことから、一体的でない」と主張しているが、前橋バイオマス発電所燃料供給契約書(乙第15号証)の第5条(供給に係る努力義務又は保障)に、「・・・(中略)・・・乙は、甲が必要とする数量の木質バイオマス燃料を甲に供給できない限り、第三者に対して木質バイオマス燃料又は木質バイオマス燃料を製造するための木材等の原料を供給しないことを約束する。」として、両法人は合意している。
(3)しかし、この条文を読み解けば、「計画量の木質バイオマス燃料を確保できない限りにおいては、第三者に供給してはならない」と両法人は平成29年12月13日に契約しているのだが、そもそも、前橋バイオマス燃料及び前橋バイオマス発電は、平成27年7月10日に被告に提出した事業計画【甲25号証】において、前橋バイオマス発電は、年間7万トンの木質バイオマス燃料を燃やし発電し、前橋バイオマス燃料は、年間7万トンの燃料を生産する計画が示されている。
(4)したがって、当初から木質バイオマス燃料の事業計画は7万トンですべてが成り立っており、それ以上の生産能力は、前橋バイオマス燃料にはないことは明白である。
いくら、前橋バイオマス発電が、被告を説得して環境アセスメント条例で定める毎時4万ノルマル㎥の排ガス量を超える燃料の使用を可能にして、一方の前橋バイオマス燃料が、当初の木質燃料の製造計画能力よりも実際には水増しした製造能力を有する設備の導入に成功したことにより、平成29年12月初めから実施した試運転開始後に、乙15号証のような契約を双方で交わしたから、と主張しても、それは当初想定していた計画そのものを両法人が自ら否定するという結果を意味するだけである。
(5)前橋バイオマス燃料が前橋バイオマス発電に供給する量しか生産する計画がないことは、仕入れ先と契約した木質バイオオマス安定供給協定書を見れば一目瞭然である【甲73号証】。ちなみに、その協定内容を次に示しておく。
●協定日:平成26年10月2日
〇甲:トーセン 東泉清壽
〇乙:前橋バイオマス燃料 東泉清壽
〇丙:-
〇供給量:80,000
〇状態:チップ
〇間伐材:50,000
〇製材端材:30,000
◎協定日:平成26年10月2日
○甲:県産材加工協同組合 東泉清壽
○乙:トーセン 東泉清壽
○丙:-
○供給量:30,000
○状態:チップ
○間伐材:-
○製材端材:30,000
◎協定日:平成27年1月15日
○甲:群馬県素材生産共同組合 橋爪洋介
○乙:トーセン 東泉清壽
○丙:-
○供給量:10,000
○状態:チップ
○間伐材:10,000
○製材端材:-
◎協定日:平成27年1月15日
○甲:群馬県森林連合会 星野已喜雄
○乙:トーセン 東泉清壽
○丙:-
○供給量:20,000
○状態:チップ
○間伐材:20,000
○製材端材:-
◎協定日:平成27年1月15日
○甲:群馬県森林連合会 星野已喜雄
○乙:県産材加工協同組合 東泉清壽
○丙:前橋バイオマス燃料 東泉清壽
○供給量:20,000
○状態:チップ
○間伐材:20,000
○製材端材:-
(6)また、平成28年6月28日の補助金交付申請書【甲15号証】の中に、平成27年度に書かれた木質バイオマス利用施設等整備事業診断書において、事業効果の妥当性として、「計画によると年間生産量は7万トンであり、・・・」と明記されている。そして、最後に、事業計画実施の際の留意事項として、「①原材料の仕入れ量(生産量7万トン)が確保できるかどうか、②年間7万トンの生産を達成するだけの作業効率を確保できるかどうか。」と締めくくられており、生産量7万トンの確保と作業効率を心配していることが強くうかがえる。このことからも、本件事業の計画は、発電への供給量である7万トンを確保するためにすべてが動いていることがわかる。
(7)被告がなぜ今頃になって平成29年12月13日に両法人の間で作成された乙15号証を提出してきたのか。原告には、その真意は不詳だが、このような当初計画と相違する文書を被告が入手しながら、当初計画との不整合性を看過し、事業者のデタラメな事業計画を擁護する主張を繰り返しているのを見ると、そこには、環境アセスメントを事業者に義務付けなかった被告の別の意図が隠されていることを強く推認させる。
(8)さらに、単純に考えても、木質バイオマス燃料を製造するために、原料の木質燃料を全県下より輸送してきているのに、そしてそれを全量言い値で買ってくれる事業所が目の前にあるのに、わざわざ輸送費を払ってまでも木質バイオマス燃料を販売するために、近隣の別の木質バイオマス発電所に運ぼうとしても、採算がとれるのかどうか疑問が生じる。
あるいは、当初から被告は、両法人がその実際の製造能力に余裕のあることを承知で、環境アセスを免除した上で、本件事業を許可したのではないのか、釈明を求めたい。
2 放射能対策が適正であるとの被告の主張への反論
(1)被告は、自主管理基準を設け、当該基準が適正であると主張し、その証拠として乙8・9号証を挙げた。
(2)ここでまず、乙8号証は、「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について」であるが、これは平成23年11月2日に“当面として”作成された指標であり、具体的な検査方法も何も示されていない。仮に、薪の放射性セシウムの濃度の最大値を40ベクレル/㎏と仮定しても、原告が終始一貫指摘しているのは、その40ベクレル/㎏以上のものが伐採されたりした場合、前橋バイオマス燃料及び発電においては、受入検査でそれらをロットアウトにできる精度ある測定方法が確立されていないことである。
(3)その証左として、前橋バイオマス燃料及び発電は、受入時に放射性セシウムを測定するトラックスケールの能力をいまだに示していない。検査をバックグラウンドの変化を3倍としているが、3倍ものバックグラウンドを変化させるだけの放射能はいったいどれほどだろうか。原告が、このトラックスケールを製造するメーカーに確認したところ、メーカーの技術担当者は「40万ベクレル程度の放射線源がなければ検出不能」と証言している。被告はきちんと事業者にこのことを確認したのか、釈明を求めたい。
(4)乙9号証は、「福島県木質バイオマス安定供給手引き」である。木質バイオマス利用施設における放射線管理の目安が証拠として挙げられているが、木質系燃料の受入管理の目安として、「100ベクレル/㎏程度以下で管理」とある。だが、これは、燃焼灰や排ガスの放射能濃度の試算結果から設定した目安であって、科学的な根拠では有り得ない。
(4)また、焼却灰の処分にしても、焼却灰を「1/30~1/40に減量化される」としているが、実際は、「200倍前後」に濃縮されるため、100ベクレル/㎏の材料は200倍に濃縮されるため、焼却灰は20,000ベクレル/㎏になる、特定廃棄物である8,000ベクレル/㎏の2.5倍にもなってしまう。
(5)さらに、排ガスによる環境影響にしても、木質系燃料の燃焼空気量を 3,500㎥ N/トンとし、排ガス処理装置の除去率を99%に設定しただけの保守側の試算結果に過ぎない。
(6)したがって、本手引きから引用した「100ベクレル/㎏だから排ガスも焼却灰も安全である」という被告の主張は、科学的にも証明されている訳ではなく、あくまで、経済性からの論理に他ならないのは明白である。
第2 求釈明への回答について
1 求釈明1について
(1)被告は、「木質チップを天然乾燥した場合の(湿量)含水率は45%程度であり、人工乾燥した場合の(湿量)含水率は40%程度である(甲64.乙15-別紙1)。そして、前橋バイオマス発電では、天然乾燥した木質チップと人工乾燥した木質チップを併用して燃料として使用するため、平均すると(湿量)含水率は43.125%程度となると想定されている。したがって、(湿量)含水率が36%まで下がることはない。」と主張する。
(2)ところが、前出の木質バイオオマス安定供給協定書【甲73号証】によれば、木質チップ燃料8万トンのうち、製材端材は3万トンであり、被告が主張する天然乾燥5万トンは含水率45%で、人工乾燥は3万トンであることから、含水率の比率を計算しても、含水率は43.125%にはならないことがわかる。よって、含水率43.125%ありきの逆計算より導き出された数字であると言える。
(3)被告は、年間における間伐材の産地や形状、自然乾燥期間の変化、そして、人工乾燥したチップの混合比率など含水率計算の前提条件をきちんと事業者からヒヤリングして、確認したのか。その経緯と根拠について明確な釈明を求めたい。
(4)また、原告は、低位発熱量の方程式(全国木材チップ工業連合会報告資料)からカロリー値計算、メガジュール値計算から含水率を導き出したが、被告も、この方程式から、同様に導き出し、含水率43.125%との違いを明確にし、その理由を科学的に説明する必要がある。被告の釈明を求めたい。
2 求釈明2について
(1)被告は、「一般に、燃料の含水率が高いほど、当該燃料の発熱量は低くなるから、燃料使用量は増えることになる。逆に、燃料の含水率が低いほど、当該燃料の発熱量は高くなるから、使用燃料は相対的に減ることになる。」と主張する。
(2)また被告は、「環境配慮計画では、天然乾燥した木質チップの(湿量)含水率を45%と見積もり、他方、排ガス量の計算(乙12)では、天然乾燥による燃料と人工乾燥による燃料を併用した場合における全体の(湿量)含水率として43.125%と見積もったのである。燃料使用量9,770㎏/hと9,300㎏/hとの差は、この仮定した含水率の差により生じたものである。」と主張する。
(3)さらに被告は「また、条例アセスメント実施要件該当性判断においては、本件運用により(乾量)含水率20%として計算できる。そして、仮に(湿量)含水率45%として排ガス量の計算式(乙12)に当てはめた場合、結局、本件運用により排ガス量は39,200N㎥/h程度となり、40,000N㎥/hを下回り条例アセスメントの対象とならないため、関電工が含水率を偽装する理由はない。」と主張する。
(4)だが、そもそも環境配慮計画には、使用燃料の含水率は記入されていない。被告は「45%と見積もった」と主張するが、その根拠が見当たらない。この事業計画が始まった当初から、製材端材は含水率が多いので、大型プレス機による脱水が想定されており、環境配慮計画が提出された平成28年5月18日時点で、人工乾燥による3万トンのチップ燃料は想定されていたはずである。だとするならば、含水率45%で逆計算し、燃料使用量が9,770㎏/hになることを証明されたい。
(5)被告は、「本件運用により」と二度表現しているが、そもそも、この運用自体に正当性や妥当性が証明されたわけではなく、本件裁判において、それらについて審理を通じて追及しているのである。
(6)被告と関電工は、この運用を正当だの妥当だのとでっち上げ、木質燃料の製造工場を併設した本発電事業において、環境アセスメントの実施を課さずに企てたのだから、自分たちに都合の良い「本件運用」を適応すればそのようになるのは当たり前である。このことは即ち、前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電、そして、被告と関電工とトーセン、さらにほかの出資者の森林組合などから構成される事業者らは、切っても切れない間柄であることを物語っている。
3 求釈明3乃至6について
(1)被告は、「原告らは、関電工の排ガス量計算における(湿潤)含水率(43.125%)と、前橋バイオマス燃料の燃料供給計画から計算される(湿量)含水率(42.938%)との整合性を問題としている。しかし、上記各含水率は異なる算出方法による計算上の含水率であり、完全に一致することまで要求される性質のものではない。」と主張している。
(2)このように被告らは、含水率を1,000分の1単位まで計算し求めているが、常識的に見ても、これは相当の精度で、計算式における前提条件が明確にならなければ求められるものではない。しかも、計算上だけではなく、実際の「本件運用」時の条件との誤差はあってはならないのである。なぜなら、原告が当初から求めているのは、排ガス量など科学的に証明される「本件運用」のための条件とも言える代物だからである。
(3)被告らは、「異なる算出方法」などと主張するが、そもそも算出方法に複数の異なるものなどあってはならないのである。それは、実際のものと一致しなければならないからである。被告は、なぜそうした含水率が導き出されたのか、関電工ら事業者の説明をうのみにするだけでなく、自らさまざまな木質燃料のサンプリングや成分の分析や燃焼試験の結果、あるいは類似事業の事例などから明確な燃料の状態(質や量など)をきちんと確認したのか、などを明らかにする必要がある。
4 求釈明9について
(1)被告は、「既に述べたとおり、空気比の値『1.3』は、前橋バイオマス発電が燃料のサンプリングをボイラーメーカーへ提出した上で、ボイラーメーカーが納入済の先行機の実績およびボイラーの性能・使用目的を考慮した上で算出した値である。この点、空気比を過大にすると排ガスとしてボイラーから持ち去られる熱量が大きくなり、ボイラー効率(熱効率)の低下を招く。また、燃料性状が安定していれば空気比を上げなくとも完全燃焼が可能である。」と主張する。
(2)だが、メーカーに提出したサンプルの素性や量を明確にした上での試験結果、さらには、先行機の実績データや燃料の素性や条件、ボイラー性能などが明確にされなければ納得できるものではない。さらなる釈明を求めたい。
以上
**********
■既に法廷で2年の審理期間が過ぎていますが、バイオマス発電+燃料施設は、環境アセスメントも実施することなく、稼働してしまっています。しかし、いくら群馬県の環境行政が機能不全に陥っているとはいえ、きちんとルールは適用されなければなりません。
既に、この群馬県の劣化したお役人には、まともな行政を遂行する能力が失われています。だから、彼らになりかわって、裁判所が、この点をきちんと判断して、毅然たる判決を示すことにより、群馬県民のための環境権が復権され、本来の姿を取り戻す唯一の方策と言えるでしょう。
併せて、デタラメな事業計画で、費用を水増しして、4億8千万円もの補助金をせしめた関電工やトーセンらから、我々の血税を取り戻さなければなりません。
なお、9月5日午後4時からの裁判も、3階のラウンドテーブル法廷で、非公開の弁論準備の形式で開かれる予定です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】