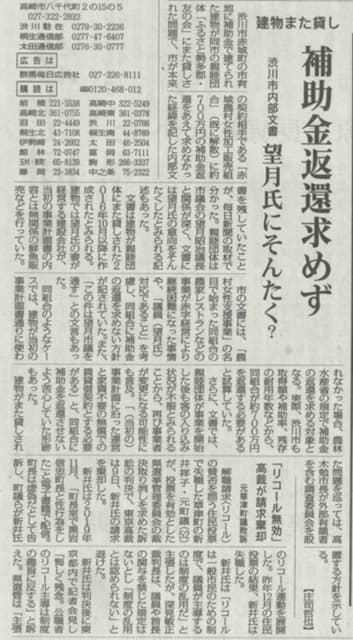■安中市と高崎市と富岡市が境界を接する安中市岩野谷地区、高崎市吉井町上奥平地区、富岡市桑原地区には、廃棄物処理施設として中間施設や最終処分場が集中しています。これまでにも住民は、廃棄物処分施設の計画が持ち上がるたびに反対運動を展開していきましたが、業者と癒着した行政の前に、ほとんどの場合、敗れ去り、今日の「廃棄物銀座」と呼ばれる景観を呈する惨状となってしまいました。
なかでも、平成18年から安中市岩野谷の大谷地区の一番奥に計画されている㈱環境資源による関東屈指の大規模な産業廃棄物最終処分場計画は、地元の生活環境や営農環境保全の観点から、最後のとどめを刺されかねないため、地区住民は深刻な脅威として対処してきました。そうした中、突如として群馬県知事が今年2021年2月3日に㈱ジョウソウに対して、この大規模サンパイ廃棄物最終処分場の設置許可を出してしまいました。
その手続きの経過と内容を確認すべく当会では情報開示請求を群馬県と安中市に行いました。その結果、茂木英子・安中市長の地元に計画されているこのサンパイ場に対して、茂木市長は県議時代から反対の意向を示していたことから、群馬県知事の山本一太が、わざわざ2020年12月25日のクリスマスの朝、安中市長ら幹部と面談していたことが分かりました。

↑
安中市岩野谷地区の大谷(おおや)の県道わきにあるサンパイ場に反対する住民らが立てた看板。↑



↑
大谷の県道沿いには他にも多数の産廃反対の看板が並ぶ。群馬県知事はこれらが目に入らないらしい。↑
当日朝、山本知事は、知事戦略部秘書課の福島康嗣・秘書第一係長を連れて、秘書第二係の澤田卓也・主査(技)の運転する公用車で安中市に向かいました。併せて、サンパイ場の申請許可手続きをしている環境森林部の岩瀬春男部長も、廃棄物・リサイクル課の水澤俊也課長を連れて、朝7時に県庁に登庁した同課の富田典之・係長(技)の運転で、スバルインプレッサに乗り合わせて、知事の乗った公用車ととともに、安中市役所に朝9時に到着し、安中市役所の2階の応接室で約20分間にわたり、安中市幹部らと面談しました。
そして、会議録によれば、安中市から、茂木英子・市長、粟野好映・副市長、清水裕之・市民部長、小野恭義・環境政策課長が出席し、群馬県から「㈱ジョウソウの設置許可申請について、廃棄物処理法の許可要件を満たしているため、県が許可しなければならない」旨を安中市長に説明し、その際、群馬県からは資料の提出は何もなく、全て口頭での説明だったようです。

↑
大谷を流れる岩井川の一番上流にある新山の溜池の堰堤。水田の灌漑用水をここで蓄えている。↑

↑
新山の貯水池(溜池)。正面奥の山間に大規模サンパイ場計画が進められ、排水はこの溜池に注がれる。また廃棄物からの浸出水は処理後、岩井川沿いの土手に排水管を埋設し、下流方向に延長放流されるという。今回の群馬県の設置許可処分は、処分場の排水の混じった灌漑用水を水田に引き込んでもよいというに等しい。↑

↑
さらに進むと、高崎市との境界にある県道に出る。左が高崎市で、すぐわきに昭和電気鋳鋼のサンパイ処分場がある。右が安中市で、すぐそばに大和建設のサンパイ中間処理施設がある。↑

↑
昭和電気鋳鋼のサンパイ場設置標識板。↑


↑
大和建設のサンパイ中間処理施設。↑



↑
富岡市の埋め終わった一般廃棄物最終処分場。↑

↑
富岡市桑原地区にある田村組の中間処理施設。↑

↑
同じく桑原地区にある7年前に戸田建設と西松建設の共同企業体である中央環境資源開発㈱が計画したアスベスト中間処理施設計画の跡地。現在は装弾メーカーのダイセルパイロテクニクス社が猟銃の銃弾などの保管庫として使用している。火薬庫も迷惑施設ではあるものの、得体のしれないサンパイを持ち込むどこの馬の骨ともわからぬサンパイ業者よるはずっとマシということで、地元の方々も納得。↑
■一方、安中市にこの日の群馬県知事の来訪について、情報開示請求を行いましたが、当日12月25日の予定表として、9時に件名(場所)として「群馬県山本知事、環境森林部長来庁(応接室)」、要件等として「産業廃棄物処分場の件ほか」、担当部署として「環境政策課」、出席者として「市長・副市長」が予定されていたことが分かりました。しかし、不思議なことに、山本一太が管理職らを引き連れて、市長のお膝元の岩野谷地区に計画されている関東最大クラスの産廃処分場に関する説明であるにもかかわらず、会議メモの類が一切存在しないというのです。
このため、約20分間の山本知事と茂木市長との面談で、一太知事が「茂木さん、悪いけど、どうしても法令上、県としてこれ以上、㈱ジョウソウの設置許可申請について、手続きを延ばすことができない。なぜなら廃棄物処理法の許可要件を満たしているからだ」などと言ったようですが、茂木市長は当然「私の住んでいる地元なので、このサンパイ場問題はどうしても地元住民の皆さんによる反対の意見を尊重しなければなりません。私に説明をしたという既成事実をつくりにおいでになったのでしょうか。だったら、絶対に安中市として認められないので、県には許可を絶対に出さないでほしい」と言うはずですが、それを確認するための証拠となる会議録ないし会議メモが存在しないというのです。
■こうした不可思議な行政同士の対応を見るにつけ、地元岩野谷地区でかつて地元住民が粘り強く抵抗したにも関わらず、群馬県と安中市が結託して、サイボウ環境㈱に対して一般廃棄物最終処分施設の設置許可と、運搬業許可を与えた経緯が思い出されます。
当時も、群馬県は「設置許可は単なる手続きの一過程であり、事業者は個別法をクリアしなければならないのだから、心配ない」などと、地元が廃棄物銀座になることを心配した住民に出まかせを言い、安中市は「個別法の手続きでは、事業者とは絶対に協議の場に着かないので心配いらない」などと言って住民を安心させておきながら、事業者は「安中市がテーブルに着こうとしない」と群馬県に報告し、群馬県は「事業者がそれほどなんども協議を申し入れても安中市が応じなかったのだから、県として農振除外手続を認めてやろう」と事業者の便宜を図る始末でした。
今回も、安中市で審査される森林法や農振法などによる手続きが必要であることから、安中市は「絶対に業者と交渉しない」と言っており、それを聞いているだけなら、「安中市は住民側のことを最優先してくれている」などと錯覚しがちですが、すべて群馬県と示し合わせた茶番であることは、以前、サイボウ環境の一般廃棄物管理型最終処分場でも痛いほど見せつけられました。
■というわけで、このままだと、今回の施設設置許可処分を引き金に、いよいよ岩野谷地区の安心・安全な生活環境の保全が永遠に取り戻せなくなるリスクが現実のものになりかねません。そこで、地元住民として、行政不服審査法による処分取り消しを求める審査請求をすることにしました。
とりあえず処分庁である群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課を訪れて、富田係長に審査請求のやりかたについて相談したところ、廃棄物処理法という法令に基づく処分の為、審査請求書の提出先は環境大臣ということがわかりました。
また、環境省の産業廃棄物に関する事項についての担当窓口は、環境再生・資源循環局廃棄物規制課(電話03-3581-3351(内線6878)、FAX03-3594-8264)であることも教えてもらいました。
早速、環境省の廃棄物規制課に電話をしたところ、電話に出た職員に用件を説明すると「それは別の担当者の管轄だが、自分は今日はテレワーク中なので、あとで電話をさせるので、小川さんの連絡先を教えてほしい」と言われたので、筆者の携帯番号を伝えました。
すると、1時間半ほどして、担当者と称する勝木職員から電話が有り、あらためて事情を説明したところ、「もう審査請求書の案を作成済みであれば、郵送で構わないので、行政不服審査法で定めた審査請求の用件を満たした書式で書いた審査請求書を2部提出してほしい」と説明がありました。
■そこで、本日令和3年6月18日付で、次の内容の審査請求書を環境大臣あてに郵送しました。
*****6/18環境大臣あて審査請求書*****ZIP ⇒ 202106181r.zip
審査請求書
令和3年6月18日
環境大臣 殿
審査請求人 群馬県安中市野殿980番地
小川 賢
(連絡先090-5302-8312(電話番号))
行政不服審査法第19条第2項等に基づき、次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
群馬県知事山本一太が、令和3年2月3日付で株式会社ジョウソウに対して為した産業廃棄物処理施設設置許可処分
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和3年3月26日
3 審査請求の趣旨及び理由
(1) 請求の趣旨
ア 審査請求人は、群馬県安中市岩野谷地区に在住する納税者住民である。
イ 岩野谷地区は、岩井、野殿、大谷の3区域から構成されており、このうち岩井・野殿区域は東邦亜鉛安中製錬所の鉱毒による大気汚染、土壌汚染、河川・地下水汚染の影響を受けており、未だに安全・安心な生活環境の保全が担保されていない。
ウ 岩野谷地区は、隣接する高崎市吉井町上奥平地区並びに富岡市桑原地区における廃棄物処理施設の設置計画及び設置実現が多発していたことから、その影響が実際に岩野谷地区に及ぶことが懸念されており、良識ある住民らにより監視が続けられてきたが、平成2年頃から、大谷区域でサイボウ環境による管理型一般廃棄物最終処分場の設置計画が持ち上がった。住民らは反対運動を展開したが、平成9年に群馬県知事が設置許可を出してしまっため、平成19年に開業されてしまった。その後、大和建設の中間処理施設が稼働したり、大谷区域の谷津と呼ばれる山間に次々に産業廃棄物最終処分場の設置計画が群馬県に提出されてきた。
エ 今回のジョウソウによる産業廃棄物最終処理施設(サンパイ処分場)は、前記のサイボウ環境の処分場が稼働した平成19年当時から、同処分場設置手続きや地上げに関与していた関係者が次の案件として地元で画策していたもので、安中市後閑にある不動産業者が中心となり、「環境資源」という名前を付した会社が、地元の地権者や周辺住民の同意書、下流の水利組合員からの同意書を取り付けたりしていたが、その後、環境資源は群馬県に対して事前協議を申請し、平成25年8月19日に群馬県知事が事前協議終了通知を環境資源に発出した。
オ その後、環境資源は平成25年10月22日付で産廃処分場設置の許可手続きのための本申請を群馬県知事に行ったことから、危機意識を共有した地元区長会は、平成27年3月29日(日)午後2時から、岩野谷公民館2階講義室において「廃棄物処分場に関する特別講座」を開いた。この特別講座には、大谷地区住民を主体に、岩井地区、野殿地区の住民らを含め総勢40名余りが参加した。そして、設置許可手続きの最終段階にある環境資源のサンパイ処分場の設置阻止に向けて、安中市の市長や副市長も参加し、安中市職員による出前講座のあと、専門家による特別講座が行われた。
カ その後、環境資源による表立った動きは見られず、地元住民の間では、環境資源が財政的に行き詰まったとして、安堵する声も聴かれるようになった。
キ そうした状況下で2年半が経過した平成29年10月14日、突然㈱ジョウソウという聞き慣れない事業者による「株式会社ジョウソウ(旧環境資源)管理型最終処分場事業住民説明会」が開催され、審査請求人も地元住民から連絡を受けて急遽、同日午後6時半から安中市商工会館3階の大研修室に行った。ジョウソウの説明では、環境資源を引き継いだとのことであったが、審査請求人は、「単に引き継いでも、会社名が変わり経営陣が入れ替わっており、最初から事前協議をしなければならないことをよく認識したほうがよい」とアドバイスをした。
ク その後、ジョウソウの動きも見られないまま3年が経過した今年3月9日に、地元住民から「群馬県がジョウソウの大規模産廃計画に対して設置許可を出したという未確認情報がある」との通報を受け、直ちに群馬県に情報開示請求を行い、3月26日に開示を受けた文書で、群馬県知事がジョウソウの本件計画に対して練和3年2月3日付で設置許可処分を出したことを知った。
(2) 請求の理由
ア 審査請求人は、平成26年7月30日に次の内容の意見書を群馬県の本件許可申請に係る実施機関宛に提出した。以下に引用する。
<引用はじめ>
平成26年7月30日
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
環境森林部廃棄物・リサイクル課 御中
株式会社環境資源産業廃棄物処理施設設置許可申請にかかる
生活環境保全上の見地からの意見書
1. 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名:
安中市野殿980番地 小川 賢
2. 意見書を提出する対象事業の名称:
株式会社環境資源産業廃棄物処理施設設置
3. 施設設置に関して利害関係を有する理由:
①当該施設が設置予定場所(安中市大谷字新山1259番2、外9筆)のある岩野谷地区の住民であり、サンパイ銀座化する地元のイメージダウンの影響を強く受ける。
②設置予定場所から西北西1.7㎞の地点に3700㎡の山林を保有しており、当該施設から発生する粉じん汚染の影響を強く受ける。
③当該施設から搬出される30~40万㎥に及ぶとみられる大量の土砂の行き先のひとつとして挙げられる市内郷原のベントナイト掘削跡地に至るルートを生活道路としている地区に住んでおり、多数のトラックの輸送による騒音、振動、交通事故リスクの影響を強く受ける。
4. 生活環境保全上の見地からの意見:
(1) 杜撰な計画のまま当該施設設置申請がなされており生活環境保全上、重大な脅威がある。
設置申請書には平成25年10月22日の日付があるが、今回縦覧された申請内容を見ると、紙の色や質が異なっているページがあったりして、あきらかに申請後差し替えた形跡がある。
このことについて、実施機関である廃棄物・リサイクル課に確認したところ「平成25年10月22日の本申請後、いろいろな変更・修正・訂正部分がある。今回、縦覧に供したのは、その時点での計画内容であり、これで確定した内容と言うわけではない」というコメントであった。
これでは、未成熟な申請内容に対して、意見書を出すことになり、そもそも、意見書を出す意味がない。
もっとも、実施機関としては、形式的に手続きを進めるだけだから、地元自治体や住民らやどのような意見書が提出されても、第三者機関を装った審査会で、そうした意見に対して、いちいち討議するわけではなく、結局、設置許可という最終目的に向けたひとつの過程に過ぎないと考えているのである。
従って、いくら地元住民が、とりわけ、当該施設から排出されるサンパイの浸出水が流れ込むため池や灌漑用水路の水を使って農地を耕作させられることになる水利権者らが、このような無謀で杜撰な計画には許可を出さないでほしい、といくら叫んでも、実施機関は平然と許可手続きを進めるのである。これには、平成19年4月に、同じく地元の大谷字西谷津で稼働を開始したサイボウ環境㈱による管理型一般廃棄物処理施設の際にも、実施機関が地元住民の生活権や水利権を無視して許可を出したという前例がある。
今回の申請に際して、環境資源の役員をしていた中島信義は、かつてサイボウ環境の申請手続きの際に、群馬県の林務部長や環境局長の任にあった人物である。
環境資源の渉外担当をしている角田穣は、中島信義の懐刀として、サイボウ環境の申請手続きの際に、サイボウの社長らによる進入道路(市道)の境界確定に関わる虚偽公文書の作成及び行使で、地元住民が警察に告発した際の火消し役として暗躍した人物である。
さらには、当時、中島信義の部下として、サイボウ環境の申請手続きの行政側の実務担当だった青木勝は、現在、群馬県環境森林部長である。
これらの人物は、サイボウ環境の処分場施設設置申請手続や、許可後の、間組による進入道路の工事手続、大林組による準備工事の過程で、道路法、河川法、建築基準法、農地法などの違法行為を住民が告発や指摘をしたにもかかわらず、警察と結託したりし全て握りつぶした。
とりわけ、処分場の浸出水の放流先である下流の水田耕作者が最後まで水利権を主張し、許可の無効確認を求めた行政訴訟において、群馬県は安中市と結託して、業者に溜池を作らせ、井戸を掘らせて地下水をくみ上げ、さらには高崎市の水道局から水道管を引っ張って来て(大谷地区の水道は以前から高崎市水道局から給水されている)、溜池の脇に設置し、水田耕作者があくまでも天水による水稲栽培にこだわったにもかかわらず、灌漑用水の確保はなされたという論理で、下流耕作者の水利権を無視して、直ぐ上流に管理型一般廃棄物処分場をサイボウ環境に作らせたのである。
また、県道から処分場までの1キロ余りの距離に、廃棄物を満載した大型ダンプトラックが通行可能な搬入道路(進入道路とも言う)を設置する必要があったため、この工事について、安中市は、既設の地元生活道路である市道を業者が拡幅することを認めるとともに、一部の区間の隣接地権者に反対者がいたため、あらたに県道との間に道路を建設し、安中市に寄付させて市道認定した。さらに、市道に隣接した土地の所有者らとの境界の確定書についても、サイボウ環境が、3名分を勝手に偽造し、1ヵ月半前に死亡したはずの人物の署名と押印をしたりするなど、3名分を勝手に偽造し、それを安中市は受理した。
また、県道とサイボウ環境が市に寄付した市道との取付部においては、道路法による交差点協議で境界確定書が、サイボウ環境から群馬県に提出されたが、この時も、隣接の山林の地権者が30年前に亡くなっているにもかかわらず、サイボウ環境が偽造書類を作成し、群馬県に提出して受理された。
これらの業者の犯罪行為について、地元住民らが警察に告発したが、いずれも作成したのはサイボウ環境ではなくてサイボウから境界確定業務を請け負った測量会社だったとして、刑事裁判ではサイボウ環境ではなく測量会社が有罪(しかし執行猶予付き)となった。だが、不思議なことに、サイボウ環境が虚偽の境界確定書を行政に提出した(偽造公文書行使)にもかかわらず、刑事裁判ではこの点について行政も警察も、さらには、前橋地裁も判決で不問にした。
こうした信じられないほどの行政と業者との癒着の経緯が過去に実際に起こっていることから、今回も、当該施設設置について、杜撰な計画申請にもかかわらず、本申請の最終段階である公告縦覧までステージを進めることができた構図が見て取れる。
このような、いわゆる申請業者と許認可権者の間の「デキレース」により、生活安全上の問題が十分にチェックされないまま、設置許可が出されてしまうことに地元住民として強い危機感を感じている。
(2) 杜撰な計画のまま設置許可に向けた本申請の手続きが進むことに対する懸念
上記のとおり、当該施設の建設計画は、サンパイ行政に携わっていたOB幹部が業者に天下り、かつて部下だった現役の行政幹部に対して、許可申請をしているため、いわゆる官業の形をとった、官官談合手続ともいえる構図となっている。
だから、事前協議を経たにもかかわらず、平成25年10月22日の設置許可申請日以降も、何度も業者と行政との間で変更・修正・訂正が繰り返され、それらが平然と申請書で差し替えられている。驚くべきことに、実施機関である廃棄物・リサイクル課の担当者によれば、「さらに今後も、どのような変更・修正・訂正が起きたとしても、それらは軽微な変更として取り扱われる」という。このため、縦覧に供された申請書を見て意見書を書いても、それは全く仮の計画を対象にしたものであって、外形的に体裁が整ってさえいれば、後で業者の都合のよいように自由に計画変更ができるのである。
こうして、行政にとっては天下り先や裏金の確保として、一方業者にとっては、ひとたび申請許可が出れば、巨額の利権が保証されたようなものであることから、双方の思惑が一致して、呆れるほどズサンな計画であっても、利権重視の当事者同士で、どんどん手続が進行するのである、
しかも、手続の過程で、後述の添付資料2でも明らかなように、行政側が懇切丁寧に業者に対して修正を指南しているため、本申請からわずか8カ月足らずで今回の公告縦覧に至っている。
意見書提出者の地元利害関係人としては、この8か月間に業者と行政との間でやりとりがあったのかを確認すべく、7月16日の従来最終日に情報開示請求を行ったところ、7月24日に電話で開示決定通知があったため(添付資料1参照)、同28日に8ページの資料の開示を受けた(添付資料2参照)。
これを見ると、平成25年12月24日に10項目の指示が業者に対して出されている。
①焼却残渣と不燃性廃棄物はサンパイの種類から削除。
②業者の関係者の個人情報の記載がいずれもいい加減なので訂正。
③埋立予定のサンパイの種類から一般廃棄物を除外。
④水質関係で、処理後のpH値の整合性がないので要確認。
⑤水質関係で、チラウムというニセ化学物質名を記載したり、水質維持管理面で受け入れ基準を規定しておらず要チェック。
⑥公図の情報で、面積がデタラメで所有者名が無記載。
⑦長期借入金の資金手当ての記載がデタラメで、融資の実現性が無記載。
⑧施設構造について、処分場周囲に張り巡らせるフェンスの仕様が未記載、排水管のサイズが未記載、調整池で「穴吹」など他案件の情報をコピペした形跡、排水先の開渠の管理責任が曖昧。
⑨維持管理体制に関する「散霧処理」「電磁的記録」「監視カメラ」「遮水工の点検と破損時の措置」「調整池破壊時の措置」「浸出液処理設備の異常発生時の措置」「水質測定時の採取・検査体制」についての記載不備。
⑩当該施設の災害防止計画について、「散霧処理」「即日・中間覆土」「漏水検知システム、モニタリング、漏水個所の止水方法」「地震時の点検個所と機能回復方法」などの未記載。
さらに、2日後の12月26日には追加の6項目の指示を業者に出している。
①「埋立容量計算」「覆土計画量」の記載が不備。
②「縦断面図・横断面図」の記載不備。
③「土量計算」で、切土・盛土量一覧表が不正確。
④覆土材の確保計画書で、覆土13万㎥と残土30万㎥の計画がデタラメで、覆土置場、残土処分場の目途がない。
⑤浸出水処理計画で、1日あたりの浸出液の計算がデタラメ。
⑥プロセス計算量で、流入汚水量・設計汚水量の想定が不一致。
続いて、平成26年1月7日に3回目の指示として5項目が業者に示されている。
①搬入道路の横断面図の盛土勾配がデタラメ、補強土についても未記載。
②地下水集排水管の配置図と構造図での仕様とサイズの記載が不一致。
③構造図の門扉とフェンスの材質が未記載。
④展開検査場の未記載。
⑤雨水排水計画で、「雨水排水の流れ図」「洪水調整池への排水路」「雨水排水流入フローと集水面積、雨水排水設備計算書」「洪水調整池の集水面積と流出係数」「降雨量(毎時141㎜)」について、未記載あるいは記載不十分。
その後、平成26年5月12日に、4回目として追加4項目の指示が出ている。
①許可申請書の申請者欄が未記入。
②プロセス計算書における炭酸ソーダ注入ポンプの計算式に漏れ。
③見積図書仕様書における、騒音基準値と振動基準値の不整合。
④搬入道路横断面図の図面不明瞭。
これほど多くの修正指摘項目が本申請以降に存在すること自体、業者における生活環境保全上の観点が初めから疎かになっていることを如実に物語っている。
この背景として、やはり前項で指摘したように、12年前に退官した元・群馬県環境行政のトップだった人物が業者に天下り、その威光によって、行政手続きなどどうにでもなるとする業者側の緊張感の不足が挙げられる。また、サイボウ環境の廃棄物処分場計画で、虚偽公文書作成・行使をしたサイボウに対して、犯罪を不問にしたことから、不誠実な業者でも全く処罰を受けなる心配はない、とする前例主義を持ち出して、「行政手続法の観点から迅速に手続きを進めなければならない」という本末転倒な行政論理を、行政側も業者側もかざしているのである。
こうして、一旦、サンパイ場の許可がおりれば、あとはいくら地元住民が反対運動を起こしても、時間をかけて、アメとムチで対応すれば施設設置工事に着手できることになる。
その間、水利権者をはじめ地元の利害関係者らがいくら行政に対して、悲痛な叫びを投げかけても、群馬県はシランプリを決め込む。このことはサイボウ環境の施設設置手続きから施設着工までに行政がとった対応から、明らかである。だから、生活環境保全上の観点からいくら我々住民が意見書で意見を述べても、無意味なのである。
(3) ダイオキシン類の排出による周辺の生活環境や営農環境への重大かつ深刻な影響
申請書の第1面に、「設計計算上達成することができる排ガスの政情、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値」として、放流水質のPH:5.8~8.6、BOD:10㎎/L以下、COD:20mg/L以下、SS:10mg/L以下、T-N:10mg/L 以下、Ca2+:160mg/L以下、ダイオキシン類2.4pg-TEQ/Lとある。
もともと、デタラメな業者による杜撰な計画なので、本当にここに書いてある数値が維持できるのかどうかも、あてにならないが、この数値自体、言語道断で許せないレベルである。
環境省の基準によれば、JIS K0312に定める方法による水質(水底の低質を除く)のダイオキシン類は年平均値で1pg-TEQ/Lが上限となっているが、当該施設のダイオキシン類による生活環境への水質負荷は、この2.4倍となっている。
(4) 全窒素(T-N)の高レベル排出による農業用水への重大かつ深刻な影響
上記に示す通り、当該施設から排出される水質のT-N値は10mg/L以下とあるが、水稲は農業用水中の窒素(特にアンモニア性窒素)濃度が高いと、栄養生長期(苗を本電位移植後約40日間)に過繁茂状態となり病害を受けやすくなる。また穂くび分化期に多量の窒素があると下部節間が伸びすぎて倒伏したり登熟不良となったりする。これらの結果、水稲の減収を招く。このため、農水省は昭和45年(1970年)、各種の調査研究成績に基づいて水稲に被害が発生しないための望ましい農業用水のT-N基準として、1mg/Lを発表している。
ところが、当該施設が出す水質のT-N負荷は、その10倍となっている。これは周辺や下流の生活環境、営農環境保全上、重大かつ深刻な影響を及ぼすため、到底容認でいない。
(5) 化学的酸素要求量(COD)の高レベル排出による下流水道施設への重大・深刻な影響
水道法では、基準項目の1つとして,CODが10mg/L以下と定めている。だが、現在では「快適基準」として推奨される3mg/Lをクリアするようにしている水道事業者も多い。環境庁が「好ましい」とする水質基準も3mg/Lとしている。現在、この基準をクリアしている湖沼は、全体の4割程度にすぎない。だからといって、当該施設のようにCODが20mg/Lになる汚濁排水を農業用溜池や農業用水路に流入させていいはずがない。岩井川の水源でもある新山の溜池から出てゆく水は、碓氷川を経て烏川を経由し利根川にそそぐ。この流域には多数の水道施設があることは誰でも知っている。
従って、下流の首都圏の住民に出来る限り安全な水質の水資源を供給するのは、我々銃流域に暮らす地元住民の責務である。よって、当該施設から排出される水質のCOD負荷レベルが20mg/Lというのは到底容認できない。
(6) 浸出水処理施設のデタラメな計画仕様による生活環境保全への重大な影響
申請書の第1面に、排水処理量として「浸出水処理量 最大200㎥/日」とあるが、面積33,536.72㎡の処分場に年間降水量1800㎜が降り注ぐとすると、自然蒸発・蒸散量が多少あるにしても、ほぼ全量が浸出水として当該施設外部に排水される。よって、33,536㎥×1.8m/365日=165.4㎥/日となり、見かけ上はクリアするかもしれないが、実際には365日常時運転することはありえない。メンテナンスの期間が当然必要になる。したがって、排水処理施設の処理量の設定には疑義がある。
また、当該施設より一回り小さいサイボウ環境の処分場の浸出水処理施設は、最大100㎥/日の処理量だが、地元住民が内部に立ち入ることは許されていないので、だれも稼働中の浸出水処理施設を見た者がいない。サイボウの計画でも、今回の当該施設の浸出水処理施設と同様な仕様だったが、本当に稼働させるのかどうか、そのまま処理せずに垂れ流しにするのか、地元住民にとって、一旦施設が稼働してしまうと、に内部立入が業者や行政によって拒否されて実態が分からない為、全て秘密のベールに覆われてしまうことになる。
よって、こうした情報秘匿の実態を見るにつけ、実施機関が設置申請に対して許可を出してしまうと、あとは、地元住民として、永久に実態を知らされないままとなってしまう。したがって、申請手続きの中で行政がいくら指摘したり、業者がいくら耳触りの良いことを述べたりしても、全く信用できない。
(7) 行政から住民への情報提供の不正確・不十分性による計画内容の理解阻害の影響
「廃棄物処理施設設置計画予定地 明細書」で、安中市の保有する公有地(道、山林)がある。そのうち456.49㎡は「払下げ予定」とあるが、安中市の岡田義弘・前市長は、市道の用途廃止をした方が、業者の事業推進に対してブレーキになるという説明であったが、どうやらその説明がウソだったようだ。このほかにも、市有財産が、サンパイ業者にいつのまには払下げられてしまう事態が、サイボウ環境の処分場設置申請手続きでも同様に行われていた。
納税者である住民へのこうした行政の背信行為は、行政と住民との円滑な意思疎通のための信頼感醸成に対する挑戦である。
(8) 番号3の「産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項」の「4 生活環境境への負荷に関する事項」における周辺への悪影響
処理前の水質レベルの酷さに加え、処理後の水質についても、前述のとおり、ダイオキシン類やCOD、T-Nの計画値が、到底容認できないレベルとなっている。しかも、浸出水処理施設がきちんと稼働するかどうか、稼働後の周辺住民の立ち入りはサイボウ環境の施設を例にとっても、実現されておらず、生活環境上に与える不安は深刻であるので、絶対に申請を許可しないでほしい。
(9) 番号12の(別紙6)「施設の設備及び維持管理に要する資金の総額及びその調達方法を記載した書類」におけるデタラメ情報による生活環境保全上への影響
①「(1) 施設の設置等に要する資金」の「用地費」
同資金として7,000千円×15年=105,000千円とあるが、これは土地の保有者である須藤良人らへの借地料のようだ。高崎市で税理士事務所を営む須藤良人は、業者の役員(監査役)にも名を連ねている。また業者は、15年間という事業期間だけを想定しており、16年以降は、事業継続を前提にしていない。
因みに安中市松井田町松井田字百八にある安中・松井田一般廃棄物最終処分場(着工:昭和61年9月25日、竣工:昭和62年3月15日、敷地面積:30,084㎡)は、回転円盤法+凝集沈殿法の浸出液処理設備を保有・運転しているが、埋め立てが完了した平成15年2月28日から既に11年が経過してもなお、浸出水の水質が一向に改善せず、安中市は多額の予算を投入して浸出液処理設備を稼働させ続けている。
当該施設の場合、業者は15年しか事業を想定しておらず、埋め立てが完了後は「野となれ山となれ」という実に無責任な計画である。
よって生活環境保全上の観点から、当該施設の設置は許されてはならない。
② 同じく「造成費」「建物費」
業者は、それぞれ23億円+11億円=34億円を見込んでいるが、これはサイボウ環境の時の施設設置に要したコストと同額である。しかし、今回、当該施設の建設に際して業者は、40万㎥もの掘削をして、サンパイの埋立量を少しでも多くしようと画策している。この土砂の掘削費や、残土の運搬処理費用(しかも、残土処分地や残土仮置地など未決定の状況)などを勘案すると、到底34億円では追いつかないと思われる。となると、土堰堤工事や遮水工、浸出水処理施設工事などが、その分手抜きされることになる。結局、安全対策がないがしろにされてしまうので、生活環境保全上に深刻な悪影響を与える。
③「(2)施設の維持管理に要する資金」
ここで、保守管理費、光熱水費、人件費、その他を計上しているが、役員報酬の計上も見当たらない。さらに、何年間の期間なのか記されてない。多分15年間なのだろうが、その後はシランプリとなると、生活環境保全上、深刻な問題が生じるのは自明の理である。
④「(3)資金の調達方法」
自己資金1億円、制度金融28億円、金融機関からの借入7億円の合計36億円で、設備費と、操業開始費用である維持管理費×1/2を賄うという計画のようだが、資本金300万円のペーパー会社に28億円もの融資をする政府系金融機関があるのか。また、民間の金融機関でこんな吹けば飛ぶようなペーパー会社に7億円も貸し付けるところがあるのか、信憑性に欠ける。
こんないい加減な資金計画でも、本申請として業者が平然と提出し、それを平然と受理する行政も行政である。業者も行政も「許可が出たら、金融機関がそれを担保に金を貸すだろう」と思っているのかもしれないが、こんなデタラメな計画では生活環境保全上の観点から地元住民、利害関係者として、到底容認できない。
(10) 番号13の「履歴事項全部証明書」
出資者として、ここにあるオージービジネス有限会社の登記謄本が掲載されているようだが、この会社は、静岡県清水市大内にある中間処分業兼産業廃棄物収集運搬業者で、破砕の他に石膏ボードの分離と廃棄物を原料とした燃料、RDFを製造している。したがって、廃棄物の最終処分の経験はなく、しかも、同族会社らしいが、実態は不明である。こうした業者が36億円ものコストをかけて、安全、安定、安心な事業ができるのだろうか。生活保全上の観点から地元住民、利害関係者として、到底容認できない。
(11) 同じく「金銭消費貸借契約書」
ここに7通の金銭消費貸借契約書があるが、いずれも平成25年5月31日に締結し、借入金弁済期日は平成26年12月30日となっている。また、債権者としては、藤江哲彦が1億415万円、オージービジネス有限会社が2億8360万円、岡村譲二が1480万円、鬼形忠雄が1459万5千円、中島信義が300万円、伊東功が300万円となっているが、鬼形忠雄は環境資源の代表者であり双方代理となっており、民法上問題がある。
また、中島信義が300万円を貸し付けているが、いくら退官後10年以上が経過しているとはいえ、行政の表も裏も知り尽くし、当時の部下が現在の環境森林部長という関係であるから、極めて道義的に問題である。
このような役所の幹部職員の天下り先に対して、これほど便宜を図ってやる必要はどこにあるのか。生活環境保全上の観点から、こうした業者に対する設置許可を出すことは納税者である県民との信頼に違背するものである。
(12) 業者の「定款」
環境資源の定款は平成18年5月24日となっており、登記を同5月26日にしたことからこの日が会社設立日となる。この時、役員として、鬼形忠雄、角田穣のほかに、中島信義がおり、平成25年6月15日まで約7年間、取締役に就任していた。この他、取締役として平成21年2月1日に石原正巳が就任し、その後、平成22年2月18日に岡村譲二、平成24年5月28日に藤江哲彦、平成25年6月15日に岡村知洋と江口由佳子が取締役に就任した。また、予定地の山林を保有する地権者の須藤良人が、監査役として、平成22年6月10日に一旦退任したが、そのまま登記せず、平成25年6月15日に再び監査役に就任した。このように、役員の任期切れ(定款によれば役員の任期は4年以内とある)に気づかず、役員変更登記を3年間もほったらかしにしていたことから、罰金の対象になったはず。このように杜撰な業者の組織と運営管理の実態を見るにつけ、本当に、34億円もの大事業を遂行する能力があるのか、極めて疑わしい。こうしたデタラメな業者が推進する当該施設は、生活環境保全上、さまざまなトラブルが予想されるので、設置許可を出してはならない。
(13) 業者の「納付税額」
環境資源の納付税額一覧表によれば、法人市民税は年間たった6万円しか納入していない。利害関係者である意見提出人でさえ、現在、地方税として年間約24万円納付している。しかし、群馬県は、サンパイ税を業者に課税しようとせず、森林環境税を我々中山間地の生活環境保全に尽力する我々住民に課税し始めた。
この様な理不尽な課税体系の下で、わずか年間6万円しか法人市民税を支払っていない業者の推進する迷惑施設の事業に、許可を与える筋合いはどこにも見当たらない。
(14) 番号18の「電気式漏水検知システム概要」
ここでは4種類のシステムが示されているが、どのシステムを採用するのか不明。また、メンテナンスは特に必要ないという記載もあるが、到底あり得ない。漏水時の対応策として、サンパイを掘り出して補修するなどと説明があるが到底信じられない。従って、このようなシステムは実際には、気休めにしかならない。一旦漏水が発生したら(それは遮水シートの劣化で数年以内に必ず発生すると思われる)、周辺や下流の地下水は確実に汚染されることになる。よって、生活環境保全上から、当該施設の建設は許可するべきでない。
(15) 番号19の「最終処分場の災害防止計画書」
この中で、「即日覆土」とあるが、信用できない。また「二重遮水シート」とか「自己修復性マット」を使用するとあるが、15年間以上はおろか、数年間の耐久性さえ保証されない。一旦造られたら、周辺の地価類汚染は不可避となり、対策は不可能である。下流域への洪水対策は防災調整池と雨水排水処理設備で行うというが、時間当たり100ミリを超える集中豪雨や、1日当たり400ミリ以上の豪雨で池の容量が満杯になり、処理設備の能力をはるかに超えた場合、どのような対策を取るというのか。地震発生時は直ちに処分場の各設備を点検し、異常が有れば関係機関へ連絡し、補修を行うというが、土堰堤が崩壊したり、大規模な土石流が発生したりして、周辺や下流域に災害を及ぼした場合、どのように対処するのか。単なる作文では済まされない。岩野谷地区を流れる岩井川の水源域にこうした人工構造物を造成することは、災害時のリスクが地域に広い範囲に及ぶため、これ以上、大規模な造成を行わせないように、当該施設の建設は許可すべきでない。
(16) 番号26の「残土及び覆土材の確保計画」
業者は、残土処分及び覆土の確保地として、安中市郷原の豊洋ベントナイト掘削跡地を予定しているという。しかし、当初、業者は藤岡の佐田建設の工事用残土置き場を借りるため契約交渉中だと説明していた。また、今年の3月には、環境資源の角田穣らが、当該施設計画地の直ぐとなりの高崎市吉井町上奥平地区の地権者をこっそり回って、30万とも40万㎥とも言われる残土の埋立の打診をして問題になり、地元議員が3月定例の高崎市議会で質問をした際に、高崎市は群馬県から何も聞いていないとして、環境資源からの残土持ち込みは決して許さないという趣旨の発言があった。このことは、実施機関である群馬県が、業者の行動を黙認していたことになる。やはり、群馬県の環境行政の元トップが天下った業者の底力を、群馬県が認識していたということができる。
未だに残土処理のめどがついていないにもかかわらず、群馬県廃棄物・リサイクル課では、「どうやら安中の郷原に決まったらしい」などと無責任なことを言っている。
確かに安中市の都市整備課の計画係に聞いてみると、都市計画の線引きをしていない安中市では、残土条例の制定が遅々として進んでいない。これは、環境資源を含むサンパイ業者の意向を汲んでいた前安中市長が、残土条例の制定に不熱心だったこともあるが、市議会の中にも、サンパイ業者の息がかかったのがいるため、未だに残土条例の交付のめどが立っていない。都市整備課計画係によれば「平成27年度中には何とかしたい」というが、前市長の息のかかった残党が幹部として居座っているため、残土条例を持たない安中市内に大量の残土が処分される恐れがある。
そうなると、当該施設建設工事に伴って発生する切土量448,367㎥を一旦、ベントナイト掘削跡地に運び込み、そこから、土堰堤用に14,980㎥の土を建設工事現場に戻し、さらに、覆土用として130,000㎥の土を、必要に応じて郷原から大谷の奥まで運搬することになる。20㎥の土砂を運ぶダンプトラック換算で、工事期間中2万3千台近くのトラックが市内を往来し、さらに、土堰堤工事で7,500台が右往左往し、その後も15年間に覆土を運搬するダンプが延べ6万5000台市内を行き交うことになる。
そうすれば、意見書提出人の住む野殿地区の生活道路でもある市道にダンプトラックが殺到し、通勤や通学、買い物に出かける住民らの交通安全が脅かされ、沿線周辺に住む住民は騒音や振動、粉じんなどに悩まされ、しかも、重量車両の頻繁な通行によって市道は痛み、その補修等の費用も住民に転嫁されることになる。
また、郷原のベントナイト掘削跡地に残土を埋め戻すというが、現地のスペースと、残土量のバランスがとれているのかどうか、全く記述が無い。にもかかわらず、群馬県廃棄物・リサイクル課では、特に業者に対して訂正指導をした形跡が無い。いくら、現・環境森林部長の元上司が、業者の取締役(現在は出資者)としてかつての威光を盾に実施機関に対して圧力をかけているとはいえ、余りにも業者に対して対応が甘いのではないか。このような疑惑が根底にあるため、きっぱりとそうした関係を払拭し、しがらみと決別するためにも、生活環境保全上の観点から、当該施設に許可を出してはならない。
なお、業者は、豊洋ベントナイトから平成26年3月31日付で県知事宛ての「開発行為期間延長届出書」の写しを申請書に添付しているが、この届出書を受理したのも西部環境森林事務所である。つまり、当該施設の設置申請を受け付けて、許可手続きをしている環境森林部廃棄物・リサイクル課と同じ部内の部署同士なのである。これでは、完全にマッチポンプのデキレースではないか。
(17) 番号28の「見積図書仕様書」
このなかで、「浸出水処理施設は、・・・長期安定的に処理するものである」だとか、「埋立期間約10年間(経済動向による変動あり)」だとか、根拠のないことが記されている。このうち「第6節 保証」において、当該施設の保証期間はわずか2年で、屋根や外壁の仕上げや基礎部の雨水・地下水の侵入防止に関わる部分の建築工事に関する瑕疵担保期間は10年で、水槽部分の防水が10年、防食が5年としている。これではあまりにも杜撰な工事を誘発しかねない。埋立が終われば、当該施設を造った業者も、その施設を運営する環境資源も、あとは他人事だというに違いない。だから、当該施設の設置申請に対して許可を出してはならない。
以上
<以上引用終わり>
イ 審査請求人は、上記意見書を群馬県に提出したが、3月26日に部 分開示された全情報を見ても、審査請求人の懸念する事項について、群馬県が事業者にどのような指導をしたのか、そして事業者である環境資源がどのような対応をしたのかどうかすら、全く確認できていない。
ウ まして、環境資源は既に存在すらしておらず、千葉県に拠点のある城装 という事業者が主体となって設立したジョウソウなる法人が、なぜ環境資源がそれまで行政や地元関係者と協議をしてきた経緯や結果をそのまま継承しえるのか、などなど、不明点や疑問点について、合理的な説明もなく、手続きの途中でバトンタッチできるのか、上記意見書を提出した地元住民として、また納税者県民として、そのことについて、群馬県や安中市から合理的な説明を受けていない。
エ そもそも群馬県は、特定地域に廃棄物処理施設が集中することを避けるために、条例を制定しているはずである。そのことを群馬県廃棄物リサイクル課に指摘すると、「本件は環境資源が設置計画を申請した時点ではまだ発効しておらず、適用外だ」という。しかし、今回の事業者はジョウソウであり、そもそも事業者が実質的に異なるのであるから、適用外という判断は当てはまらない。また、ジョウソウは地元関係者に対して同意書を採っているのかどうかも確認できておらず、環境資源が平成19年当時に取得した同意書(これすら、偽造の疑いを免れない)をそのまま踏襲しているとなれば、その有効性についても疑問符がつく。
オ さらに群馬県知事は、今年2月3日の設置許可処分の前段として、令和2年12月25日の午前9時ごろ、環境森林部長や廃棄物リサイクル課長を同道し、安中市長らに面談の為、安中市役所を訪問している。その際、「設置許可申請のための書類が揃っているので、これ以上、先延ばしできない」などと安中市側に説明したという。審査請求人はこのことについて、安中市側に情報開示請求をしたところ、安中市には当該協議に関する議事録がない、とのことで、どのような説明が群馬県側からなされたのか確認できていない。すくなくとも、審査請求人が意見書で述べた懸念事項等について、明確な説明が短時間でなされたとは到底思えない。
カ 地元住民らが強く反対し、安中市行政としても設置を望んでいない、このような関東圏で最大クラスの大規模サンパイ処分場設置について、県民の安全・安心な生活環境の保全を司る群馬県が、住民の声にも耳を傾けようとせず、十分な検討や精査も尽くさないまま、設置許可処分をすることはできない。よって、「1記載の処分を取り消す」との裁決を求める。
4 処分庁の教示の有無及び教示の内容
なし。
5 証拠書類等
①産業廃棄物処理施設設置許可証
②産業廃棄物処理施設設置許可申請書
③公文書部分開示決定通知書(審査請求人が本件処分を知った日は開示日の令和3年3月19日(金)10時30分~11時ごろであることを示す)
④行政文書開示決定通知書(県知事が令和2年12月25日(金)09時に安中市役所を訪れたことを示す)
⑤公文書開示決定通知書(令和2年12月25日に群馬県知事が環境森林部長、同部廃棄物・リサイクル課長、同係長、秘書課係長を同道して安中市長らと面談し、知事が「ジョウソウの設置許可申請について、廃棄物処理法の許可要件を満たしているため、県は許可しなければならない」と安中市長に説明したことを示す)
ZIP ⇒ 202106182r15.zip
⑥審査請求人のブログ記事(2014年7月10日掲載)
ZIP ⇒ 202106183r6.zip
⑦同上(2014年7月13日掲載)
ZIP ⇒ 202106184r7.zip
⑧同上(2015年4月10日掲載)
ZIP ⇒ 202106185r8.zip
⑨同上(2015年4月11日掲載)
ZIP ⇒ 202106186r91.zip
202106187r92.zip
以上
**********
■今回の設置許可処分でもっとも不可解なのは、サンパイ施設許可申請者の地位承継がなぜこんなにも簡単にできるのか、ということです。サンパイ施設の設置許可後であれば、施設の譲り受けや借り受け、あるいは事業法人の合併や分割について、ある程度現実味があるかもしれません。
しかし、今回は市内の不動産屋が主体となって設立した環境資源が、県の大物職員OBらを使って、地元の一部の住民をカネで釣って、強引に同意をとり、なんとか事前協議を終えたものの、本申請になってからカネ詰まりとなり、事業から撤退するにあたり、そのまま県外、それも千葉県市原市にある㈱城装にそっくり申請者の地位を承継させることができるものなのか、筆者には全く理解できません。
群馬県廃棄物・リサイクル課いわく、「廃棄物処理法に、地位継承が出来ないとは書いてない。なので、地位継承ができると認識している」というのです。こんな法律があるのでしょうか。なぜなら、最初に事前協議だけでもなんとかクリアさせて、次に本申請をしておけば、あとは資力のある中堅のサンパイ事業者に権利を高く売りつけて、それまで投資したコストを回収すればよく、後から承継したサンパイ業者にとっても、最初のダーティな仕事をやらずに済むので都合がよいわけです。
しかも、施設の敷地境界線から300m以内に住む関係住民の同意についても、たとえ承継前のサンパイ業者があれこれ押印偽造などを駆使して10年や20年前に作成したものでも有効だということになるため、あらたに承継して許可申請者となった業者のこともしらない関係住民の同意書はそのまま問答無用で流用されることになります。こんな理不尽なことがまかり通ることなど信じられません。もし本当にそれが可能だとすれば、廃棄物処理法自体、重大な欠陥があります。おそらくこの法律自体、政治的な思惑もあって、こうした欠陥を敢えて見逃す内容に仕立て上げられたものだと言えるでしょう。
■地元住民が、突然㈱ジョウソウという聞き慣れない事業者による「株式会社ジョウソウ(旧環境資源)管理型最終処分場事業住民説明会」が開かれたのは平成29年10月14日でした。その1年後の平成30年10月19日にジョウソウから「会社情報の変更等に関する申立書」が群馬県廃棄物・リサイクル課あてに提出されました。
当然、ゼロから手続きを始めるのがスジであり、もういちど近隣住民の同意を得るために地元住民を含む周囲地権者、土地所有者、土地使用者への説明会の開催が必要となるはずです。そもそも、長年にわたり、環境資源の計画について、地元住民と揉め続けてきた事実を、群馬県はどのように考えているのか、極めて強い不信感を覚えます。
【ひらく会情報部】