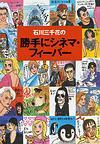
この本を読みながら石川さんがここで取り上げる映画はほぼ全部リアルタイムで見ていることに気付く。なんだか懐かしい。彼女は僕より少し年上なので、最初のほうは少し苦しいが、おぼろげな記憶はある。70年代から映画を見始めた。
本格的に外国映画を見たのは74年のことだ。忘れもしない。ウイリアム・フリードキンの『エクソシスト』である。この1本で完全に映画に嵌った。僕は怖がりなのでホラーなんてお断りだったのに、中学の友人に誘われてついつい見てしまった。今はなき梅田東映パラスである。あの大スクリーンであのリンダ・ブレアを見たのだ!衝撃で、2,3日寝れなかった。
その後、すぐにイタリア映画『青い体験』を見に行った。これは中学生だから、である。(こういうエッチっぽい映画に嵌る時期だったのだ。)映画はまぁまぁ、だったが、同時上映されていた(昔は2本立ロードショーなんてのもあった)わけのわからない映画に魅了された。フランソワ・トリュフォーの『アメリカの夜』である。(それにしても当時の番組編成は異常としかいいようがない。こんな2本立ありえない!)
子供だったから、正直言うとなんだかわからない映画だった。だが、この映画の大人の香りに触れたことは大きい。偶然からとはいえ凄い映画と幼少の頃に出会っている。(まぁ、中3だが)その後、僕がトリュフォーに嵌るには当然の成り行きだろう。
さて、こんな昔話を書こうとしてたのではない。石川さんの昔話の感想だった。だが、もうどうでもよくなった。だいたこんなところに書くことは何もない。この本は実に面白かった。それだけである。ただ、言いたかったのは、あの頃(70年代から80年代)映画は共通体験だった、ということだ。映画は今のように消費され一過性のものではなく、みんなの記憶に残るものだった。だから、ここに取り上げた作品はあの時代を生きた誰もが納得にいくものなのだ。
だが、今、映画は数ある娯楽のひとつでしかない。すぐに忘れられる。しかも、優れた映画は誰も見ない。なんだか詰まらない時代になったものだ。ヒット作は押しなべてTV局が作ったくだらないTVもどき。みんなの心に残る大作はない。
74年。野村芳太郎監督『砂の器』が公開された。僕の映画体験の原点はあれだ。何度見たことだろうか。宿命の調べにのって日本全国を横断する父と子巡礼の旅。あの映画は国民的大ヒットを記録した。そして僕のような映画ファンを日本中に生んだ。たくさんの観客が支持して、しかも映画自体も優れている。そんな映画は今はもうない。
最後にもうひとつ。石川さんが取りあげた映画の中に、シドニー・ルメットの『狼たちの午後』があった。とてもうれしい。高2の時にこれを見た。映画の面白さを堪能した作品だ。忘れられない。
ここに取り上げられた映画のほぼすべてがどこで誰と見たか、覚えている。あのころ映画は特別なことだったからだ。だが、今、映画はただの日常になってしまっている。なんだか、悲しい。
この本を読んで、思いついたことがある。74年から08年まで、僕は自分が見た映画や芝居のメモをつけている。これから暇な時に(そんな暇はないが)月1回くらいのペースでノートを見ながらその1年を振りかえってみよう。と、いうことで石川さんのこの本に倣って来月から僕も「プレイバックシリーズ」をすることに決めた。第1回は1991年にしよう。もし、よかったら読んでください。
本格的に外国映画を見たのは74年のことだ。忘れもしない。ウイリアム・フリードキンの『エクソシスト』である。この1本で完全に映画に嵌った。僕は怖がりなのでホラーなんてお断りだったのに、中学の友人に誘われてついつい見てしまった。今はなき梅田東映パラスである。あの大スクリーンであのリンダ・ブレアを見たのだ!衝撃で、2,3日寝れなかった。
その後、すぐにイタリア映画『青い体験』を見に行った。これは中学生だから、である。(こういうエッチっぽい映画に嵌る時期だったのだ。)映画はまぁまぁ、だったが、同時上映されていた(昔は2本立ロードショーなんてのもあった)わけのわからない映画に魅了された。フランソワ・トリュフォーの『アメリカの夜』である。(それにしても当時の番組編成は異常としかいいようがない。こんな2本立ありえない!)
子供だったから、正直言うとなんだかわからない映画だった。だが、この映画の大人の香りに触れたことは大きい。偶然からとはいえ凄い映画と幼少の頃に出会っている。(まぁ、中3だが)その後、僕がトリュフォーに嵌るには当然の成り行きだろう。
さて、こんな昔話を書こうとしてたのではない。石川さんの昔話の感想だった。だが、もうどうでもよくなった。だいたこんなところに書くことは何もない。この本は実に面白かった。それだけである。ただ、言いたかったのは、あの頃(70年代から80年代)映画は共通体験だった、ということだ。映画は今のように消費され一過性のものではなく、みんなの記憶に残るものだった。だから、ここに取り上げた作品はあの時代を生きた誰もが納得にいくものなのだ。
だが、今、映画は数ある娯楽のひとつでしかない。すぐに忘れられる。しかも、優れた映画は誰も見ない。なんだか詰まらない時代になったものだ。ヒット作は押しなべてTV局が作ったくだらないTVもどき。みんなの心に残る大作はない。
74年。野村芳太郎監督『砂の器』が公開された。僕の映画体験の原点はあれだ。何度見たことだろうか。宿命の調べにのって日本全国を横断する父と子巡礼の旅。あの映画は国民的大ヒットを記録した。そして僕のような映画ファンを日本中に生んだ。たくさんの観客が支持して、しかも映画自体も優れている。そんな映画は今はもうない。
最後にもうひとつ。石川さんが取りあげた映画の中に、シドニー・ルメットの『狼たちの午後』があった。とてもうれしい。高2の時にこれを見た。映画の面白さを堪能した作品だ。忘れられない。
ここに取り上げられた映画のほぼすべてがどこで誰と見たか、覚えている。あのころ映画は特別なことだったからだ。だが、今、映画はただの日常になってしまっている。なんだか、悲しい。
この本を読んで、思いついたことがある。74年から08年まで、僕は自分が見た映画や芝居のメモをつけている。これから暇な時に(そんな暇はないが)月1回くらいのペースでノートを見ながらその1年を振りかえってみよう。と、いうことで石川さんのこの本に倣って来月から僕も「プレイバックシリーズ」をすることに決めた。第1回は1991年にしよう。もし、よかったら読んでください。

























