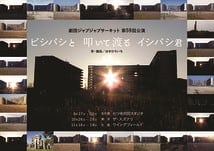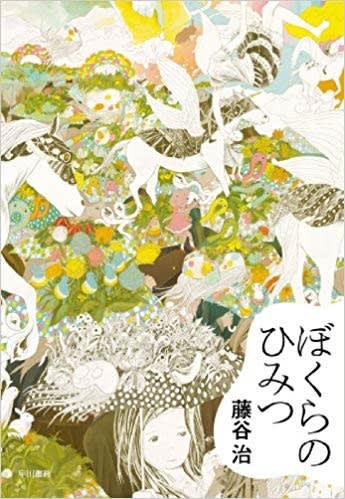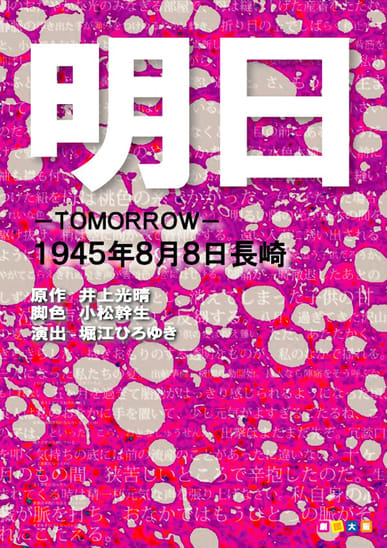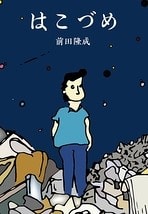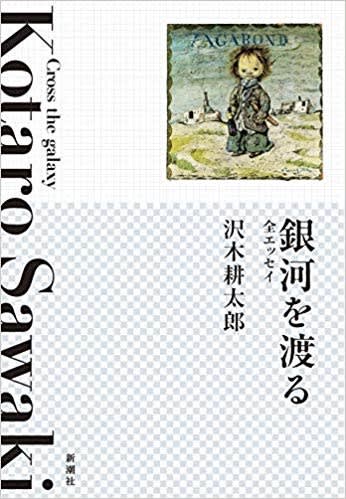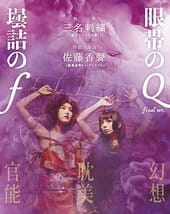3組の夫婦のお話だ。それぞれの事情が描かれていく。彼らがお互いと向き合い、今感じることをぶつけ合うわけではない。どちらかというと、あきらめだ。わかり合えない。でも、まだ終わりではない。それどころか、始まってもいない。3つの話は基本的には交わらない。オムニバスというわけではないけど、並行して描かれる。ニアミスくらいはする、その程度だ。近くに住んでいる。10階建てのマンション。3階建て . . . 本文を読む
思ったほど、凄い映画ではなかったけど、新人のデビュー作としてはなかなかの力作だ。2時間13分という長尺を最後まで見せる。もっとコメディタッチになるのか、と思ったのだが、そうはならない。ただ、この話なのにシリアスだけで、押し通せるわけでもない。そんなこんなで、なんだか収まりどころがよくないから、見ていて居心地が悪い。
でも、それはこのお話の重さのせいなのだろう。なんとも救いようのないお話だ。冒頭で . . . 本文を読む
一夏の冒険譚だ。ふたりの少年が旅に出る。そこにひとりの少女も絡んでくる。よくあるパターンであろう。93分の短い映画は、テンポよく進んでいく。感情的には描かれない。彼らの危ない冒険は、時には犯罪だし、やってることはめちゃくちゃだ。破滅的というわけではないけど、危険だし、最後は事故ルし。だけど、この冒険を通して、彼は確実に変わっていく。以前の彼ではない。供に旅する少年は彼を導き、最後は . . . 本文を読む
今回のジャブジャブはなんと上演時間が90分ほど。こんなにも短いジャブジャブは初めてではないか。このなんとも人を食ったようなタイトルも、いつもと少し違うし、作品自体もいつも以上にサラリとしていて、なんだか不思議。
自然災害でとんでもないことになった人たちが主人公。基本的にはいつもと変わらない。彼らのやりとりを通して、今ある現状を見せていく。そこにいつものようなミステリ要 . . . 本文を読む
スパイダーマンの悪役を主人公にしたヒーローもの。ダークヒーローというのも、もうパターンになっているから、殊更これが新しいわけではない。それより、この映画を見ながら、「ひとつの体を2人が共有するヒーローものって、元祖はウルトラマンだったのではないか、」ということを改めて思い出させてくれたのは少し新鮮。ただ、正義と悪が同じ体の中で戦う、とかいうのもデビルマンとか、昔からある。何一つ目新しいものはない。 . . . 本文を読む
今だからこそ、意味を持つ映画なのかもしれない。題材がとてもタイムリーだから、大ヒットした。だが、映画自体は大してことはない。中田秀夫はもう以前のような輝きを失った、ということが決定的になった。彼のキャリアの頂点はあの『リング』であり、そこに尽きる。そして、あの頃作った『仄暗い水の底から』が最高傑作だろう。と、いうことがこの映画を見ながら、改めて認識させられる。それってとても残念なこ . . . 本文を読む
『船に乗れ!』3部作以降新刊が出たなら必ず読むようにしている藤谷浩の2010年の作品。たまたま読んでいなかったのを発見して、借りてきた。(ということは、先の「必ず」というのは嘘だ。僕が知らない間にいろんな本が出ている、ということなのだろう。まぁ、当然のことだ。世界は僕を中心にして回っているわけではない。)
これはなんとSFタッチの作品。(というわけでもないが)2001年10月12 . . . 本文を読む
大量生産される高校生ものの青春映画の1本。もうこのジャンルは観客に飽きられてしまったのに、まだまだどんどん量産されていく。鉱脈だと思い企画したもののもうブームは去っていたのだ。なのに、作った以上公開しなくてはならない。でも、当然劇場は閑古鳥が啼いている。(なつかしい言い回しだ)その悪循環はまだまだ続く。
そういえば、この映画自体もなんだか懐かしい映画だ。昔、こういうタ . . . 本文を読む
これはストーリーだけを聞くと、とてもわかりやすい芝居のはずなのに、実際に見てみると、なんだか不思議な芝居なのだ。その理由はお話が常に2人の対峙で進行するからだろうか。さらには時制もジグザグに進行する。今の時間がどこなのか、よくわからない。この居心地の悪さ、何とも言いがたい不安感、それがこの芝居の身上だろう。向き合う2人もいつも居心地の悪さを露呈する。あとひとり、そこに誰かが来ればも . . . 本文を読む
このエッセイのような芝居は都市論でもあり、路上観察考でもある。大阪の町をランニングする。反時計回りに大阪城を走る集団とぶつかってしまった男は(大阪城の外周は反時計回りに走るのがルールらしい)、東横堀川にかかる橋をジグザグに走ることにする。そこから彼は異界を彷徨うことになる。大阪にかかる八百八橋をテーマにして、彼が偶然出逢うさまざまな人たちとのドラマが綴られていく。
. . . 本文を読む
舞台中央には大きな時計がある。装置はそれだけ。時計を囲む青い通路は、川の流れを象徴するのか。時間は11時2分を指している。芝居が始まるとすぐ、時計の針が外されて、その円い時計自体が舞台となる。この円形舞台とその周囲で繰り広げられるここで暮らす人たちの幾つものお話が折り重なるようにして描かれていく。
昭和20年8月9日午前11時02分までの24時間、とある家族とその周囲の人たちの姿 . . . 本文を読む
一貫した姿勢を貫く。自分の美意識で統一する。前田隆成のひとり劇団。芝居自身のスタイルもそうだし、タイトルも、さらには文庫本のブックカバーになるチラシもそうだ。いろんな意味でのこだわりが凄い。栞になるチケットもおしゃれだし、はがきのアンケート用紙も可愛い。この前、僕が見た第〇回公演から今回までで3本目になる。毎年1回、公演して、毎回キャストが1人ずつ増えるから今回は3人。
&nbs . . . 本文を読む
25年ぶりの沢木さんの全エッセイ、ということだ。『路上の視野』『象が空を』に続く3冊目なのだが、先の2作とは少し趣を変えて、量的にはそれほど膨大ではない。2段組だった先の2作は圧巻だった。特に『路上の視野』はあの頃の僕にとってバイブルだった。80年代の20代の僕にとって沢木さんの著書を読むことは最高の至福だった。あの頃、沢木さんと、川本三郎、藤原新也は僕の神様だった。あれから30年 . . . 本文を読む
偏愛2部作として『眼帯のQ』とともに上演された。台 本、 三名刺繍(劇団レトルト内閣)、 楽曲・演出 佐藤香聲(銀幕遊學◉レプリカント)のコンビによる連作。2作とも見たかったのだが、今回はこちらのみしか見られなかった。今まで、何度となく見てきた『眼帯のQ』は、今回ファイナルヴァージョンとなったらしい。どんな風に進化したのか、目撃したかったのに、残念だ。
さて、こち . . . 本文を読む
三島由起子監督がこういうエンタメ映画にチャレンジするということで期待した。タッチは抑えた地味めで悪くない。だけど、お話の方があまりといえばあんまりな展開で、さすがにこれではついて行けない。古書を巡るミステリーだと思って見ていたのに、お話が完全に嘘くさくて乗れない。鎌倉を舞台にして、雰囲気自体は悪くないだけに残念だ。
祖母の死から始まって彼女の残した古書を巡るミステリーが展開するの . . . 本文を読む