丸沼芸術の森所蔵 ベン・シャーン展 -線の魔術師-
埼玉県立近代美術館で 1月14日まで

リルケ「マルテの手記」より 《愛にみちた多くの夜の回想》 1968年
「一行の詩のためには、あまたの都市 あまたの人々、あまたの書物を見なければならぬ… 」 リルケ「マルテの手記」 新潮文庫 大山定一 訳
すてきなポスターをもらったとき 壁に飾ろうと考えた。
震えるような線が忘れられない。 こころに届く画家の思い、 やさしさやつよさや哀しみをのせて走る線がこころを揺らすからだ。 筆は毛を間引いている。 ひたすら線に思いをこめて、 かすれたり震えるような線、 太くて力強い線もある。 線だけで描くせかいを楽しんだ。 深い思いが伝わる。
「丸沼芸術の森」は ワイエスのコレクションでおなじみになった。 鉛筆やコンテによる作品、 油彩、水彩、 テンペラ、グワッシュ、 ドローイング、リトグラフなど ポスターもありベン・シャーンの魅力を紹介。 展示 292点。
パンフレットによれば
ベン・シャーン(1898 − 1969) 1930年代から60年代にかけて、アメリカで活躍した画家。 リトアニアのユダヤ人家庭に生まれ、8歳のときに家族とともにニューヨークへ移住。 移民の子として貧民街で育ち、 少年の頃から石版画工房で働きながら美術を学んだシャーンは、 一貫して人種差別や迫害、 貧困をテーマに制作。 ポスターや本の装丁など、グラフィック・デザインの分野でも活躍。
描くものに対して、 つねに鋭い批判の眼差しと 深い愛情を投げかけた。
「私は憎むものを描く。 私は愛するものを描く」
19世紀のフランスで無実の罪をきせられた大尉のこと、 第五福竜丸の被爆のシリーズを手がける。 「出航」「網元、日本の男」「ニュース報告」 「彼の妻-久保山夫人」etc。

独特の線の魅力は、日本の画家やグラフィック・デザイナーにも大きな影響を与えた。
← ポスター裏面
「一行の詩のためには… リルケ「マルテの手記」 より) 《扉Ⅰ》 1968年

















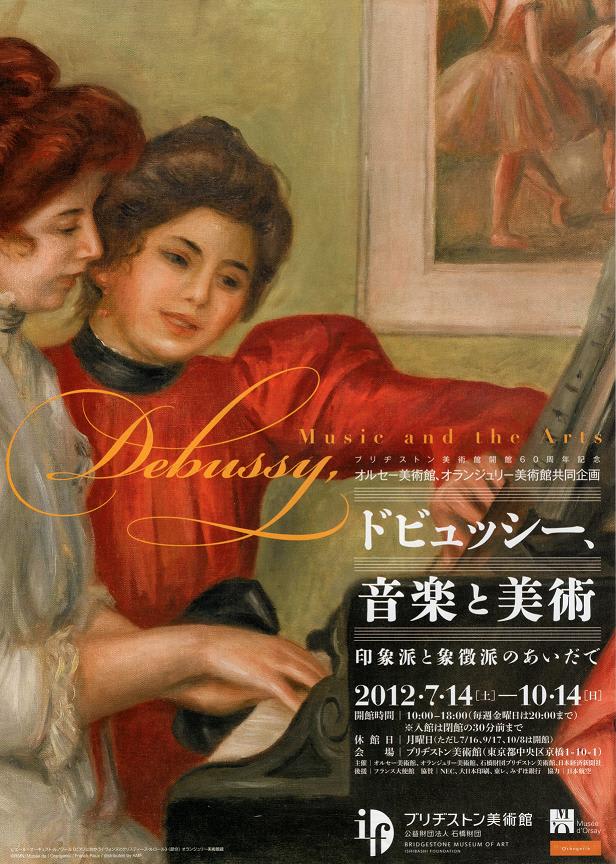






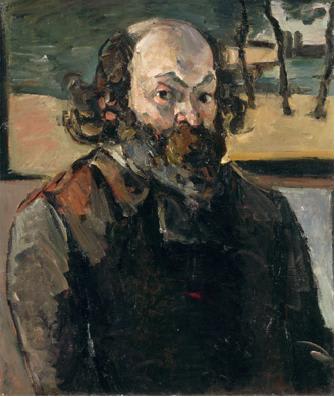






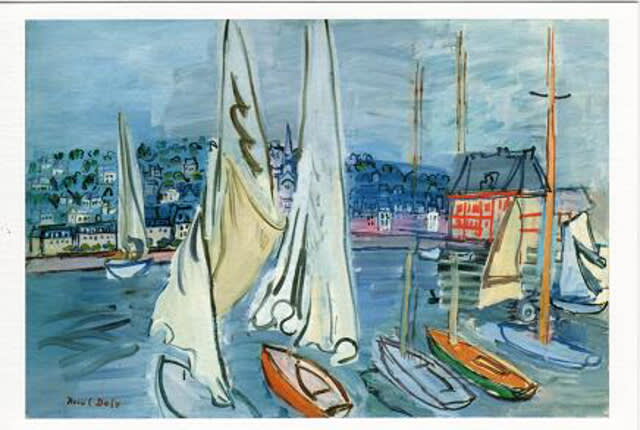











 メモ) 桜の絵画に 平安以降詠まれてきた和歌や俳句、 画家たちの言葉が添えられて鑑賞が深まった。 爛漫の桜 山かげのさくら 歴史を物語る桜 闇に映える桜 月光や朝陽に照らされる桜など堪能。 詳細は
メモ) 桜の絵画に 平安以降詠まれてきた和歌や俳句、 画家たちの言葉が添えられて鑑賞が深まった。 爛漫の桜 山かげのさくら 歴史を物語る桜 闇に映える桜 月光や朝陽に照らされる桜など堪能。 詳細は




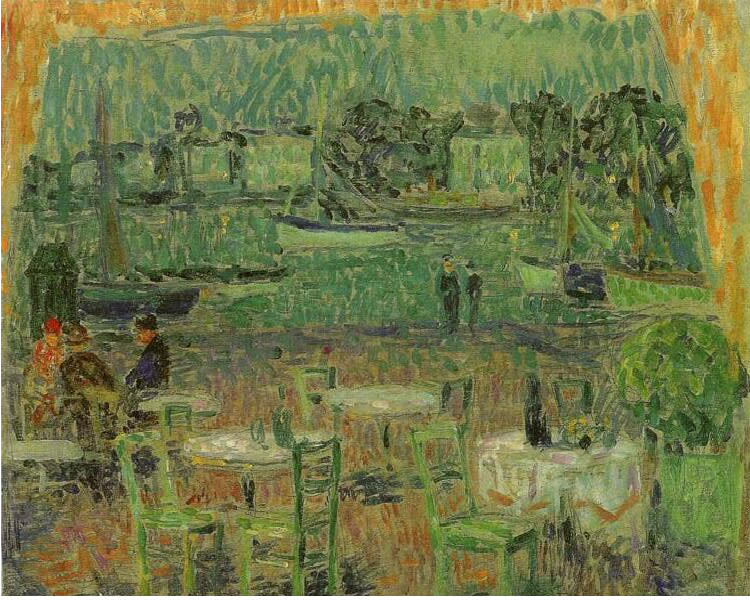

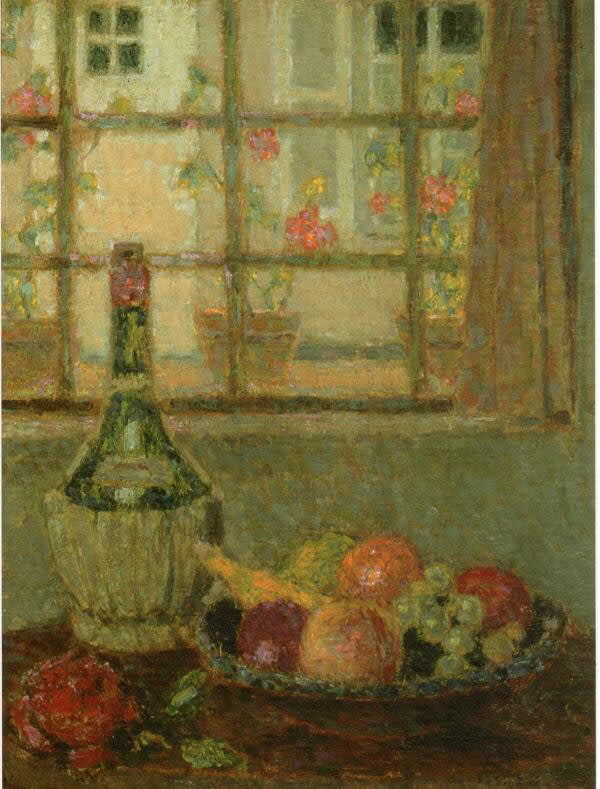











 あこがれはますます募って。
あこがれはますます募って。
 ← 蓋付瓶 レースグラスにさらに襞を寄せている。 すごい技!
← 蓋付瓶 レースグラスにさらに襞を寄せている。 すごい技! 










