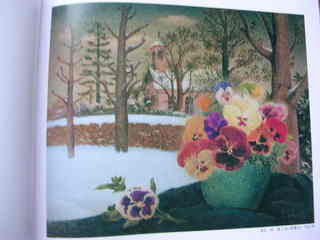写真:蔵前橋
打って変わって本日快晴です。 江戸東京博物館の
ボストン美術館所蔵 肉筆浮世絵展 江戸の誘惑 を見ました。
隅田川の畔をそぞろ歩き、 遊里の世界を覗いてきました。 観光バスがつぎつぎ到着、大にぎわいです。 江戸の情緒と美人の競演、 遊女に囲まれ 狂歌や能、謡いなどの見立絵が楽しかったです。
三味線のさはりを誰かつけぬらん たまにあふ夜もつんとばつかり (紺屋安染)
(喜多川歌麿 三味線を弾く美人図)
なめてみる あまいからいハ すいぞしる からもやまとも あれみ三聖 (七十三叟蜀山人)
(見立三酸図 鳥文斎栄之) (楊貴妃、花魁、小野小町)
こういう情趣にほどとおい まったく似合わないと… しきりにおもふ沼蛙 勉強になりましたとさ。

さすが北斎の娘、葛飾応為オイの三曲合奏図。 三味線、琴、胡弓。 奏でるひと三様の身のこなし、指の動き、手元、鮮やかな着物の柄、 印象に残りました。(ぜひご覧いただきたく 画像を追加しました)
唐獅子図は、北斎が袱紗に描いたもの。 提灯絵の復元も面白い 虎や蛇の躍動感。 保存のため解体され、絵は平らにのばされていた。 元の絵が分からないまま、組み合わせに試行錯誤し、 立体に復元するまで6ヶ月かかったそうです。


ほかの作品紹介は こちら
太鼓の音もなくひっそりした櫓をみあげ 九州の熱戦に思いを馳せました。 国技館の向かいが隅田川、 両国から一区間だけ水上バスに乗ります。
蔵前橋、厩橋、駒形橋、吾妻橋をくぐると 名にし負はばいざ言問はむ… 言問橋… ものがたりも浮かんできます。 桜橋までたったの10分、 遙かな眺めを恣にして、ぜいたくな時を過ごしました。 ふわりふわりとカモメの波乗り、 ポンポン船がゆく。 高層ビルも、ありやなしやと走りよる。
流れあり桜紅葉をのせて去る みつ子
デッキに上がると西日がまぶしい。 春は花見、 秋は月見と、いつも愛されてきた隅田川に、 縁台、朝顔、柳下の納涼など 美人を重ねて進みました。