 鑑賞のまえに、 地階 センター・ホールで
鑑賞のまえに、 地階 センター・ホールで
ミュージアム・コンサート 「勅使河原宏映画の音楽など」 を聴いた。
演奏 鈴木大介(ギター)
曲目
・勅使河原宏監督の作品と武満徹の音楽
「燃えつきた地図」~「サマー・ソルジャー」
「白い朝」
「ホゼー・トレス2」
ワルツ「他人の顔」より
・武満徹:エキノクス
・カタロニアの音楽
リョベート編:カタロニア民謡集 より
モンポウ:歌と踊りNo.13「鳥のうた」
グラナドス:スペイン舞曲集は 12曲中 2曲
5番の「アンダルーサ」 は、以前から気に入りだ。 哀愁をおびた甘美な旋律が心に響く。 ギターの調べは 遙かな高みへ吹き抜け、 椅子に座ると深遠な井戸の底で聴くような感じだ。 採光もよい。 午後のひととき、 静かな時間にひたる。
これから観るものが 楽しみになった。
埼玉県立近代美術館 「勅使河原宏展-限りなき越境の軌跡」
メモ
企画展は 「シュルレアリスム展」 「澁澤龍彦-幻想美術館」、「勅使河原宏展」へと繋がっている。 映画、 陶芸、 書、 油絵、 活け花。 竹によるインスタレーション(芸術的空間、竹の造形、彫刻にも思える)。
草月流三代目家元としても活躍。 今まで誰も試みなかった植物表現である。
青竹の柱。 割った竹を組んでできる造形、 その空間をくぐりぬけ会場に入る趣向だ。 しなう竹の香と色、 青い表と裏の白、 節目のリズム、 自然が醸すあかりの柔らかさ。
前衛彫刻のような花器と 花の競演。
海外でのインスタレーション、 生け花など写真によるパネル展示、 モニターTVによる映像など。
オペラ「トゥーランドット」 1996、グラン・テアトル(ジュネーブ)の舞台装置も竹でつくった。
源氏物語「夕顔」 による 能「半蔀ハジトミ」 のもようは映像で。 夕顔の咲いたハジトミを押しあげ、 美しい女人が現れる…。 1986年 宝生流舞台、 立花供養の花が舞台に置かれている。 勅使河原宏の作品で 竹、 蓮の葉と花、 柳、 ケムリノキ。
寄りてこそそれかとも見め黄昏れにほのぼの見つる花の夕顔

土門拳記念館の庭園の設計 いけばな作品など (写真はチラシより)
書 「竹」 は、文字であり絵でもあった。 等身大で、 質感もあった。
「変幻」

最先端の芸術、 アングラ。
映画 砂の女・豪姫・利休など 8/10より講堂にて上映。
「パリ 大茶会」 松籟の宴 などビデオによる。
展示のすべてを語っていた 言葉…
自分にとって 未知のものに向かって 冒険していきたい
私の仕事はいつもその連続だった
勅使河原宏
アンコールを含めコンサートが終わったのは4時過ぎ、 展覧を駆け足で見た。
再度観に行かなければ…








































 ①
①  ②
② ③
③  ④
④




 お城の天井にも 歴史を感じる。
お城の天井にも 歴史を感じる。 オオバギボウシ
オオバギボウシ













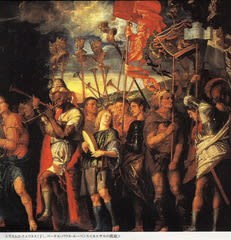




 ぴゅうー ぴー
ぴゅうー ぴー 









 それにしても、 みごとな笹飾り、 真菰を編んで
それにしても、 みごとな笹飾り、 真菰を編んで

















