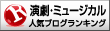ライトノベル・セレクト№22
『親の離婚から175日』
親の離婚から175日。もう数えるのはやめ。だって、今日はイナゴ(175)だ。
いなごの佃煮をお母さんが買ってきた、離婚の一週間前。
デパートの物産展で、珍しそうだったからって。
そのイナゴの佃煮を前に、食卓は数秒、こじれた国際会議のような沈黙になった。
で、数秒後、ヤバイと思って、わたし食べちゃった。
ガリ、グチュ……あの食感は忘れられない。それから、家族みんなが少しずつ食べた。それを食べれば、とんでもないことを言わずに済むかというように。
わたしは、もう一生、イナゴの佃煮は食べないだろう。
だからイナゴの日をきっかけに数えることは止め。
『第六十一回浪速高等学校演劇研究大会』
看板がまぶしかった。
おとつい、リハに来たときは看板もなく、雑然とした中でマイクも使えなくて、スタッフの人や、実行委員の先生や生徒が右往左往。
本選に出るんだという実感は、当日の今、看板を見てようやく湧いてきた。
出番は、初日の昼一番。二つ驚いたことがあった。
朝一番に道具の確認に一ホリの裏側にまわった(会場のLホールは、テレビの実況ができるように奥行きが二十五メートルもある。そこで真ん中のホリゾントを降ろして、後ろ半分を出場校の道具置き場にしている。ちょっとした体育館のフロアー並)
わたしたちが、ささやかに畳一畳分に道具を収めたときは、まだ半分くらいの学校が搬入を終わっていなかったが、スペースはまだ三分の二くらい余裕で残っていた。
さすがLホールと思ったのだが……。
そのときは、溢れんばかりの道具で、担当のスタッフが苦労していた。
R高校などは、四トントラック二杯分の道具を持ち込んでいた。
お陰で、わたしたちの道具は奥の奥に追い込まれ、確認するのも一苦労。
で……ウソ、衣装が無かった!?
「衣装はこっち!」
道具の山のむこうにタロくん先輩の声。
実行委員を兼ねている先輩はR高校の搬入を見て、「こら、あかんわ」と思った。
それで、すぐに必要になる衣装と小道具は、駅前のコインロッカーに入れておいてくれたのだ。さすが大手私鉄合格の舞監である。
もう一つの驚きは、パンフだった。
予選からの出場校百二校のプロフィールが書いてある。
三分の一ほど読んで、「?」と、思った。
創作脚本ばかりなのである。
数えてみた。
なんと出場校百二校中、創作劇が八十七校。
なんと八十五パーセントが創作劇。
後日確認すると、卒業生やコーチの作品が十校あり、創作劇の率は九十五パーセント!
この本選に出てきた学校で既成の脚本はわたしたちのY高校だけ。
大橋先生は、コーチではあるがれっきとした劇作家である。『すみれ』は八年も前に書かれた本であり、上演実績は十ステージを超えていた。
タマちゃん先輩が、予選の前に言っていた。
「浪高連のコンクールは、創作劇やないと通らへん」
ジンクスなんだろうけど(わたしたち予選では一等賞だったもん)この数字は異常だ。
本番の一時間前までは、他の芝居を観ていいということになった。
出番は昼の一番なんで、午前中の芝居は全部観られる。
わたしは、午前の三本とも観た。ナンダコリャだった。
例のR高校、幕開き三十秒はすごかった。なんと言っても、四トントラック二杯分の大道具。ミテクレは、東京の大手劇団並み。
しかし、役者がしゃべり始めると、アウト。台詞を歌っている(自分の演技に酔いしれている)ガナリ過ぎ。不必要に大きな動き。人の台詞を聞いていない。
だいいち、本がドラマになっていない。ほとんど独白の繰り返しで劇的展開がない。
わたしは、大阪に来て八十本ほど戯曲を読んだ。劇的な構造ぐらいは分かる。
昼休みは、道具の立て込み(と言っても、平台二個だけ)をあっという間に終えて、お握り一個だけ食べて、静かにその時を待った。
乙女先生は、台詞だけでも通そうと言った。
「静かに、役の中に入っていけ、鏡でも見てなあ」
大橋先生の言葉でそうなった。
わたしは、眉を少し描き足し、念入りにお下げにし、静かにカオルになっていった……。
本ベルが鳴って、お決まりのアナウンス。
客電がおちて、山中先輩のギターでうららかな春の空気が満ちてきた。
そして、タロくん先輩のキューで幕が上がった……。
肌で感じた。観客の人たちと呼吸がいっしょになり、劇場全体が『すみれ』の世界になっていく。
スミレの宝塚風の歌は、いっそうの磨きがかかって、大拍手。進一に進路のことを言われたときは、本気でむくれているみたいだった。
アラブの戦争が始まり、上空をアメリカ軍の飛行機が飛んでいく。
ついこないだの、マサカドさんとの体験が蘇り、恐怖が湧いてくる。そして、カオルとしてしみじみと語る十七年間の人生、宝塚への夢。
その夢を無惨に打ち砕かれた、あの夜の空襲……そして互いの生き方への理解と共感が自然にやってきた。
友情と共感の象徴として、でも、互いにそうとは気づかずに、無邪気に紙ヒコーキを折って、新川の土手に……。
「いくよ。いち、に、さん!」
紙ヒコーキを飛ばす。
「すごい、あんなに遠くまで……!」
荒川での視界没と重なる感動。そして透けていく身体……。
「おわかれだけど、さよならじゃない」
新大阪の思い出が予選のときよりも強く蘇ってくる。
「わたし、川の中で消えていく……そうしたら海に流れて、いつか雨か風になってもどってこられるかもしれないから……」
「カオルちゃん……!」
スミレの渾身の叫び……。
そして、ここで初めて種明かし。
消え去る直前に、カオルはゴ-ストジャンボ宝くじの一等賞に当選!
賞品は、新たな人間としての生まれ変わり!
「これで、また、宝塚を受けることができるじゃない!」
そして、もうひとつどんでん返しがあって。人間賛歌のフィナーレ!
満場の手拍子、予選とちがって裏拍。予選以上に観客のみなさんが共感して、手拍子は満場の拍手にかわった!
楽屋にもどって、びっくりした。
たくさんの人たちが、楽屋、そしてその前の廊下に溢れていた。
真由さんに、仲鉄工のおじさん。「Z情報」の伯父さん……そして、お父さんと秀美さん。タキさんにトコさん。竹内先生に亜美と綾まで……由香と吉川先輩は、ちゃっかりと、楽屋の奥でお弁当を広げていた。
そうだ、わたしってば、メールを一斉送信にしたんだ!
こうやって、午後の二本は見損ねてしまった。
時間を決めて、その夜は有志の者が(けっきょくほとんど全員になっちゃったけど)志忠屋に集まって、気の早い祝賀会になった。
わたしも、仲間も、これはいけると手応えを感じていた。栄恵ちゃんなど、
「近畿大会は、土曜にしてくださいね。わたし日曜は検定やから」
で、これを皮切りに、お父さんとかまで、それぞれに都合を言い立てた。
出演するのは、わたしたちなんだけどね……タマちゃん先輩と目配せをした。
二日目の芝居は全部観た。
正直、ドラマになっているものは一つもない。
想像妊娠や、引きこもり、新型インフルエンザの流行の悲喜劇、親子の断絶。アイデアというかモチーフは様々だが、人物描写が類型的。
ドラマとは、人の対立と葛藤があり、互いに関係しあって、最後には人間に変化があるもの。この五ヶ月で、わたしが学んだドラマの基本である。
みんな、そこを踏み外している。ただ刹那的なギャグや、スラプスティック(ドタバタのギャグ)、劇的な台詞が、なにも絡むこともなく、散りばめられているだけ。
最後の芝居の半ばごろ、頭が痛くなってきた。なんとか見終わって、ロビーに出た。
「はるか、大丈夫?」
乙女先生が心配げに顔をのぞき込む。
「ちょっと芝居あたりしたみたいです。大丈夫、すぐによくなりますから」
ロビーのソファーに座り込んだ。
昨日、今日の二日間で観た芝居や、『すみれ』が、頭の中でグルグル回っている。
「はるか、芝居も終わったこっちゃし、いっしょに先帰ろか」
「講評とか聞きたいんです……」
「わたしが、代わりに聞いといたるから。な、そないし」
「さ、いくぞ」
早手回しに、栄恵ちゃんが、わたしのバッグを持ってきた。
「大丈夫ですよ。いい結果、家で待っててください」
その笑顔に押されるようにして、わたしは、大橋先生と家路についた……。
『親の離婚から175日』

親の離婚から175日。もう数えるのはやめ。だって、今日はイナゴ(175)だ。
いなごの佃煮をお母さんが買ってきた、離婚の一週間前。
デパートの物産展で、珍しそうだったからって。
そのイナゴの佃煮を前に、食卓は数秒、こじれた国際会議のような沈黙になった。
で、数秒後、ヤバイと思って、わたし食べちゃった。
ガリ、グチュ……あの食感は忘れられない。それから、家族みんなが少しずつ食べた。それを食べれば、とんでもないことを言わずに済むかというように。
わたしは、もう一生、イナゴの佃煮は食べないだろう。
だからイナゴの日をきっかけに数えることは止め。
『第六十一回浪速高等学校演劇研究大会』
看板がまぶしかった。
おとつい、リハに来たときは看板もなく、雑然とした中でマイクも使えなくて、スタッフの人や、実行委員の先生や生徒が右往左往。
本選に出るんだという実感は、当日の今、看板を見てようやく湧いてきた。
出番は、初日の昼一番。二つ驚いたことがあった。
朝一番に道具の確認に一ホリの裏側にまわった(会場のLホールは、テレビの実況ができるように奥行きが二十五メートルもある。そこで真ん中のホリゾントを降ろして、後ろ半分を出場校の道具置き場にしている。ちょっとした体育館のフロアー並)
わたしたちが、ささやかに畳一畳分に道具を収めたときは、まだ半分くらいの学校が搬入を終わっていなかったが、スペースはまだ三分の二くらい余裕で残っていた。
さすがLホールと思ったのだが……。
そのときは、溢れんばかりの道具で、担当のスタッフが苦労していた。
R高校などは、四トントラック二杯分の道具を持ち込んでいた。
お陰で、わたしたちの道具は奥の奥に追い込まれ、確認するのも一苦労。
で……ウソ、衣装が無かった!?
「衣装はこっち!」
道具の山のむこうにタロくん先輩の声。
実行委員を兼ねている先輩はR高校の搬入を見て、「こら、あかんわ」と思った。
それで、すぐに必要になる衣装と小道具は、駅前のコインロッカーに入れておいてくれたのだ。さすが大手私鉄合格の舞監である。
もう一つの驚きは、パンフだった。
予選からの出場校百二校のプロフィールが書いてある。
三分の一ほど読んで、「?」と、思った。
創作脚本ばかりなのである。
数えてみた。
なんと出場校百二校中、創作劇が八十七校。
なんと八十五パーセントが創作劇。
後日確認すると、卒業生やコーチの作品が十校あり、創作劇の率は九十五パーセント!
この本選に出てきた学校で既成の脚本はわたしたちのY高校だけ。
大橋先生は、コーチではあるがれっきとした劇作家である。『すみれ』は八年も前に書かれた本であり、上演実績は十ステージを超えていた。
タマちゃん先輩が、予選の前に言っていた。
「浪高連のコンクールは、創作劇やないと通らへん」
ジンクスなんだろうけど(わたしたち予選では一等賞だったもん)この数字は異常だ。
本番の一時間前までは、他の芝居を観ていいということになった。
出番は昼の一番なんで、午前中の芝居は全部観られる。
わたしは、午前の三本とも観た。ナンダコリャだった。
例のR高校、幕開き三十秒はすごかった。なんと言っても、四トントラック二杯分の大道具。ミテクレは、東京の大手劇団並み。
しかし、役者がしゃべり始めると、アウト。台詞を歌っている(自分の演技に酔いしれている)ガナリ過ぎ。不必要に大きな動き。人の台詞を聞いていない。
だいいち、本がドラマになっていない。ほとんど独白の繰り返しで劇的展開がない。
わたしは、大阪に来て八十本ほど戯曲を読んだ。劇的な構造ぐらいは分かる。
昼休みは、道具の立て込み(と言っても、平台二個だけ)をあっという間に終えて、お握り一個だけ食べて、静かにその時を待った。
乙女先生は、台詞だけでも通そうと言った。
「静かに、役の中に入っていけ、鏡でも見てなあ」
大橋先生の言葉でそうなった。
わたしは、眉を少し描き足し、念入りにお下げにし、静かにカオルになっていった……。
本ベルが鳴って、お決まりのアナウンス。
客電がおちて、山中先輩のギターでうららかな春の空気が満ちてきた。
そして、タロくん先輩のキューで幕が上がった……。
肌で感じた。観客の人たちと呼吸がいっしょになり、劇場全体が『すみれ』の世界になっていく。
スミレの宝塚風の歌は、いっそうの磨きがかかって、大拍手。進一に進路のことを言われたときは、本気でむくれているみたいだった。
アラブの戦争が始まり、上空をアメリカ軍の飛行機が飛んでいく。
ついこないだの、マサカドさんとの体験が蘇り、恐怖が湧いてくる。そして、カオルとしてしみじみと語る十七年間の人生、宝塚への夢。
その夢を無惨に打ち砕かれた、あの夜の空襲……そして互いの生き方への理解と共感が自然にやってきた。
友情と共感の象徴として、でも、互いにそうとは気づかずに、無邪気に紙ヒコーキを折って、新川の土手に……。
「いくよ。いち、に、さん!」
紙ヒコーキを飛ばす。
「すごい、あんなに遠くまで……!」
荒川での視界没と重なる感動。そして透けていく身体……。
「おわかれだけど、さよならじゃない」
新大阪の思い出が予選のときよりも強く蘇ってくる。
「わたし、川の中で消えていく……そうしたら海に流れて、いつか雨か風になってもどってこられるかもしれないから……」
「カオルちゃん……!」
スミレの渾身の叫び……。
そして、ここで初めて種明かし。
消え去る直前に、カオルはゴ-ストジャンボ宝くじの一等賞に当選!
賞品は、新たな人間としての生まれ変わり!
「これで、また、宝塚を受けることができるじゃない!」
そして、もうひとつどんでん返しがあって。人間賛歌のフィナーレ!
満場の手拍子、予選とちがって裏拍。予選以上に観客のみなさんが共感して、手拍子は満場の拍手にかわった!
楽屋にもどって、びっくりした。
たくさんの人たちが、楽屋、そしてその前の廊下に溢れていた。
真由さんに、仲鉄工のおじさん。「Z情報」の伯父さん……そして、お父さんと秀美さん。タキさんにトコさん。竹内先生に亜美と綾まで……由香と吉川先輩は、ちゃっかりと、楽屋の奥でお弁当を広げていた。
そうだ、わたしってば、メールを一斉送信にしたんだ!
こうやって、午後の二本は見損ねてしまった。
時間を決めて、その夜は有志の者が(けっきょくほとんど全員になっちゃったけど)志忠屋に集まって、気の早い祝賀会になった。
わたしも、仲間も、これはいけると手応えを感じていた。栄恵ちゃんなど、
「近畿大会は、土曜にしてくださいね。わたし日曜は検定やから」
で、これを皮切りに、お父さんとかまで、それぞれに都合を言い立てた。
出演するのは、わたしたちなんだけどね……タマちゃん先輩と目配せをした。
二日目の芝居は全部観た。
正直、ドラマになっているものは一つもない。
想像妊娠や、引きこもり、新型インフルエンザの流行の悲喜劇、親子の断絶。アイデアというかモチーフは様々だが、人物描写が類型的。
ドラマとは、人の対立と葛藤があり、互いに関係しあって、最後には人間に変化があるもの。この五ヶ月で、わたしが学んだドラマの基本である。
みんな、そこを踏み外している。ただ刹那的なギャグや、スラプスティック(ドタバタのギャグ)、劇的な台詞が、なにも絡むこともなく、散りばめられているだけ。
最後の芝居の半ばごろ、頭が痛くなってきた。なんとか見終わって、ロビーに出た。
「はるか、大丈夫?」
乙女先生が心配げに顔をのぞき込む。
「ちょっと芝居あたりしたみたいです。大丈夫、すぐによくなりますから」
ロビーのソファーに座り込んだ。
昨日、今日の二日間で観た芝居や、『すみれ』が、頭の中でグルグル回っている。
「はるか、芝居も終わったこっちゃし、いっしょに先帰ろか」
「講評とか聞きたいんです……」
「わたしが、代わりに聞いといたるから。な、そないし」
「さ、いくぞ」
早手回しに、栄恵ちゃんが、わたしのバッグを持ってきた。
「大丈夫ですよ。いい結果、家で待っててください」
その笑顔に押されるようにして、わたしは、大橋先生と家路についた……。