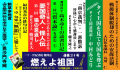七月十五日(水)晴れ。
朝食は、赤ウインナー、目玉焼き、キャベツの千切りにシジミのちから。昼食は無し。夕食は、レタスのナムル、サバの文化干し、明太子に黒霧島。
午後から、私が役員の末席を汚している大行社の幹部会議があり出席。五時近くに終了。横浜駅に車を置いたままになっていたので、「そごう」の地下で買い物をしてから帰宅。
私が小学生の低学年の頃の愛読書と言うのは『少年クラブ』『日の丸』『冒険王』といった漫画の月刊誌だった。付録が沢山ついていて、発売日がとても楽しみだった。たとえ漫画雑誌と言えど、あれほど発売日が待ち遠しいと言う思いは、この時以来ない。好きだったものは柔道漫画の『イガグリくん』(なぜか三澤浩一さんのイメージと重なる)と『赤胴鈴之助』。前者は、有川旭一が書いて、『赤胴鈴之助』は武内つなよしが書いていたが、実は、両作品とも福井栄一と言う人が原作で当初は彼が書いていたらしい。彼が過労のために急死し、有川と竹内が引き継いで書いた。ということを出久根達郎氏の『本の気つけ薬』(河出書房新社)で知った。
漫画は、原作者が亡くなられても、後を引き継いで書けるが、小説となるとそうは行かない。唯一、私が知っているのは、父の新田次郎氏の死後にご子息の藤原正彦氏が書き上げた『孤愁 = SAUDADE サウダーデ』 (文藝春秋)ぐらいか。
今は亡き 悲願の人の 悲願を継ぐ とは野村先生の句である。
朝食は、赤ウインナー、目玉焼き、キャベツの千切りにシジミのちから。昼食は無し。夕食は、レタスのナムル、サバの文化干し、明太子に黒霧島。
午後から、私が役員の末席を汚している大行社の幹部会議があり出席。五時近くに終了。横浜駅に車を置いたままになっていたので、「そごう」の地下で買い物をしてから帰宅。
私が小学生の低学年の頃の愛読書と言うのは『少年クラブ』『日の丸』『冒険王』といった漫画の月刊誌だった。付録が沢山ついていて、発売日がとても楽しみだった。たとえ漫画雑誌と言えど、あれほど発売日が待ち遠しいと言う思いは、この時以来ない。好きだったものは柔道漫画の『イガグリくん』(なぜか三澤浩一さんのイメージと重なる)と『赤胴鈴之助』。前者は、有川旭一が書いて、『赤胴鈴之助』は武内つなよしが書いていたが、実は、両作品とも福井栄一と言う人が原作で当初は彼が書いていたらしい。彼が過労のために急死し、有川と竹内が引き継いで書いた。ということを出久根達郎氏の『本の気つけ薬』(河出書房新社)で知った。
漫画は、原作者が亡くなられても、後を引き継いで書けるが、小説となるとそうは行かない。唯一、私が知っているのは、父の新田次郎氏の死後にご子息の藤原正彦氏が書き上げた『孤愁 = SAUDADE サウダーデ』 (文藝春秋)ぐらいか。
今は亡き 悲願の人の 悲願を継ぐ とは野村先生の句である。