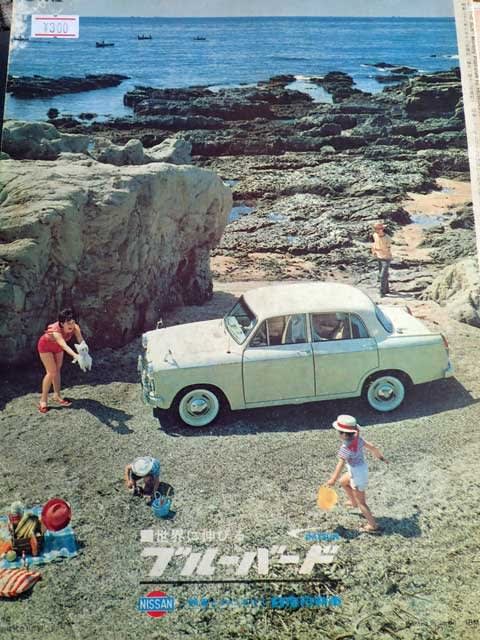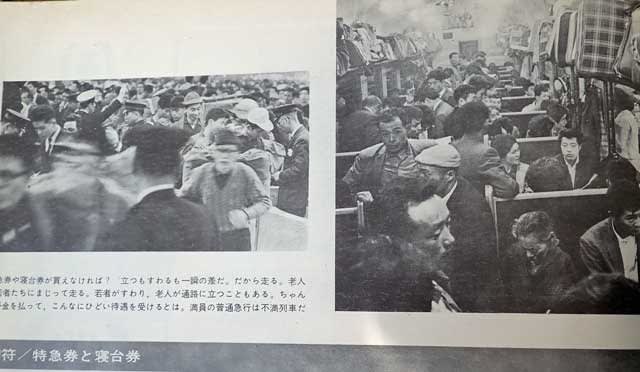前回に引き続き「雨宮敬次郎展」の運転会のはなし。


今回は参加車両について。
会場が中央本線の塩山駅に近い事、題材が郷土の鉄道王という事もあって集まったメンバーは中央線、中央本線の列車を主に持ち込みギャラリーの前で快走させました。

わたしもこの間入線させたTOMIXの209系1000番台をデビューさせます。
リアルではE233系の改装が終わり次第順次入れ替えられる予定なので、実車がみられるのもあと少しですね。

どのイベントでも、どこで走らせても子供たちの人気は「お寿司の列車」です。
グランシップの様な傾奇いた車両や編成は今回だれもが自粛していたのですが、お寿司だけは外すわけには行きません。
さて、市民会館という会場の性質上「ホールで催し物がある間は一時客が途切れる」のですが、そのタイミングで多少メンバーの趣味を出した編成を快走させました。

わたしが持ち込んだのは「SL銀河」ですが、前のグランシップの時にモジュールベースの歪みから線路に段差が生じ、スノープラウが引っかかるというトラブルでTOMIXのC58が使えなかった苦い経験から、今回は同じC58でもKATOのそれを代打に使いました。
そういえばC58はまだKATOがリニューアルしていないのですが、そろそろ普通の仕様をファインスケールで出してほしいものです。

OE88の先頭に立つのは、先日の帰省で入線した「宮沢模型のEF55」
ややオーバースケールで大き目のサイズですが長編成の先頭では適度に目立ってよかったかもしれません。予想通り急カーブへの追従性も高かったですが、ベースのTOMIXEF58の宿命で「運転席にライトが来てしまい車内が光る」というサプライズが(爆)

当初は走らせるかどうか微妙だったKATOの「やまびこ」
実は会場に来ていた小学生からのリクエストでした。それも「485系が見たい」というリクエストで(驚)
次回はLimaの3連でも持っていこうかな(笑)

運転会の締めはE257とドラえもん海底列車のそろい踏み。およびメンバー持ち込みのコンテナとタンカーの専用列車がフィナーレを飾りました。

実は閉会30分前にホールのイベントが終了し、帰りの客が展示に目を止めたので一日の中で一番ギャラリーが多かったのが「閉会最後の30分間」だったりします。一日の客密度の振れ幅が時間によって極端に変わるのは、この種のホール系の特徴ですね。


今回は参加車両について。
会場が中央本線の塩山駅に近い事、題材が郷土の鉄道王という事もあって集まったメンバーは中央線、中央本線の列車を主に持ち込みギャラリーの前で快走させました。

わたしもこの間入線させたTOMIXの209系1000番台をデビューさせます。
リアルではE233系の改装が終わり次第順次入れ替えられる予定なので、実車がみられるのもあと少しですね。

どのイベントでも、どこで走らせても子供たちの人気は「お寿司の列車」です。
グランシップの様な傾奇いた車両や編成は今回だれもが自粛していたのですが、お寿司だけは外すわけには行きません。
さて、市民会館という会場の性質上「ホールで催し物がある間は一時客が途切れる」のですが、そのタイミングで多少メンバーの趣味を出した編成を快走させました。

わたしが持ち込んだのは「SL銀河」ですが、前のグランシップの時にモジュールベースの歪みから線路に段差が生じ、スノープラウが引っかかるというトラブルでTOMIXのC58が使えなかった苦い経験から、今回は同じC58でもKATOのそれを代打に使いました。
そういえばC58はまだKATOがリニューアルしていないのですが、そろそろ普通の仕様をファインスケールで出してほしいものです。

OE88の先頭に立つのは、先日の帰省で入線した「宮沢模型のEF55」
ややオーバースケールで大き目のサイズですが長編成の先頭では適度に目立ってよかったかもしれません。予想通り急カーブへの追従性も高かったですが、ベースのTOMIXEF58の宿命で「運転席にライトが来てしまい車内が光る」というサプライズが(爆)

当初は走らせるかどうか微妙だったKATOの「やまびこ」
実は会場に来ていた小学生からのリクエストでした。それも「485系が見たい」というリクエストで(驚)
次回はLimaの3連でも持っていこうかな(笑)

運転会の締めはE257とドラえもん海底列車のそろい踏み。およびメンバー持ち込みのコンテナとタンカーの専用列車がフィナーレを飾りました。

実は閉会30分前にホールのイベントが終了し、帰りの客が展示に目を止めたので一日の中で一番ギャラリーが多かったのが「閉会最後の30分間」だったりします。一日の客密度の振れ幅が時間によって極端に変わるのは、この種のホール系の特徴ですね。