いよいよ、クライマックスです。(やっとか)
ここの内容は、司法試験受験生から、宅建受験生までも、必要で、最も重要な項目を扱っています。
そして、項目別過去問(上記)を解く前に、まずここを読んでくださいね。
前回までのあらすじ・・・取り消しても、不動産が騙したやつの名義になっているのに、そのまま放置する事例が横行した、その解決策は?でした。
今回こそ、終結を。
しかし、このような場合を直接処理する民法の条文はありません。ここが難点。
立法者がもともと予想していなかったからだ。だから、裁判にもなったわけですね。
A→Bに売却、その後Aが取消、でも名義をBのまま放置、その後BがCに売却、Cは名義を移転。Cは穏やかに過ごしていたとき、Aから実はこういうことだから、戻してくれといってきた。
AとCの紛争勃発です。どちらが勝つか、となります。
177条の条文の第三者の定義からみると、Bは無権利、そこから買ったCも無権利、となるとAは登記がなくても勝てる? 素直に読むとね。
でも、これを裁判所が素直に認めるわけいきませんね。それは、裁判所が登記所を信用をがた落ちするよう陥れていますからね。
こうなると、誰も登記所を信用しないことになって、マズいでしょう。
そこで、考えました。なんとかせにゃ、いかんとね。
解決策は、勝手に裁判官が考えることではなく、今ある民法の条文をうまく使って解決するということです。
といっても、第三者間の紛争は、2つのパターンしかないのですが、となるとどちらをとるかになりますね。
Cを勝たせるために、善意なら勝たせる1つめのパータンか、先に登記をすれば勝つという177条で処理する2つめのパターンかですね。
実は、判例は、後者で決着しました。あー、先に答えいっちゃった。
ではどうして、177条をとったかですね。ここが今日の重要ポイントです。ぼーっとしてたらダメだよ。
177条は、ポイント2つありました。覚えていますか。
一つは、二重譲渡した場合の処理でした。そういう状況なら、よーいドンで先にテープをカットした、つまり登記した方を勝たせた訳ですね。これ、裁判なら、1秒で決着がつきます。裁判官も、1日100件くらいこなせます。
もう一つは、負ける方も、ぼっーとしていたから負けても仕方ないじゃん、といえる状況が必要でしたね。やれるのにやらなかったから、あ「ウサギとカメ」でした。
では、この未知の紛争は、どう見たらよいのでしょうか。
実は、判例は、Bを起点に、ぱっと見ると、二重譲渡類似に見えるだろ、とすこし脅しました。そう見れよ、と。
まあ、見れないことないですね。BからCは確かに譲渡、一度BにAは譲渡したので、取消したのだから、BからAに譲渡したのと同じでしょ、といったのです。
まあ、これは裁判官が勝手に作ったルールではなく、177条をうまく使っただけだ、としたかったのでしょう。
でも、本当の狙いは、もっと深いものでした。つまり、登記所の信用を落とさないようにするには、名義が実体に合致していることが必要ですね。
もし、ここに177条のルールを適用すると、どうなりますか。取り消したAは、すぐに回復しないとCが後で登記したら大変だとなりますね。それをねらったんです。
真実、実体と登記との一致ですね。
あ、177条のもう一つのポイント、できるのにしなかった方が負けるということもいいですね。これかなり重要ですよ。
Cが現れる前にAは登記を回復できるわけですから、それをしないでボっーとしていたら負けても仕方ありません。そういえますね。ここも、ズバリはまりましたね。
ということで、177条のルールをここに応用したわけです。
これが3つめの対第三者紛争の問題でした。これで、知識的に完璧になりましたね。第三者の問題は。
今回もちょっと長くなりましたので、もうちょっとの続きは次回で。では、また。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
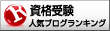
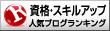
ここの内容は、司法試験受験生から、宅建受験生までも、必要で、最も重要な項目を扱っています。
そして、項目別過去問(上記)を解く前に、まずここを読んでくださいね。
前回までのあらすじ・・・取り消しても、不動産が騙したやつの名義になっているのに、そのまま放置する事例が横行した、その解決策は?でした。
今回こそ、終結を。
しかし、このような場合を直接処理する民法の条文はありません。ここが難点。
立法者がもともと予想していなかったからだ。だから、裁判にもなったわけですね。
A→Bに売却、その後Aが取消、でも名義をBのまま放置、その後BがCに売却、Cは名義を移転。Cは穏やかに過ごしていたとき、Aから実はこういうことだから、戻してくれといってきた。
AとCの紛争勃発です。どちらが勝つか、となります。
177条の条文の第三者の定義からみると、Bは無権利、そこから買ったCも無権利、となるとAは登記がなくても勝てる? 素直に読むとね。
でも、これを裁判所が素直に認めるわけいきませんね。それは、裁判所が登記所を信用をがた落ちするよう陥れていますからね。
こうなると、誰も登記所を信用しないことになって、マズいでしょう。
そこで、考えました。なんとかせにゃ、いかんとね。
解決策は、勝手に裁判官が考えることではなく、今ある民法の条文をうまく使って解決するということです。
といっても、第三者間の紛争は、2つのパターンしかないのですが、となるとどちらをとるかになりますね。
Cを勝たせるために、善意なら勝たせる1つめのパータンか、先に登記をすれば勝つという177条で処理する2つめのパターンかですね。
実は、判例は、後者で決着しました。あー、先に答えいっちゃった。
ではどうして、177条をとったかですね。ここが今日の重要ポイントです。ぼーっとしてたらダメだよ。
177条は、ポイント2つありました。覚えていますか。
一つは、二重譲渡した場合の処理でした。そういう状況なら、よーいドンで先にテープをカットした、つまり登記した方を勝たせた訳ですね。これ、裁判なら、1秒で決着がつきます。裁判官も、1日100件くらいこなせます。
もう一つは、負ける方も、ぼっーとしていたから負けても仕方ないじゃん、といえる状況が必要でしたね。やれるのにやらなかったから、あ「ウサギとカメ」でした。
では、この未知の紛争は、どう見たらよいのでしょうか。
実は、判例は、Bを起点に、ぱっと見ると、二重譲渡類似に見えるだろ、とすこし脅しました。そう見れよ、と。
まあ、見れないことないですね。BからCは確かに譲渡、一度BにAは譲渡したので、取消したのだから、BからAに譲渡したのと同じでしょ、といったのです。
まあ、これは裁判官が勝手に作ったルールではなく、177条をうまく使っただけだ、としたかったのでしょう。
でも、本当の狙いは、もっと深いものでした。つまり、登記所の信用を落とさないようにするには、名義が実体に合致していることが必要ですね。
もし、ここに177条のルールを適用すると、どうなりますか。取り消したAは、すぐに回復しないとCが後で登記したら大変だとなりますね。それをねらったんです。
真実、実体と登記との一致ですね。
あ、177条のもう一つのポイント、できるのにしなかった方が負けるということもいいですね。これかなり重要ですよ。
Cが現れる前にAは登記を回復できるわけですから、それをしないでボっーとしていたら負けても仕方ありません。そういえますね。ここも、ズバリはまりましたね。
ということで、177条のルールをここに応用したわけです。
これが3つめの対第三者紛争の問題でした。これで、知識的に完璧になりましたね。第三者の問題は。
今回もちょっと長くなりましたので、もうちょっとの続きは次回で。では、また。






















