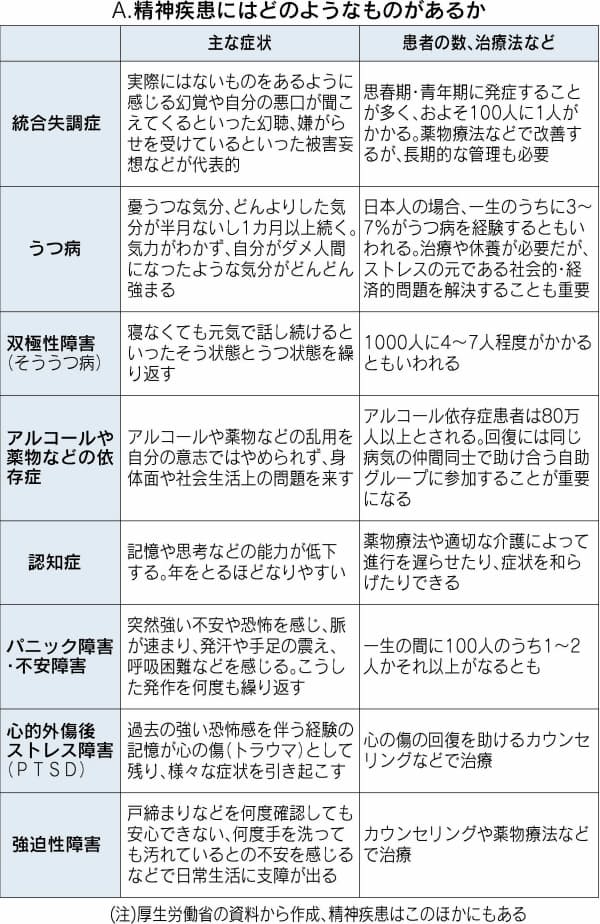FAで西武から巨人へ移籍し、入団発表の席で長嶋監督(左)と笑顔で握手する清原和博内野手=1996(平成8)年11月24日、都内のホテル
FAで西武から巨人へ移籍し、入団発表の席で長嶋監督(左)と笑顔で握手する清原和博内野手=1996(平成8)年11月24日、都内のホテル
6シーズン活躍した村田修一も戦力外の憂き目
ドラフトも終わり、間もなく日本シリーズがはじまるが、その日本シリーズ終了の翌日までが第2次戦力外通告の期限(日本シリーズ進出チームはシリーズ終了から5日後まで)になる。
そんな中、2年連続のV逸、そして球団史上初めてクライマックスシリーズ進出を逃した巨人が10月13日、主力選手のひとりである村田修一に来季は構想外であることを告げた。
2011年オフにFAで移籍してきて以来、6シーズンに渡り巨人のサードを守ってきた主砲だけに、衝撃が走ったのは言うまでもない。
1993年にFA制度が導入されて以降、延べ100人以上の選手が権利を行使して他球団へと移籍したが、最も多くのFA選手を受け入れてきたのが巨人だ。
落合博満をはじめ、23人もの選手がFA制度によって巨人のユニフォームに袖を通してきた。
しかし、巨人の選手として現役を引退できた選手は現在まででわずか4人のみ。他球団に移籍した選手にはほとんどない現象なだけに、巨人だけが持つ「特徴」と捉えることもできる。
ポジションが被ることも多かった野手
これまでに巨人がFAで獲得した選手を振り返ると、その内訳は野手11人、投手12人とほぼ均等だ。まずは野手から見ていきたい。
▼落合博満(94~96年)=96年オフに自由契約を申し出て日本ハムへ
▼広沢克己(95~99年)=99年オフに自由契約となり阪神へ
▼清原和博(97~05年)=05年オフに自由契約となりオリックスへ
▼江藤 智(00~05年)=05年オフに人的補償で西武へ
▼小笠原道大(07~13年)=13年オフにFAで中日へ
▼村田修一(12~17年)=17年オフに自由契約 ※現役
▼片岡治大(14~17年)=17年限りで現役引退
▼相川亮二(15~17年)=17年限りで現役引退
▼金城龍彦(15年)=15年限りで現役引退
▼脇谷亮太(16年~)※現役
▼陽 岱鋼(17年~)※現役
巨人にFAでやってきた野手を見ると、他球団の主力選手がほとんど。さらに落合博満も広沢克己も清原和博も以前の在籍球団ではファーストを守っていたように、ポジション被りが目立った。事実、落合と広沢が在籍していた頃は広沢がレフトを守り、清原を獲得する際には落合がチーム事情を察して自ら自由契約を申し出るという異例の事態にもなっている。
巨人への移籍はセカンドキャリアにつながる!?
続いて、巨人にやってきた投手たちも見てみよう。
▼川口和久(95~98年)=98年限りで現役引退
▼河野博文(96~99年)=99年オフに自由契約となりロッテへ
▼工藤公康(00~06年)=06年オフに人的補償で横浜へ
▼前田幸長(02~07年)=07年オフに自ら退団を申し入れてメジャーに挑戦
▼野口茂樹(06~08年)=08年に自由契約。12球団合同トライアウトを受けたのち独立リーグへ
▼豊田 清(06~10年)=10年オフに自由契約となり広島へ
▼門倉 健(07~08年)=08年に自由契約となりメジャーに挑戦
▼藤井秀悟(10~11年)=12年1月に人的補償で横浜へ
▼杉内俊哉(12年~)※現役
▼大竹 寛(14年~)※現役
▼山口 俊(17年~)※現役
▼森福允彦(17年~)※現役
野手のFA選手は1990年代から2000年代前半の長嶋茂雄政権時に多く獲得していたが、投手に関しては原辰徳の第2次政権時に5人と多い。そして、野手以上に故障等に苦しむことが多かったせいか、在籍年数も短く短期間で自由契約になる選手が多かった。
野手・投手ともにほとんどのFA選手にとって巨人は“安住の地”とはならなかったが、現役を引退した巨人のFA選手23人中、6人がコーチやスタッフとして再び巨人のユニフォームに袖を通している。これを見る限り、能力の高さを買われたFA選手たちにとってのセカンドキャリアには繋がっていると言えそうだ。
今回自由契約になった村田修一、そして巨人に在籍しているFA選手たちは、そのキャリアを終えるときにどこのユニフォームを着ているのだろうか。
文=福嶌弘(ふくしま・ひろし)
【福嶌弘プロフィール】
1986年、神奈川県生まれ。バイク・クルマの雑誌の編集部を経て2015年からフリーライターに。父が歌う「闘魂込めて」を聴いて育ったため、横浜出身ながら生来の巨人ファン。『甲子園名門野球部の練習法』(宝島社)『プロ野球2017 シーズン大展望』(洋泉社)、『がっつり!プロ野球』(日本文芸社)などに執筆。