ということば、最近認知症に関連してよく使われている。
私の最新著『奇跡のはじまり』を読んだある友人からいただいた感想の中に、私の介護メソッドが「ユマニチュードのように、さらに具体的かつ分かりやすい形で社会に浸透してゆく事を願ってやみません」と書かれていたので、今さらのようにこのことばの定義を調べてみた。
「「見つめる」「話しかける」「触れる」「立つ」を基本に、“病人”ではなく、あくまで“人間”として接することで認知症の人との間に信頼関係が生まれ、周辺症状が劇的に改善するというメソッド」だという。
私はこの解説を読んでちょっと驚いた。
「へえ、この介護メソッドのどこが新しいんだろう。これって当たり前のことなんじゃないの?私なんかいつもやってることばかりじゃない」
私は、いつもそう思っている。
ただ一方で、さまざまな介護現場では必ずしもこれが当たり前にはなっていない現実も数多く存在する。
たまに「ええ?そんなんでイイの?」と思うような現場にも遭遇する。
きっとこういうユマニチュードのようなことが今さらのように強調されて「相手の人間性に触れることが大事ですよ」と言われなければ気がつかないほど介護の現場ではこうした基本的なことがおろそかにされているのかもしれないし、難しいことなのかもしれない。
なぜそうなるのか。
それは、介護する人たち自身がとっても疲れていること。
そして、何よりも、介護する側の人たちが「こうすれば楽に車椅子に乗せられます」「こうすれば腰を痛めないでお風呂のお世話ができます」といった技術的なことやノウハウばかりに気を取られ、自分がお世話する相手(つまり、介護される人)と「コミュニケーション」を取ろうという意識そのものが欠如しているからだ。
私が、大手の介護企業と契約してこれまで二百近い施設を回って延べで一万人近いお年寄りたちと接してきたのも、妻の介護でやってきたことも「コミュニケーション」以外の何ものでもない。
私たちは、介護施設に「音楽を演奏」しに行っているのではない。
「音楽でどうやったら一人一人の方とコミュニケーションが取れるのだろうか」という思いで行っている。
自分の目の前にいる人たちは全て戦争を経験している人たちだ。
現在施設に入居されている人たちはまず間違いなくその年代の人たちだ。
もうそれだけでも尊敬に値するし、一人一人から聞きたいことは山のようにある、と思いながら演奏する。
これがなければ介護施設で演奏しても、「単なる自己満足」で終わってしまう。
「音楽はコミュニケーション」。
「介護もコミュニケーション」。
私にとってはこれが当たり前だ。
家族だって夫婦だって仕事だって、コミュニケーションをどうやってうまく行っていくかが「上手に生きる」コツ。
ある意味、これに失敗すると「生きる」ことに失敗することにもつながっていきかねない。
特に、介護の現場、とりわけ認知症のお年寄りで一番厄介なのは、このコミュニケーションの取り方が難しいことだ。
施設には、認知症やパーキンソン病など、本人の意志に関係なく大声や罵声や暴力的な言動に走る人がいる。
これはこれで本人の責任ではない。
病気がそうさせているだけなのだ。
ただ、そうは思っても、この状況に不慣れだったりその認識がないとコミュニケーションの基本は根底から覆されてしまう。
ことばで説得しようとしても拒否されたり、手をひいて「おウチへ帰りましょう」と連れて行こうとしても手を払いのけられたりすると、慣れない人はきっと頭に血が上ってしまうだろう。
あるいは、落ち込んでしまうかもしれない。
しかし、人間は視点を変えるとけっこううまく物事を理解できたり行動もスムーズに行うことができたりする。
ポイントは、「コミュニケーションの方法はいくらでもある」と思うことだ(きっと、ユマニチュードというのは、この辺をうまくことばにしているのだろう)。
ことばだけが意志を通じ合う方法ではないし、スキンシップも認知症の患者さんとかには、逆に「攻撃されている」と理解されてしまうことがある。
だからこそ「音楽」というコミュニケーションツールは介護の現場にはとても有益だと思っている。
この思いは、介護現場を経験すればするほど「確信」に近いものになっている。
自分の妻には音楽を「リハビリ」のツールとして使っている。
お年寄りには、いろいろな意味での「コミュニケーション」ツールとして音楽を活用している。
別にユマニチュードなどということさら新しい言い方をしてみなくても、病気の治療も介護も音楽も基本は「コミュニケーション」なんだから、「見つめる」「話しかける」「触れる」「立つ」なんてこと、至極当たり前のことだと思うのだが。
私の最新著『奇跡のはじまり』を読んだある友人からいただいた感想の中に、私の介護メソッドが「ユマニチュードのように、さらに具体的かつ分かりやすい形で社会に浸透してゆく事を願ってやみません」と書かれていたので、今さらのようにこのことばの定義を調べてみた。
「「見つめる」「話しかける」「触れる」「立つ」を基本に、“病人”ではなく、あくまで“人間”として接することで認知症の人との間に信頼関係が生まれ、周辺症状が劇的に改善するというメソッド」だという。
私はこの解説を読んでちょっと驚いた。
「へえ、この介護メソッドのどこが新しいんだろう。これって当たり前のことなんじゃないの?私なんかいつもやってることばかりじゃない」
私は、いつもそう思っている。
ただ一方で、さまざまな介護現場では必ずしもこれが当たり前にはなっていない現実も数多く存在する。
たまに「ええ?そんなんでイイの?」と思うような現場にも遭遇する。
きっとこういうユマニチュードのようなことが今さらのように強調されて「相手の人間性に触れることが大事ですよ」と言われなければ気がつかないほど介護の現場ではこうした基本的なことがおろそかにされているのかもしれないし、難しいことなのかもしれない。
なぜそうなるのか。
それは、介護する人たち自身がとっても疲れていること。
そして、何よりも、介護する側の人たちが「こうすれば楽に車椅子に乗せられます」「こうすれば腰を痛めないでお風呂のお世話ができます」といった技術的なことやノウハウばかりに気を取られ、自分がお世話する相手(つまり、介護される人)と「コミュニケーション」を取ろうという意識そのものが欠如しているからだ。
私が、大手の介護企業と契約してこれまで二百近い施設を回って延べで一万人近いお年寄りたちと接してきたのも、妻の介護でやってきたことも「コミュニケーション」以外の何ものでもない。
私たちは、介護施設に「音楽を演奏」しに行っているのではない。
「音楽でどうやったら一人一人の方とコミュニケーションが取れるのだろうか」という思いで行っている。
自分の目の前にいる人たちは全て戦争を経験している人たちだ。
現在施設に入居されている人たちはまず間違いなくその年代の人たちだ。
もうそれだけでも尊敬に値するし、一人一人から聞きたいことは山のようにある、と思いながら演奏する。
これがなければ介護施設で演奏しても、「単なる自己満足」で終わってしまう。
「音楽はコミュニケーション」。
「介護もコミュニケーション」。
私にとってはこれが当たり前だ。
家族だって夫婦だって仕事だって、コミュニケーションをどうやってうまく行っていくかが「上手に生きる」コツ。
ある意味、これに失敗すると「生きる」ことに失敗することにもつながっていきかねない。
特に、介護の現場、とりわけ認知症のお年寄りで一番厄介なのは、このコミュニケーションの取り方が難しいことだ。
施設には、認知症やパーキンソン病など、本人の意志に関係なく大声や罵声や暴力的な言動に走る人がいる。
これはこれで本人の責任ではない。
病気がそうさせているだけなのだ。
ただ、そうは思っても、この状況に不慣れだったりその認識がないとコミュニケーションの基本は根底から覆されてしまう。
ことばで説得しようとしても拒否されたり、手をひいて「おウチへ帰りましょう」と連れて行こうとしても手を払いのけられたりすると、慣れない人はきっと頭に血が上ってしまうだろう。
あるいは、落ち込んでしまうかもしれない。
しかし、人間は視点を変えるとけっこううまく物事を理解できたり行動もスムーズに行うことができたりする。
ポイントは、「コミュニケーションの方法はいくらでもある」と思うことだ(きっと、ユマニチュードというのは、この辺をうまくことばにしているのだろう)。
ことばだけが意志を通じ合う方法ではないし、スキンシップも認知症の患者さんとかには、逆に「攻撃されている」と理解されてしまうことがある。
だからこそ「音楽」というコミュニケーションツールは介護の現場にはとても有益だと思っている。
この思いは、介護現場を経験すればするほど「確信」に近いものになっている。
自分の妻には音楽を「リハビリ」のツールとして使っている。
お年寄りには、いろいろな意味での「コミュニケーション」ツールとして音楽を活用している。
別にユマニチュードなどということさら新しい言い方をしてみなくても、病気の治療も介護も音楽も基本は「コミュニケーション」なんだから、「見つめる」「話しかける」「触れる」「立つ」なんてこと、至極当たり前のことだと思うのだが。















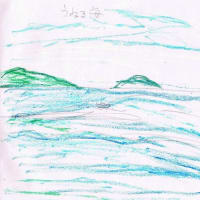


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます