『母の眠り』というのは1998年に公開された映画のタイトル。
メリル・ストリープ、レネ・ゼウィルガー、ウィリアム・ハートといった名優たちの共演する安楽死がテーマの映画だ。
しかし、実際に映画を見るとこのテーマはそれほど重要なテーマにはなっておらず(確かにこのテーマを軸にして作られていることはわかるのだが)、むしろ「人生にとって大切なものは何なのか、私たちの生活にとってかけがえのないものは何なのか」をとても素直に考えさせてくれる名画だと私は思っている。
メリル・ストリープとウィリアム・ハート(この人はNYの隣の州ニュージャージー州の大学でアメリカ文学を教える教授)という夫婦の娘であるレネ・ゼウィルガーは、NYで有名雑誌の記者として上昇志向に燃える典型的なキャリアウーマン。
それに対して母親は完璧な主婦であることを誇りとする女性(都会以外に住むアメリカの母は案外このタイプの人が多い)。
母親の生き方を嫌いけっして母親のようにはなりたくないと思って生きている娘が、ある時母が癌にかかったことにより自宅に戻り母の介護をすることになる。
キャリアウーマンとしての自分の人生を母の介護で棒にふってしまうと嘆く娘に、母は死の間際にこう言い残す。
「人が幸せになるのはとても簡単なことなのよ。今あるものを愛せばいいだけなの。あなたも、なくしてしまったものを求めるのをやめたら、人生はもっと穏やかになるはずよ。あなたは今たくさんのものを持っているじゃない。それを愛しさえすればいいのよ」。
この映画が私たちに教えてくれるのは、「ありのままの自分を受け入れられない限り人はずっと不幸であり続けるのでは」ということだと私は思っている。
毎日病気に苦しむ人たちばかりを病院で見ていると、どの患者さんもどの家族もいっけん不幸をたくさん背負って生きているように見えるけれども、それはハタで見ているだけの話で、認知症で家族が何を話しかけてもただ俯いているような患者さんの家族がそれだけで不幸なのかどうかを判断することはできない。
「人間は年を取ればボケてしまうんだから、別にしょうがないじゃないか」と思えば、認知症の方を抱える家族の気持ちも少しは和らぐはず。
私自身も妻の病気と介護、そしてリハビリなどを抱えてまったく「大丈夫」とは思わないけれども、別に自分一人だけがこんな問題を抱えているわけじゃないし(世の中にはもっともっと背負いきれないものを背負わされてしまっている人たちがたくさんいるわけだから)、逆に、自分の妻という存在の「かけがえのなさ」に気づくことができたわけだし、自分自身の生き方を改めて見つめ直すことだってできたんだから、かえって「幸せじゃん」と思えないこともない。
病気も障害もそれを受け入れられない限り不幸は永遠に続くわけだし、人生は短いんだからそんなことで貴重な時間を無駄にはしたくない。
「なったものはしょうがない」し「起こったことはしょうがない」。それよりも今自分にあるものは何なのかを考えれば、映画『母の眠り』の中の母親が娘に言い残した「今あるものを愛すことができれば人はみんな幸せになれる」ということばの意味が本当に理解できるような気がしてならない。
障害があろうがなかろうが、今目の前にいる「大事な人」こそかけがえのないものと考えられる人生の方がはるかに幸せなのではと思う(それは、ダウン症の子供を持つ家族の方たちがよく言うことばでもある)。
少なくとも私には「かけがえのないもの」があるから私は幸せなのかなと思うし、本当はどんな人にも「かけがえのないもの」はあるはずなのに、それを見ようとしないのか、見えていないのか。
「なくしたもの」や「過去」を探し続けるから今の目の前にある大事な「それ」が見えなくなるのだろうか。
不幸は、自分と誰かを比較する時始まるのではないかといつも思っている。
「あの人の方が私よりお金持ち」「あの人の方が私より頭が良い」「あの人の方が私よりやせている」…。
人と競争することを強いられる「都会」の中で人はいやおうなく「比較」するクセを身につけてしまったのかもしれないとも思う。
そうでなくては「都会」というたくさんの人が住む社会では生き残っていくことができないから。
NYという都会でのキャリアを目指す娘が田舎で家庭の主婦として満足している母親を受け入れらないというこの映画の図式は、別にアメリカだけでなく世界中どこにでもあるだろう。
しかし、自分の母親より大事なもの、かけがえのないものなんてこの世の中に存在するはずはないし、自分の娘より大事なものなんてあるはずがないといった当たり前のことを見えなくしているのがやはり「都会」なのかなという気もする。
ちょっとノンビリとした伊豆の風景の中で生活していると、案外「かけがえのないもの」は「都会」よりも見え易くなっているのかもしれない。
メリル・ストリープ、レネ・ゼウィルガー、ウィリアム・ハートといった名優たちの共演する安楽死がテーマの映画だ。
しかし、実際に映画を見るとこのテーマはそれほど重要なテーマにはなっておらず(確かにこのテーマを軸にして作られていることはわかるのだが)、むしろ「人生にとって大切なものは何なのか、私たちの生活にとってかけがえのないものは何なのか」をとても素直に考えさせてくれる名画だと私は思っている。
メリル・ストリープとウィリアム・ハート(この人はNYの隣の州ニュージャージー州の大学でアメリカ文学を教える教授)という夫婦の娘であるレネ・ゼウィルガーは、NYで有名雑誌の記者として上昇志向に燃える典型的なキャリアウーマン。
それに対して母親は完璧な主婦であることを誇りとする女性(都会以外に住むアメリカの母は案外このタイプの人が多い)。
母親の生き方を嫌いけっして母親のようにはなりたくないと思って生きている娘が、ある時母が癌にかかったことにより自宅に戻り母の介護をすることになる。
キャリアウーマンとしての自分の人生を母の介護で棒にふってしまうと嘆く娘に、母は死の間際にこう言い残す。
「人が幸せになるのはとても簡単なことなのよ。今あるものを愛せばいいだけなの。あなたも、なくしてしまったものを求めるのをやめたら、人生はもっと穏やかになるはずよ。あなたは今たくさんのものを持っているじゃない。それを愛しさえすればいいのよ」。
この映画が私たちに教えてくれるのは、「ありのままの自分を受け入れられない限り人はずっと不幸であり続けるのでは」ということだと私は思っている。
毎日病気に苦しむ人たちばかりを病院で見ていると、どの患者さんもどの家族もいっけん不幸をたくさん背負って生きているように見えるけれども、それはハタで見ているだけの話で、認知症で家族が何を話しかけてもただ俯いているような患者さんの家族がそれだけで不幸なのかどうかを判断することはできない。
「人間は年を取ればボケてしまうんだから、別にしょうがないじゃないか」と思えば、認知症の方を抱える家族の気持ちも少しは和らぐはず。
私自身も妻の病気と介護、そしてリハビリなどを抱えてまったく「大丈夫」とは思わないけれども、別に自分一人だけがこんな問題を抱えているわけじゃないし(世の中にはもっともっと背負いきれないものを背負わされてしまっている人たちがたくさんいるわけだから)、逆に、自分の妻という存在の「かけがえのなさ」に気づくことができたわけだし、自分自身の生き方を改めて見つめ直すことだってできたんだから、かえって「幸せじゃん」と思えないこともない。
病気も障害もそれを受け入れられない限り不幸は永遠に続くわけだし、人生は短いんだからそんなことで貴重な時間を無駄にはしたくない。
「なったものはしょうがない」し「起こったことはしょうがない」。それよりも今自分にあるものは何なのかを考えれば、映画『母の眠り』の中の母親が娘に言い残した「今あるものを愛すことができれば人はみんな幸せになれる」ということばの意味が本当に理解できるような気がしてならない。
障害があろうがなかろうが、今目の前にいる「大事な人」こそかけがえのないものと考えられる人生の方がはるかに幸せなのではと思う(それは、ダウン症の子供を持つ家族の方たちがよく言うことばでもある)。
少なくとも私には「かけがえのないもの」があるから私は幸せなのかなと思うし、本当はどんな人にも「かけがえのないもの」はあるはずなのに、それを見ようとしないのか、見えていないのか。
「なくしたもの」や「過去」を探し続けるから今の目の前にある大事な「それ」が見えなくなるのだろうか。
不幸は、自分と誰かを比較する時始まるのではないかといつも思っている。
「あの人の方が私よりお金持ち」「あの人の方が私より頭が良い」「あの人の方が私よりやせている」…。
人と競争することを強いられる「都会」の中で人はいやおうなく「比較」するクセを身につけてしまったのかもしれないとも思う。
そうでなくては「都会」というたくさんの人が住む社会では生き残っていくことができないから。
NYという都会でのキャリアを目指す娘が田舎で家庭の主婦として満足している母親を受け入れらないというこの映画の図式は、別にアメリカだけでなく世界中どこにでもあるだろう。
しかし、自分の母親より大事なもの、かけがえのないものなんてこの世の中に存在するはずはないし、自分の娘より大事なものなんてあるはずがないといった当たり前のことを見えなくしているのがやはり「都会」なのかなという気もする。
ちょっとノンビリとした伊豆の風景の中で生活していると、案外「かけがえのないもの」は「都会」よりも見え易くなっているのかもしれない。















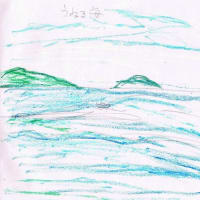


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます