なんということばの矛盾だろうと思う。
「返さなければいけない奨学金って何よ」。
返さなければいけないんだったら単なる「ローン」、借金じゃないの?と思う。
経済的な問題を抱えている学生、あるいは才能豊かな人の才能をより伸ばすために「奨学する」ためのお金が「奨学金」なのじゃないのと思う。
私がアメリカの学生だった時、いろいろな奨学金をもらっていた(もちろん、それらのお金を1セントも返してはいないしその必要性もない)。
州立の学校だったので州からの奨学金(つまり、アメリカ国民の税金だ)、あるいは、財団からの奨学金、そしてプライベートな人からの奨学金、など。
大学院時代は、 私は担当のフルートの先生の助手としてお給料をもらっていた。
いわゆるteaching assistantという奨学金だ(なので、週に何時間かは先生の代わりに学部の学生を教えていた)。
この奨学金で一番オイシイ特典は、毎月給料がもらえることよりも学費が全額免除になることだ。
アメリカの大学の学費がベラボウに高いことは日本でもよく知られている(高いのは私立だけじゃない、公立だって高いのだ)。
なので、この teaching assistantという奨学金を得たい学生はゴマンといる。
その狭き門をなんとか突破して大学院生活を送った。
正直これがなかったら私はアメリカで勉強を続けていられたかどうかわからない。
それと、音楽の学生にはもっと別の奨学金の可能性がある。
学内にあるオーケストラ、吹奏楽のバンド、室内楽、個別の楽器の優秀な学生に、一般の有志が個人的な奨学金を作っている。
例えば、オーケストラのコンサートマスターには Aさんというお金持ちが「 Aさんチェア(つまり、その席に座る人に与える奨学金という意味)」とかいうネーミングで毎月2万円奨学金を与えるとか、オーボエの主席には Bさんが「Bさんチェア」で3万円の奨学金を与えるとかいった風に(ジュリアード音楽院なんか、こんなプライベートな奨学金だらけだ)。
だから、自分の得意な分野でそれぞれの奨学金の可能性にチャレンジすれば良いわけだ。
だから、自ずと演奏のレベルも上がっていく(スポーツ選手の奨学金も同じ理屈で優秀な学生を集めて各大学はレベルを上げていく)。
どうして、こんな制度や考え方が日本では普及しないのか不思議でしょうがない。
今頃になって「給付型奨学金」を導入しようとかしないとか議論しているから日本の才能がどんどん外国に流れていくのだと思う。
アメリカではありとあらゆる分野にこうした個人の奨学金、企業からの奨学金、あるいは財団からの奨学金が用意されている。
私が学生だった70年代、化学( chemistry)はサイセンスの中では比較的「日陰者」扱いの分野だった。
誰も本気で研究したがらない地味な分野だった(あまりお金にならない学問だと思われていたからだ)。
おかげで、日本人とか中東からの留学生とか東洋人の優秀な学生がたくさん奨学金をもらって研究を続けていた。
しかし、時代は変わり、今やbio chemistryをはじめ、この化学分野は最も発展性のあるサイエンスとして世界中で脚光を浴びている。
しかし、こうした分野での「業績」や「成果」はほぼアメリカが独占している。
当然のことだ。
だって、彼らが「お金を出して世界中の優秀な頭脳を育てていた」のだから(日本人ノーベル賞学者のほとんどはアメリカで勉強したか研究してきた人たちだ)。
多分、日本もやっと気づいたのだろう(気づいていてもなかなか実行に移せないのがこの国の空気だ)。
ただ、いかんせん日本は数十年遅れている(私が学生だったのは70年代だ)。
70年代にアメリカでは既にバリアフリー、ユニバーサルデザイン、多様性という考えが当たり前だったことも忘れてはならない。
しかも、現在、世の中はどんどん内向きになっている。
ネットやスマホが普及したせいできっと外国のことをわかった気になっている「エセグローバリズム」が多くなったせいかもしれない。
ネットで見る「世界」はホンモノの世界ではないということをもっと知るべきだ。
シカゴの移民局で簡単な手続きをするだけで3時間も4時間も並ばされ、あげくの果てに黒人の担当者にイヤミを言われアゴでせせら笑われた屈辱が(私にとっては)ホンモノの外国だ。















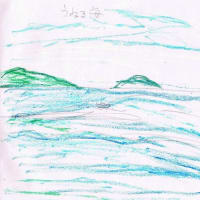


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます