今日の午後の光景。
私は、交差点の赤信号で車を停車させた。
私の停車位置は信号から数えて10台目ぐらい後方。
つまり、信号からけっこう遠い位置で私の車は停まった。
待っている最中すぐ左の歩道を歩いていた一人の老人がいきなり私の車の目の前を横切り道路の向こう側に渡っていった。
あっと言う間だった。
信号からも遠いし信号も赤だから「えい、や」とばかり横断してしまったのだろうが、その渡り方がいけない。
私の車線側の車はみんな停まっている(赤信号だから当然だ)。
しかし、反対車線を通行している車はある(これも当然だ)。
なのに、この老人、私の車の前を通り過ぎて向こう側に行くのにまったくと言っていいくらい左側を確認していなかった(左をまったく見ていなかった)。
つまり、左から車が来るはずがないと思い込んでいるらしい。
たまたま車は一台もその瞬間に来なかったからよかった。
でも、もしこの人が私の目の前を突っ切り反対車線に出た瞬間に向こうから車が来ていたら…。
この光景を目撃した瞬間、先日報道されていたある自動車事故のことを思い出した。
その事故は老人ではなくまだ一才にもならない赤ちゃんを背中に背負い自転車で同じように道路を横断しようとして反対車線の車にはねられた若いママ(この場合、はねられたという表現自体正しくないと思う。この人は自ら車にぶつかりに行ったようなものだ)。
ママは怪我はしたけれど助かり、赤ちゃんは亡くなった。
ネットには、この母親を非難するコメントで溢れかえっていた。
たまたま向こうからやってきたドライバー(二十代の若い介護士さんらしい)と亡くなった赤ちゃんがかわいそう…。
私もそう思う。
でも、今日私が見た光景もそうだが、どちらの当事者にも言える過失は、やはり自己中心的な行動なのではと思う。
信号まで行くのがメンドくさいから渡ってしまえ…という気持は誰にも起こる気持だが、その行動を起こす前に考えるべきことはたくさんあるはずだ。
自分の背中に赤ん坊を背負っている(しかも、まだ首も座っていないガラス細工のような存在だ)。
これだけでも重大なことだ。
おまけに自転車を運転している…。
今日の高齢者の方も、左を確認しようという気はさらさらないように見えた。
みんなすごく自分勝手。
こんなに身勝手な行動がいつから当たり前になってしまったのだろうか。
午後この買い物に出る前、午前中は家でパンを作っていた。
ちょうど二次発酵中に玄関のドアがノックされた。
誰だろう?宅配の車が来た気配もないが…と思いながらドアを開けると近所の一人暮らしの(八十代の)おばあさん。
「これ、ウチのみかん。そのまま食べてもおいしいよ。私はママレードにしたけれど… 」と大きな甘夏を袋にいっぱい置いていった(ついこの前も自家製の大根をくれたばかりだ)。
小さい頃は、都会のど真ん中に暮らしていた(今は山の中の一軒家だが)。
でも、「こんな光景、小さい頃よくあったよナ」とおばあさんが帰った後そんなことを思い出す。
どこでも普通に人と人が密接に結ばれていたはずなのに今はSNSとかネットとか、そんな仮想領域でしか人と人はつながらない。
昨年から通っている「看取りセミナー(ほぼ隔月、東大本郷で開かれている)」で「ドゥーラ」ということばを知った。
ギリシャ語語源のこのことばのもともとの意味は「他の女性を助ける経験豊かな女性」ということだそうだ。
それが転じて「妊娠、出産、育児の現場で寄り添う女性」つまり「助産婦」とか「産婆」さんのことを指すことばに変わったという。
この「ドゥーラ」という概念を、出産、子育ての現場だけでなく介護、看取りの領域にまで広げていこうという動きがここ数年世界的に広まってきている。
その根本にあるのは、現在の介護現場と出産現場のあまりにも酷似している環境だ。
どちらも、本来あるべき「家庭」という空間から「病院」という空間に移り、医療行為という専門性に全てが集約されてしまっている。
本当は、「家で生まれて家で死ぬ」が普通だったのが、ある時から人間は「病院で生まれて病院で死ぬのが普通」に変わってしまった。
だからこそ起きる「子育ての迷い」や「人と人の心の絆の欠如」「(人の一生に起きるさまざまな)悩みと絶望」といったものにもう一度「原点」に戻って対処していこうという動きがこの「ドゥーラ」ということばには含まれているのだ。
このセミナーの主宰者であるK先生(この方は看護士さんでもある)から「みつとみさんのやっていることは、音楽の領域でありながらこのドゥーラの考え方にとても近いので、<音楽ドゥーラ>という新しい立場で発言なさっては?」と勧められた。
いや、しかし、私がそんなことばを大上段に名乗るには私自身がまだあまりにもドゥーラについて勉強不足です。ですので、もう少し勉強させてください」と言ってその申し出はとりあえず丁重に辞退した。
しかし、私がやってきた「(フルムスという女性オーケストラの活動を含め)女性支援のための音楽活動」やこれまでの「音楽を世の中へどうしたら役立てていくことができるのか」といった運動のベクトルはたしかにこの「ドゥーラ」に限りなく近い。
こうした人と人との絆がどんどん希薄になる地球という星をもっと「良い空気」で満たすには音楽の役割もけっして少なくないのではと思う。
音楽療法なんてことばを使わなくても、もう音楽という存在自体が「セラピー」だし、十分人々や世の中の「癒し」になっているのだから。
ふと、60年以上前の5月15日に実家で生まれた弟の誕生風景を思い出した。
実家の居間で出産した弟を取り上げるお産婆さん(実家の近所には何人かのお産婆さんが看板を掲げていた)。
お風呂で産湯につかっている生まれたての赤ん坊。
祖母や叔母から「入ってきてはいけない」と言われた「禁断の光景」は、(私の脳内でのみ)今でも忠実に再現される。
そうか、明日があの日だったのか…。















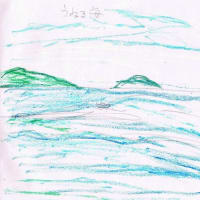


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます