★ 下郷農協探訪記 その3 ★ (8/26-8/28)
下郷農協は、農協の合併が全国的に進む中
合併を拒否して設立以来の単協を貫いています。
「下郷農協って農協なの?」って思ったことありませんか?
近くにあるJAとは違ってますよね。
【下郷農協の歴史】
下郷農協は、1948年、
もと小作だった人たちが中心になって設立されました。
その後、下郷第一農協(JA)が発足しても
下郷農協は地域の発展をめざし独自に歩んでいきます。

1952年、少し山手の「鎌城地区」に信州から開拓団が入植。
鎌城地区の畜産をきっかけに大きく発展してきました。

大原地区で農業を営む人
鎌城地区で畜産を営む人
安全なものを求める都会の人たちが
手を組んで産直を始め、今の形になりました。

(つづく)
下郷農協は、農協の合併が全国的に進む中
合併を拒否して設立以来の単協を貫いています。
「下郷農協って農協なの?」って思ったことありませんか?
近くにあるJAとは違ってますよね。
【下郷農協の歴史】
下郷農協は、1948年、
もと小作だった人たちが中心になって設立されました。
その後、下郷第一農協(JA)が発足しても
下郷農協は地域の発展をめざし独自に歩んでいきます。

1952年、少し山手の「鎌城地区」に信州から開拓団が入植。
鎌城地区の畜産をきっかけに大きく発展してきました。

大原地区で農業を営む人
鎌城地区で畜産を営む人
安全なものを求める都会の人たちが
手を組んで産直を始め、今の形になりました。

(つづく)






















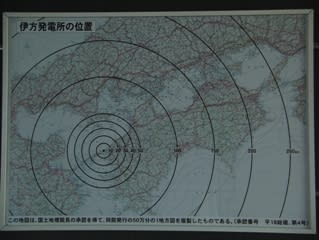






 理事長 丸井一郎です。
理事長 丸井一郎です。 今年の高知の夏は雨ばかりで、
今年の高知の夏は雨ばかりで、 幸いにして高知地方は、「寒さの夏はおろおろ歩き」
幸いにして高知地方は、「寒さの夏はおろおろ歩き」 「土といのち」の野菜に誇らしく感謝しつつ、
「土といのち」の野菜に誇らしく感謝しつつ、 津野町 天竺舎の雨宮智子です。
津野町 天竺舎の雨宮智子です。








 まず高温のチャツネを充填して脱気の準備をします
まず高温のチャツネを充填して脱気の準備をします 次に蓋を緩めて脱気をします
次に蓋を緩めて脱気をします
 以上で脱気作業は完了です 。
以上で脱気作業は完了です 。


 玉ねぎを微塵切りにする。
玉ねぎを微塵切りにする。


 油・ホールスパイスを中火で加熱、
油・ホールスパイスを中火で加熱、

 全体に火がまわれば、
全体に火がまわれば、
 水分が少なくなってきたら、
水分が少なくなってきたら、 なるべく空気が入らないように中身を詰めます。
なるべく空気が入らないように中身を詰めます。
 蓋をきっちり締め、加熱殺菌。脱気。
蓋をきっちり締め、加熱殺菌。脱気。
 瓶に詰める前にちょっぴり試食。
瓶に詰める前にちょっぴり試食。





