12月25日(水ん)、晴れ。
うららかな一日でした。
映像は、昨日の郡山城址。
チョッとした時間調整のため久しぶりに立ち寄りました。
天守閣はありません。
櫓と城門は、昭和の終わり期に、再建されました。

右が追手門、左が追手向い櫓。


追手門再建の時使われた台湾檜の切り株。
直径1メートル90センチほどあります。

再建は、昭和56年ころだったと思います。
当時でも、国内ではこれほどの檜の大木が見つからなかったので、台湾から調達した経緯があります。
丁度この頃、将棋博物館がオープン。
大山博物長の要請で「平安大将棋・平安小将棋」駒を推定復元しました。
その時、年輪が積んだ檜が欲しかったので、この切り株を使うことを思いつきました。
運よく関係者からこの切り株の端材を入手して、これで復元制作。
その一部が、手元に残したこの「醉象」。
もう一つの「醉象」は、ある方を経由して福井県の朝倉遺跡資料館に差し上げました。
それは、朝倉駒には「醉象」が1枚しか出土せず、本物を一組展示する時に、もう1枚欲しいということでした。
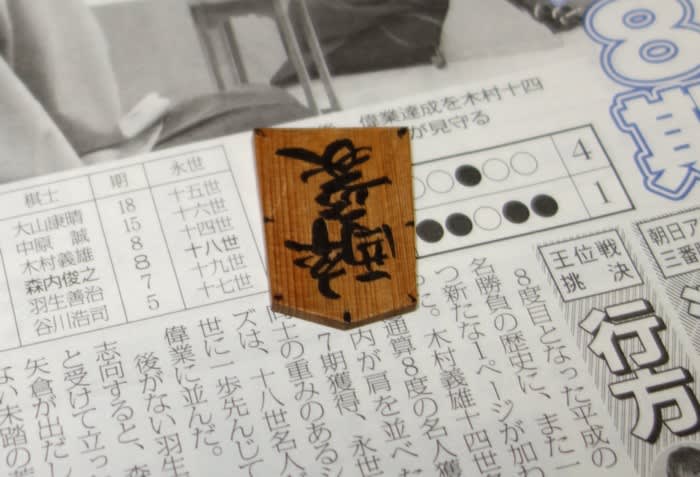
一方、将棋博物館に収めた「平安大将棋・平安小将棋駒」は、その後、どこにあるかは不明。
不明のままではいけないので、所在を近々確かめようと思っています。
柳沢文庫正面玄関、破風造りの馬寄せ。

柳沢文庫では、旧郡山藩・柳沢家の資料類が保存顕彰されています。
昔は良くお邪魔しました。
うららかな一日でした。
映像は、昨日の郡山城址。
チョッとした時間調整のため久しぶりに立ち寄りました。
天守閣はありません。
櫓と城門は、昭和の終わり期に、再建されました。

右が追手門、左が追手向い櫓。


追手門再建の時使われた台湾檜の切り株。
直径1メートル90センチほどあります。

再建は、昭和56年ころだったと思います。
当時でも、国内ではこれほどの檜の大木が見つからなかったので、台湾から調達した経緯があります。
丁度この頃、将棋博物館がオープン。
大山博物長の要請で「平安大将棋・平安小将棋」駒を推定復元しました。
その時、年輪が積んだ檜が欲しかったので、この切り株を使うことを思いつきました。
運よく関係者からこの切り株の端材を入手して、これで復元制作。
その一部が、手元に残したこの「醉象」。
もう一つの「醉象」は、ある方を経由して福井県の朝倉遺跡資料館に差し上げました。
それは、朝倉駒には「醉象」が1枚しか出土せず、本物を一組展示する時に、もう1枚欲しいということでした。
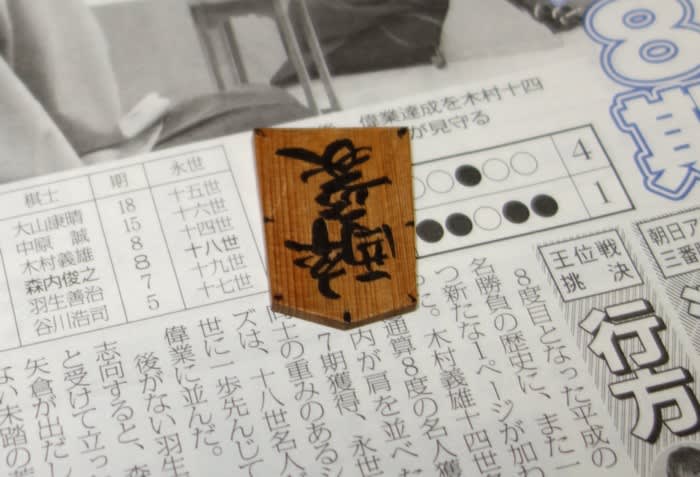
一方、将棋博物館に収めた「平安大将棋・平安小将棋駒」は、その後、どこにあるかは不明。
不明のままではいけないので、所在を近々確かめようと思っています。
柳沢文庫正面玄関、破風造りの馬寄せ。

柳沢文庫では、旧郡山藩・柳沢家の資料類が保存顕彰されています。
昔は良くお邪魔しました。
駒の写真集
リンク先はこちら」
http://blog.goo.ne.jp/photo/11726
















