2020年7月30日(木)
仕事帰りに本屋に立ち寄る、木曜日の習慣が戻ってきた。H.G.ウェルズの短編集、『タイム・マシン』がタイトルになっているがそれではなく、「他九篇」の中の『盲人国』という作品が目当てである。
南米の山中にある盲人の国に、男がさまよい込む。「盲人国では片眼のものでも王様だ」という格言を思い出し、一瞬さもしい野心を抱きかけるが、ほどなく自分の浅はかさを思い知ることになる。
「ヌネスは事のしだいを徐々に理解しはじめた。つまり、彼が外の世界から来たとか、目が見えるからといって、ここの人々に驚嘆され、尊敬される可能性はあまりないということがわかってきたのである。彼らに視覚について下手な説明をしても、未熟な人間が自分のちぐはぐな感覚のとまどいを説明しようとしているのだと思われるのが関の山だった。彼はやや意気を挫かれて、彼らの教訓の聞き役に廻った。最年長の盲人が、生命とか哲学とか宗教についてまず説明をはじめた・・・」
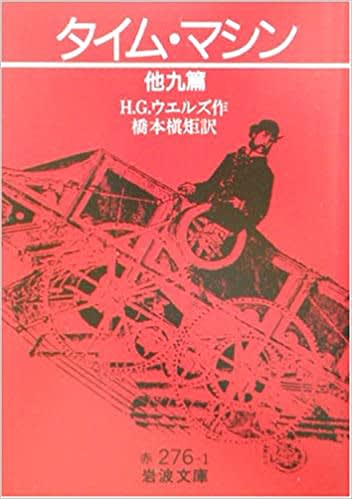
あわせてボクシングの手頃な入門書があればと思ったが、驚いたことにS書店のスポーツのコーナーにはボクシング関連書籍がない。ただ一冊、歴代ボクサーの誰が一番強かったか、階級別に写真入りで論じたマニアックな本があるだけで、他の格闘技は解説本がいくらでもあるのに、ボクササイズまで拡げて探索してもボクシングは見つからない。
不思議に感じつつレジへ向かおうとして、マラソンの棚に目が行った。松下茂典『円谷幸吉 命の手紙』、ずっと気にかかっているその件については既に多くが書かれているが、パラパラめくると知らないことがあれこれ飛び込んでくる。あの日、国立競技場のトラックで円谷をかわしたジョン・ヒートリーが妹を自死で失っていたこと、円谷家の人々と長く深くやりとりし、次のオリンピックで来日するのを楽しみにしつつ昨2019年に病没したことなども。一考してカゴに入れた。

帰宅後、夜に入って李登輝 元台湾総統の訃報が伝わる。享年97歳。
数日前から深刻な不調が報じられ覚悟していたのに、非常に残念な気もちが胸底に沁みだしてくるのを抑えられない。見事に生ききった李氏その人はクリスチャンでもあり、満腔の賞賛と感謝こそあれ「残念」という方向には感情があまり動かない。残念だというのは、こうした政治家 ~ politician ならぬ statesman が、台湾人にはあるのに日本人には見出し難いことである。
「22歳まで日本人だった」という李氏の言葉は、見かけほど平らかなものではない。国際法的にいえば単なる事実の確認ともとれることで、夥しい数の旧植民地の人々がある年齢までは実際に日本人だった。対する李氏の言挙げが、「(同じ境遇にあった多くの人々と違って)私はそのことを恥としない」という意味を含むのはわかりやすいが、そこで了解をうちきってすむものか。実は1945年を境に、多くの日本人が日本人であることをやめたのではないか。「22歳まで日本人だった」という述懐は、「その後あなた方はいったい何人になったのか」という鋭い問を胚胎する。
一方、その後は台湾人(中華民国国民)となった李氏は、日本人であった自分自身から引き継いだものを否認することも抑圧することもなく、台湾人政治家としての人生の中に確かに生かしていった。台湾の誇りを育み台湾人という国民を創出しつつ、武士道の価値を語り、芭蕉を懐かしむことができた。このように日本の良いものが台湾に引き継がれる一方、日本では衰微していき現在も衰微しつつある、それをこの機に痛感して「残念」だというのである。こんな人々と協働して東アジアに島々の連環を創り出せたら、どんなに痛快だったろう!
セントルイスで知り合った台湾人医師夫妻と、今もメールのやりとりをしている。地震が起きれば互いに見舞い合い、新元号が令和と決まったときには「お互いのつれあいの名前が入っている」と言祝いでくれた人々である。
「同文同種」今日篇(2019年4月18日)
https://blog.goo.ne.jp/ishimarium/e/eb3c6febe4a84ed9aec2c25fecc45b2f
夫人の御尊父は既に他界されたが、確か李登輝氏の盟友の一人であったはずだ。自在に日本語をあやつって昔話を聞かせてくれる、そのような世代の人だった。
合掌

https://diamond.jp/articles/-/244630
Ω









