2023年5月9日(火)
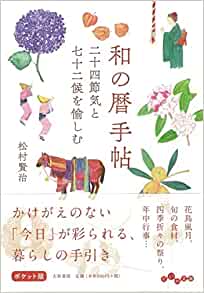
立夏 旧暦四月節気(新暦5月5日頃)
この時期に夏が始まるということの実感との乖離ばかりが意識され、節気の意義が以前はよくわからなかった。
感じ方が変わってきたのは、たぶん二つの理由がある。
一つは、季節の特徴を各相のピークに確かめるのではなく、変化の兆しを敏感に嗅ぎとる姿勢に、価値を認めるようになったこと。
もう一つは、たとえば「春」「夏」といった言葉の本来の意味に、注意を向けるようになったことにある。
「夏」といえば「夏休み」であり、八月である。あのうだるような蒸し暑さを「夏」とするなら、五月初旬の「立夏」はいかにも実感がない。しかし本来、「夏」とは太陽が力強くその生命力を発散して万物のうえに働かす、晴れ晴れと清々しいこの開放感に与えられた名称なのであろう。八月の蒸し暑さはその爛熟の顛末であって、「夏」の本質ではない。
***
「立夏」や「夏立つ」は夏の代表的な季語にもなっています。群や歳時記のうえでは夏のはじまりですが、気配はまだ春の色合いが濃い時期です。
野山の新緑が目にまぶしく、風が爽やかで心地よくなります。
新暦では、ゴールデンウィークの終盤あたりから夏に向かって季節が歩きだします。
P.48-49
七十二候
立夏初候 鼃始鳴(かわずはじめてなく)新暦5月5日~9日
立夏次候 蚯蚓出(みみずいずる) 新暦5月10日~14日
立夏末候 竹笋生(たけのこしょうず) 新暦5月15日~20日
6日から7日にかけて久しぶりにまとまった雨が降った。その直前にしきりに蛙が鳴き、それを聞きながら刈っておいた裏庭の梨の木の回りに、今朝は膝の高さのタケノコが5、6本も生えている。
令和の世にも節気は立派に通用し、内外の「気」をつなぐカレンダーとして有効利用可能である。
Ω




























