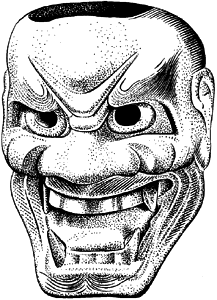2023年6月4日(日)
つまりこの日は辻堂を通って茅ヶ崎まで、招かれて話をしにいったのだけれど、案の定こちらが大いに教わって帰ってくることになった。シラス丼まで振る舞われて、申し訳ないことこのうえない。
旧約聖書の『コヘレトの書』から、問題の部分を末尾に示す。
冒頭の一行、すなわち
「何事にも時があり/天の下の出来事にはすべて定められた時がある」
との託宣、知らなければそのまま読み過ごすところ。読み進めば「殺す時」「憎む時」などと物騒な話で、それらすべてにわたって細大もらさず神が用意されると、そういうことか。
否、そう単純ではない。T牧師が分かりやすく解き明かしてくださった要点は「何事にも時があり」と「天の下の出来事にはすべて定められた時がある」というこの二つの「時」に対して、原語ではそれぞれ違う言葉が用いられているというのである。そうだったのか。
翻訳の多くは、これに自ずと対応して訳語を変えている。たとえば口語訳聖書では、
「天が下のすべての事には季節があり、すべてのわざには時がある。」
「季節」と「時」で訳し分けている。「生まれる時、死ぬ時」以下にずらずらと列挙されるのは、すべて「時」であって「季節」ではない。これすなわち「人の時」であり、人はそれぞれのもくろみに従い、特定の時点であれこれの行動を起こす。
しかし天が下には、それとは異なる天の季節というものがあり、神の計画に従って粛々と進んでいく。いわば二重の時間の中に置かれていながら、もっぱら自分が時を選んで物事を進めていくように人は思い込む、そうしたダイナミズムを俯瞰的に示したものらしい。
他の訳を列挙すれば、
「天が下の萬の事には期あり、萬の事務(わざ)には時あり」(文語訳)
「天の下では、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある」(新改訳)
「天の下では、すべてに時機があり、すべての出来事に時がある」(聖書協会共同訳)
新共同訳を除く全てが二つの時の一つを別の言葉に訳し変え、両者の違いを示唆している。「原文に忠実」をモットーにするはずの新共同訳が、敢えて同じ「時」の語を当てて違いを消去したのはなぜなのか、その意図はよくわからない。
ついでに英語・フランス語を見ると…
"For everything there is a season, and a time for every matter under heaven." (New Revised Standard Version)
"Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel:" (仏聖書協会版)
後続部分との関連から、日本語訳の「時」にあたるのが time と temps、「時期」「時機」「季節」に相当するのが season または moment であることがわかるが、「天の下のすべてのこと」との組み合わせが日本語訳と英仏訳では逆になっているように見える。違うのかな?
さて、そうなるといよいよ原文 〜 ヘブライ語を見なければならない。これがそれだ。
לַכֹּ֖ל זְמָ֑ן וְעֵ֥ת לְכָל־חֵ֖פֶץ תַּ֥חַת הַשָּׁמָֽיִם׃
זְמָ֑ן zeman 天の「時」 season
עֵ֥תהַ eth 人の「時」 time
So if any distinction intended, as seems probable, between the word zeman and eth, the author implies by the use of the former term that whatever occurs has been determined or fixed by God.
(The Interpreter's Bible, vol.5, P.43)
さて、「天の下」云々が season と time のどちらに関連するかだが、何しろ自分のヘブライ語がよちよち歩きにも達しないレベルだから、はっきりしたことは言えそうにない。語の配置を素直に見れば、文末に置かれた「天の下の」はより近くに配置されたעֵ֥תהַ(time)を修飾するようであり、手許の英訳と仏訳はそのように訳している。
しかし「すべてのことには(神の)季節がある」とするのが書き手の主張だとすれば、「天の下の」という決め言葉をこちらと結びつけるのは自然な発想である。修飾語と被修飾語が離れた位置に置かれたり、我々の感覚には不自然と感じられる語順をとったりすることは、たとえばラテン語では珍しくなかったような気がする。
さらに、「天の下のすべてのこと」には、(人の)時 time があると同時に、(神の)季節 season があるというふうに、「天の下」が両方にかかるとする第三の説も考えられる。よく見れば新改訳と聖書協会共同訳はこの説に与して読点(、)で文を三分しているように見える。
つまり…
「天の下」は time にかかる ・・・ 英語訳、仏語訳
「天の下」は season にかかる ・・・ 文語訳、口語訳、新共同訳
「天の下」は両者にかかる ・・・ 新改訳、聖書協会共同訳
「ギリシア語(新約)はカッチリしていて訳に揺らぎの余地がないが、ヘブライ語(旧約)は読み解くのに感性の助けが要る」という意味のことをセントルイスの教会で Don Howland 牧師から聞いた。四半世紀も前のことだが、今になってその意味が少しわかってくるようである。
サザン通り界隈に多くの教会がひしめく茅ヶ崎の町で、同信の人々とともに過ごした幸せな半日。
***
『コヘレトの言葉』3章1~11節 (新共同訳聖書による)
1: 何事にも時があり/天の下の出来事にはすべて定められた時がある。
2: 生まれる時、死ぬ時/植える時、植えたものを抜く時
3: 殺す時、癒す時/破壊する時、建てる時
4: 泣く時、笑う時/嘆く時、踊る時
5: 石を放つ時、石を集める時/抱擁の時、抱擁を遠ざける時
6: 求める時、失う時/保つ時、放つ時
7: 裂く時、縫う時/黙する時、語る時
8: 愛する時、憎む時/戦いの時、平和の時。
9: 人が労苦してみたところで何になろう。
10: わたしは、神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。
11: 神はすべてを時宜にかなうように造り、また、永遠を思う心を人に
与えられる。それでもなお、神のなさる業を始めから終りまで見極
めることは許されていない。
Ω