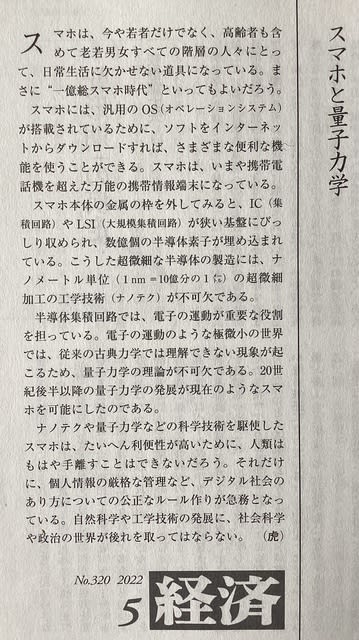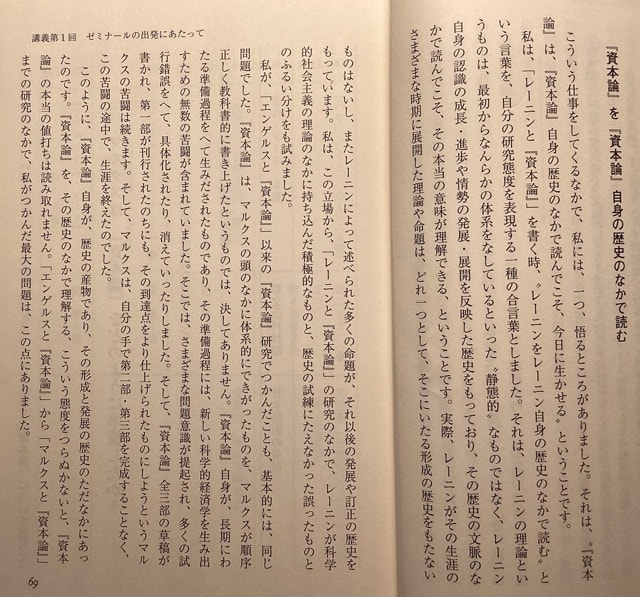志位さんが紹介した命題三項の第1の該当部分の『資本論』本文。(新版『資本論』2 p 470)
一般に経験が資本家に示すものは、絶えず続く過剰人口、すなわち資本の当面の増殖欲に比較しての過剰人口である——とはいえ、この過剰人口の流れは、発育不全な、短命な、急速に交替する、いわば未熟のうちに摘み取られる代々の人間から形成されているのではあるが。もちろん、経験は、他面では、歴史的に言えばやっときのう始まったばかりの資本主義的生産が、いかに急速にかつ深く人民の力を生命の根源でそこなってしまったか、産業人口の退化が、もっぱら農村から自然発生的な生命要素を絶えず吸収することによっていかに緩慢にされるか、また農村労働者さえも——自由な空気にめぐまれ、最強個体のみを繁栄させる〝自然淘汰の原理〟が彼らのあいだで実に全能の力をもって支配しているにもかかわらず——すでにいかに衰弱しはじめているか、を賢明な観察者に示している。自分を取り巻いている労働者世代の苦悩を否認する実に「十分な理由」をもつ資本は、その実際の運動において、人類の将来の退化や結局は食い止めることのできない人口の減少という予想によっては少しも左右されないのであって、それは地球が太陽に墜落するかもしれないということによっては少しも左右されないのと同じことである。どの株式思惑においても、いつかは雷が落ちるに違いないということはだれでも知っているが、自分自身が黄金の雨を受け集めてそれを安全な場所に運んだあとで、隣人の頭に雷が命中することをだれもが望むのである。〝大洪水よ、わが亡きあとに来たれ!〟これがすべての資本家およびすべての資本家国家のスローガンである。それだから、資本は、社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命にたいし、なんらの顧慮も払わない。肉体的、精神的萎縮、早死、過度労働の責め苦にかんする苦情に答えて資本は言う——われらが楽しみ(利潤)を増すがゆえに、われら、かの艱苦に悩むべきか?と。しかし、全体として見れば、このこともまた、個々の資本家の善意または悪意に依存するものではない。自由競争は、資本主義的生産の内在的な諸法則を、個々の資本家にたいして外的な強制法則として通用させるのである。
(アンダーラインは志位さんの引用部分)
不破さんの講義より
(『「資本論」全三部を読む 新版』2 p149)
「大洪水よ、わが亡きあとに来れ!」
マルクスは、ここで、有名な言葉を引用しています
「大洪水よ、わが亡きあとに来たれ!」(『資本論』②471ページ、〔Ⅰ〕285ページ)
これは、誰の言葉かというと、フランス革命前の、フランスの国王ルイ十五世の愛人ポンパドゥール夫人の言葉とされています。フランス王室の大浪費がフランス革命の原因の一つになるのですが、〝こんな賛沢三昧をやっていると財政が大破綻をきたすぞ〟と忠告されたのにたいして、〝そんなことは私の知ったことじゃないわ、大洪水(財政破綻)がくるなら、私が死んでからにしてよ〟と言ったというのです。
マルクスは、これが資本の精神だ、として、こう続けます。
「〝大洪水よ、わが亡きあとに来たれ!〟これがすべての資本家およびすべての資本家国家のスローガンである。それだから、資本は、社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命にたいし、なんらの顧慮も払わない。 ……しかし、全体として見れば、このこともまた、個々の資本家の善意または悪意に依存するものではない。自由競争は、資本主義的生産の内在的な諸法則を、個々の資本家にたいして外的な強制法則として通用させるのである」(同前〔Ⅰ〕285〜286ページ)。
ここには、 資本主義社会の現実にたいするたいへん深い分析があります。
第一は、資本は、労働者の健康と寿命にたいし、なんらの顧慮も払わずに、ひたすら労働日の非人間的延長を追求する、ということです。それは、個々の資本家が善意の人物か悪意の人物かということで決まってくる問題ではありません。 剰余価値の最大限の追求を内在的な法則とする資本主義社会では、この点で立ち後れる資本は、自由競争に負けてしまいます。だから、ここでは、剰余価値の最大限の追求が、個々の資本家の善意・悪意を越えて、外的な強制法則として、すべての資本家の意識と行動を支配するようになるのです。
第二は、では、資本主義社会は、いかなる仕組みによって、「大洪水」を防止するのか。マルクスが、「資本は、社会によって強制されるのでなければ、……」と言っていることが、重要です。労働日の無制限の延長による労働者階級の衰退という「大洪水」を避けるには、社会的強制によって、 資本の意志と行動を規制する以外にありません。これは、なによりもまず、労働者階級の要求ですが、それは同時に、資本主義社会自体を「大洪水」から防衛するための客観的要請でもあります。そして、ここに、労働日の標準化のための工場立法が、資本主義社会で可能とも必然ともなる大きな根拠があるのです。
マルクスの工場法論と現代日本
マルクスのこの文章を読む時、私の頭に連想される一つの文章があります。それは、日本の電機企業ソニーの会長だった故盛田昭夫氏が、「日本型経営」が、労働者や下請企業への抑圧や環境への無関心さなどの面で、世界の主要国の企業活動から大きく立ち遅れ、世界水準に達するためには、抜本的な改革が必要だと論じた論文のなかで、どうしたらこの改革が実現できるか、という問題について、次のように述べた文章です。
「日本の現在の企業風土では、敢えてどこか一社が改革をやろうとすれば、その会社が結果的に経営危機に追い込まれてしまうような状況が存在しています。そのためどこも積極的に動こうとしません。こうした自己防衛優先の意識が問題なのです。……いずれにしても、日本企業の経営理念の根本的な変革は、一部の企業のみの対応で解決される問題ではなく、日本の経済・社会のシステム全体を変えていくことによって、初めてその実現が可能になると思います」(盛田昭夫「『日本型経営』が危い」『文芸春秋』1992年2月号)。
一社だけで改革をやろうとすれば、競争社会では、その企業が経営危機に追い込まれる、経営の根本的改革は、「日本の経済・社会システム全体」を変えなければできない、こういう主張ですが、 「日本の経済・社会システム全体」の変革といえば、当然、法律的な規制もともなった社会的な強制が必要になってきます。〝資本は、社会によって強制されるのでなければ、労働者や下請企業や環境の利益にたいし、なんら顧慮を払わない。盛田氏のこの文章を、マルクス流に翻訳すれば、まさに『資本論』でのマルクスの命題と、同じ文章になるではありませんか。マルクスの分析は、現代の日本資本主義にも通じる法則を、みごとに解明したものだと、言ってよいでしょう
こう見てくると、資本主義の法則と工場立法についてのマルクスの分析には、現在の日本における〝ルールある経済秩序づくり〟の要求と運動にもつながる面が、見えてくるのではないでしょうか。
なお、社会的な強制という点では、マルクスは、工場法は、労働者にたいしても強制的な性格をもつことを、指摘したことがあります。クーゲルマンへの手紙の一節です。
「工場法にかんしては——これは、労働者階級が発展と運動のための余地を得るための第一条件です——私は国家の命令により、つまり強制法として、資本家にたいしてばかりか、労働者自身にたいしても出すことが必要であると考えます。(五四二ページ、注五二で私は、労働時間制限にたいする女性労働者の抵抗をヒントとしてあげておきました)」(マルクスからクーゲルマンへ 1868年3月17日 全集32四四四ページ)。
マルクスがここで援用しているのは、「第六篇 労貫」のなかの指摘で(『資本論』③963〜964ページ、〔Ⅰ〕578ページ)、賃金形態(出来高賃金など)によっては、労働者自身が「労働日を延長すること」を個人的な利益とすることがありうることを述べた文章です。こういう場合には、その部分の労働者の一時的、個人的な利益をそこなっても、法的な強制によって、労働日の規制を実現することが、労働者の肉体的な退化をふせぐ不可欠の手段となるのです。