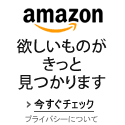今日は1日ノアさんの依頼作品。そんな中、大家さんが今日は誰もいないの?って話で、アトリエに来てこの作品を作っているのを見て、どうしてあっちこっち張ってあるの?って聞かれたのね。それってちゃんと答えて良いのかな?真面目に話すと伝わらないと、何言っているんだかチンプンカンプンだろうし
正直、理解はして貰えなくても、せめてそうなんだ・・位の気持ちで聞いて貰えるのなら、きちんと話すけれど・・・って言うと、どうやら興味を持って聞いてくれるらしく、それなら・・・と、普通は本棚の整理みたいに、1巻、2巻・・・みたいな順番だったり、大きい順、小さい順とか、右からみたいに
順番ってものでスタートしたりする。そうする事で能率効率を良くするって気がするのね。これが幾何学模様のテーブルだったりすれば、外側から中心に向かって順番に・・・ってそのやり方で作るのね。けれど、こんな絵の場合、難易度がこことここでは違ったりするのね。例えば丸を切る・・・。
そんな場合は、同じ形に何枚切る?って話で、狙って切る、同じ大きさに合わせて切る・・・そう言うのは、蕎麦の太さで、うどんの太さで、きしめんの太さで・・・とそれに応じた太さの統一感をキープしないとならず、ただ切れば良いって言うのとは違うのね。つまり切るって言うのは必然なのね。
それが出来ると、今度は王冠のような丸になると、段々小さくとか、段々大きくなんて、段々・・・って難易度が加わって来る。いかに滑らかに少しずつずらして行くか?ってね。ただこれは点で構成される技術であって、基礎になるもの。同じ事を繰り返す事から変化を加えるって話だから。
例えば音楽ならAからA´になった位の話。その切るとは全く逆になるものが割る。これは必然では無く偶然であり、こうしないとならないでは無く、こうなっちゃった・・・これでも良いかな?そんな感じであって、体験の人達にはこれが向いているのね。それを言葉で表現するとクラッシュって言う形。
どんな形でも、何もルールらしきものが無い。ただあるとしたら、四角や丸と言った形に名称があるようなものを入れると、そこだけが目立ってしまうって言う位で、比較的初心者には向いている仕上げ方になる。ここまでは点の説明。これとは逆にある線での仕上げとなると、点では1パーツ単体で良いが、
線は髪の毛みたいに上から下まで10パーツみたいなものが1セットで1つなんで、単体1つのパーツの点とでは、難易度は全く違って来る。しかも、点でも段々大きく、小さくがあるように、髪の毛を段々細く・・・なんてやれば、1.2.3.4...としたいのに、1.2.5.4...となっては太くなったり細くなったり。
これでは全然段々には見えない。つまりこの絵の中に非常に難しい場所と比較的簡単な場所があるって事。その時にもし順番にやって行ったとしたら?調子の良い時と調子の悪い時が人にはあったりして、それなのに、無理やり難しい所が順番だから・・・と進んだり、逆に調子が良いのに簡単な所を進めても
その日は凄く進んでも、いきなり難しい場所の日は全く進まないなんて事になったりする。こんな事が理由の1つだったりするし、またほかの見方で言うのなら、これが将棋や囲碁の基盤だとするのなら、1か所をどんどんと進めても他の展開が読み切れない。要するに、あぁここは何とかなるって部分は、
調子が悪い時に取って置く場所なんて思ったり、今度は色なんて事に置き換えて考えるのなら、あぁ色鉛筆で塗っていた色がタイルだとこんなに強調されたのかぁ・・・じゃ他の場所は何に置き換えるんだろう?と下絵で塗った色をタイルに変換して行くのに、あっちこっちの色合わせをして見たいって事。
こんなのも理由の1つ。常に物の考え方にはこんな事が付いて来るもので、タイル屋さんの時はタイル屋さんの目線だけだったが、これが建築士になると、どの分野にいくらの値段を掛けるか?まで考えないとならないだろうし、色々と考える事は増えると思うのね。
こんな話をすると、細かいパーツだけでも無理だわっ・・・って思うのに、面倒な話だねぇ・・・って。いや、ただ俺も教わった訳じゃないんで、そうかな?・・・と思ってやっているだけなんだけれどね・・・なんて話で終わったんだけれど。まっ今日も少し進んだのね。
正直、理解はして貰えなくても、せめてそうなんだ・・位の気持ちで聞いて貰えるのなら、きちんと話すけれど・・・って言うと、どうやら興味を持って聞いてくれるらしく、それなら・・・と、普通は本棚の整理みたいに、1巻、2巻・・・みたいな順番だったり、大きい順、小さい順とか、右からみたいに
順番ってものでスタートしたりする。そうする事で能率効率を良くするって気がするのね。これが幾何学模様のテーブルだったりすれば、外側から中心に向かって順番に・・・ってそのやり方で作るのね。けれど、こんな絵の場合、難易度がこことここでは違ったりするのね。例えば丸を切る・・・。
そんな場合は、同じ形に何枚切る?って話で、狙って切る、同じ大きさに合わせて切る・・・そう言うのは、蕎麦の太さで、うどんの太さで、きしめんの太さで・・・とそれに応じた太さの統一感をキープしないとならず、ただ切れば良いって言うのとは違うのね。つまり切るって言うのは必然なのね。
それが出来ると、今度は王冠のような丸になると、段々小さくとか、段々大きくなんて、段々・・・って難易度が加わって来る。いかに滑らかに少しずつずらして行くか?ってね。ただこれは点で構成される技術であって、基礎になるもの。同じ事を繰り返す事から変化を加えるって話だから。
例えば音楽ならAからA´になった位の話。その切るとは全く逆になるものが割る。これは必然では無く偶然であり、こうしないとならないでは無く、こうなっちゃった・・・これでも良いかな?そんな感じであって、体験の人達にはこれが向いているのね。それを言葉で表現するとクラッシュって言う形。
どんな形でも、何もルールらしきものが無い。ただあるとしたら、四角や丸と言った形に名称があるようなものを入れると、そこだけが目立ってしまうって言う位で、比較的初心者には向いている仕上げ方になる。ここまでは点の説明。これとは逆にある線での仕上げとなると、点では1パーツ単体で良いが、
線は髪の毛みたいに上から下まで10パーツみたいなものが1セットで1つなんで、単体1つのパーツの点とでは、難易度は全く違って来る。しかも、点でも段々大きく、小さくがあるように、髪の毛を段々細く・・・なんてやれば、1.2.3.4...としたいのに、1.2.5.4...となっては太くなったり細くなったり。
これでは全然段々には見えない。つまりこの絵の中に非常に難しい場所と比較的簡単な場所があるって事。その時にもし順番にやって行ったとしたら?調子の良い時と調子の悪い時が人にはあったりして、それなのに、無理やり難しい所が順番だから・・・と進んだり、逆に調子が良いのに簡単な所を進めても
その日は凄く進んでも、いきなり難しい場所の日は全く進まないなんて事になったりする。こんな事が理由の1つだったりするし、またほかの見方で言うのなら、これが将棋や囲碁の基盤だとするのなら、1か所をどんどんと進めても他の展開が読み切れない。要するに、あぁここは何とかなるって部分は、
調子が悪い時に取って置く場所なんて思ったり、今度は色なんて事に置き換えて考えるのなら、あぁ色鉛筆で塗っていた色がタイルだとこんなに強調されたのかぁ・・・じゃ他の場所は何に置き換えるんだろう?と下絵で塗った色をタイルに変換して行くのに、あっちこっちの色合わせをして見たいって事。
こんなのも理由の1つ。常に物の考え方にはこんな事が付いて来るもので、タイル屋さんの時はタイル屋さんの目線だけだったが、これが建築士になると、どの分野にいくらの値段を掛けるか?まで考えないとならないだろうし、色々と考える事は増えると思うのね。
こんな話をすると、細かいパーツだけでも無理だわっ・・・って思うのに、面倒な話だねぇ・・・って。いや、ただ俺も教わった訳じゃないんで、そうかな?・・・と思ってやっているだけなんだけれどね・・・なんて話で終わったんだけれど。まっ今日も少し進んだのね。