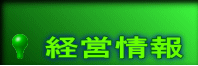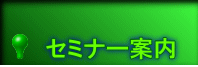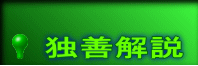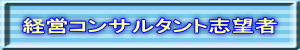■■【経済の読み方】 2013年 11月を時系列的に見る
世の中の動向は、アラカルト的に見ることも大切ですが、時系列的に見ると、また異なった面が見えてきます。
ここでは、これまでブログ掲載してきました内容をコンパクトにまとめてご紹介します。
■ 日本の貿易赤字はどのくらいかご存知? 2013/11/29
私が子供の頃は、日本は資源が乏しいけど、豊富な労働力があるから、海外から資源を輸入して、それを加工して輸出するという「加工貿易」が望ましいと社会科の時間に学びました。
1970年に私はアメリカ駐在を命じられ、ニューヨークを拠点に全米を飛び回りました。いわゆる「企業戦士」で、「安かろう、悪かろう」とさげすまされながら、日本製品を海外に輸出をする先駈けをしてきました。
やがて日本製品の優秀さが認められますと、為替レートが1ドル360円が208円に切り上げられ、それが為替レートの自由化でドンドンと円高に向かいました。当時から比べるとドルの価値は三分の一以下に減ってしまったと言うことです。
それでもリーマンショックまでは、日本製品は海外に溢れるとまで言われるほど、輸出や海外進出でもてはやされ、貿易黒字は拡大するばかりでした。
ところが、今や日本は12兆円の貿易赤字国となってしまいました。
福島第一原発以来、原油や天然ガスの輸入額の増加、それに追い打ちを掛けるように円安となり、2年連続で過去最大の赤字を更新するにまで至っています。
日本貿易会(JETRO)によりますと、2013年度の日本の輸出額は、円安が進んだため自動車や関連部品のほか、情報通信機器向けの半導体の輸出などが増え、前年度比で9.8%増える見通しです。
一方、輸入額はそれを凌駕し、発電などに使う原油や天然ガスの輸入が円安の影響で拡大していることや、スマートフォンの輸入増加などで、前の年度に比べて14.1%増える見透しです。
このため輸出から輸入を差し引いた貿易収支は12兆円の赤字になる計算です。
円安傾向と世界経済の回復で今後は輸出の増加が続くと見られます。しかし日本企業の海外生産へのシフトは停まらず、円安でも予想通りには輸出は増えず、今後も貿易収支の赤字は続くと考えます。
■ 技術のゆくえ 2013/11/27
NHKのクローズアップ現代という長寿番組は、キャスターの国谷裕子氏のお人柄にもよりますが、テーマの採り上げ方がすばらしい。
11月26日は、「ウェアラブル革命 ~“着るコンピューター”が働き方を変える~」というテーマでした。
メガネ型端末や通信機能が付いた腕時計という、SFぽい電子機器で、身につけることができるという意味で「ウェアラブル・コンピューター」と言います。2016年には1億台以上が普及すると予測されていると言いますので、時代の変化の早さを感じますね。
これらの機械は日常生活を便利にするだけではなく、私たちの働き方を根本から変える言われています。メガネ型端末をベテラン看護師に付けさせ、それを利用して派遣社員でもできるようになるというのですから驚きです。
社員証型の端末で社員の動きや会話をくまなく収集し、業務改善に使うという利用法も紹介されました。
一方で、スマホを身ながらの自転車や自動車運転も問題視されていますが、利用者のモラルの高揚が一層強く求められますね。
■ TPPは年内妥結ができるのか 2013/11/26
アメリカのソルトレークシティーでTPP(環太平洋パートナーシップ協定)の首席交渉官会合が開催されました。
「政府調達」の分野で、新興国などの公共事業に対して外国企業の参入条件を緩和する方針が確認されました。
しかし、関税撤廃や知的財産保護などの重要分野における交渉は難航しています。
とりわけ関税撤廃の分野では、難航しています。
参加各国が日本に対して、すべての貿易品目を関税撤廃の対象とするよう求めています。一方、日本は、コメや麦などの重要5項目を関税撤廃の例外とするよう主張を崩していません。
年内妥結を目指して12月にシンガポールで閣僚会合が開催され、その場で政治決断が委ねられることになりました。
多くの課題が結着されてきましたので、残された課題が少なくなったと言えます。しかし、日本としては譲れない問題が残されています。ただ、各国ともアメリカの強引な動きから、年内妥結の意識は高まっています。
最後に日本が押し切られるのかどうか、予断は許されません。
■ 外国人旅行者を日本に呼び込む 2013/11/23
2013年10月までに日本を訪れた外国人旅行社は866万人と、日本政府観光局から発表されました。「年間1000万人」という目標を立てていましたが、これが射程距離内に入ってきたと言えます。
多い月には100万人を超えていますので、余す2か月で140万人は楽勝とも言えます。
前年比の伸び率を国別に見ますとタイ、ベトナム、インドネシアの伸び率が35~64%と延びています。その背景には、訪日ビザの発給要件緩和の効果が大きいとみられます。これを後押ししているのが、円安とLCCの就航があげられます。
日銀の「最近の訪日外国人増加の背景と、わが国経済への影響」というレポートによりますと、経済効果として、金額にして3兆円といいます。これによる雇用者数は20万人だそうです。
これは、大きな効果と言えますが、なかなか実感できないのは私だけでしょうか。
さらに外国人を日本に呼ぶのは、観光案内や食文化の紹介などクールジャパン政策の推進だと言われています。
私は、自分で国内出張したときに感ずるのは、無線LANの利用環境です。いまだにホテルでLANを利用するのに利用料金を請求されます。それも先日名前の通っているホテルチェーンで、24時間で1,500円ほどとられました。
一方、福岡市のように、ビジネスパーソン訪問者が多い都市では、ちょっとしたところで無線LANを無料で利用できます。欧米では、無料の無線LANサービスがあたり前のような時代に、あまりにも日本のネット利用環境は貧弱すぎます。
この辺が改善されませんと、東京オリンピックが開催されるとは言え、2020年までに2000万人という目標は厳しいでしょう。
■ 最新の日銀景気判断は? 2013/11/21
日銀の金融政策決定会合は、国内の景気判断をこれまでと同じで「緩やかに回復している」という表現を据え置来ました。また、今年4月に導入しました大規模な金融緩和策はそのまま継続すると発表しました。
総理大臣官邸で開かれた経済財政諮問会議を受けて、安倍総理大臣は、「今後の人口減少や厳しい財政状況を踏まえれば、公共事業費も一層重点化と効率化を図っていかなければならない」と述べ、関係閣僚に対し、指示を出しました。
■ ユニクロは大丈夫か? 2013/11/18
NHKスペシャルの「成長か、死か ~ユニクロ 40億人市場への賭け~」という番組をご覧になった方も多いでしょう。
企業理念として「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」ということを地で行っている気がします。
◆1 ユニクロの急成長
今年、初めて売上高1兆円という大台を超えた、衣料品チェーン「ユニクロ」を展開しているファーストリテイリングです。海外を含め、年間150店舗という驚異的なペースで海外大量出店を原動力として、年々売り上げを伸ばしています。
しかし、それでも世界4位という、柳井社長としては満足できない地位にいます。ZARA(スペイン)やH&M(スウェーデン)を追いつけ、追い越せと「2020年に世界4,000店舗、売上高5兆円」という目標を掲げています。
そのユニクロが、ライバルが及び腰でいるBOPビジネス(最貧国市場)に2013年7月に、バングラデシュで着手しました。上位を狙うための差異化(差別化)戦略として、ある意味では掛けと言えます。
衣料品という、差異化(差別化)が難しい商品で、これだけの急成長を遂げているユニクロに敬意を表する人も多く、私もその一人です。
◆2 BOPビジネス展開に対する評価
衣料品という、差異化(差別化)が難しい商品で、これだけの急成長を遂げているユニクロに敬意を表する人も多く、私もその一人です。
しかし、BOPビジネスとユニクロが展開している先進国や新興国とでは、現状では経営手法が異なります。
例えば、ブランド戦略です。「ユニクロ」のブランドを、そのままバングラデシュで使っています。もし、バングラデシュで成功したとしますと、先進国や新興国では、「ユニクロ製品は、価格の割には品質が良い」というイメージを壊しかねません。
ファーストリテイリングでは、完全子会社傘下に、「ユニクロ」というブランドとともに「GU」などのブランドも持っています。私は、BOPビジネスと戦略を変え、ここではGUなり、他のブランドを使うべきではないかと考えます。
バングラデシュへの進出にGUの展開で成功を収めた人を、そこのトップに据えたのですから、それを活かすべきではないかと考えます。
バングラデシュは、イスラム教徒国であり、その特質をキチンと掴んだ商品戦略ができていませんでした。
事前にマーケティング調査をしていますが、一人の女性に任せっきりという、マーケティング調査でありがちな過ちをしています。どんなに優秀な人であっても、一人の人間のものの見方は、時として独善に陥りやすいです。複数のマーケティング担当による、事前調査が必要でした。
◆3 BOPビジネスに成功するには
バングラデシュは、イスラム教徒国であり、その特質をキチンと掴んだ商品戦略ができていませんでした。
調査の仕方も、これまでの成功体験に基づいたのでしょうが、相手のホンネをくみ取れないでいたために、間違えた判断に至ってしまいました。
バングラデシュの留学生上がりの人をサブとして付けるなどすることにより、彼女の判断ミスを事前に察知できたのではないでしょうか。
バングラデシュで30店舗の出店をするということで、少々、事前準備期間が身近すぎて、現地スタッフ教育の不充分だったのではないでしょうか。
最初の出店がフラッグシップ店としての位置づけとしてふさわしいのかどうかが確認できないうちに、高級住宅街に二番目の店舗を出店し、ここではコンセプトづくりが不充分なのか、商品コンセプトに誤りがあったのか、立ち上げに失敗したと言えます。
現地ライバルの方が、戦略的に天下のファーストリテイリングより上をいっているようでは、柳井会長・社長の名前が泣いてしまいます。BOPという新しい試みという勇気に拍手を送りますが、現地企業の買収などによる参入など、孫正義流の手法をここでとっても良かったのではないかと考えます。
ファーストリテイリングのますますの発展を期待します。
■ 日韓問題の早期解決 2013/11/07
韓国のパク大統領が、ヨーロッパ遊説で、日本の歴史認識に対して厳しい発言を繰り返しています。
韓国政府が、日本攻撃を止めないために、韓国内も日本をターゲットとした訴訟が頻発しています。
その一つが、戦時中に日本に徴用された韓国人労働者です。日本企業を訴えている韓国の裁判で、損害賠償の支払いを命じる判決が相次いでいます。
ご存知の通り、「日韓の経済関係は1965年に結ばれた日韓請求権協定で個人の請求権の問題が完全に解決されたことを前提に築かれている」という現代史を、韓国側の歴史認識問題があることを無視していることが問題の一つです。
一方で、日本は、近代史について、事実を明確にし、勧告にキチンと説明すべきことを説明し、謝罪するところがあるのであるなら、キチンと謝罪すべきではないでしょうか。
問題が長引けば今後の日韓のビジネスや韓国への投資にとって大きな障害となり、良好な経済関係が損なわれかねません。
日本政府は、勧告の最近の状況を無視して、中国問題解決を優先させようとしています。
では、その間、放置していて良いのでしょうか。
学生や民間企業が、この状況を憂い、政治とは切り離して対話を始めているというニュースも入っています。しかし、まだまだ充分とはいえません。政府が対応しないのであれば、民間ベースでの交流をさらに推進すべきと考えます。
■ 東京電力は本当に大丈夫なのか 2013/11/02
東京電力福島第一原子力発電所事故以前は、超優良株としてもてはやされた東電株ですが、事故以後の対応を見ていますと、何とも心許なく思っている人が多いのではないでしょうか。
トップが良くないのか、現場力が弱いのかわかりませんが、学歴の高い人達の多い東電がなぜこのようなお粗末なのか、理解に苦しむのは私だけではないでしょう。
何処に原因があるのか、追求するのがあたり前と思いますが、お座なりな結論付けをしているために、その解決策も効果なく、実行策もいい加減であるとみられても仕方がないですね。
先般、岸元首相や佐藤元首相が、日本の将来を考えて、アメリカ占領軍・進駐軍に対して、日本におけます占領政策・進駐政策に提言をしようしていたことが報道されました。
私は、彼らが本当に体を張って、首相としての仕事をしてきたのか、実は疑問に思って来ました。しかし、現代史を紐解くにつれ、見方が変わってきました。佐藤元首相が、ノーベル平和賞受賞にふさわしいのかどうかはわかりませんが、オバマ大統領よりは受賞に近いような気もします。
そのような中で、始めは頼りなく思っていた安倍首相も、ひょっとすると、大物政治家なのかもしれないという側面もチラッと垣間見て、私の認識の一部が変わりつつあるように思えます。(私は、自民党支持をしているわけではなく、客観的に見るように努力をしています)
福島原発事故に対して、安倍首相がどのような采配を振るのか、関心を持っていました。これまでのところ、まだ合格点には達していません。
最近の動向の中で、ちょっと関心を持ち始めたのは、自民党の東日本大震災復興加速化本部の提言です。
事故からの復旧や復興を加速させるための復興加速化本部の提言を受けて、経済産業省が動き始めました。廃炉作業を着実に進めるため、東京電力を持ち株会社に移行して、傘下に廃炉を担う専門組織を設ける方向で調整に入ったといいます。
東京電力の廃炉事業を東電本体で行うのではなく、分社化により、廃炉専門の事業会社を設立するという内容です。
現状では、そのホンネは、東電救済にあるのかもしれません。
廃炉専門の事業会社により、廃炉作業に当たる専門家や従業員を確保しやすくなるでしょう。東電本体は、火力発電や送電、原子力事業などの各部門をグループ全体で経営することで業務の効率化やコスト削減を徹底できるようになるでしょう。
政府には、目先の問題だけではなく、さらに中長期的に考えるべきです。その一つは、東電の課長以上、少なくても部長以上の首をすげ替えるくらいの、大なたを振るって欲しいです。非現実なことのように聞こえるかもしれませんが、そのくらいの思い切った施策が必要と考えます。
単に、専門会社を作るだけでは、名称が変わるだけで、中身は何ら変わらないのです。分社化ではなく、新規に廃炉の専門家集団を作ることにより、今後の日本だけではなく全世界の廃炉事業への布石となるようにすべきではないのでしょうか。![]() 毎日複数本発信
毎日複数本発信 ![]()