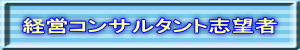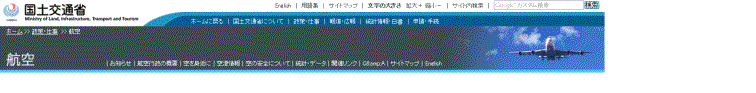■■【経営コンサルタントの独り言】 日本の食糧自給率はなぜ低いのか?
NHKの合瀬宏毅解説委員の「なぜ上がらない?食糧自給率」というテーマでの意見を拝聴しました。ご覧になった方も多いと思いますが、その概要を紹介し、私の拙いコメントを付けさせていただきます。
◆1 自給率の低い日本の現状
1965年に73%あった食糧自給率、一貫して下がり続けて、2013年度の食糧自給率は、4年連続で39%だったと報じられました。農林水産省は、食糧自給率として50%を目標にして、様々な政策を打ってきましたが、アメリカやドイツ、フランスは軒並み100%か、それ以上の自給率でありますし、オーストラリアはなんと200%を超えていると言われています。
そうした国々は農家1戸あたりの耕作面積が、日本の数十倍と広く、アメリカで日本の130倍、オーストラリアは1900倍もあります。このような国々とでは、コスト的に合わないのは自明のことのように思えます。しかも、TPPなどが締結されますと、日本の自給率は益々低下する恐れがありますことも指摘されているのです。
◆2 なぜ自給率が下がったのか
合瀬解説員は、消費者の食生活がコメ中心の食事から、肉や小麦主体の洋食へと変化していく中で、生産者が需要の変化に適応できず、消費者が求めるものを供給できなかったことが、自給率を下げた大きな原因だと説明していました。
政府は2000年以降、5年ごとに基本計画を作り、現在は50%を目標にして、莫大な予算をかけて自給率向上を目指してきましたにもかかわらず、今年はこうした数字になってしまったのでしょうか?
農水省によりますと「国内で消費された食料全体の20%余りを占めるコメが、消費税率引き上げ前の駆け込み需要などで増えた一方、大豆は台風や干ばつなどの全国的な天候不順で、全国各地の産地が生産量を減らしてしまった。さらに小麦も全国の7割を作る北海道で、去年並の生産を上げることが出来ませんでした。」ということがその理由であるようです。
◆3 食糧自給率の算出法
では、食糧自給率というのは、どの様に算出されているのでしょうか。
自給率算定の基準は、私たちの身体を支える熱量をカロリーベースで計算しています。そのカロリーベースの食糧自給率であります国内生産に、食料輸入額を加えた金額と国内で供給できたカロリーとの比率です。
換言しますと、食糧自給率は、消費者が自分が食べるもののうち、どれだけ国産品を選んだかを示す数値とも言えます。一方、農家は、農産物が売れませんと経営が成り立ちません。そのまま放置しておきますと、農家がなくなってしまい、消費者が困ることになります。
食糧が不足するのであれば、輸入すれば良いという声もあります。順調に事が運べば、それで食料をまかなうことができるでしょう。しかし、世の中は、期待通りことが進むときばかりではありませんで、ハプニングがつきものです。例えば、鶏肉加工の使用期限切れや衛生観念のなさが問題になりました。このことだけでも鶏肉価格が高騰しましたし、場合によりますと品薄ということになりかねません。
干ばつで小麦や大豆が高騰するなど、記憶にまだ新しいです。これらのことで世界的な食糧不足に陥るってしまうことも否定はできません。
◆4 狭い日本で、大幅な自給率改善は可能なのか
食料の国際価格高騰に加え、最近は円高で輸入食品の価格は軒並み上がっています。しかも温暖化の影響もあって、天候不順による食糧の供給は不安定さを増すばかりです。こうした中で多くの消費者が食糧の安定供給に不安を持っています。
自給率の算出法が「カロリーベース」であることに問題があることを報道せず、「食糧自給率が低い」という部分だけを強調して、不安感を煽るだけのマスコミの報道にも問題があります。
カロリーを押さえるダイエットがあたり前のような時代になっているにもかかわらず、カロリーベースでの自給率算定法そのものが時代に即していないのです。一説によりますと、金額ベースで算定すると食糧自給率は60%を超えるといわれています。
もちろん、この自給率では国民は生きて行けませんし、この事実で日本の自給率の問題が解消するわけではありません。
日本の自給率が低いのは、需要の減っているコメを作りすぎることが主因の一つであり、TPPの締結も目前となっている昨今、米中心の農業という発想からまず脱しなければならないと考えます。
輸入に頼り切っています小麦粉を、米粉で代用するための国の施策やそれに基づく国民の意識改革など、現状におきましてもやれる方策があるのですから、「やっています」という形式だけではなく、推進してゆくべきです。
農業法人による営農や野菜工場などという、先進的な大規模あるいは大資本農業の動きも出てきていますように、品種開発や機械化など、まだ不十分な面にも力を入れるなど農業のやり方の工夫と多様化が必要です。農業経営のあり方が変われば、就職先に困っている高齢者の受け皿も広がるでしょう。
主食用のコメの生産を押さえ、輸入に依存する小麦や大豆、さらに小麦代替のコメ粉や、家畜用のエサ米などを作って、自給率を伸ばそうという動きがありますが、これをさらにお進めてゆく必要があります。根本的な解決ではないですが、自給率算定方式を変える意思がないのであれば、コメや小麦、大豆といったカロリーが高い食品が今より多く清算されるようになれば、自給率は自ずと改善されます。
困難な問題はあるでしょうが、国民がその気になれば、自給率改善は可能です。日本全体が一丸となって、この問題に本腰を入れてゆきませんと、TPPで日本農業は大打撃を受ける可能性を否定できないのです。
 【【経営トップ15訓】】 ←クリック
【【経営トップ15訓】】 ←クリック
経営者・管理職としての心得を経営コンサルタントの視点からおこがましくも述べさせていただいてます。