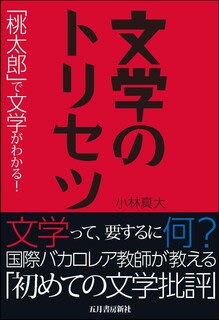場所:水軒沖
条件:大潮 6:46満潮
釣果:タチウオ19匹
今日は午後から雨らしい。おとといも釣りに行っているので今日はおとなしく朝一タチウオだけを釣って帰ってこようと思っている。数を釣りたければ大きいほうの船で行けばいいのだが、ローテーションを考えると小船になる。どっちでもいいのだが、今日はどっちに乗って行こうなどと悩めるのはなんとも贅沢な悩みだ。(どっちもボロボロの船ではあるが・・・)
しかし、朝起きて、加太のリアルタイムの風を見てみると、南からの風が12メートルも吹いている。急いで表に出てみたが、やはりこっちもかなり吹いている。普通ならこのまま布団に逆戻りなのだが、ダメ元で港まで行って船を出せなければ、「わかやま〇しぇ」で冷凍のコロッケを買って帰ろうととりあえず家を出た。
港についてみると、こんな日でも渡船客はたくさん来ている。三密を避けられるからというわけではないだろうが、去年くらいからここは大盛況だ。後半に書くつもりだが、最近はマナーの悪い人も多くて辟易するときがある。
船頭の奥さんと話をしていると、新々波止の北側なら問題なさそうよということだったのでとりあえず出港を決めた。この風では大きいほうの船は着岸のときにトラブルを起こしそうなので小船を使うことにした。
今日も雲が多く、出港時は真っ暗なのは当然だが、午前5時に近くなっても一向に明るくなってこない。


青岸を越えると風が心配なので様子を見ながらかなり手前から仕掛けを流し始める。アタリはまったくない。安全を確かめながら少しずつ沖へ。やっとアタリが出たのは南海フェリーが入港してのちのことだった。午前5時を少し過ぎたころだ。ダイヤだと午前5時10分到着だそうなのでフェリーのダイヤも正確なものだ。
アタリが出始めるとどんどんアタる。しかし、狭いデッキの上では仕掛けのさばきに手間取り、それに加えてタチウオランチャーを持ってくるのを忘れたので余計に手間取る。小船のエンジンは相変わらず不機嫌で、アイドリング状態ではしょっちゅう止まり、風が強くて魚を回収している間に船はどんどん流される。青岸の灯台が目の前に迫ってきたときはドキドキしてしまった。
そんな中でもなんとか釣りを続け、午前5時半を過ぎた頃にアタリがなくなり終了。
今日の魚の型は前回よりも少しはましであった。放流したのは3匹ほどではなかっただろうか。
今年のタチウオは型は小さいけれども、数は多そうだ。このまま魚が成長すれば月末くらいには大きいタチウオがたくさん釣れると思うのだが・・・。
僕は、電気ウキを拾った日は魚が釣れないというジンクスを持っているけれども、それも過去のものになりそうだ。今日は3個も拾った。

よく考えれば、タチウオが多いから陸っぱりの釣り人が糸を切られて電気ウキが漂流する確率が高くなり僕がウキを拾う数が増えるのであって、そういう時は魚もたくさん釣れるはずだから僕のジンクスは実は最初から矛盾していたのだ。
どちらにしてもジンクスは少ないほどよい。だからこのジンクスは過去のものになったと思っておこう。
雨は予想以上に早く降り出し、家に帰って魚をさばいているときから降り出した。大きいほうの船に燃料を補給しておかねばならないので雨を承知で港に舞い戻ったのだが、そこでいやなものを見てしまった。
これは間違いなく渡船の客の仕業だろう、駐車場でウ〇コをしているやつがいたのだ。

おとといは気が付かなかったが、おそらく土、日でやらかしたのだろう。渡船屋にもトイレはあるが、感染防止で使用禁止にしている。常連ならトイレがないのを知っているから途中で済ませてくるのだろから、遠くからやってきてトイレが閉まっているのに気付いた一見客がここでやってしまったのだろう。これで2回目だ。しかし、よく人目もはばからずやれるものだ。まあ、背に腹は代えられないところもあるのだろうけれども・・。
車を置くのもひどいもので、護岸ギリギリに駐車するやつがいる。船に乗り込もうにもそんな状態で船の前に停められると乗り降りができないのだ。
2年ほど前まではいつも閑散としていて平和なものであったが、人が多くなるといろんなトラブルが起こるというのはどこでも同じなのだろう。
叔父さんの家に寄ると、隣の家からたくさんのハバネロが届いていた。元々、ここから苗をもらって叔父さんの畑に植えてもらっているので、僕的にはその苗から採れる量で十分なのだが、どれだけの苗を植えているのか知らないが大量のハバネロだ。隣のおじさんは植えているだけで活用していないのではないだろうか。じゃあ、どうしてハバネロを植えているのだろうか・・。それはそれでもったいない。
もう、十分ですというのもなんだから、全部もらってきて贅沢にいいものだけを選んで干してみた。ハバネロは身が厚いのでまるのまま干すとすぐに腐ってしまうことは前回の収穫でわかっていた。しかし、激辛の割にはか弱い実なのである。なので、輪切りにして干すといいらしい。

かなりの量ができてしまったが、これからあれをどうやって使おうか・・・。少し悩んでしまうのである。
ハバネロとはなかなか手ごわい相手で、ビニールの手袋をはめて作業をしているのだが、どこかから漏れてくるらしく、タチウオを釣った時にできたわずかな傷からカプサイシンが染み込み、相当な痛みが出る。顔のどこかに触れるとそこも痛くなる。
遺伝子工学は相当高レベルのところまで来ているのだから、いっそ、コロナウイルスにカプサイシンを作り出す遺伝子を挿入してやったらPCR検査なんてしなくても体に取りつかれたらすぐにわかるのではないかと思ったりするのである。
条件:大潮 6:46満潮
釣果:タチウオ19匹
今日は午後から雨らしい。おとといも釣りに行っているので今日はおとなしく朝一タチウオだけを釣って帰ってこようと思っている。数を釣りたければ大きいほうの船で行けばいいのだが、ローテーションを考えると小船になる。どっちでもいいのだが、今日はどっちに乗って行こうなどと悩めるのはなんとも贅沢な悩みだ。(どっちもボロボロの船ではあるが・・・)
しかし、朝起きて、加太のリアルタイムの風を見てみると、南からの風が12メートルも吹いている。急いで表に出てみたが、やはりこっちもかなり吹いている。普通ならこのまま布団に逆戻りなのだが、ダメ元で港まで行って船を出せなければ、「わかやま〇しぇ」で冷凍のコロッケを買って帰ろうととりあえず家を出た。
港についてみると、こんな日でも渡船客はたくさん来ている。三密を避けられるからというわけではないだろうが、去年くらいからここは大盛況だ。後半に書くつもりだが、最近はマナーの悪い人も多くて辟易するときがある。
船頭の奥さんと話をしていると、新々波止の北側なら問題なさそうよということだったのでとりあえず出港を決めた。この風では大きいほうの船は着岸のときにトラブルを起こしそうなので小船を使うことにした。
今日も雲が多く、出港時は真っ暗なのは当然だが、午前5時に近くなっても一向に明るくなってこない。


青岸を越えると風が心配なので様子を見ながらかなり手前から仕掛けを流し始める。アタリはまったくない。安全を確かめながら少しずつ沖へ。やっとアタリが出たのは南海フェリーが入港してのちのことだった。午前5時を少し過ぎたころだ。ダイヤだと午前5時10分到着だそうなのでフェリーのダイヤも正確なものだ。
アタリが出始めるとどんどんアタる。しかし、狭いデッキの上では仕掛けのさばきに手間取り、それに加えてタチウオランチャーを持ってくるのを忘れたので余計に手間取る。小船のエンジンは相変わらず不機嫌で、アイドリング状態ではしょっちゅう止まり、風が強くて魚を回収している間に船はどんどん流される。青岸の灯台が目の前に迫ってきたときはドキドキしてしまった。
そんな中でもなんとか釣りを続け、午前5時半を過ぎた頃にアタリがなくなり終了。
今日の魚の型は前回よりも少しはましであった。放流したのは3匹ほどではなかっただろうか。
今年のタチウオは型は小さいけれども、数は多そうだ。このまま魚が成長すれば月末くらいには大きいタチウオがたくさん釣れると思うのだが・・・。
僕は、電気ウキを拾った日は魚が釣れないというジンクスを持っているけれども、それも過去のものになりそうだ。今日は3個も拾った。

よく考えれば、タチウオが多いから陸っぱりの釣り人が糸を切られて電気ウキが漂流する確率が高くなり僕がウキを拾う数が増えるのであって、そういう時は魚もたくさん釣れるはずだから僕のジンクスは実は最初から矛盾していたのだ。
どちらにしてもジンクスは少ないほどよい。だからこのジンクスは過去のものになったと思っておこう。
雨は予想以上に早く降り出し、家に帰って魚をさばいているときから降り出した。大きいほうの船に燃料を補給しておかねばならないので雨を承知で港に舞い戻ったのだが、そこでいやなものを見てしまった。
これは間違いなく渡船の客の仕業だろう、駐車場でウ〇コをしているやつがいたのだ。

おとといは気が付かなかったが、おそらく土、日でやらかしたのだろう。渡船屋にもトイレはあるが、感染防止で使用禁止にしている。常連ならトイレがないのを知っているから途中で済ませてくるのだろから、遠くからやってきてトイレが閉まっているのに気付いた一見客がここでやってしまったのだろう。これで2回目だ。しかし、よく人目もはばからずやれるものだ。まあ、背に腹は代えられないところもあるのだろうけれども・・。
車を置くのもひどいもので、護岸ギリギリに駐車するやつがいる。船に乗り込もうにもそんな状態で船の前に停められると乗り降りができないのだ。
2年ほど前まではいつも閑散としていて平和なものであったが、人が多くなるといろんなトラブルが起こるというのはどこでも同じなのだろう。
叔父さんの家に寄ると、隣の家からたくさんのハバネロが届いていた。元々、ここから苗をもらって叔父さんの畑に植えてもらっているので、僕的にはその苗から採れる量で十分なのだが、どれだけの苗を植えているのか知らないが大量のハバネロだ。隣のおじさんは植えているだけで活用していないのではないだろうか。じゃあ、どうしてハバネロを植えているのだろうか・・。それはそれでもったいない。
もう、十分ですというのもなんだから、全部もらってきて贅沢にいいものだけを選んで干してみた。ハバネロは身が厚いのでまるのまま干すとすぐに腐ってしまうことは前回の収穫でわかっていた。しかし、激辛の割にはか弱い実なのである。なので、輪切りにして干すといいらしい。

かなりの量ができてしまったが、これからあれをどうやって使おうか・・・。少し悩んでしまうのである。
ハバネロとはなかなか手ごわい相手で、ビニールの手袋をはめて作業をしているのだが、どこかから漏れてくるらしく、タチウオを釣った時にできたわずかな傷からカプサイシンが染み込み、相当な痛みが出る。顔のどこかに触れるとそこも痛くなる。
遺伝子工学は相当高レベルのところまで来ているのだから、いっそ、コロナウイルスにカプサイシンを作り出す遺伝子を挿入してやったらPCR検査なんてしなくても体に取りつかれたらすぐにわかるのではないかと思ったりするのである。