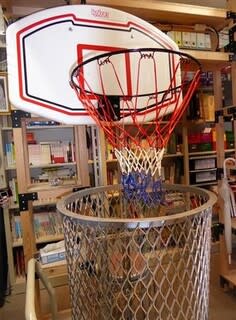場所:紀ノ川河口
条件:大潮 4:51満潮
釣果:タチウオ 1匹
しかし暑い。毎年こんなに暑いのかと思うようになったのは体力の衰えも影響しているのだろうか。それともやっぱり今年は例年になく暑いのだろうか・・。もう、日が昇ってからも釣りを続けることは自殺行為だとしか思えない。
だから今日も太陽の姿を見る前に釣りを終わってしまおうともう一度タチウオを狙いに行くことにした。当分は釣れても釣れなくてもこれだけにしておこうと思う。
今日は小船の出番なのでそれに加えて紀ノ川河口でルアーを投げてみるつもりだ。少し頑張れば禁断の仕掛けを流すこともできるのだが、燃料の残量がかなり少なっていることと、台風になる前の熱帯低気圧の影響が心配なので新々波止の南には行かないと決めた。
日の出もかなり遅くなってきた。今日は午前4時15分ごろの出港だったのだが、やっと東の空がわずかに明るくなっていた程度だ。それに加えて、この夏初めてオリオン座を見つけた。写真に撮ってはみたのだが、暗くて星を判別することができなかったので星座ソフトで再現してみるとこんな感じだった。

暑い暑いと言いながら季節は確実に進んでいる。そういえば、今週の日曜日は立秋であった。暦のうえでも季節は確実に進んでいるのである。でも暑い・・。
燃料を節約するため、河口の奥深くまでは入らず、青岸灯台の少し東側で護岸に人の影の見えないところを探して碇を降ろした。今日は少し波気があるのでポッパーを使う。まあ、何を使っても釣れないものは釣れないのでルアーは何でもよいのだが・・。
デッキの上が判別可能になるくらいの明るさまで粘ろうと思ったが、沖の方でタチウオを狙っているらしい船の影が見え始めたので居ても立っても居られずに移動を開始。行き来する船に交ざって仕掛けを流すがアタリはない。
少しずつ東の空が明るくなってくると景色は見る見る真っ赤に染まってきた。大気が不安定なのか、かなり水分を含んでいるようだ。青岸の沖に差し掛かると灯台のシルエットと相まって美しい光景となった。これはブログのネタになるぞと船の動きを止めてシャッターを押す。

再び釣りを開始すると、一度海底に沈んだ仕掛けが浮き上がる垂直の動きに反応したのだろうか、すぐにアタリがあった。とりあえず1匹確保だ。
その後は、アタリは連発するがエソばかりだ。もう少し型がよければ持って帰るのだがそれほどの型ではない。アタっては仕掛けを回収しまた投入を繰り返すので面倒この上ない。
最初に釣った動作を再現すべく船を停止させては再度発進させてみるがタチウオは来ない。
タチウオを釣っていたほかの船は気が付けばすべていなくなっており、結局殿になるまで頑張っていたことになるがその甲斐もなく今日は1匹で終了。
昔、「真夏のオリオン」という映画を観たことがあって、あらためて映画のプレビューを読んでみたのだが、そこでは、「冬の星座であるオリオンが真夏に輝けば、それは船乗りにとって吉兆となるのだという。」と語られていた。う~ん、僕はやっぱりなんちゃって船乗りでしかないのでオリオン座の吉兆にはありつけないんだろな・・。確かに今日はオリオン座を見たのだが・・。
港に戻る途中には虹が出ていた。単に大気の状態が不安定という理由だけなのだろうが、これも吉兆には程遠いようだ・・。

釣っている時間も短いのでブログの文章も短い。星空のネタを組み合わせてみてもここまでがやっとだ・・。
条件:大潮 4:51満潮
釣果:タチウオ 1匹
しかし暑い。毎年こんなに暑いのかと思うようになったのは体力の衰えも影響しているのだろうか。それともやっぱり今年は例年になく暑いのだろうか・・。もう、日が昇ってからも釣りを続けることは自殺行為だとしか思えない。
だから今日も太陽の姿を見る前に釣りを終わってしまおうともう一度タチウオを狙いに行くことにした。当分は釣れても釣れなくてもこれだけにしておこうと思う。
今日は小船の出番なのでそれに加えて紀ノ川河口でルアーを投げてみるつもりだ。少し頑張れば禁断の仕掛けを流すこともできるのだが、燃料の残量がかなり少なっていることと、台風になる前の熱帯低気圧の影響が心配なので新々波止の南には行かないと決めた。
日の出もかなり遅くなってきた。今日は午前4時15分ごろの出港だったのだが、やっと東の空がわずかに明るくなっていた程度だ。それに加えて、この夏初めてオリオン座を見つけた。写真に撮ってはみたのだが、暗くて星を判別することができなかったので星座ソフトで再現してみるとこんな感じだった。

暑い暑いと言いながら季節は確実に進んでいる。そういえば、今週の日曜日は立秋であった。暦のうえでも季節は確実に進んでいるのである。でも暑い・・。
燃料を節約するため、河口の奥深くまでは入らず、青岸灯台の少し東側で護岸に人の影の見えないところを探して碇を降ろした。今日は少し波気があるのでポッパーを使う。まあ、何を使っても釣れないものは釣れないのでルアーは何でもよいのだが・・。
デッキの上が判別可能になるくらいの明るさまで粘ろうと思ったが、沖の方でタチウオを狙っているらしい船の影が見え始めたので居ても立っても居られずに移動を開始。行き来する船に交ざって仕掛けを流すがアタリはない。
少しずつ東の空が明るくなってくると景色は見る見る真っ赤に染まってきた。大気が不安定なのか、かなり水分を含んでいるようだ。青岸の沖に差し掛かると灯台のシルエットと相まって美しい光景となった。これはブログのネタになるぞと船の動きを止めてシャッターを押す。

再び釣りを開始すると、一度海底に沈んだ仕掛けが浮き上がる垂直の動きに反応したのだろうか、すぐにアタリがあった。とりあえず1匹確保だ。
その後は、アタリは連発するがエソばかりだ。もう少し型がよければ持って帰るのだがそれほどの型ではない。アタっては仕掛けを回収しまた投入を繰り返すので面倒この上ない。
最初に釣った動作を再現すべく船を停止させては再度発進させてみるがタチウオは来ない。
タチウオを釣っていたほかの船は気が付けばすべていなくなっており、結局殿になるまで頑張っていたことになるがその甲斐もなく今日は1匹で終了。
昔、「真夏のオリオン」という映画を観たことがあって、あらためて映画のプレビューを読んでみたのだが、そこでは、「冬の星座であるオリオンが真夏に輝けば、それは船乗りにとって吉兆となるのだという。」と語られていた。う~ん、僕はやっぱりなんちゃって船乗りでしかないのでオリオン座の吉兆にはありつけないんだろな・・。確かに今日はオリオン座を見たのだが・・。
港に戻る途中には虹が出ていた。単に大気の状態が不安定という理由だけなのだろうが、これも吉兆には程遠いようだ・・。

釣っている時間も短いのでブログの文章も短い。星空のネタを組み合わせてみてもここまでがやっとだ・・。