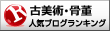お昼のNHKニュースで、
アラスカ州沖のベーリング海を、
中国海軍の艦船5隻が12カイリ以内の米国領海を通過していたことが、
明らかになった。とか、言っていました。
中国から帰化した石平教授によると、
戦後70年間、中国は、外国からの軍事的脅威は、
一度も感じたことは、ない国だそうです。
まず、いま、中国を侵略しようなんて国は、どこにもない。
アメリカでさえ、そんなことは、考もしない。
にも、関わらず、軍人の数は、世界一だそうで、
では、その世界一とも思われる軍事力をもって、
なにをなそうとしているか?
それは、南シナ海の南沙諸島を見れば、すぐわかる。
と、おっしゃっていました。
なんだか、恐ろしい話ですよね。。
***************
これは、明治時代の伊万里です。
さて、何か描いてあるか、わかりますか?
日本かぼちゃと、おそらく雀でしょうか?
あだ花(雄花)も、咲いていますね。(笑)
かぼちゃのデッサンは、やや、ラフですが、
雀のデッサンは、巧妙に描かれていて、作者は、スズメが描きたかった事がわかります。
明治時代の端唄に・・
汽車は出て行く、煙は残る。
奥州街道のかぼちゃのツルが、
農家の雪隠(せっちん/そとかわや)を倒したとか、
どうとかという、歌が流行ったとがあり、
それが、関係しているかどうかは、なぞです。(笑)
直径、40セントほど。明治時代、中期ごろか。