
↑東邦亜鉛㈱の前身の日本亜鉛㈱が1939年(昭和14年)に買収した対馬の対州鉱山。出典:同社HPより↑
■9月27日、長崎県対馬市の比田勝尚喜市長は、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(いわゆる「核のごみ」)の最終処分場選定の前提となる「文献調査」について、調査を受け入れない考えを表明しました。同市長は27日午前10時に開会した市議会本会議で、現段階では「安全であるという市民の理解を得るのは難しい」と述べたのです。
これに先立ち、対馬市議会は9月12日の本会議で、文献調査を受け入れるよう求めた市民からの請願について賛成10、反対8で採択していました。比田勝市長は市議会の決定と異なる判断を下した理由について①市民の合意形成が不十分だ②風評被害が懸念される――などを挙げて、核のゴミの受け入れにNOの見解を示したのです。
自民党をバックに当選した同市長のこの発言は、極めて重い意味を持っています。なぜなら、対馬はいまでも有害な重金属汚染の問題を引きずっているからです。
■この問題について、折から東京新聞が、対馬のカドミウム公害を引き合いにして、核(放射能汚染)や有害な重金属汚染の廃棄物が、長期間にわたり、生活環境や自然環境に及ぼす深刻な問題について、わかりやすく提起する記事を掲載しています。早速見てみましょう。
**********東京新聞「こちら特報部」2023年9月28日
核のごみ NO 調査応募巡り市長が方針
対馬 公害の歴史
原発から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分の受け入れを巡って揺れる長崎県対馬市。27日、比田勝(ひたかつ)尚喜市長は調査に応募しない意向を表明した。ただ市議会は推進派が多数を占めるほか、来春に市長選があり、予断を許さない。その対馬は昭和の時代、鉱山が操業され、カドミウム汚染に翻弄された。イタイイタイ病の発生も疑われた。過去に苦労した地に「核のごみ」を委ねていいものか。(木原育子、西田直晃)
■昭和にカドミウム汚染 大きな組織に依存する構図■

↑鎌田慧(さとし)さん(資料写真)↑
対馬市長の方針が示された27日。安堵せず、嘆息交じりで話す人がいた。
「(受け入れに伴う交付金に)群がらざるを得ない自治体は対馬だけでなく、もっと出てくるはずだ」
「本音のコラム」でおなじみのルポライター、鎌田慧さん(85)。1969年にジャーナリストとして初めて踏んだ現場が対馬だった。カドミウム汚染が取り沙汰された状況を取材し、初の著書「隠された公害」を70年に上梓した。
あれから半世紀以上。同じ地が「核のごみ」に揺れる。先行きが不透明な状況も残る。
「歴史が繰り返されている。鉱山会社から、国や電力会社へ変わっただけ。生活が行き詰まると、どこか大きな組織に依存してしまう構図は変わっていない」
■69年に取材 鎌田慧さん 「住民沈黙 企業が支配」■
過去に汚染をもたらしたのが対州鉱山だ。所在するのが旧厳原(いづはら)町。同町は、2004年に6町合併で誕生した対馬市の中でも、中心的な存在になる。市の玄関口のフェリー乗り場から西に数キロに位置する。
市観光商工課の糸瀬富喜主任は「対州鉱山は厳原町の佐須という地域にあったので、地元の人は『佐須鉱山』と呼んだ」と話す。
「同じ旧厳原でも市庁舎がある島の東側と違って、西側の佐須は農村地域。トンネルを抜けると、ぱっと日本の田舎の原風景が広がる感じだ」と続ける一方、「コロナ前までは韓国の観光客でにぎわったこともあったが、今は…」とも。
対馬と鉱山は縁深い。古代から銀を産出し、地域を繁栄させた。1939年には日本亜鉛が買収。流れをくむ東邦亜鉛は高度成長期にかけ、対州鉱業所を置いて亜鉛や鉛を掘り出した。
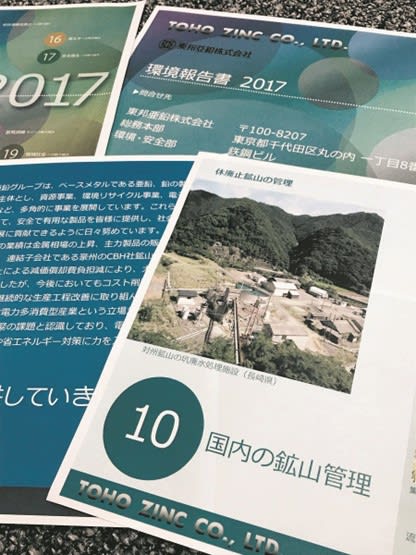
↑東邦亜鉛の2017年環境報告書。対州鉱山の管理状況を伝える↑
その一方、地元はカドミウム汚染に見舞われた。亜鉛族元素に区分されるカドミウムが原因で骨がもろくなる「イタイイタイ病」を疑う報道もあり、69年に要観察地域に指定された。
鎌田さんが取材を始めたのがこのころだ。「ほとんどの住民は無言を貫き、逃げるばかり。町にとって大切な産業。住民は企業に完全に支配されていた」
先の著書を出版した3年後の73年、「この資料は正確で聊(いささ)かかの誇張もない真実の記録です」との書き出しで企業内部から告発文が届いた。会社が組織ぐるみでごまかした資料を厚生省(現厚生労働省)に提出したと裏付ける文書だった。
鎌田さんは「1人の人間が勇気を奮い、苦難を覚悟し、いわば身をていして訴え出てくれた。対馬は国境の島、要塞の島だが、企業に牛耳られた島でもあった。そんな三重苦を背負っていた」と回想する。
■鉱山、調査で偽装工作 閉山50年でも排水検査・報告■
◆坑廃水処理水の調査、今も続く 負の記憶 考慮を◆

↑カドミウムの汚染調査で偽装工作があったことを報じた当時の東京新聞↑
対州鉱山は73年に閉山。翌年、告発文にあった不正の記事が世に出て騒動に。東京新聞も、汚染調査で偽装工作があったと報じた。
現地では長崎大が約30年にわたり、住民の健康被害の追跡調査を続けた。イタイイタイ病と同じ症状の住民が確認されていたが、原因は断定できなかった。
一方で余波は今も続く。
東邦亜鉛は鉱山保安法などに基づき、発生源対策や坑廃水処理を実施する。対州鉱山管理事務所の杉村智律所長代理は「処理水に重金属が含まれていないか調査を続け、毎月経済産業省に報告している」と語る。
閉山後、一度も基準値を超えていないという。市環境政策課の阿比留正臣課長は「問題の値は出ていないが、負担が続く面もある。国と県、市で毎年補助金も出している」と話す。
環境問題に見舞われた対馬。「核のごみ」の最終処分とも長い関わりを持つ。
■議会側、反対から一転 来春市長選で争点か■
80年代には動力炉・核燃料開発事業団の地質調査で島の一部地域が「処分地として良好」と評価された。最終処分事業を担う原子力発電環境整備機構(NUMO)は2006年ごろから説明会を複数回開いた。
なぜ対馬で説明会を開いたのか。過去の環境汚染に思いを巡らせたのか。
NUMO広報部の副部長は「(動燃の調査は)参考にしていない。説明会をいつから何度開いたか、どちらが働きかけたかは、個別のケースはお答えしていない」と繰り返した。
◆24年春に市長選、予断許さず◆
対馬は揺れてきた。07年に市議会は受け入れ反対を決議した一方、今月には調査受け入れを促す請願を採択。市長は反対を表明したが、来春には市長選を控えており、不透明さが残る。
万一、調査の応募に動いた場合、NUMOは対馬の過去に配慮するのか。
手を挙げた場合、3段階ある調査のうち、第1段階の文献調査が始まる。先の副部長は「不適地を除くための調査。次の段階の調査でさまざまな要件が設けられ、そこで判断する可能性はある」とした。
とはいえ、最終処分場の選定基準は曖昧さが残る。

↑経済産業省が入る庁舎=東京・霞が関で↑
文献調査を踏まえた選定基準については、経産省資源エネルギー庁が7月に案を公表した。景観や文化財、国土防災を考慮し、土地の利用規制が起きるというが、それ以上の記載はなく、地域事情が深く考慮されるかは不明瞭だ。担当者は「対馬で文献調査を開始しておらず、予断を持って答えられない」と話す。
選定基準はどうあるべきか。過去の苦労を無視して構わないのか。
信州大の茅野恒秀准教授(環境社会学)は「地域の歴史的経験に正面から向き合うべきだ。住民は長い時間軸の中で暮らす。その経験に寄り添わずに信頼は得られない」と訴える。
■処分地選定「地域の経験寄り添って」■
◆対馬市、寿都町、神恵内村…共通するのは◆
対馬市のほか、既に文献調査を受け入れた北海道寿都町、神恵内村にも共通するのは、高齢化や過疎化で疲弊した地元の活性化が叫ばれる点だ。
明治学院大の藤川賢教授(地域環境論)は「困窮地域ほど新たな苦労を迎えやすい」と語る。「調査を受け入れると、観光業などにデメリットがあり、賛否の対立が疲弊を招く。小規模自治体の財政に貢献するというが、予算を長期にわたって執行できるわけではない。交付金が終了すれば困窮はより厳しくなる」
そもそも選定基準の議論が十分と思えない。現状は文献調査の基準をまとめただけ。候補地を先に募り、基準は調査と並行して決められる。
先の茅野氏は「『後出しじゃんけん』のように判断基準を決める進め方。最終処分場の選定は手順を含めたゼロベースでの見直しが必要だ」と話す。
◆デスクメモ◆
対馬の過去を知るほど、対馬に迷惑施設を委ねていいかと感じた。ただ万一、応募に傾いたら「善意」に甘えていいか。苦労に苦労を重ねる危惧。善意というより、交付金を頼らざるを得ない「苦渋」の面も。各地に通じる問題。公平な最適解をどう考える。その議論こそ必要では。 (榊)
**********
■東邦亜鉛は、1937年(昭和12年)2月に日本亜鉛製錬株式会社として設立され、直後の同年6月に安中製錬所を操業開始し、1941年(昭和16年)9月に東邦亜鉛株式会社に社名変更しました。しかし、安中製錬所の操業開始に際して、当時は戦時下であったことから、東邦亜鉛は、地元住民に対して「兵隊さんの命を守る鉄兜を作るために必要な“高度鋼”を製造するためだ」として、ウソをつき騙したのです。そのため、筆者の子どものころは、地元の大人たちは東邦亜鉛安中製錬所のことを「コードコー」と呼んでいました。
製錬所は、丘陵地の北斜面に位置し、現在では55ヘクタールもの面積に拡大しており、これ以外にも工場周辺のあちこちで、農地や山林を、子会社の安中運輸の名義や、従業員の中で農家を兼業している者の名義で土地を取得しています。
このうち平地に広がるカドミウム汚染土壌の水田については、公害問題で世間の注目を浴びていた昭和40年代後半に排客土ないし15センチの上乗せ客土が対策事業として実施されました。しかし、製錬所の南側にある北野殿地区を主体とする丘陵地に拡がる畑地と、製錬所の東側に位置する岩井地区の畑地は、長年にわたる製錬所から排出される重金属を含む降下ばいじんや、敷地から風にのって伸び散る重金属交じりの土埃を浴びており、土壌汚染が深刻ですが、これまで放置されたままでした。
平成7年ごろ、これら畑地の土壌汚染対策として、圃場整備を方式による排客土のための碓氷川流域公害防除特別土地改良事業として、群馬県が主体となり、公共事業で排客土工事を施工する事業計画がスタートし、地元に公害防除特別土地改良事業(略して「公特事業」)推進委員会が設置されました。これは当時玄米中のカドミウム濃度が1ppmを超える農地を対象とした農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(土染法)に基づき、畑地においても陸稲が栽培されていたことから、畑地についても重金属土壌汚染対策が必要となる対象とされたのでした。
以来、28年にわたり計画が進められていますが、1988年に穀類、1998年にその他の食品目のカドミウム基準時の検討を開始していた、玄米中のカドミウム濃度の基準が、国際的な食品規格基準の策定を行う政府間機関であるコーデックス委員会(CAC)の下部組織である食品添加物・汚染物質部会(CCFAC)が、玄米中に含まれるカドミウム濃度の安全基準を見直した結果、2005年に小麦、野菜類、2006年に精米の基準(0.4ppm)を策定し、公表しました。
*****コーデックス委員会の食品中カドミウム国際基準値*****
コーデックス委員会が定めている食品中のカドミウムの国際基準値は、以下のとおりです(「食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関する一般規格」(General Standard for Contaminants and Toxins in Foods and Feed, CXS 193-1995)の要約)。
<食品>/<基準値(mg/kg)>/<基準値適用の食品部位>/<備考>
精米/0.4/全体
小麦/0.2/全体/普通小麦、デュラム小麦、スペルト小麦、エンマー小麦に適用。
穀類/0.1/全体/コメ、小麦、ソバ、キノア、カニューアを除く。
豆類/0.1/全体/乾燥した大豆を除く。
根菜類/0.1/地上部を除いた全体。付着した土壌を除く(流水ですすぐ又は乾いたものは優しく払い落とす)。バレイショは皮を剥いたものに適用。/セロリアックを除く。
果菜類/0.05/茎を除いた食品の全体。スイートコーン、生鮮コーンは、皮を剥いた粒及び軸に適用。/トマト及び食用きのこを除く。
葉菜類/0.2/明らかに傷んだ又は萎れた葉は除いた後の通常販売される全体部位。/アブラナ科の葉菜類にも適用する。
マメ科野菜類/0.1/可食部全体。水分が多い形態では鞘全体又は鞘を除いたものが食べられる。
アブラナ科野菜類/0.05/球茎キャベツ及びコールラビ:明らかに傷んだ又は萎れた葉を除いた後の通常販売される全体部位。カリフラワー及びブロッコリー:花蕾(未熟な花房に限る。)芽キャベツ:"button"(側芽)に限る。/アブラナ科の葉菜類を除く。
鱗茎類/0.05/タマネギ及びニンニクの乾燥した鱗茎:根及び付着した土並びに簡単に剥がれる羊皮様外皮を除いた全体部位。
茎菜類/0.1/明らかに傷んだ又は萎れた葉を除いた全体部位。ルバーブ:葉柄のみ。アーティチョーク:花蕾のみ。セロリ及びアスパラガス:付着した土を除く。
**********
■こうした中、日本政府の農林水産省は2001年から食品中のカドミウムの実態調査を開始しました。これは、コーデックス委員会で玄米中のカドミウム濃度基準が0.2ppmに決まる動きをにらんで、これを何とか0.4ppmまで緩和することを目指し、2003年に調査結果と「消費者の健康保護が図られることを前提として、基準値を合理的に達成可能な範囲でできる限り低く設定する」という考え方(ALARAの原則)に基づいて推定した基準値案を作成し、CCFACに提出しました。
その結果、日本政府のロビー活動が功を奏し、上記のとおりコーデックス委員会は、玄米中のカドミウム濃度を0.4ppmとしたのでした。
■こうした世界の動きに連動するかたちで、平成7年(1995年)頃スタートした群馬県主導の公特事業推進委員会も、このあおりを食いました。当初は、汚染農地の所有者からの事業参加の仮同意も順調に取得が進んでいたのですが、平成14年(2002年)に0.4ppmの基準値が策定されると、途端にスローペースとなりました。
それでも地元の野殿・岩井の地権者らは、何とか事業を推進すべく、仮同意の取得を進め、ついに平成19年(2007年)3月5日に100名あまりの地権者全員の仮同意文書を集めたのでした。
ところが、群馬県のスローモーな対応は相変わらず続き、年1回の本部役員会議を開くだけで、事実上足踏み状態が平成24年まで続きました。そのため、地元地権者で組織する公特事業推進委員会では、当時地元選出の2名の県議(岩井均、茂木英子)に紹介議員となってもらい、大沢正明群馬県知事に、公特事業の積極的な推進を要請する請願書を提出しました。
■すると平成25年から、群馬県がこの事業に対して積極的な姿勢を見せ始め、当初は平成29年には着工も夢ではないかもしれないという期待を地元住民に抱かせました。
しかし、当時から10年が経過しようとしている現在、期待は幻想に代わり、群馬県は以前のようなスローダウン状態に逆戻りしようとしています。そのため、こうした状況を打開すべく、昨年7月12日に筆者が3代目の公特事業推進委員会の会長に推挙されました。
以来、1年が経過しましたが、状況は深刻となっています。なぜなら、群馬県は東邦亜鉛に忖度して、積極的に公特事業を進めようとしないためです。
それどころか、平成3年度と4年度に実施された岩井畑地区における現状回復方式による公特事業(当初、2.5ヘクタール規模の区画整理事業で計画されていたが、東邦亜鉛が地元有力者を使って地権者の切り崩しを諮り、着工寸前までに0.96ヘクターまで事業規模が縮小)に基づく農地の汚染土壌の排客土工事の最終段階で、排土を埋め立てた東邦亜鉛の敷地内の場所で、群馬県が東邦亜鉛に土壌検査を指示して測定させたところ、土壌汚染対策法に定めるカドミウム(基準値45ppm)、鉛(基準値150ppm)、ヒ素(基準値150ppm)をいずれも上回ったとして、急遽、排土の移動を禁止し、下層の土を入れ替える、いわゆる天地返し工法しか許可しないと、事業を担当する県農政部に横やりを入れたのでした。
このため、野殿地区における事業の見通しに暗雲が立ち込めています。いかに、東邦亜鉛が行政に対して圧力をかけ、畑地の汚染土壌対策事業にブレーキをかけているかを痛感させられます。
■なお、日本政府は、農用地の土壌汚染防止に関する法律(土染法)は基本的に水稲や陸稲を作付けする水田や一部の畑地だけを対象にして,野菜や果実を栽培するその他普通畑は今後とも対象にしないつもりです。そのため、安中製錬所周辺の畑地の重金属汚染土壌は依然として放置されたままであり、しかも、毎年、少しずつ安中製錬所から排出される排煙中に依然として含まれるカドミウム、鉛、ヒ素などの重金属が周辺に降り積もり続けており、汚染が進行している状況にあります。
対馬市の対州鉱山跡地で依然として鉱毒が周辺環境に負荷をかけているのと同様に、群馬県安中市の東邦亜鉛安中製錬所も、長年にわたり重金属を周辺に垂れ流し、あるいは巻き散らかしてきています。対州鉱山で見せた東邦亜鉛の企業倫理の欠如は、今もなお、安中の地で遺憾なく発揮されていると言えるでしょう。
【市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※関連情報「対馬の対州鉱山の様子」
**********ブログ「水辺遍路」2020年10月25日
対州鉱山の池(仮称)(長崎県対馬) 離島 九州編

↑山腹にラピュタ感のある建物↑
対州鉱山は1973年に閉山した亜鉛鉱山。
対馬筆頭格の河川である佐須川沿いに鉱山事務所があり、閉山してから半世紀近くがたった今も鉱毒管理が行われていて、敷地内に入ることもできず、池にも会えなかった。
当初は採掘跡湖かと思ったが、立地や形態的には鉱滓ダムの可能性が高そうだ。

川沿いに三つの池があるようだが近づけず




枯れ沢となる川が多い対馬にあって、唯一、豊かな清流をもつ佐須川であるが、このあたりではさすがの佐須川もこんな具合
※参考情報「対州鉱山」
**********Wikipedia「対州鉱山」

↑対州鉱山跡(厳原町佐須地区)。2017年6月撮影↑

所在地:長崎県下県郡厳原町(現:対馬市)
座標 :北緯34.2285881687585度 東経129.2183346155609度
生産 :産出物 亜鉛
生産量 22,000t/月(1966年)
歴史 :開山 ?
閉山 1973年
所有者:日本亜鉛株式会社⇒東邦亜鉛株式会社
取得時期 1939年
概要 :
対州鉱山(たいしゅうこうざん)は長崎県下県郡(現・対馬市)厳原町樫根(かしね)にあった鉱山。
東邦亜鉛によって経営されていた亜鉛の鉱業所で、1973年(昭和48年)に閉山した。なお、対州とは対馬国、対馬島の異称。
東邦亜鉛は1943年(昭和18年)の対州鉱業所(対州鉱山)本格操業開始から、1973年(昭和48年)の閉山までの30年間経営を行っていた。当初は戦後の高度経済成長により、急速に業績を伸ばしていった。しかし昭和40年代半ばから貿易の自由化が推し進められ、外国産の安価な鉱石が輸入されるようになった。そのため、小規模で生産コストの高い国産鉱石はたちまち外国産に押され、経営が行き詰り閉山となった。
対州鉱山は急速に厳原町の産業基盤を支える重要産業に成長していった。鉱山従事者で人口が増加し、町の税収は増え、鉄筋コンクリート造のアパートや商店、映画館などの遊興施設が建設されるなど、鉱山周辺の地域に活気をもたらした。
しかし、繁栄は長く続かず、閉山後は鉱産税や電気・ガス・固定資産税の大幅な減収、下請け労働者の失業、商店の減収をもたらすなど、町の経済にとって大打撃となった。また、カドミウム汚染を引き起こすなど、町民の健康への影響も生じた。このカドミウム汚染に対して東邦亜鉛は汚染田の復元や農産物減収・健康被害者への補償を行うとともに、閉山から45年以上たった現在でも汚染が起きないよう監視機関(事務所)を設置している。
東邦亜鉛株式会社 対州鉱山管理事務所 〒817-0243長崎県対馬市厳原町樫根248(北緯34度13分43秒、東経129度13分8秒)
歴史 :
対馬では古くから、銀をはじめとする金属を産出していた(対馬銀山を参照)。
大正時代中頃に鉱山が休止。
1938年(昭和13年頃) 土佐出身の白川隆彦が鉱業権を取得し、当時の佐須、安田、久の恵等の坑を買収統合。
1939年(昭和14年)8月 日本亜鉛株式売社が白川隆彦から鉱業権を買収。
1941年(昭和16年)9月 日本亜鉛株式会社が社名を東邦亜鉛株式会社に改称。
1943年(昭和18年)8月 本格操業を開始。
1945年(昭和20年)4月 太平洋戦争の激化により、重油等の資材不足のため操業を一時休止。
1946年(昭和21年)11月 連合国軍最高司令官総司令部は日本政府に鉛の増産を指令、同時に日本各地の鉱山は自家発電力用の重油の特配を受けることになる。
1947年(昭和22年)2月 連合国軍最高司令官総司令部天然資源局技官が訪問。綿密な調査の末、対州鉱山の有望の認定を行う。
1948年(昭和23年) この年、再度の資源調査により、鉱床・鉱量の確実性が認められ、全面的な支援を受けるようになる。
1948年(昭和23年)8月 本格的に操業を再開。
1949年(昭和24年) 小茂田発電所が完成(出力450kW2基)。
1950年(昭和25年)6月 月産5,000t態勢が完成。
1951年(昭和26年)3月 厳原町南室(なむろ)に船への積出施設が完成。南室まではトラックで運搬する。この年、日見抗の開発に着手。
1952年(昭和27年) 悪水谷抗の開発に着手。
1956年(昭和31年) 月産8,500tに拡張。
1957年(昭和32年) 月産10,000tに拡張。
1965年(昭和40年)4月 鉛・亜鉛原鉱石の月処理は14,000tと磁硫鉄鉱1,500t、計15,500t。
1966年(昭和41年) 月22,000t。
1968年(昭和43年)から1971年(昭和46年)にかけ、厳原町は同町下原(しもばる)の床谷(とこや)に鉄筋コンクリート造4階建ての改良住宅192戸を建設。
1970年(昭和45年)8月 出鉱量300万tを達成。
1973年(昭和48年)8月 閉山宣言が出される。
1973年(昭和48年)10月 出鉱を停止し、鉱内撤収作業を開始。
12月20日 閉山。30年の歴史に幕を閉じる。閉山時の従業員322名のうち、本社員の多くは、群馬県の安中製錬所に配属。
<閉山後>
1974年(昭和49年)3月21日 佐須地区鉱業被害者組合の総決起集会が行われる。イタイイタイ病の再検診、汚染田の復旧、東邦亜鉛の監視機関の設置等を決議。この年、厳原町議会でも鉱害対策特別委員会を設置し、事実究明を開始。
1974年(昭和49年)5月21日 佐須・椎根(しいね)川流域の住民の検診を開始(5月24日までの3日間)。対象者は300名。検診の結果、イタイイタイ病と認定する患者はおらず、腎臓障害など軽症患者の疑いがある経過観察者が25名。
1974年(昭和49年)7月 被害者組合と東邦亜鉛の交渉の結果、企業100%負担によるカドミウム汚染田の復元を合意。
1974年(昭和49年)12月 農産物減収補償交渉がまとまる。
1975年(昭和50年) 厳原町により、休廃止鉱山鉱害防止工事が開始。鉱山の長い歴史(対州鉱山操業開始の前から)による汚染地域が河川流域の各地に存在することがわかったため。
1979年(昭和54年)12月23日 国と長崎県と東邦亜鉛により、汚染田の復元工事が開始。客土方式で行われ、心土は同町の久根浜や豆酘などから、耕土は壱岐郡(現壱岐市)郷ノ浦町から運ばれた。
1980年(昭和55年) 町による休廃止鉱山公害防止工事が完了。
1984年(昭和59年)2月 カドミウムによる腎臓障害の疑いがある経過観察者への健康補償がまとまる。
1985年(昭和60年)2月13日 汚染田の復元工事が完了。
<技術者養成>

↑東邦亜鉛株式会社対州鉱業所技術学園跡。2020年2月撮影↑
鉱山の技術者を養成するため、東邦亜鉛が「東邦亜鉛株式会社対州鉱業所技術学園」(地域では「学園」と呼ばれていた)を開設していた。詳細については不明だが、かつての校地には現在も門柱が残っている。(北緯34度13分36秒、東経129度13分23秒)
**********

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます