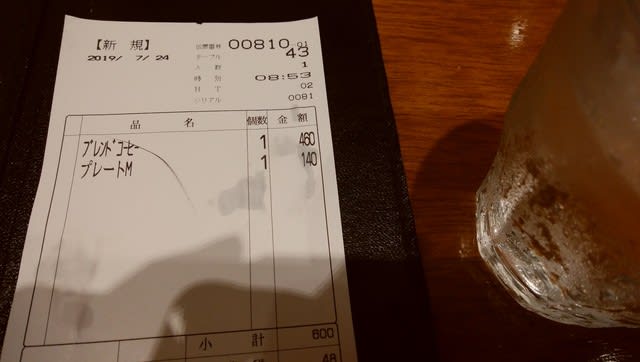せき止め乱用、10代で急増 危険ドラッグはゼロに 厚労省、薬物依存調査
2019年9月17日 (火)配信共同通信社
2018年に薬物依存などで全国の精神科で治療を受けた10代患者の4割以上が、せき止め薬や風邪薬などの市販薬を乱用していたことが厚生労働省研究班の実態調査で分かった。14年の調査では1人もおらず、近年急増していることを示した。取り締まりが強化された危険ドラッグの10代の乱用者は1人もいなかった。
「消えたい」「死にたい」などと考え、生きづらさを抱えた若者が、一時的に意欲を高めるために市販薬を乱用するケースが多いという。せき止め薬は安価で簡単に入手できる上、中枢神経興奮薬と抑制薬の両方の成分が含まれ、インターネットで「多幸感が得られる」といった情報が出ていることが背景にあるとみられる。問題を抱えた若者の支援や、薬局で大量購入を防ぐための対策強化が求められる。
全国の入院設備のある精神科1566施設を対象に調査を実施。18年9~10月に薬物関連の治療を受けた患者のうち同意が得られるなどした2609人を分析した。
大人も入れた全世代では、乱用した薬物は覚醒剤が最多で56%を占め、睡眠薬・抗不安薬の17%が続いた。前回の16年調査から大きな変化はない。シンナーなどの揮発性溶剤(6%)と危険ドラッグ(3%)は減り、市販薬(6%)と大麻(4%)はわずかに増えた。
10代は34人で、41%が市販薬を使用し、次いで大麻が21%だった。危険ドラッグは1人もいなかった。前々回の14年調査では、市販薬0%、大麻4%、危険ドラッグ48%で、傾向が変化していた。
市販薬でも大量に服用するなどの誤った使い方を続けると、中断した際に感情的苦痛に襲われて、やめられなくなり、生活が破綻する恐れがある。
大人を含めた市販薬乱用者の4割は女性で、9割以上が男性だった危険ドラッグ乱用層がそのまま移行したとは考えにくいという。