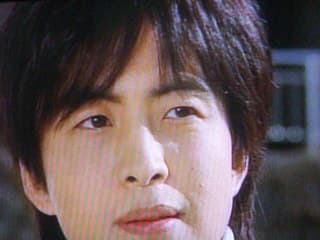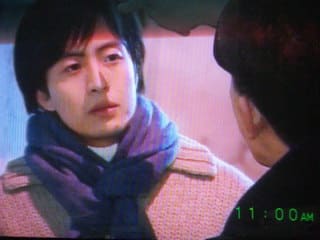新聞の特集版「ナントカ学」に、「冬なのに梅はなぜ咲く」という記事がありました。
新聞の特集版「ナントカ学」に、「冬なのに梅はなぜ咲く」という記事がありました。
東京で、平年より11日早く18日に咲いたという書き出しで、「受粉媒介の昆虫」のことや、梅の木の「渡来説」「在来種説」云々が、書かれていたのですが、 した写真の「南高生が・・・」の記事が、目に泊まったわけです。
した写真の「南高生が・・・」の記事が、目に泊まったわけです。
昨年に「地域団体商標制度(地域ブランド)」の認定第一号になった「南高梅」のこと、和歌山に住んでるのに、高級品だということしか知りませんでした。
戦後まもなく、「梅優良母樹調査選定委員会」ができ、5年がかりで、県立南部高校の竹中先生と、生徒達が調査に協力し、「高田家」の大粒の梅を、63年「種苗名称登録(当時)」に出願された。と言う逸話があって、その時に「品種名」を何にするかで、委員長だった、竹中先生が、「少しぐらいは、宣伝になるだろう」と、軽いノリで、南部高校の通称名「南高」とつけたそうです。
この「南高梅」自分の花粉では、受粉できず、別品種の梅を近くに植えておかないと実を結ばないとか・・・
最新バイオ技術で、「欠点」を克服するための計画がたちあがったそうで、将来の新品種名だけは、決まってて、「スーパー南高」だそうですよ。
梅は、実を採る目的の「実梅」と、花を楽しむ「花梅」に分けられる。
園芸ブームが起きた江戸時代中期、盛んに改良され、野梅系(やばいけい)、緋梅系(ひばいけい)、豊後系(ぶんごけい)の、3系約300種。
野梅は、野生種に近い性質をとどめた系統で、花も葉も小ぶり。
緋梅系は、正しくは枝や幹の内部が紅色になるものをさすが、この系統のものはほとんどが花も紅や、緋いろになる。
豊後系は、花や葉が大きく、アンズとのかけ合わせでつくられた雑種と考えられている。
参考になりましたでしょうか。
全て、新聞記事より、抜粋いたしました。
 昨日に引き続き、新聞記事の
昨日に引き続き、新聞記事の です。 みなさん「苺」の表面の粒々、あれは何だかご存知ですか? あれが「苺の果実」なんですって
です。 みなさん「苺」の表面の粒々、あれは何だかご存知ですか? あれが「苺の果実」なんですって あの粒々の中に、種がはいってるんだそうですよ。 「果実」は、めしべの下にある子房(しぼう)が発達して、中にある胚珠と呼ばれる部分が、種になる。 「柿」、「桃」、「蜜柑」等が子房が発達したもの。 苺の場合、めしべが100以上あって、受粉すると、めしべがはえる土台になる花托(かたく)部がふくらんでくる。 ということで、私達が「果実」と思ってたのは、ふくらんだ花托だったというわけです。 めしべの子房は、ほとんど変化のないまま中に種が出来るんですね。 苺の実は、「膨らんだ花托の廻りに小さな果実がたくさんついたもの」ということになります。 子房以外の部分が膨らんで果実のように見えるものを「偽果(ぎか)」というそうです。 「林檎」、「梨」も 偽果で、めしべの土台が、種子を包み込むように、大きくなったんですね。 そういえば、柿や、桃って、種がわかりやすい(いかにも種)ですよね。 偽果っていうことすらしらなかったので、この記事(DO科学)は、とても勉強になりました。
あの粒々の中に、種がはいってるんだそうですよ。 「果実」は、めしべの下にある子房(しぼう)が発達して、中にある胚珠と呼ばれる部分が、種になる。 「柿」、「桃」、「蜜柑」等が子房が発達したもの。 苺の場合、めしべが100以上あって、受粉すると、めしべがはえる土台になる花托(かたく)部がふくらんでくる。 ということで、私達が「果実」と思ってたのは、ふくらんだ花托だったというわけです。 めしべの子房は、ほとんど変化のないまま中に種が出来るんですね。 苺の実は、「膨らんだ花托の廻りに小さな果実がたくさんついたもの」ということになります。 子房以外の部分が膨らんで果実のように見えるものを「偽果(ぎか)」というそうです。 「林檎」、「梨」も 偽果で、めしべの土台が、種子を包み込むように、大きくなったんですね。 そういえば、柿や、桃って、種がわかりやすい(いかにも種)ですよね。 偽果っていうことすらしらなかったので、この記事(DO科学)は、とても勉強になりました。











 新聞の特集版「ナントカ学」に、「冬なのに梅はなぜ咲く」という記事がありました。
新聞の特集版「ナントカ学」に、「冬なのに梅はなぜ咲く」という記事がありました。


 )「カット版冬ソナ」にはちょっと不満です。
)「カット版冬ソナ」にはちょっと不満です。





 }
} 

 を撮ったので、綺麗じゃなくってすみません
を撮ったので、綺麗じゃなくってすみません ビョンホンsiiが、河田アナのこと憶えてらして、「お久しぶりです。」って日本語で挨拶されたんですよ。 でも、ちょっと~河田アナ、いくら似てるって言われてても、ズニ乗りすぎだよん
ビョンホンsiiが、河田アナのこと憶えてらして、「お久しぶりです。」って日本語で挨拶されたんですよ。 でも、ちょっと~河田アナ、いくら似てるって言われてても、ズニ乗りすぎだよん

 タダの凹み穴
タダの凹み穴
 ツウの方はご存知でしょうけど、ご存じない方の為に・・・ 左上は、「アサヒプライムタイム」・・・ きめ細かく、泡持ちの良い「こだわりの泡」。 右上、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」・・・世界に誇る麦芽の芳醇さと、ホップの素晴らしい香り。 左下、「キリンブラウマイスター」・・・芳しいホップの香りときめ細やかな泡、舌に広がる濃いうまみ。 右下、「ヱビス・ヱビス黒」・・・ おすすめ2商品を自分の好みで調整して楽しんで
ツウの方はご存知でしょうけど、ご存じない方の為に・・・ 左上は、「アサヒプライムタイム」・・・ きめ細かく、泡持ちの良い「こだわりの泡」。 右上、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」・・・世界に誇る麦芽の芳醇さと、ホップの素晴らしい香り。 左下、「キリンブラウマイスター」・・・芳しいホップの香りときめ細やかな泡、舌に広がる濃いうまみ。 右下、「ヱビス・ヱビス黒」・・・ おすすめ2商品を自分の好みで調整して楽しんで という特徴をふまえて・・・さーどれにしますか~~
という特徴をふまえて・・・さーどれにしますか~~
 私の記憶違いでしょうか
私の記憶違いでしょうか
 でしたよね~~
でしたよね~~