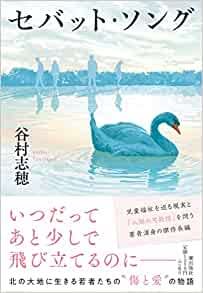
昨年の最新刊『過怠』があまりに素晴らしかったから、今回文庫になったこの小説も(これも、かなりの大作!)期待できると思い読み始めた。(2019年11月刊行)さすがに『過怠』を超える作品とは言い難い。まぁ、当然だろう。いくら彼女でもなかなか凄いものを連発できないし、できなくてもかまわない。もちろん、つまらないわけではないし、それどころか『過怠』を読んでなかったら、かなり高い評価をしそうなレベルの作品であることは確かだ。まぁ、人は欲張りだから、ついつい比較してしまい、つまらない文句も言う。(すみません)児童自立支援施設を舞台にして、そこで暮らし、出ていった兄妹のその後を施設長親子との交流を通して描く。
少人数の登場人物に絞り、彼らのそれぞれの視点からドラマは進展する。4人の主人公がお互いに絡みあいながら、ささやかなお話は小さな幸せにつながる。父と娘。父が世話をした兄と妹。自立支援施設の施設長として虐待を受けてきたことで犯罪に手を染めた子供を受け入れ更生させる男と21歳になるその娘。仕事一筋で家族を顧みる余裕のない父。娘は新人理学療法士でまだ働き出したばかり。そんな彼女が父が以前担当した兄妹と出会う。父の見せてくれたユーチューブの配信動画で見た妹の歌がきっかけだ。
セバットとは「冬の間一帯が氷結する大沼湖畔にあって、凍らずに白鳥等の渡り鳥が羽を休める場所。語源はアイヌの人々が「狭い場所」という意味でそう呼んだ説がある」ということらしい。
なかなか象徴的なタイトルで作品内容をうまく表現している。だがお話としては「狭い話」になってしまったのも事実だろう。世界は広がらない。4人のそれぞれの想いはしっかりと描けているけどそれがどこにつながるかというレベルでの狭さが残念なのだ。両親による児童虐待。それでも親を求める子供たちの想い。それを理解し支えようとする施設の院長の苦悩。彼の娘はそんな父親を尊敬しながらも、満たされない思いを抱えて大人になる。仕事と家庭というどこにでもある問題を根底に持ちつつ、その先を描くはずだが、なんだか小さく収まってしまった印象が残る。
どうしようもない現実の前で息をひそめて生きている兄と妹。そんな兄を好きになる施設長の娘。理想を追求するばかりの施設長についていけないスタッフの造反や彼の家族の諦め。ラストで4人のお話はうまく収まるが、それだけでは納得がいかない。児童自立支援施設に身を寄せる子供たちの現実を変えるために、理想を実現するために自分の人生をかける。そんなきれいごとはきれいごとでしかないのか。彼の娘と彼が受け止めた兄妹の兄が一緒になる結末を簡単なハッピーエンドにはできないのはわかるけど、この困難の果てに差し込める一条の光を単純には信じきれない。

























