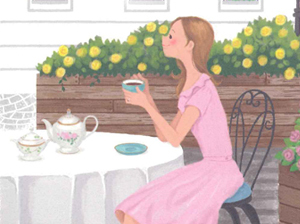2月のラボ便り
2月のラボ便り
皆様、こんにちは。
寒い日が続いておりますが、お元気にお過ごしでしょうか?
今回のラボ便りでは
人工授精についてお話させて頂きます。
人工授精は精子を直接子宮内に届ける治療方法です。
タイミング治療では、
膣内に射出された精子が、膣と子宮の間にある頚管で全て阻まれることがあります。
その場合、精子は子宮や・その先にある卵管まで到達しない為、
卵子と出会うことが出来ません。
人工授精では子宮内へ直接精子を注入することで、
卵子と出会う可能性を上げることが出来ます。
精子の状態が良くなかった場合や、
性交障害、タイミング療法で結果が得られなかった場合などに有効な治療方法です。
人工授精を行う際は、
細く柔らかいカテーテル(チューブ)を使用し、調整した精子を直接子宮内に注入します。
精液を調整する目的としては、
1、より多くの運動精子を集める
2、精液中の不要な成分を取り除く
があります。
精液中には、正常な運動精子以外に、
不動精子や奇形精子、細菌や白血球、衣類の繊維などの不純物が含まれています。
射出された精液をそのまま子宮内に注入すると、
細菌感染の恐れや精液中に存在するプロスタグランジンによる子宮収縮作用によって、
痛みを感じることがあります。
精液を調整する際は、試験管内の特殊な培養液に精液をのせ、遠心分離機にかけます。
そうすることにより、
不純物が試験管内の上層へ取り除かれ、良好精子が下層へ集まります。
このようにして集めた調整精子を、排卵前の時期に子宮の中へ送り届けます。
人工授精後の妊娠が成立するまでの流れは、自然妊娠と全く同じです。
子宮の中へ送り届けた精子は、精子自身の力で卵管を泳ぎ、卵子と出会って受精が起こります。
人工授精も自然妊娠の範疇となります。
人工授精を数回行っても妊娠に至らない場合には、
ピックアップ障害などの人工授精では解決出来ない不妊原因が疑われるため、
体外受精へのステップアップをお勧め致します。
何かご不明な点がございましたら、
いつでもスタッフまでお声掛け下さい。















 12月のラボ便り
12月のラボ便り