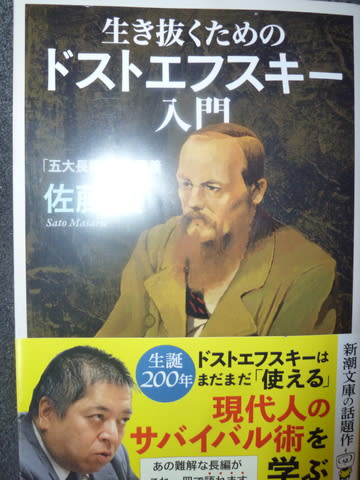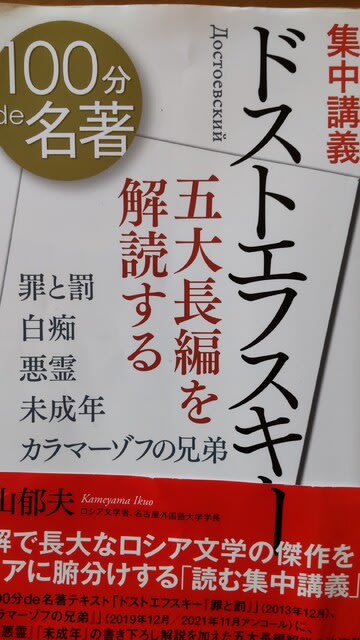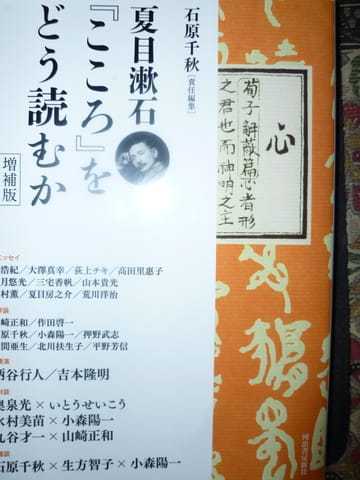スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。
『なぜ漱石は終わらないのか 』の第十四章では,それまでの漱石の小説とは異なった愛を巡る言説が『明暗 』にはあるということが論じられています。神の観念 idea Deiは,神に関して現実的に存在する人間が有する観念という意味と,神が自己自身に関して有する観念という意味の二様があるという主旨のことをいっています。畠中は単に二様の意味があるといっているだけで,前者が具体的にどのような観念であり,後者が具体的にどのような観念であるかを説明しているわけではありません。ただ,たとえ僕のようにそれらの観念を分類しているのではないとしても,現実的に存在する人間の知性 intellectusの一部を構成する神の観念と,神の無限知性 intellectus infinitusのうちにある神の観念は,同一の観念ではなく異なった観念であるとみていることは間違いないでしょう。したがって少なくともそれらを別種の観念として峻別するという点では畠中も僕と一致しているのであって,その点に着目する限り,僕の分類が僕に特殊の分類であるわけではないということが分かります。
作家の目的 は『道草』を対象とした対話の中で出てきたのですが,『道草』についてはこのブログで詳しく紹介したことがありませんでしたので,この機会に取り上げておきます。明暗 』の前に書かれた小説ですから,『道草』を書いている当時の漱石がモデルになっているというわけではなく,それよりも前の漱石がモデルとなっているというべきでしょう。つまり年齢を重ねた漱石が,まだ若かった頃の自分自身をモデルとして小説を書いたということになります。人間身体は限定されたものであるから自らのうちに一定数の表象像しか同時に判然と形成することができないということから生ずる 」。
新潮文庫版の『カラマーゾフの兄弟 』の「大審問官」の中に,キリストという意訳 がみられるということが『生き抜くためのドストエフスキー入門 』では指摘されているわけですが,この意訳が生じる要因がどういうところにあったのかということを,佐藤は推察しています。一言でいえばそれは,日本におけるキリスト教の理解の限界だというのが佐藤の見解です。ドストエフスキー はこのことを踏まえて「大審問官」を書いているのです。したがって,原卓也によってキリストと訳されている部分は,偽キリストという意味かもしれないのであって,確かにキリストという解釈も可能ではあるのですが,偽キリストという解釈も可能な文章になっていると佐藤はいっています。デカルト René Descartesもそれに従っている,ユダヤ教あるいはキリスト教的な創造主としての神Deusを,世界に対して外的なものでなく内的なものとしてみる解釈もできます。すなわち,神の自由意志voluntas liberaを想定して,その自由意志の下に神によって産出されることになる被造物としての世界が,創造主としての神のうちに余すところなく含まれているので,被造物としての世界が神の外部に出ることはあることも考えるconcipereこともできないとする見方です。ただこの見方は,第一部定理一五 については十全に説明しているといえますが,第一部定理一八 については十全には説明しきれません。神があらゆる被造物の内在的原因 causa immanensとして働くagereのであれば,包み込む存在existentiaである筈の神が,部分的にではあれ世界の内に包み込まれる事態も想定しなければなりませんから,これでは神が世界を包み込むこと自体が成立しなくなってしまうからです。第一部定理三二系一 により,それがスピノザの哲学に該当しないということはそれ自体で明らかです。しかしこの説明は,神の自由意志を,神の本性 naturaの必然性necessitasといい換えても成立するでしょう。そしてスピノザは第一部定理一六 では,神の本性の必然性necessitate divinae naturaeから無限に多くのinfinitaものが無限に多くの仕方で発生するといっているのです。なのでこのときにこれらの定理Propositioを,ユダヤ教あるいはキリスト教における神と世界の関係にあたる,創造主と被造物という関係でみること自体が,実は誤解なのであるということがここでは指摘されているのです。神がなければ何もあることも考えることもできないということはスピノザの哲学においてもその通りではあるのですが,それは神が創造主であって世界が被造物である,あるいは世界を構成する各々の個物res singularisが被造物であるという関係を,十全に示しているというわけではないのです。このような仕方で神と世界の関係を解さないように注意しなければなりません。
昨年の11月のことになりますが,亀山郁夫 の『ドストエフスキー 五大長編を解読する』という本を読み終えました。これはNHKの100分de名著というテレビ番組の別冊として出版されているもの。この100分de名著のシリーズは何冊か出ていて,その中には読んでみたいものがいくつかありました。最初にどれを読むのがよいかと考えていたのですが,これを選択しました。出版されたのは2022年1月です。罪と罰 』で,次が2019年12月に放映された『カラマーゾフの兄弟 』です。この本の第1章は『罪と罰』,第3章が『カラマーゾフの兄弟』で,このふたつはそのときの番組のテキストに加筆と修正を加えたもの。五大長編のうち残るみっつの『白痴』と『悪霊 』と『未成年』は第2章にまとめられていて,この部分はこの本のために書き下ろされたものです。ドストエフスキー の小説を読んでいないという人には十分には理解できないと思います。したがって,テレビでの講義とはいえ,入門書のような性格を有した本ではありません。ドストエフスキー 父殺しの文学 』を出版しているわけですが,たとえばそちらをよく読みこんでいたとすると,こちらの内容はそれほど深みが感じられないということになるかもしれません。なので読む順番からしたら,こちらを先に読んで,その後に『ドストエフスキー 父殺しの文学』を読む方がいいかもしれません。この本はその導入というような性格を明らかにもっていますから,いきなりそれを読んだら難しく感じられるかもしれない『ドストエフスキー 父殺しの文学』を,より容易に理解できるのではないかと思います。デカルト René Descartesの方法論的懐疑 doute méthodiqueを振り返れば,デカルトは自身の思惟Cogitatio,とくに思惟した内容はとにかく疑ったのです。それは,自身の精神mensが能動的に考えるconcipere場合も,受動的に表象するimaginari場合も含めて思惟作用とその思惟内容をすべて疑ったという意味です。その結果effectusとして疑い得ないとした事柄が,すべてを疑っている自分の精神は確実に存在しているということでした。ですからデカルトがこのことを発見したときは,自分の精神が,とくにすべてを疑っている自分の精神が,それ以外のすべての事物から切り離されたものとして発見されたのです。これに対して第二部公理二は,自分が思惟することを現実的に存在する人間は知っているということをいっているのであり,そのことだけを確実に知っているということを意味しているわけではありません。これはそれ自体で明らかといえるでしょう。ですからデカルトが発見したすべてを疑っている自分の精神というのは,デカルトが確実に存在すると認識できる唯一のものですから,確実に存在する自分の存在existentiaのすべてを意味します。しかしスピノザの場合は,確実に存在する自分の存在のすべてを思惟する精神に還元できるわけではありません。それは自分が確実に知っている事柄のすべてではなく,その一部であるからです。ですからこの場合は単に自分が思惟していることを知っているからといって,自分の思惟内容まで疑う必要はありません。要するに方法論的懐疑を実行する必要はないのです。よってそうした疑いを解消するための何か,デカルトの場合でいえば完全な存在としての神Deusのようなものをもち出してくる必要もないのです。第一部定義一 により,自己原因causam suiではないものが現実的に存在しているということの不可思議さにスピノザはこだわったと吉田はみているわけです。このことの正当性はここでは問うことはせず,吉田のさらなる探究をみていきます。
『夏目漱石『こころ』をどう読むか 』の荻上チキのエッセーでは,ゲートキーパー という観点から『こころ』が論評されているのですが,その中でウェルテル効果というものに言及されています。これも僕は初めて知った用語なので,ここで説明しておきます。デカルト René Descartesがいう神Deusは主意主義的な神になったのだと吉田は指摘しています。このことはここまでの論述から明らかだと思われますが,もう少し具体的な説明を施しておきましょう。
『なぜ漱石は終わらないのか 』の第十三章は『道草』がテーマに設定されています。この『道草』は自伝的小説のような内容なのですが,その中から,作家が小説を書く目的が読解されています。夏目漱石 が誕生する物語であると指摘しています。ドストエフスキー もルーレット で負けた借金の返済のために小説を書くということがあったのであって,それは芸術がどうこういうよりも,身の切迫に迫られて,書かざるを得なかったから書いたわけです。漱石は賭博で借金をするというようなことはありませんでしたが,状況としてはそれと同じようなことがあったのであって,とにかく金を稼ぐ必要があったから小説を書いたのだといわれています。ステノ Nicola Stenoは喜んで自然科学の研究を断念し,カトリックの普及に努めることになったと推測されます。なのでステノが地層学の研究から離れたのは必然であったと吉田はいっているのですし,もしかしたらステノはそうした予兆を感じていたから,地層学の研究を続けることを断念したのかもしれないと僕は思います。これは確かに,聖書の記述と自然科学の研究を両立させようとすることに伴う困難なのであって,そうした限界がステノにあったということについては,僕は吉田の見解opinioに同意します。しかし吉田のこの部分の講義内容は,ステノの研究成果については全面的に否定しているようにみえますし,聖書の記述と自然科学の研究を両立させようとすれば限界を迎えるということについても,ステノの個別の事例としてではなく,一般的な事例として説明されているようにみえます。このふたつの点については,吉田は意図しているというわけではないかもしれませんが,補充の説明が必要だと僕は思います。
『なぜ漱石は終わらないのか 』の第九章で,長男の次男化 ということが論じられているのですが,これに関連することが,『こころ』の私と兄との間にもみられるのではないかと僕には思えました。書簡六十七の二 が公開書簡の形式であったから現にあるような内容になったとすれば,その影響によって,書簡六十七の二は書簡六十七 よりも,遺稿集Opera Posthuma に掲載する価値のある書簡になった可能性が残されます。この場合は,これらふたつの書簡によって,ステノ Nicola Stenoとアルベルト Albert Burghの人間性の相違を考察するのは危険が伴うことになります。僕はアルベルトが書簡六十七の二のような内容を有する書簡を書くことができたとは思いませんから,それを書くことができたというだけで,知性的にステノがアルベルトより優れていただろうと思いますが,ステノが書簡六十七のような書簡を書いた可能性の方は否定できないので,この書簡の内容だけで,ステノの人間性を評価することは避けなければならないと思うようになりました。デカルト René Descartesの哲学を指していることがだれにでも明白なのですが,その改革者がスピノザだけであったというようには断定できないからです。同様に,この書簡の中では『神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』に対する言及もあるのですが,『神学・政治論』とはっきり書かれているわけではなく,新哲学の改革者が書いたといわれていて,ステノ自身もそう思っている本とだけいわれています。
『カラマーゾフの兄弟 』の中には,「大審問官」というタイトルでイワンが書いた物語があります。いわば小説内小説ですが,新潮文庫版の「大審問官」の訳には不備があるという主旨のことが『生き抜くためのドストエフスキー入門 』で示されています。ドストエフスキー の原語版に,キリストに該当するロシア語は一度も出てこないそうです。キリストと訳されている部分は,直訳すれば彼なのであって,ここでいわれている彼を,イワンがキリストであると解しているのは間違いないでしょうし,この物語を聞かされるアリョーシャもまたキリストであると解したのは間違いないでしょう。ですから意訳としてキリストという語を充てることには問題はないかもしれませんが,ドストエフスキーの言語版にキリストに該当する原語が一度も出てこない以上,この彼をキリストと意訳してしまうのは不備ではないかと佐藤は指摘しているのです。バチカン写本 を見せてしまったとだけいっているので,ステノ Nicola Stenoがチルンハウス Ehrenfried Walther von Tschirnhausに近づいたというのはその部分からの僕の類推ですが,この一件がおとり捜査のような仕方で行われたとするなら,そのように解するのが自然なのは自明でしょう。ホイヘンス Christiaan Huygensにはバチカン写本のことを秘匿し,ライプニッツ Gottfried Wilhelm Leibnizに対してもすぐにはそれを見せず,スピノザの許可を得ようとしたのですから,その事実だけで警戒心が欠如した人物であったというのはどうかという思いが僕にはありますが,その部分を考慮に入れないとしても,ステノが自身の立場を秘匿し,うまい具合にチルンハウスがライプニッツに対して抱いたような思いをステノに対しても思わせることに成功したなら,その時点では死んでいたスピノザの許可を求めることができなかったチルンハウスが,バチカン写本をステノに見せてしまったとしても,警戒心が欠如していたというようにいえるのかは疑問が残ります。もっとも,これはステノが自身の立場を秘匿していた,いい換えればステノがカトリックの説教師であるということを知らなかったという場合のことであって,実際には知っていたという場合もあり得るのですから,その場合には確かにチルンハウスには警戒心が欠如していたといえることは僕は否定しません。
『夏目漱石『こころ』をどう読むか 』の荻上チキのエッセーを読んだときに,『こころ』という小説では,直接的にではあれ間接的にではあれ,多くの死 が語られているということに僕が気付いたのは,このエッセーが,ゲートキーパーという視点から書かれたものであったからです。こういう視点から『こころ』を読むというのは僕にとっては類例がない,もしかしたらあるのかもしれませんが,それがきわめて少ないものでした。スペイク に申し出たわけですが,その時点でスピノザの遺産がどれほどのものであるか分かっていませんでした。なのでレベッカがスペイクに遺品目録を作成する権限を与えたのは,その内容を詳しく知りたかったからだということになるでしょう。この路線で解すると,ナドラーがここでいっていることは一貫性があることになります。スピノザの生涯 Spinoza:Leben und Lehre 』にも書かれていることであって,むしろナドラーがフロイデンタール Jacob Freudenthalの調査に依拠している事柄です。これは『ある哲学者の人生 Spinoza, A Life 』の方に詳しく示されている記録が残っていますから,この嘆願書がこの日に出されたことは史実です。
『なぜ漱石は終わらないのか 』の第九章の中で,長男と次男の関係の複雑さについて語られている部分があります。それから 』では次男に代助 という名が与えられているのです。逆にいえば漱石がそういう名を与えたということは,漱石はそのことに自覚的に小説を書いていたということになります。門 』という小説は,この長男と次男の関係が破壊されているという主旨のことがいわれています。宗助は長男ではありますが,各地を転々とした上で東京に出戻ってきたのであって,経済的にはむしろ困窮しています。それで父親が形見として残した屏風を売ることになるのですが,この屏風は正月に出すようなこの家,野中家ですが,その野中家の象徴のようなものなのです。長男である宗助は本来であればそれを受け継がなければならない存在,単に屏風を動産として受け継ぐという意味ではなく,野中家を受け継ぐという意味でも受け継がなければならないのですが,それを経済的な事情によって売ってしまうのです。これは長男が相続した家督を経済的に次男が売ってしまうという物語としてあるべきプロットなのであって,ここでは長男である宗助が次男化してしまっているのです。コレルスの伝記 Levens-beschrijving van Benedictus de Spinoza では,宿主が懇願を受けて葬儀の世話をしたとあります。この宿主がスペイク を意味するのは間違いありませんが,だれから懇願を受けたかは定かではありません。スピノザの友人だったかもしれませんし,もしかしたら地域の公職者であったかもしれません。そしてこの葬儀にかかる費用の全額に関しては,リューウェルツ Jan Rieuwertszがすべてを支払うという約束の保証になったと書かれていますが,この部分は日本語の文章として不自然であるように思えます。リューウェルツは葬儀の費用をスペイクに支払うことを保証したという意味であって,日本語の意味からすれば,リューウェルツは保証人になったということだと思います。シモン・ド・フリース Simon Josten de Vriesの弟であったと思われます。
『生き抜くためのドストエフスキー入門 』で汎悪霊論 が触れられている直後に,チホンとスタヴローギンの信仰に対する考え方の比較が考察されています。
汎悪霊論 について書いたときにいったように,僕はドストエフスキー がスピノザを知っていたとは思いません。普通に考えて,ドストエフスキーがスピノザのことを知るような機会があったとは思えないからです。ただ,ドストエフスキーとスピノザを繋ぐラインがまったくなかったというわけではありません。細いものではありますが,1本だけそういうラインは確かにありましたので,それを紹介しておきましょう。悪霊 』でフェージカがスタヴローギンの使嗾 によってスタヴローギンの妻であるマリヤを殺す場面は,火事も含めて『ファウスト』をモチーフにしていると『ドストエフスキー 父殺しの文学 』の中で指摘されています。『ファウスト』の作者はゲーテですが,ドストエフスキーとゲーテ の間には一定の関係があって,ドストエフスキーはゲーテのことを評価していました。つまりドストエフスキーはゲーテを読んでいたのです。妹の薬 を処方してもらっているのは,根岸駅の近くにあるチェーン店の薬局 です。これはてんかんの薬だけでなく,目薬 も同じです。薬局は同一店に集中させた方がよいと僕は考えているのでそのようにしています。このチェーン店の薬局になったのは,僕が中心に妹の世話をするようになった時点で,そうなっていたからです。そしてそれ以降はそれで何の不都合もありませんでしたから,今でもそのようにしています。
『夏目漱石『こころ』をどう読むか 』の中に,荻上チキのエッセーが掲載されています。このエッセーは僕には意外な観点から『こころ』に触れています。しかし荻上のエッセーについて触れる前に,僕はこのエッセーを読むことによって気付いたことがありますので,それを先にいっておきます。それは,『こころ』という小説は,直接的であれ間接的であれ,多くの人の死が語られているという点です。ここでは物語の順序ではなく,時系列でどのように死が語られているかをみていきます。夏目漱石「こゝろ」を読み直す 』でいわれているように,先生の結婚相手のの名前が静 と名づけられる理由を構成しているといえます。第四部定理四系 から明白であるといわなければなりません。第二部定理二九備考 では,知性の秩序とはいわれていませんが,ふたつの秩序が比較されていて,自然に共通の秩序に対応する秩序は知性の秩序といわれることになります。ただこのことはここでは重視する必要はありません。
『門 』の中で,宗助と御米の過去が詳しく語られるのは第十四節です。そこで宗助が御米を友人から奪ったことが明かされます。この友人は安井といい,宗助は最初は御米を安井の妹として紹介されるのですが,そうでないことはすぐにはっきりとしました。安井が病気になって回復したということ以外に詳しいことは語られないので,実際に安井と宗助,そして御米の間に具体的に何があったのかは分かりません。とにかく後に宗助と御米は結婚し,各地を転々とした後,物語が進捗していく時点では東京に住んでいます。なぜ漱石は終わらないのか 』の第九章の中で小森が指摘しています。実際にこの日の夜,御米が宗助にある告白をします。これは,自分は子どもを産むことができないということを,易者に指摘されたというものです。この易者は,御米は人に対して済まないことをした記憶があって,その罪が祟っているから子どもはできないといったのです。結婚後の6年間で,これまでに実際に御米は何度か懐妊はしていたのですが,子どもを産むことはできませんでした。第四部定理一八備考 でいわれていることは,一種の道徳的命令として解することができるといっているように思えます。もちろん実際にはこれは命令ではないのですが,仮に命令というものがあるとしても,『エチカ』においてはすべてこのような類のものになります。しかしそれは僕たちが道徳的命令として理解しているものとはあまりに異なっているといわざるを得ないでしょう。ですから國分がいっているように,『エチカ』はあるいはスピノザの哲学は,一切の道徳命令を発することはないというように解して間違いありませんし,とくに,たとえば他人を殴打するなというような類の命令を道徳に求めているのであれば,スピノザの哲学からはそのような命令は生じ得ないと解しておく方がよいでしょう。これはスピノザが,第四部定理八 において,善bonumと悪malumをそれぞれ意識された喜びlaetitia,意識された悲しみtristitiaと規定していることからの必然的な帰結です。この意識conscientiaを超越したような善悪が存在するということをスピノザは認めないのですから,自己の意識を超越したような善悪に関する道徳的命令は発令されようがないのです。第四部定理四系 により,現実的に存在する人間は常に受動 passioに隷属するのですから,スピノザは超越的規範の有用性,あるいはそうした超越的規範から発せられるような道徳的命令の有用性を否定するnegareことはありません。そうした命令が受動的な人間を,理性ratioに従っている人間がなすのと同じように行為させる限り,その規範および命令は有用であるとしかいいようがないからです。これは受動的な人間を敬虔pietasにさせるような規範や命令は有益utileであるという意味なのであって,たとえば聖書が神Deusを愛することと隣人を愛することについて服従することを命令するのは有用であるというのが一例になります。
先月のことになりますが『夏目漱石『こころ』をどう読むか』という本を読み終えました。2014年5月に河出書房新社から発売された本が,2022年12月に増補版として出版され,僕が読んだのはその増補版の初版です。増補版には2本のエッセーと1本の評論,そして三者対談がひとつ,新しく収録されています。反転する漱石 』の中に収録されています。また小森陽一の「『こころ』を生成する心臓」は,初出が「成城国文学」で,ちくま文庫版の『こころ』の解説として掲載されています。第四部定理三七備考一 との関係です。かつて僕は,そこでいわれている宗教心 religioというのが,僕たちが宗教心とか信心といった語で表そうとすることとはかなり隔たりがあるのであり,だからそこで畠中が,神を認識する限りにおいてすべての欲望 cupiditasと行動を宗教心と関係させるとは訳さずに,宗教心に帰すると訳したのは適切だったといいました。ただ本来であれば,宗教心に変わる適切な日本語があるのなら,宗教心に変えてそちらの訳語を用いる方がなお適切であるだろうと僕は考えているのです。