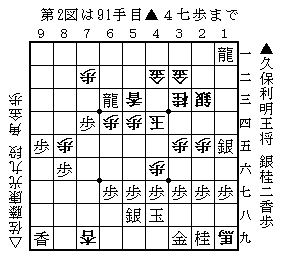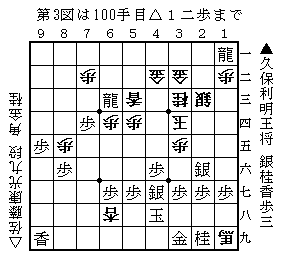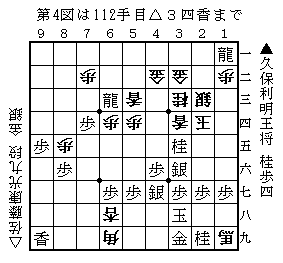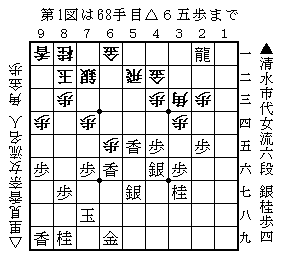『罪と罰』からもうひとつ,ドストエフスキーの小説がいかにキリスト教と関係しているかを示す例をあげてみます。

『罪と罰』ではラスコーリニコフが自首する前に,ミコールカというペンキ職人が犯人は自分であると警察に名乗り出ます。ミコールカは出身地こそ同じですがとくにラスコーリニコフと関係があるというわけではなく,なぜ彼がいわば身代りに自首しなければならなかったのか,僕にはよく理解できませんでした。その事情を亀山郁夫が『ドストエフスキー 謎とちから』で解説しています。

ミコールカは異端派のひとつ,逃亡派のセクトで終末論的世界観に浸っていました。ペンキ職人とはいっても自堕落な生活を送っていて,それはこのセクトとの関係から説明されます。ラスコーリニコフが老婆とリザヴェータを殺したのはこのミコールカが住んでいたアパートの上階でした。つまりミコールカの近辺で起こった殺人事件であり,このことがミコールカにある恐怖感を与えるのです。しかしそれは,単に殺人が起きたというだけの恐怖感ではありませんでした。
物語の舞台は1866年。いわゆる異端派がロシア正教から分離したのが1666年のことで,ちょうど200年の節目にあたっていました。このゆえに,異端派の間では,この年にアンチキリストが出現すると強く意識されていました。つまりミコールカは,この殺人のうちに,反キリストの出現を強く感じ,そのために恐怖を覚えたわけです。そのために警察の庇護を求めてわざと自首をしたというのが亀山の見解です。
ドストエフスキーが本当にそれを意図していたかどうかは僕には分かりません。ただ,ラスコーリニコフの思想の中に,反キリスト的な部分があるということだけは,疑いようのないことだと思います。
こうしたことはよほどロシアのキリスト教の事情に精通していなければ理解できないことです。ラスコーリニコフの場合が分かりやすい形でドストエフスキーとキリスト教の関係を示しているとすれば,このミコールカの場合には,分かりにくい形で暗示されているといえるでしょう。そしてこうした暗示は,僕が気付かない仕方で,ほかにもドストエフスキーの小説のうちに織り込まれているのではないかと思われます。
第二部定理九系証明は,スピノザによる第二の訴訟過程を省略したとしても,以下のような仕方で可能になると僕は考えています。
まず観念の対象ideatumとなる何らかのもの,Aがあるとします。そしてこのAの中にXが生じると仮定します。ここではXを,事物そのものと考えてもいいですし,ある働きないしは作用というように考えても構いません。どちらの場合でも成立すると僕は考えていますから,そのどちらの場合も含むと仮定しておきます。
このXの観念が神のうちにあるということは,第二部定理三から明らかです。そして第二部定理三は,どのような意味においても無限であるものの観念も,また自己の類において有限であるものの観念も,すべてが神のうちにあるということを明らかに意味しています。したがってこの証明の過程におけるXそしてAについては,それが無限であろうと有限であろうと,同じように神のうちにあるということになります。
そこで問題となるのは,Xの観念が神のうちにあるというとき,その観念がどのような形式で神と関連付けられるのかということです。ここで鍵になってくるのが第二部定理七における平行論です。第二部定理七は,それ自体では延長の属性と思惟の属性の間の平行関係だけを示しています。しかしこの同じ平行関係は,神の客観的属性である思惟の属性と,形相的属性である延長の属性をはじめとする無限に多くの属性のすべてとの間で,同じように成立します。これは第二部定理七備考で示されていることですから,スピノザが否定することはできません。
すると,XがAのうちに生じると仮定されているのですから,Xの観念はAの観念のうちに生じるということが帰結します。いい換えれば神はAの観念を有する限りでXの観念を有するということになり,思惟の絶対的力を有する限りでXの観念を有するということにはなりません。いい換えれば,観念の対象の中に起こることの観念は,神がその対象の観念を有する限りで神のうちにあるということになります。
念のために付け加えれば,Xは別にAの中に固有に生じるのではなく,たとえばBのうちにも生じるかもしれません。しかしその場合には,神はAの観念を有する限りでXの観念を有するでしょうし,Bの観念を有する限りでも同様にXの観念を有するでしょう。つまり,神はXの観念を有するために,AとBの両方の観念を有すると説明されなければならないのではありません。

『罪と罰』ではラスコーリニコフが自首する前に,ミコールカというペンキ職人が犯人は自分であると警察に名乗り出ます。ミコールカは出身地こそ同じですがとくにラスコーリニコフと関係があるというわけではなく,なぜ彼がいわば身代りに自首しなければならなかったのか,僕にはよく理解できませんでした。その事情を亀山郁夫が『ドストエフスキー 謎とちから』で解説しています。

ミコールカは異端派のひとつ,逃亡派のセクトで終末論的世界観に浸っていました。ペンキ職人とはいっても自堕落な生活を送っていて,それはこのセクトとの関係から説明されます。ラスコーリニコフが老婆とリザヴェータを殺したのはこのミコールカが住んでいたアパートの上階でした。つまりミコールカの近辺で起こった殺人事件であり,このことがミコールカにある恐怖感を与えるのです。しかしそれは,単に殺人が起きたというだけの恐怖感ではありませんでした。
物語の舞台は1866年。いわゆる異端派がロシア正教から分離したのが1666年のことで,ちょうど200年の節目にあたっていました。このゆえに,異端派の間では,この年にアンチキリストが出現すると強く意識されていました。つまりミコールカは,この殺人のうちに,反キリストの出現を強く感じ,そのために恐怖を覚えたわけです。そのために警察の庇護を求めてわざと自首をしたというのが亀山の見解です。
ドストエフスキーが本当にそれを意図していたかどうかは僕には分かりません。ただ,ラスコーリニコフの思想の中に,反キリスト的な部分があるということだけは,疑いようのないことだと思います。
こうしたことはよほどロシアのキリスト教の事情に精通していなければ理解できないことです。ラスコーリニコフの場合が分かりやすい形でドストエフスキーとキリスト教の関係を示しているとすれば,このミコールカの場合には,分かりにくい形で暗示されているといえるでしょう。そしてこうした暗示は,僕が気付かない仕方で,ほかにもドストエフスキーの小説のうちに織り込まれているのではないかと思われます。
第二部定理九系証明は,スピノザによる第二の訴訟過程を省略したとしても,以下のような仕方で可能になると僕は考えています。
まず観念の対象ideatumとなる何らかのもの,Aがあるとします。そしてこのAの中にXが生じると仮定します。ここではXを,事物そのものと考えてもいいですし,ある働きないしは作用というように考えても構いません。どちらの場合でも成立すると僕は考えていますから,そのどちらの場合も含むと仮定しておきます。
このXの観念が神のうちにあるということは,第二部定理三から明らかです。そして第二部定理三は,どのような意味においても無限であるものの観念も,また自己の類において有限であるものの観念も,すべてが神のうちにあるということを明らかに意味しています。したがってこの証明の過程におけるXそしてAについては,それが無限であろうと有限であろうと,同じように神のうちにあるということになります。
そこで問題となるのは,Xの観念が神のうちにあるというとき,その観念がどのような形式で神と関連付けられるのかということです。ここで鍵になってくるのが第二部定理七における平行論です。第二部定理七は,それ自体では延長の属性と思惟の属性の間の平行関係だけを示しています。しかしこの同じ平行関係は,神の客観的属性である思惟の属性と,形相的属性である延長の属性をはじめとする無限に多くの属性のすべてとの間で,同じように成立します。これは第二部定理七備考で示されていることですから,スピノザが否定することはできません。
すると,XがAのうちに生じると仮定されているのですから,Xの観念はAの観念のうちに生じるということが帰結します。いい換えれば神はAの観念を有する限りでXの観念を有するということになり,思惟の絶対的力を有する限りでXの観念を有するということにはなりません。いい換えれば,観念の対象の中に起こることの観念は,神がその対象の観念を有する限りで神のうちにあるということになります。
念のために付け加えれば,Xは別にAの中に固有に生じるのではなく,たとえばBのうちにも生じるかもしれません。しかしその場合には,神はAの観念を有する限りでXの観念を有するでしょうし,Bの観念を有する限りでも同様にXの観念を有するでしょう。つまり,神はXの観念を有するために,AとBの両方の観念を有すると説明されなければならないのではありません。